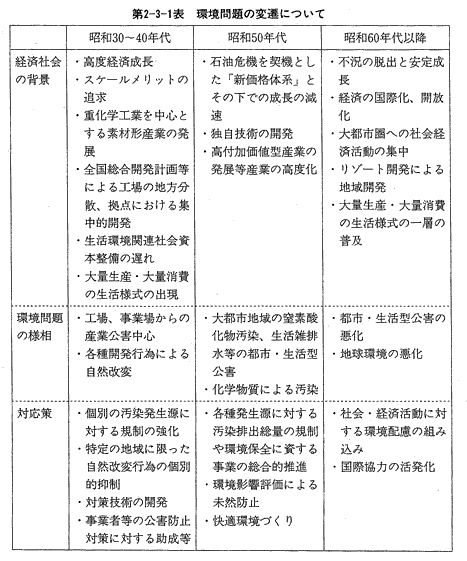
1 行政への環境配慮の組込み
前節で見たとおり、環境保全のための行動は、国民や企業にとって必ずしも有利なことではないため、国民や企業の自発的な努力にのみ委ねたのでは環境を十分に守っていくことは困難である。このため、我が国では、公害や自然破壊の問題への対応を図るべく、社会的ルールとして各種の規制措置などを制度化し、また、対策技術の開発を推進するとともに、事業者等の公害防止対策に対する融資、助成措置等を講じてきた。他方では、公共的な事業として、下水道や廃棄物処理施設などの環境保全に資する社会資本の整備に努めていった。これまでの環境問題の変換とそれへの対応を概観とすると次の表のとおりである(第2-3-1表)。こうした行政の発展の中で、汚染物質の排出の規制を中心とした対応により、フローの、言わば一過性の公害への対策は充実、強化されてきており、経済社会の持続可能性を高める前提は整ってきた。しかし、蓄積性の汚染対策などストックとしての環境の保全のための対策は、比較的少数に限られている現状にある。
(1) 法制及び行政組織への環境配慮の組込み
我が国は、戦後の高度成長の過程で、環境汚染が進み、生活環境が悪化したのみならず、四日市ぜんそく、水俣病、イタイイタイ病の例に見られるように、国民の生命、健康にまで大きな影響が生ずるに至った。
また、かけがえのない自然の改変が進行した。こうした環境破壊は、工場、事業場といった個定発生源からの産業公害が中心であった。このため、対応の仕方としては、大気汚染や水質汚濁の発生源を規制していくことが主たる施策であった。国レベルでの対応を見ると、製造等の種別ごとに、産業所官の省庁において発生源を規制する仕組みが設けられた。
大気汚染関係では、昭和37年には「ばい煙の排出の規制等に関する法律」(施行は厚生省及び通商産業省)が、水質汚濁関係では、33年に「公共用水域の水質の保全に関する法律」(施行は経済企画庁)及び「工場排水等の規制に関する法律」(施行は大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省及び運輸省)が制定された。しかし、これらの規制は、経済発展との調和が図られるべきとされていたことのほか、産業の規制の行える地域が公害の著しい地域に限られていたことに見られるとおり、発生した問題を後から追う形で対策がなされたこともあって、必ずしも十分なものとはなり得なかった。このため、公の政策として対処すべき公害の範囲を定め、国、地方公共団体及び事業者のそれぞれの責務を明確化するなど施策推進の基本的原則を明らかにし、公害対策を総合的、統一的に実施していくべく、42年に「公害対策基本法」が制定された。このような枠組み整備を契機として各種公害対策が体系的、総合的に充実強化されていった。
43年には、規制対象地域の拡大、自動車排出ガスの規制を目的に、「大気汚染防止法」(施行は、厚生省、通商産業省及び運輸省)が制定され、また、「騒音規制法」(施行は、農林省、通商産業省及び建設省)も新たに制定された。公害の防止を直接の目的としない関係法律においても、例えば、43年に制定された「都市計画法」では、「都市計画は、公害防止計画に適合したものでなければならない」との規定を置くなどの整備が図られた。
特に、45年の第64国会(言わゆる「公害国会」)では、公害問題の激化を受けて、公害対策基本法等の一部改正、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律、公害防止事業費事業者負担法、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律等の新規制定といった郊外関係14法案が成立し、公害関係法全般の充実、強化が行われた。
この一連の改正の中で、公害対策基本法等から「生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにする」旨の、言わゆる「経済発展との調和条項」が削除され、経済優先ではないかという疑念を払拭し、公害の防止に取り組む国の基本的な姿勢が明確にされた。また、大気汚染、水質汚濁については、規制を受ける地域を限定した、言わゆる指定地域性を改め、全国を対象地域とするなどの規制の強化、農用地の土壌については、過去に汚染された農用地の汚染の除去等に関する制度の整備が行われたほか、公害防止事業費事業者負担法の制定により公害防止事業についての事業者の費用負担義務の明確化などが図られた。さらに、別途、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により工場における公害防止体制の整備が図られた。
法制度の整備と並行して、行政組織の整備も進められた。45年に、公害に関し、講ずべき施策の整理・推進、公害に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に当たること等をその任務とし、本部長の内閣総理大臣の下、専属のスタッフを有する「公害対策本部」が設置された。その設置により、国の公害行政の統括的な責任の所在が明らかにされ、山積みした課題に対処するための政策立案中枢が生まれることが期待された。
しかし、公害対策本部は、臨時的な機関であり、対策の企画、調整以外の公害規制の実施権限は各省庁に分散したままであったことから、激化しつつあった公害問題に一層強力に対処するため、公害規制権限を一元化した行政機関の必要性が認識されるようになった。また、光化学スモッグ問題を契機に、環境問題に対する科学的研究を強力に推進すべきことが認識されるようになった。さらに、自然保護行政の分野でも、自然破壊が進行していったことから、公害対策と併せてこれらの対策を推進していくことが必要であるとの認識が高まっていった。諸外国でも、当時、各種の環境問題が激化しており、各国で環境保全のための一元的行政組織、制度の整備が進められていた。スウェーデンでは42年(1967年)に環境保護長庁が、45年(1970年)には、英国に環境省、米国に環境保護庁が、46年(1971年)には、フランスに環境省がそれぞれ設置された。なお、諸外国における行政機関の現在の所掌事務等の概要は次の表のとおりである(第2-3-2表)。
こうした背景を踏まえ、我が国では、平成3年度から数えてちょうど20年前の昭和46年7月に、環境行政を効果的に実施していくために、環境庁が設置された。環境庁は、公害の防止のみならず自然保護も含めた環境問題全般について、基本的な政策の企画、立案、推進を行い、各省の環境関係の経費の見積もりの方針の調整、環境保全に関する事務の総合調整等を行うとともに、「公害対策基本法」、「大気汚染防止法」、「自然公園法」等の環境関係諸法の施行等の事務を一元的に行うほか、それぞれ関係省庁が行っていた公害関連公共事業のうち、自然公園関係等の一部の事業を所掌することとなった(第2-3-3表)。
環境庁の設置後今日に至るまで、環境関係の法制度の整備は更に進み、例えば、自然環境保全法、大気汚染防止法等の改正法(無過失賠償責任の導入)、公害健康被害補償法(その後、昭和62年に、公害健康被害の補償等に関する法律に改正)(施行は、環境庁、通商産業省)、振動規制法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制に関する法律、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(施行は、環境庁、通商産業者)、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律(施行は、通商産業者、建設省、農林水産者、大蔵省、厚生省、運輸省、環境庁)といった法律が制定されている。
また、環境問題の発生の原因または現象機構の解明、防止技術の開発等の調査、研究は環境行政の不可欠な基礎をなすものであることから、国立の試験研究機関における公害防止等に関する試験研究費が環境庁に一括して計上され、環境庁から配分されることとなった。49年3月には公害に関する総合的な研究を行う機関として国立公害研究所が設立された。
環境庁設置後も、環境問題により適切に対処していくべく、組織の強化が随時行われていった。特に、最近では、地球環境問題への取組の必要性が高まり、我が国としての対策の強化が課題となったが、平成元年には、地球環境問題に関する行政各部の所管事務の円滑な調整を行うことを任務とした地球環境問題担当大臣として環境庁長官が任命され、2年には、環境庁に地球環境部が新設されるといったように組織の強化が図られていった。また、関係省庁においても所官に係る地球環境問題を始めとする環境問題に積極的に対処するため、組織の強化が図られている。
国立公害研究所についても、従来の公害分野のみならず自然保護分野を研究領域に加えるとともに、地球環境及び地球環境の両面に渡る研究の体制の強化を目的として2年に「国立環境研究所」に改組され、同年には地球環境研究とモニタリングの中核的拠点としてどう研究所内に「地球環境研究センター」が設置された。また、気象庁においては、平成2年に世界気象機関の要請を受けて温室効果気体の世界資料センターとしての温暖化情報センターを設置し、工業技術院では、3年に公害資源研究所を資源環境技術総合研究所に改組するなどその他の機関における地球環境問題を始めとする環境問題への取組のための組織の強化が図られてきている。
(2) 地方公共団体の行政への環境配慮の組込み
地方公共団地においても、環境問題に対する取組が行われた。環境問題は、まずもって地域の問題として認識されていた。地方公共団体は、このような地域的な、しかし、その地域の住民にとっては深刻な課題を最初に受けとめることとなり、住民の批判、運動の矢面に立たされたことから、国における施策の実施に先立ち、自らの力で公害の解決に当たった。
昭和24年には、東京都が「工場公害防止条例」を制定したのを始めとして、多くの地方公共団体で公害防止条例が制定された。これらの条例の多くは、大気汚染、水質汚濁等のおそれのある工場の設置等の許可手続きを定めることが中心で、当初は定量的な基準によって排出規制を行うことはなかなか困難であった。しかし、公害規制を直接の目的とする法律が制定されたのが30年代に入ってからであったことと比較し、公害対策に先鞭をつけたものとして意義は高く、国の対策にも影響を与えた。その後、公害問題が激化してくると、地方公共団体の中には、地域全体の汚染物質を全体として削減する手法を採用するなど、先駆的な取組を進めていくものもあった。現在では、全都道府県において公害防止条例が制定されている。
また、公害防止条例の制定以外にも工夫して公害対策が進められた。企業との間で結ばれた公害防止協定については、法律、条例による規制を細かく補完する役割を果たすものとして我が国に定着していった。
なお、地方に遅れて発展していった法律による排出基準については、環境問題が地域の事情等によって状況の異なることを考慮し、法律に基づき国が定める全国一律の基準に加えて、一層の厳しい基準を定めることのできるいわゆる「上乗せ基準」、あるいは国が規制していない施設に適用される「横だし基準」を地方公共団体が設定することを防げないものとされた。例えば、大気汚染防止法第4条に基づく上乗せ排出基準は、21都府県で、水質汚濁防止法第3条に基づく上乗せ排水基準は、全ての都道府県で定められている。また、規制効果の判定等を行い、適切な措置を講じて行くためには、発生源の監視測定とこれに基づく規制等が行わなければならず、これらの事務は環境行政の基本ともいうべきシステムとなっているが、これらの事務は、国から都道府県や政令で定める市に委任され、地方の環境行政部局が法に基づく強力な権限行使を行う基盤となった点も重要である。このような国と地方との適切な連携によって、地域の特性に応じた施策が推進されていったことが我が国の公害の迅速な改善に役立ったと言えよう。
一方、自然保護の分野でも、我が国の自然環境が急速に破壊されつつある状況に対応して、地域における自然保護を強力に推進するため、各都道府県において自然保護条例の制定が進められた。昭和45年に北海道において自然保護条例が制定されたのを皮切りに、ほとんどの都府県で条例制定の検討が開始され、昭和47年3月までに22道県において自然保護条例が制定された。これらの自然保護条例には、大別して三つのタイプが見られた。第一のタイプは、自然保護に関する県の施策ないし責務や自然保護審議会の設置等自然保護に関する基本的事項を定めた「自然保護基本条例」であり、第二のタイプは、国道、県道等の沿道の修景美化を内容とする「沿道修景美化条例」であった。これらに対し、第三のタイプは、狭義の「自然保護条例」とも言うべきもので、おおむね、自然保護に関する基本的事項を定めるとともに、特別の必要から保護すべき地域を定め、その地域内における一定行為につき許可あるいは届出制を採用しているものであった。しかしながら、こうした許可制等を採用する条例に関して、土地利用に関する公用制限を法律の根拠を有しないで条令で実施できるか否かが問題とされ、そのような問題点を解消するためにも、根拠法の制定の緊急性が高まり、昭和47年6月の自然環境保全法制定の大きな原動力の一つにもなった。自然環境保全法は、自然環境保全に関する基本法的な性格と、自然環境保全地域の指定等を通じての実施法的性格とを併せ持っているが、前者の部分においては、基本理念や地方公共団体の債務を明らかにするとともに、後者の部分では、都道府県自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全審議会に関する根拠規定が設けられ、これにより都道府県条例に基づき指定する自然環境保全地域における公用制限等の規制措置が担保され、それまでに制定された自然保護条例の趣旨も盛り込みつつ、すべての都道府県において自然環境保全条例が制定されることとなった。自然環境保全に係る問題も国レベルの傑出した自然の保護から、地域における身近な自然の保全、活用まで様々であるが、自然環境保全に基づく権限の一部は、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律などと同様に、都道府県に属し、あるいは委任されており、さらに同法に基づき国が実施する自然環境保全基礎調査についても、都道府県の協力を得て実施するなど、国と地方との連携により自然環境保全施策の推進が図られている。
また、地方環境行政組織も整備されていった。地方公共団体の公害関係行政従事人員については、環境問題の激化にしたがって増加していった(第2-3-1図)。
また、都道府県の公害担当組織の所属部は当初、企画開発担当部局が多かったが、次第に専門部局を設置するとことも出てきた(第2-3-4表)。また、公害問題に関する試験研究を実施する機関も相次いで設置され、昭和50年代の初めには都道府県・政令指定都市の全て及び一部の市に地方公害研究機関が設置された。こうした動きは、環境問題の激化に伴う対応の強化を目指すものであった。しかし、昭和50年代には、多くの公害対策が定型化されていくに従い、環境行政関係人員の数は減少に転ずるとともに、組織的にも、環境専任部局が保健部局等と統合される動きが見られている。その一方で、最近、地球環境問題を担当する組織を設ける地方公共団体も出てきており、公害研究所についても、地球環境問題や自然保護問題を研究分野に取り込むものも出てきた。
このように、環境行政の推進のための体制が整備され、我が国は、国、地方公共団体の双方が連携し、規制の強化、発生源の監視、指導、取締りを進めていった。国及び地方公共団体の環境保全環境予算の推移は、次に示すとおりである(第2-3-2図及び第2-3-3図)。
(3) 具体的施策における環境配慮
環境問題の変化に従い、環境保全に関する政策手段の内容も多様なものとなり、充実強化されていった。
? 環境行政の目標の明確化
環境を保全していくためには、どの程度の水準の環境の状況の実現を目指すのかが明確にされていることが望ましい。このため、我が国では、公害対策基本法に基づき、環境基準を定めることとされ、二酸化硫黄などの5種類の大気汚染物質、一般環境騒音、自動車交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音、公共用水域中の水銀など9種類の有害物質、BODで示される有機物質などの5種類の生活環境を阻害する水質汚濁物質等、土壌汚染に係わる10種類の有害物質について実際に基準が定められている。環境基準は維持されることが望ましい環境の水準であって、この基準を根拠に直ちに汚染原因者等に汚染削減を強制できるものではないが、行政実務上は、多様な施策を合理的に組み合わせたり、広範な関係者間に的確な役割分担を作り出したりする上で、この環境基準が大いに役立っている。
? 汚染行為、自然改変行為に対する規制等の充実
ア 汚染行為等に対する規制等の充実
排出規制は、汚染物質削減の最も直接的な政策手段である。排出規制は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に基づき定められている。現在、煙突や排水口などから排出される汚染物質のうち36の物質について定量的な値をもって基準値が定められている。これらの法に基づき発生源からの排出行為の限度を定める基準値は、汚染の進行や対策技術の進歩などに応じて機動的に改訂され、逐次、規制の強化、拡大が進められた。
例として、まず、窒素酸化物に対する対策を取り上げてみよう。窒素酸化物は、物の燃焼に起因して必然的に発生するものであって、発生源としては、工場などの固定発生源に加え、トラック、常用車等の移動発生源の占める割合も大きい。このため、我が国の経済活動の拡大、高度化に伴って、窒素酸化物による大気汚染が懸念されるところとなった。まず48年に、対策の目標となる環境基準(53年に改定)が定められた。これを踏まえ、工場に対する排出基準が定められ、その後、排出基準の強化や規制対象施設の拡大が行われた(第2-3-4図)。自動車については、48年に窒素酸化物に係る自動車排出ガス規制が行われた。その後も、自動車一台ごとの規制の対象物質や対象車種が拡大されるとともに、規制値の強化が図られてきた。
しかし、ここの発生源に対する排出規制だけでは、経済活動の拡大により汚染物質排出源そのものが増加した場合、環境基準の確保が困難となる。このため、工場、事業馬頭が集中した地域等における総量規制制度が大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に導入された。窒素酸化物については、工場等の固定発生源から排出される窒素酸化物に対する総量規制制度が、東京特別区等、横浜市等及び大阪市等の三地域について56年に導入された。一方、自動車については、交通量の増加等が原因となっていることから、根本的には、低公害車への転換・導入・事業活動に係る自動車の使用の合理化、自動車に過度に依存しない都市構造の構築等の総合的な対策が必要となっている。このような状況を背景として、新たな法律案(「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法案」)が平成4年の第123国会に提出された。
また、水質汚濁防止対策についても、当初は、工場、事業場等の個別発生源に対する排水の濃度規制の強化から始まった。しかし、内湾、内海、湖沼等の閉鎖性水域においては、その水域に流入する汚濁負荷量の総量を削減することが肝要であることから、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全臨時措置法の改正により、54年に、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について水質総量規制制度が導入され、三次にわたる総量規制の中で総量削減計画に基づき生活系、産業系統にわたる汚濁負荷量削減対策が実施されている。湖沼についても、水質環境基準の達成状況が悪いなどの問題が生じていたが、水質汚濁の原因が水質汚濁防止法の規制対象である工場・事業場によるもののほか、生活系、農畜水産系など多岐にわたっていることから、これらに対するものを含めた総合的な対策の推進を図るべく、59年に「湖沼水質保全特別措置法」が制定された。同法では、水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し、道計画の下で下水道整備等の水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置、さらには、湖辺の自然環境の保護等の対策を総合的・計画的に進めることとなった。
また、近年の水質汚濁の主な原因としては生活排水があり、その対策を進めるために、平成2年に水質汚濁防止法等の一部を改正し、生活排水対策に係る行政及び国民の債務の明確化、都道府県による生活排水対策重点地域の指定及び関係市町村による生活排水対策推進計画の策定等を内容とする生活排水対策に関する規定が整備された。一つの例として、全国で初めて、生活排水対策重点地域に指定された群馬県甘楽町における生活排水対策推進計画について、その施策の体系図と生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な各種施設を、具体的にどのように整備しようとしているのかを示す計画図を紹介する(第2-3-5図及び第2-3-6図)。
このように、汚染物質の削減について見ても、個別排出規制に始まり、必要な場合には、特定の地域に依存する各種の発生源を全体として取り上げ、これら発生源全体からの排出量の抑制をすることを狙いとする総量規制の導入、さらには、下水道整備等の社会資本の整備、土地利用対策などを適切な形で組み合わせていくといった多角的な取組を行っていくように製作の内容も多様化していった。
特に、汚染物質の削減対策としては、排出口に着目した対策にとどまらず、そこに至るまでの過程を考慮したものがある。こうしたものには、硫黄酸化物対策として行われる使用源燃料中の硫黄分の規制、特定の排出口を持たないため生産設備そのものを汚染物質の漏出を防ぐ形とすることを求める粉じんに係る構造規制、スパイクタイヤのように使用に伴い不可避的に環境影響が生じる物質や製品についての製造、販売や使用の禁止などがある。さらに、最近では、リサイクルのための再生資源の利用指導、特定のクロロフルオロカーボン(CFC)の生産規制や排出抑制等広がりを見せている。
なお、以上に見てきた規制措置は、主に一過性の汚染を抑制することを狙いとしたものであるが、中には持続可能性に、より直接に関連する蓄積性の汚染防止を狙いとするものもあり、こうした施策が発展しつつあることも重要である。これらには、多様な排出形態が考えられる化学物質についての製造や使用の規制、例えば、PCB等の化学物質の製造や使用等の規制、土壌汚染防止のための規制や土壌汚染に関する環境基準の設定、汚染が蓄積しやすい湖沼に係る汚濁負荷量規制および閉鎖性海域に係る総量規制、地下水の汚染防止を防ぐための規制などがあり、規制には至らないものの酸性雨の蓄積的影響や化学物質の環境中の残留状況の監視測定も行われている。
このほか、近年、地球環境保全の観点からの施策も行われるようになっており、前述のCFCの排出抑制もその一環である。また、我が国は、地球温暖化問題への対応の基本的姿勢として、地球温暖化対策を計画的、総合的に進めるため「地球温暖化防止行動計画」を策定(2年)し、それに基づき、関係省庁において各種施策を実施している。
イ 自然改変行為に対する規制等自然環境保全対策の充実
自然環境は、そのストックとしての価値に着目して保護が図られなければならないものである。
環境庁の設立によって、自然公園、国民公園、温泉及び鳥獣保護といった自然保護行政に関する権限を環境庁が所掌することとなったが、従来の自然保護関連の法律は、自然公園法の場合の風景地の保護、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の場合の鳥獣の保護というように、多様な自然を限られた側面からとらえ、それぞれの観点から必要な措置を講じようとするものであった。そこで、これら個別的な法律の運用を総合的に調整するための基本理念を整備するために、47年に国土全般的にわたる自然環境の保全の基本的方向を明らかにすることなどを内容とする「自然環境保全法」が制定され、併せて、自然公園法の改正が行われた。これにより、個別的な施策について見ると、自然環境に関する基礎的資料を収集する自然環境保全基礎調査の実施、専ら自然環境の保全を目的とした自然環境保全地域等の指定や自然公園地域における規制の強化が行われた。
これらの施策は、基本的には、自然性の高い地域を地域指定し、当該区域内の人間活動を規制することにより、自然を保護していくということに力点が置かれていた。他方では、生活環境の変化や都市型生活様式の普及に伴い、自然とのふれあいを求める声が大きくなっていった。このような状況の下で、開発を抑制するという規制的措置だけでなく、自然とのふれあいが自然への理解を深め、自然を慈しむ心を育てる上で欠かすことのできないものであるとの認識に立って、積極的に自然とのふれあいの場を確保・創出していくことが重要課題としてとらえられるようになった。このため、50年代半ば以降には、自然とのふれあいの増進、自然教育の推進等のため、従来からの自然公園の利用施設の整備の推進に加え、ふるさと自然公園国民休養地、自然観察の森等の多角的な施設整備が展開されるようになった。
また、野生生物の保護についても、我が国では、まず、鳥獣保護区の設定等の規制的措置により、鳥獣の保護管理の強化が図られていった。しかし、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の取引に関する条約(ワシントン条約)」が48年に採択されるなど鳥獣にとどまらずに野生生物全般を保護していこうとする国際的な動きに対応して、ワシントン条約等国際的な野生生物保護対策を国内においても実施するため、組織の整備や商取引の規制を含む法制度の整備が図られていった。すなわち、47年の日米を初めとして、渡り鳥等保護のための二国間条約又は協定が調印され、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の保護の分野での国際協力の仕組みが次第に整備された。これらの条約等の対象となる鳥類の輸出入と国内取引を規制するための「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」が47年に制定されている。62年には、ワシントン条約の規制対象種の国内での取引を規制するための「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が制定され、国内での取引規制が行われることとなった。また、特に、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)の指定地として釧路湿原、伊豆沼、クッチャロ湖、ウトナイ湖を登録し、その保全と適正利用を図ってきた。さらに、使用が原則禁止されていたかすみ網については、野鳥の保護の徹底を期するため、その販売、所持も原則的に禁止されることとなった。そのほか、絶滅のおそれのある種の保護対象の基礎資料として絶滅のおそれのある種の保護対策の基礎資料として絶滅のおそれのある種の現況を把握するために調査を行い、日本版レッドデータブックの作成を行うとともに、絶滅のおそれのあるイリオモテヤマネコ、トキ、シマフクロウなどの保護・増殖事業が進められた。
以上のとおり、自然保護の分野においても直接の自然改変行為に関する規制的措置が発展していったことに加え、各種の事業との連携、自然改変行為に結び付く各種の行為に関する対策へと施策の手法は広がりを見せつつある。また、地球的な観点からの対策も行われるようになってきている。
? 環境保全に資する対策技術の開発及び事業、施設の助成
汚染源の排出規制や自然改変行為の制限といった規制的措置に加えて、政府においては、公害防止技術や省エネルギー技術など環境保全に資する技術開発を積極的に推進してきた。また、環境保全に資する行為の促進や規制措置の迅速、円滑な徹底を図るために、特定の施設の整備などを助成する措置が、汚染者負担の原則に沿いつつ対象を限定して講じられている。公害防止施設等の設置等に対する特別償却等の税制特別措置、公害防止施設に対する公害防止事業団等による資金の貸付け及び施設の建設譲渡等を行う事業並びに日本開発銀行、中小企業金融公庫等による低利の資金の貸付けといった助成措置が実施されている。
また、自然保護の分野では、自然保護への国民の参加を拡大していく観点から「ナショナル・トラスト(国民環境基金)」活動を行う公益法人に対する寄附について税制の優遇措置が設けられている。
? 環境保全に資する公共事業等の促進
多数の省庁によって、環境保全に資する公共事業等の促進が図られている(第2-3-7図)例えば、大気汚染による公害を防ぐため、緩衝緑地整備事業(建設省)が、水質保全対策として、下水道整備事業(建設省)、コミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽設置整備事業(厚生省)、農業集落排水施設整備事業(農林水産省)、河川浄化事業(建設省)等が、土壌汚染の除去対策として公害防除特別土地改良事業(農林水産省)等が、廃棄物処理対策については、廃棄物処理施設整備事業(厚生省)、港湾環境整備事業(運輸省)がそれぞれ行われている。また、道路交通公害対策については、道路交通を円滑化するバイパス・環状道路等の整備、道路構造の改善や沿道環境の整備(建設省)、物流施設の適正配置(通商産業省、運輸省、建設省)、低公害車普及のための助成(環境庁、通商産業者、運輸省)等が、航空機騒音対策については、公共用飛行場周辺の騒音防止対策(運輸省)や防衛施設周辺の騒音防止対策(防衛施設庁)が行われている。
自然環境等の保全については、自然公園内の施設整備や公園内の民有地買上げ、公園外での自然教育の場の整備、絶滅のおそれのある野生生物の保護・増殖(環境庁)、多自然型川づくり(建設省)、重要自然維持地域保安林整備事業(農林水産省)等が行われている。
このように、環境保全に係る公共事業等が広く各省庁において実施されている。これら広範な事業の効率的な推進を図るため、関係省庁による予算要求に先立ち環境庁において、環境保全に要する経費の見積方針を調整し、その方針に基づいて同経費の取りまとめ、予算要求を行うこととなっている。
また、公害対策基本法に基づき、現に公害が著しい地域等において「公害防止計画」が策定され、公害防止事業やこれに関連する事業を含め各種の公害防止に関する施策を総合的、計各的に講ずることとなっている。
公害防止計画は、現在、36地域で策定されている。計画に基づく公共事業等のうち、廃棄物処理施設整備事業、緩衝緑地整備事業等については、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき、国の負担又は補助率のかさ上げ等国の財政上の特別措置が講じられており、それによって事業の促進が進められてきている。
? その他の公共事業等へ環境配慮の組込み
排出規制によって汚染物質の一般環境中への排出を抑制することは重要な政策手段であるが、環境汚染は、ひとたび発生するとその回復には困難な面があり、こうした点を是正して環境保全に万全を期すためには、環境汚染の未然防止の徹底を図ることが重要となる。このための有効な手段が環境影響評価である。国際的な動向を見ると、環境影響評価は、米国において、44年(1969年)に、「国家環境政策法」が制定され、同法に基づき、人間の環境の質に重大な影響を及ぼす勧告、立法の提案、その他の主要な連邦政府の行為に関し、環境影響評価を行うことが義務付づけられたのがその最初である。同法に続いて、仏、スウェーデンといった国でも環境影響評価の法制度化がなされた。ECでは、60年に「一定の公共及び民間プロジェクトの環境影響のアセスメントに関する理事会指令が出され、一定の範囲のプロジェクトについて加盟国の環境影響評価が義務づけられた。独では、この指令を受けて、平成元年に環境影響評価が法制度化された。また今日では、韓国、中国、タイ等の開発途上国でも環境影響評価の制度化が行われている(第2-3-5表)。
我が国で環境影響評価が政府の施策として広く実施されるようになったのは、47年の「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解からであると言える。この閣議了解を嚆矢として、以後、港湾法や公有水面埋立法等の改正などによる各事業法や事業官庁による行政指導の中で環境影響評価が位置づけられていった。地方公共団体においても、47年の閣議了解に基づき、国に準じて所要の措置を行うよう要請されたことなどを契機として、多くの団体で制度化が進められた。これらの環境影響評価は、その手続きなどがそれぞれ異なっており、また、評価手順等十分整備されていないものもあり、制度として統一的な手順を定める必要が生じ、このため、法制化について検討が進められ、政府として法案を取りまとめ、国会に提出したが、審議未了のため廃案となった。結局、59年に「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、行政措置による環境影響評価を行うこととなった。閣議決定は、行政措置とはいえ、行政における最も権威のある意思決定の方式であり、我が国における環境影響評価の歩みの中で一つの新しいスタートとしての意義がある。その後、これに基づき、行政実例が積み重ねられていった。現在までの実績は、第2-3-6表のとおりである。
なお、ここの事業の実施計画の段階での環境配慮のほか、国全体の、あるいは地球全体の開発方針の立案の段階など事業化以前の段階において環境配慮を組み込むことも重要であり、この面では、全国を対象に、環境庁において「環境保全長期構想」(61年)を策定しているほか、国土庁及び環境庁が全国の区域について国土の利用に関する計画である「国土利用計画(全国計画)」(60年)を定めている。また、地域のレベルでは、環境庁において「環境利用ガイド」をモデル的に策定しているほか、国土利用計画(都道府県計画及び市町村計画)、首都圏整備計画等の地域計画において環境に配慮するとともに、フローの汚染を防ぐだけでなくストックとしての環境の質を高めることをも意識した「環境管理計画」が一部の地方公共団体において策定されている。