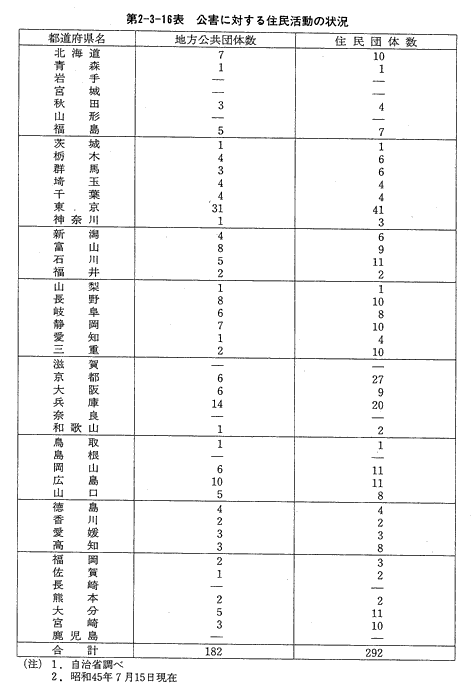
3 市民、住民団体の取組
我が国の環境問題、特に公害問題の歴史の中で、住民運動は大きな役割を果たした。激化する環境破壊によって財産や身体に被害が及ぶようになり、自らの権利を守るべく、地域住民等は、団結して様々な運動を起こしていった。特に、昭和30年代以降の産業公害が著しかった時には、大気汚染、重金属による水質汚濁等により健康被害などを被った地域住民は、工場に対する直接行動を起こし、あるいは、これが成果を収めない場合には裁判に訴えたり、行政庁や議会に陳情するなど被害や権利の回復を求めた。
公害問題に関し集中した審議が行われた、いわゆる「公害国家」が開かれるなど公害が爆発的な様相を呈した昭和45年には、全国で活動している住民団体は、自治省の当時の調査で把握できたものだけで、292団体で182市町村に及んでいた(第2-3-16表)。
住民団体の結成の端緒を見ると、? 発生した公害に対する防止対策や補償を求め結成されたもの、? 公害発生のおそれのある工場進出等に対する反対運動として結成されたもの、? 生活環境の美化など市民の意識啓発を目的として結成されたものがあったが、?及び?の類型に属するものが特に多かった。行政的な対策が未成熟の段階では、国民の権利は自らが守るしかなく、住民運動で工場の進出が阻止されたり、公害裁判で被害者である住民側が次々と勝訴するなどして公害行政に大きな影響を与えた。
例えば、古くは33年の江戸川における製紙工場の排水による漁業被害を巡って起きた漁民と工場との乱闘事件を一つの契機として「公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「工場排水等の規制に関する法律」画制定されたり、38年から39年にかけて三島・沼津地域で起こった石油コンビナート建設反対運動は、結果として、コンビナート計画を中止させ、地域開発政策に一つの転機をもたらした。また、47年の四日市公害裁判の判決では、コンビナート各企業に対し、? 共同不法行為責任の成立を認め、? 企業は、危険のあることを知り得る汚染物質の排出については、経済性を度外視して、世界最高の技術、知識を動員して防止措置を講ずべきであり、そのような措置を怠れば過失は免れないとする旨の判断が示された。この、訴訟は、他のいわゆる4大公害訴訟のうちの他の訴訟(熊本水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病)がいずれも一つの企業が重金属を排出した結果生じた公害を問題にしたものであるのに対し、コンビナートを形成している多数の工場からの排出による公害が問題とされた最初の訴訟であり、しかもばい煙による公害という全国各地に見られる公害が訴訟として裁かれた点で注目を集めた。この裁判における原告側勝訴の判決により、各地で公害による損害賠償問題が大きく取り上げられる情勢となった(第2-3-17表)。
企業の側でも、47年の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正により無過失損害責任制度が導入されたことを考え併せて、補償を巡る問題の迅速な解決が必要であるとの認識が持たれるようになり、行政上の救済制度の成立が求められるまでになった。こうした状況を背景にして、公害患者に対する民事責任を踏まえた行政救済制度として、48年に「公害健康被害補償法」が制定された。
しかしながら、公害により失われた生命、健康は、事後的な救済によって取り戻せるものではなく、公害による被害を発生させないような十分な対策を定める法律や条例の制定を求める気運が高まっていった。他方では、こうした観点から、裁判の上でも、交通施設の新設や地域開発に伴う公害や自然破壊を懸念し、これら事業の差し止めを求める訴訟も数多く提訴されたが、これまでの訴訟では、例えば、差し止め請求自体が不適法として却下されたり、請求権は認められても、要件を極めて厳格に解し、生活妨害、睡眠妨害等の身体的被害を伴わない日常生活上の被害では足らないとして請求が棄却されたりして住民側の敗訴に終わっている。
このような状況も一つの要因となり、環境破壊の未然防止は、住民が個人的な権利の侵害を予防するために起こす個々の訴訟行為によるのではなく、環境破壊を防ぐための事前調査を行ったり、その結果を事業決定に当たって考慮するなどを内容とする環境影響評価をもって行うべきとの認識が高まり、その制度化が求められるようになった。
以上のとおり、環境法制度の充実、強化に与えた住民運動の影響は極めて大きなものがあったと言えよう。
なお、現在でも、公害を発生させた企業に対する反対運動、あるいは行政に対して政策転換を要求する運動のほか、リサイクル運動、ナショナルトラスト運動、生活排水対策を推進する運動など、自らの生活の在り方を反省して環境に負荷をかけない新しい生き方を求めていく運動が各地に見られ、環境保全に係る市民運動は、多様な展開を見せている。公害がなくなり、被害の補償や権利の回復のための運動の必要がなくなって、これに費やされている市民の力が積極的に環境を改善していく運動にますます振り向けられるような社会状況が、今後に創出されるならば、持続可能な社会を作る上で一層有意義なことと言えよう。