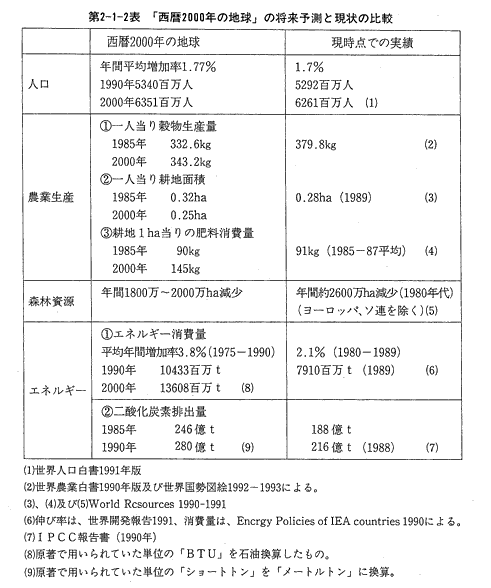
2 地球環境の未来についての予測
今日の人類の活動がこのまま趨勢的に拡大していっても、地球は、これを養い得ることができるのだろうか。また、地球は、人類の活動から生ずる廃物、不要物を受け入れることができるのだろうか。この点については、昭和46年(1971年)に発表された「成長の限界」(ローマクラブ)や昭和55年(1980年)に発表された「西暦2000年の地球」などの研究がかつて行われたことがある。これらのうち後者の予測結果の概要は次表に掲げるとおりである(第2-1-2表)。
かつてのこうした指摘は、今日では、現実への妥当性を失ったのであろうか。
国連の推計によれば、今後、世界の人口は、2000年(平成12年)には、約62億5000万人、2025年(平成37年)には約85億人で、1990年の約1.6倍となると想定されている。その後、2050年(平成62年)には100億に達し、最終的には2150年頃に116億人で横ばいになると予測されている。先進国と開発途上国で比較すると2025年までの人口増加分の約96%を開発途上国が占めることとなる。開発途上国では、食料、水、衛生施設等についての不足が既に深刻化しており、このような人口増加がこれらの国々の福祉を一層低下させるものと懸念される。
食料事情でみると、生産量全体は増加すると予測されるものの、開発途上国全体で一人当り供給カロリーが1.4BMR(基礎代謝(BMR)の1.4倍、約1520カロリー)に満たない人口が、2000年で約5億3000万人に増加すると予測されている。穀物の不足量は、1980年代前半には7000万t程度だったのが、2000年には約1億1000万tに達すると見込まれている。この予測は、穀物生産の増加を前提としたもので、このうち、単位面積当たりの収穫の向上(寄与率63%)と耕地の増加(寄与率22%)等により、現状(1986年)より3億5800万t(45%増)の収穫量増加があることになっている。耕地の増加は、面積に換算すると8300万haの増加であるが、この増加は、差引勘定による純増であり、農地として開拓すべき土地は更に広い。処女地が農耕地に開拓される一方で、劣悪となった農地は放棄されている。放棄される農地については、土壌の流出によって、年間700万〜800万haが失われ、150万haが、浸水、塩類集積、アルカリ化によって失われているとする推計がある。他方、耕地の増加分のうち83%はラテンアメリカ及びサブサハラアフリカで占めることになると想定される。これは、耕地の熱帯林地域への拡大を意味することになる。ちなみに、国連食糧農業機関(FAO)によれば、各年の農業用地の拡大、燃料用木材の伐採等による熱帯林の減少面積は、現状で毎年1700万haと推定している。適切な措置を講じていかないと熱帯林の減少を通じて天然資源全体の劣悪化を招くことになる。また、地球温暖化の関係でみると、森林は、大気中の二酸化炭素を吸収し、幹や枝、根、土壌中に貯える働きを持っているが、森林が失われると、この膨大な吸収固定能力が失われるばかりでなく貯えられていた炭素を再び大気中に二酸化炭素として放出することになる。このような放出量は、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の報告書(平成2年)では、年間17億t(1985年)に及ぶものと推定されている。人口増加の圧力が高まったり、一層の食料事情の改善を目指そうとする場合、環境への圧力は以上の予測以上に更に増すことになる。
また国立環境研究所を中心に開発しているシミュレーションモデルを用いて予測された今後の二酸化炭素排出量を見てみよう。この結果によると、二酸化炭素排出量は、特別の対策がないと2025年(平成37年)で1985年(昭和60年)の1.4倍から2.4倍、2100年で2倍から7倍の範囲で増加する。この排出量の伸びにより大気中の二酸化炭素濃度は増加し、来世紀末には3から5℃の気温上昇が予想される(第2-1-3図)。
ちなみに、前掲のIPCC報告書によれば、地球温暖化の影響は、多岐に渡ると推測されている。
気温の急速な上昇により、植生が影響を受け、半乾燥地帯などで森林が減少し、また、気温だけでなく、気候も大きく変化し、陸上生態系については、気候変化についていけない動植物のいくつかの種は絶滅の危機に瀕することが予想されている。大部分の地域で降水量が増加することが予想されているが、蒸発量も増加する。こうした降水の変化からアフリカサヘル地方のような限界的な地域では、水利用の可能性が急減すると予想される。また、中緯度、高緯度地域では積雪の地域分布やその期間が減少し、また北半球の永久凍土が著しく減少し、地形の不安定化、侵食や地滑り等が生じる。海水の膨張、陸氷の解け出しによる海面の上昇も予想されている。こうした気候の変化は、まず、自然環境に大きく依存する農業に大きな影響を与える。米国南部や西ヨーロッパのような穀倉地帯の生産が減少し、アフリカサヘル地方やブラジル等の特に環境上影響を受けやすい地域では、生産の減少を始め深刻な影響を受けることが予想される。海面上昇は、いくつかの島しょ国で居住が不可能となり、都市の低地等を脅かし、河川への海水の遡上を招き、何千万の人々が移住を余儀なくされる。降水量の増大は、河川の氾濫等の自然災害の増加を招き、農業や都市に大きな影響を及ぼす。また、降水量や気温の上昇により、病原虫やウィルスが高緯度に移動し、多くの人々の健康に影響を与える可能性がある。こうした影響は、特に、人口が集中し、衛生状態が急激に悪化しやすい大都市で大きくなると予測されている。
このように、「成長の限界」や「西暦2000年の地球」等の膨大な研究成果に基づく警告にもかかわらず、人類は、自らの手により自らの生存基盤を掘り崩す道を進んでしまう可能性を有していると言えよう。
我が国は、食料を始め、一次産品の多くを海外に依存している。世界全体の輸入量に占める我が国の輸入量の割合を見ると、石油で13.4%(昭和63年)、穀物で11.7%(平成元年)、木材で26.3%(平成元年)など、海外依存度は極めて高い。海外のこととはいえ、これら一次産品の生産環境が悪化することは日本にとっても大きな影響を及ぼす。例えば、畜産濃厚飼料の原料となるとうもろこしの作柄が、米国の干ばつで極端に悪化した昭和58年には、商品価格が高沸し、我が国にも大きな混乱がもたらされたことは記憶に新しい。