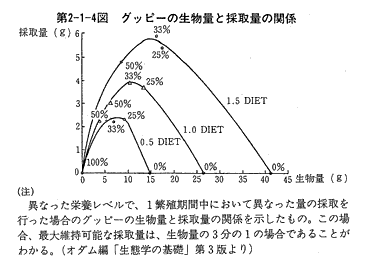
3 環境と持続可能性
以上のような人類社会の「持続可能性」に関する危機を克服し、人類社会の永続的な発展を保証するための政策の理念として、「持続可能な開発」の考え方が地球環境問題に関する様々な国際会議で使われるようになった。
「持続可能性については、歴史的に見れば、まず、漁業資源の乱獲競争の反省から生まれた「最大維持可能生産量」の理論を通じて、資源利用の「持続可能性」について論じられるようになったのが最初である。ここでの「持続可能性」の概念は、魚類等の特定の再生可能な生物資源に関し、その収穫には一定の物理的限界があるため、一定量の資源のストックから生み出される純再生産量だけが利用可能であって、それ以上の利用を行えば、ストックが減少し、資源の枯渇を招くということを前提に論じられたものである。この概念の具体的適用には、最大維持可能生産量レベルの判定が科学的に難しいこと、対象となる特定生物の利用が他の生物資源を含む生態系全体にどのような影響をもたらすかが考慮されていないことなどの問題点があるが、地球の環境をどう管理すべきかに関して議論する上で良い接近方法を提供するものとなった。次に示す図は、グッピーという魚を例にして、実験的に求めた生物のストック量とフローとして維持可能な生産(収穫)量との関係を示したものである(第2-1-4図)。
地球環境と人類活動との間の今日の関係は長く維持できるものではないとの懸念を世界的に巻き起こすきっかけの一つとなったのが、前記のローマクラブの「成長の限界」や「西暦2000年の地球」であった。人類の未来に対する深刻な懸念が次々と出される中で、こうした懸念を生じないような政策の方向が提案されるようになった。それが、「持続可能な開発」という考えである。この言葉が、世界的に普及した文書の中で初めて使われたのは、国際自然保護連合(IUCN)が、国連環境計画(UNEP)及び世界自然保護基金(WWF)の協力の下に、昭和55年(1980年)に作成した「世界環境保全戦略(WorldConservation Strategy)」の中であった。
さらに、「持続可能な開発」という言葉を一般的に定着させたのは、UNEPにおいて我が国がその設置を提唱して発足した「環境と開発に関する世界委員会(WCED)」により、昭和62年(1987年)に公表された報告書「われら共有の未来(OurCommon Future)」である。この報告書は、国際的に高い評価を受け、昭和63年(1988年)、この報告書を歓迎し「持続可能な開発」が、国連、各国政府並びに民間の各種機関・組織及び企業にとって中心的な指導原則となるべきことなどの点を内容とする決議(42/187)が国連総会で行われた。同年にトロントで開催された先進7カ国の首脳会議でも、同じく高く評価された。
WCEDのこの報告書によれば、「持続可能な開発」は「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことがないような形で、現在の世代のニーズも満足させるような開発」と定義されている。この概念は、次の二つの鍵となる考え方の上に成り立っている。
? 貧しさを改善しないとかえって環境破壊が進むこと
? 環境が人類を養う能力には、長い目で見れば限りがあること。
第1点に関連して、世界中の貧困状態の人々が人間としての基本的なニーズを満たせるような「開発」が行わなければならないということになる。なぜなら、貧困は、環境破壊の大きな原因となるためである。すなわち、貧しい人々は、生存のために農業用地や燃料採取のために森林を伐採し、家畜の過度の放牧を行ったりして、環境資源をその再生能力の限界を超えて消費し、また、こうした生活の基盤である環境資源の過剰消費が、一層の貧困をもたらすといった悪循環が生まれるからである。なおここでいう「開発」は、従来の国民所得の指標(例えばGNP)で表されるよりも広い概念を含むものであるとされている。経済の量的拡大だけでなく質的向上も含むものであって、所得の公平な分配、教育、健康、きれいな空気、水、自然の美しさの保護といった経済外の価値と結び付いた人間の欲求や福祉をも考慮したものでなければならないとされている。
また、第2点に関連して、環境汚染を防止することは当然のこととして、「開発」による資源の利用は、現在の世代と将来の世代の公平性の確保の観点から、、環境の受容能力の範囲で行われるべきこととなる。例えば、森林や漁業等の再生可能資源であれば、将来の世代に残すストックを減少させない水準で利用していくこと、石油、鉱物等の非再生可能資源であれば、代替資源の利用技術を開発し、普及できるような可能性が高まるよう、ゆっくりとした速度で開発し、消費していくことが望ましいのである。
持続可能な開発の考え方とその具体的な実現方策については、後術の第4章に見るとおり、公平性の概念、特に世代間の公平性の具体的意味は何か、将来の世代のために残すべき環境資源の質や量をどう評価するといった問題についての検討が必要である。しかし、この考え方は、第1に、貧困を脱しようとして行われる近視眼的な経済活動がかえって環境を破壊し、経済そのものにとっても有害であること、第2に、先進国で営まれている比較的裕福な生活は、それを維持するに必要な費用を正確に負担したものではなく、その費用を将来世代への言わば「つけ回し」をして賄われているものであることを人々に気付かせた点で大きな意義を持つ。さらに、現在に生きる世代が、特に先進国で比較的に裕福な生活を送っている人々が、将来世代の生活基盤を確保するよう考慮を払い、必要な自制を行うことが、地球の破局を避ける道であることを骨太に訴えた点も、単なる終末論的な悲観論と異なり、人々を大いに勇気づけるものであった。我々には、この「持続可能性」という考え方を政策の実行の中で活かし、肉付けしていくことが求められている。以下では、我が国の事例及び我が国に係わりの深い事例に即して、我々が目先の経済的利益を追求するために、環境破壊を起こすようなことをどれだけなくしてきたか、将来世代のために残されるべき環境のストックを我々がどれだけ保護してきたか見ることとしよう。