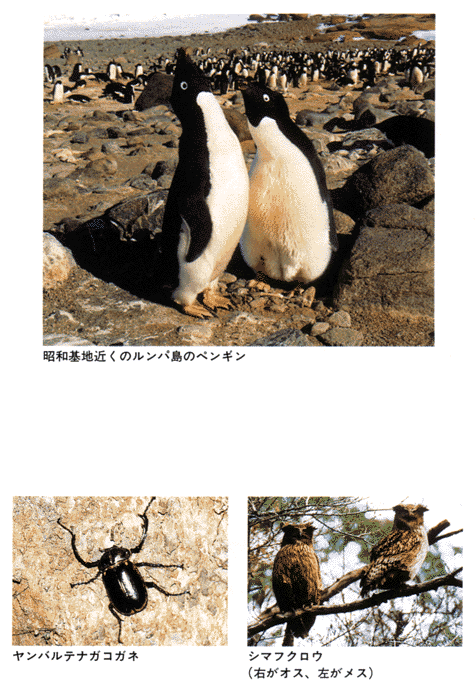
4 南極
1991年(平成3年)10月、スペインのマドリッドにおいて、「南極の環境保護に関する議定書」が採択され、南極の環境保護について新たな枠組みが作成された。以下、南極の環境について紹介する。
南極は南極条約等において、南緯60°以南の地域とされ、総面積5,250万km
2
、そのうち陸地は1,400万km
2
を占め、そのうち南極大陸は1,250万km
2
である。南極の平均気温は-50℃であり、南極大陸自体の98%は陸氷に覆われ、その平均的な厚さは2,450mにもなる。南極における人間活動は、こうした厳しい環境や、南極条約による制限によって、調査、研究活動に限られている。
こうした厳しい南極環境にも生態系が形成されている。夏の間に氷の間からわずかに現れる陸地に、藻類を中心とする生物が生息し、生態系を形成する。また、南極の陸地を繁殖地とする鳥類も存在する。南極の陸上には種子植物が2種知られているほか、菌類、藻類、苔類等が存在する。南極の陸上で繁殖する鳥類はペンギン類をはじめ15種ほど知られている。哺乳動物は陸上には生息していない。一方南氷洋には哺乳類としてアザラシ類が6種、クジラ類が10種生息している。海鳥では、南極の陸上で繁殖する15種を含め、100種ほど生息する。また、魚類やオキアミなども数多く生息している。こうした生物は、南極の厳しい環境にもかかわらず固有かつ貴重な生態系を構成している。
一方、南極は、「科学の大陸」とされているように、気象観測や地球物理学といった研究の場として貴重な存在である。既に述べたようにオゾン層の破壊についての研究が南極における観測データをもとに進められている。
こうした南極の環境は、南極条約が南極における人間活動をほぼ科学調査のみに限ってきたことによって保全されてきた。しかし、1991年(平成3年)に、南極における鉱物資源活動のモラトリアムが切れ、また、南極観光が年間約3,000人を受け入れるなど伸びてきており、また、各観測基地からの廃棄物の取扱の問題が大きくなってきた。こうした状況を受けて、1991年(平成3年)10月に新しい南極環境保護の枠組みとして「南極の環境保護に関する議定書」が南極条約の下、採択された。同議定書は、南極は、科学的な観測、研究の場として、そして人間の開発の手の及んでいない唯一の大陸として、その貴重な自然環境、生態系とともに今後とも保護されるべきこと等を定めている。