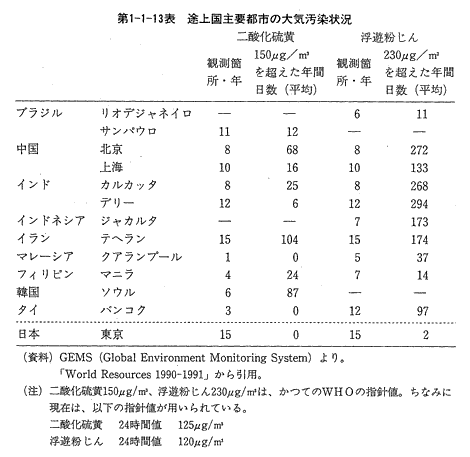
8 開発途上国の公害問題
開発途上国、特に工業化を進めている国において、大気汚染、水質汚濁等の公害問題が深刻化している。特に人口、経済活動が集中する都市において公害が著しい。
アジアの途上国を中心とした世界各主要都市の大気汚染の状況をみよう。代表的な大気汚染物質である二酸化硫黄について、150μg/m
3
を超える年平均日数は、1988年(昭和63年)発表のデータでは、北京で68日、ソウルで87日、テヘランでは104日となっている。また、同じく浮遊粉じん(ハイボリュームエアーサンプラーによる値)については、230μgm
3
を超える年平均日数は同じく1988年公表のデータでは、北京で272日、カルカッタで268日、テヘランで174日となっている。比較のために東京の値を示すと、同じデータによると、二酸化硫黄については0日、浮遊粒子状物質については2日であり、いかに途上国の大都市が大気汚染にさらされているかが分かる(第1-1-13表)。
我が国の隣国でもある中国を例に取ると、1980年代の二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、降下ばいじんの全国平均値は第1-1-31図のとおりであり、改善はみせているものの我が国の状況と比べるとかなり状況は悪いと言えよう。
河川の汚濁について見よう。世界の主要な9河川について、1979-81年から1985-87年にかけて(昭和50年前後から同55年前後まで)のBOD中央値の変化を見ると、メキシコのレルマ川、インドのサバルマーティ川(アーメダバード)の汚染の進行が著しく、また、マレーシアのクラング川のように汚染が急速に進行している河川も見られる。汚染の著しいサバルマーティ川の測定地点が人口206万人のアーメダバードであることから分かるように、都市内での汚染状況は、ここに挙げた河川でもさらに高いものと思われる(第1-1-14表)。
マレーシアのクラング川は、繊維産業、冶金工場、蒸留工場、タピオカ工場、ココナッツ工場といった、中小の古い工場によって汚染されており、アンモニア態窒素等でもマレーシア政府の定める暫定水質基準値を超えている。パキスタンのカラチでは、町を流れる川へ一日当たり237トンのBODが流れ込むが、その84.5%が約800の工場からの無処理排水によるものとみられている。
これらの開発途上国の公害は、途上国の社会経済状況や国際経済とも深く関連しあっている。こうした背景などについては、第3章で述べる。