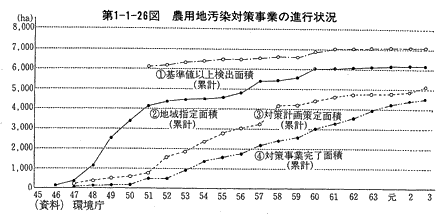
3 土壌、地盤
(1) 土壌
土壌汚染は、公害の中でも最も歴史の旧い汚染の一つであり、渡良瀬川流域の農用地汚染は明治時代に既に社会問題化している。戦後も神通川流域などで、カドミウム等による農用地汚染が続出し、大きな公害問題を引き起こした。これを受けて、農用地については「農用地の土壌汚染の防止等に関する法律」に基づき、カドミウム、銅、ヒ素について基準値を設け、これを超えて汚染された農用地について対策事業を行うこととなっている。平成2年度までに行われた調査により、基準値を越える農用地は延べ7,050haであり、内6,150haが対策地域として指定され、事業が進められている(第1-1-26図)。
農用地以外の土壌についても、特に都市再開発などの際に、工場や研究所の跡地で有害物質による汚染が明らかになる例が頻出している。このような市街地土壌汚染事例は、概ね昭和50年以降に顕在化し、これまでに地方公共団体等を通じ環境庁で把握している事例は72件である。これらについて汚染原因別にみると、製造工程等の施設の破損にともなう漏出、廃棄物処理法施行前の工場の敷地内での不適正な廃棄物の埋立、汚染原因物の不適切な取扱等によるものが多い。汚染源となった事業種では、電気メッキ、熱処理業、化学工場が多く、汚染物質は六価クロム、水銀、鉛、カドミウム等が多くなっている(第1-1-7表)。この事態を受けて、平成3年8月に農用地、非農用地を通ずる土壌汚染に係る環境基準が設定された。
なお、アメリカでは、規制が緩かった時代の廃棄物最終処分場跡地の汚染や工場から漏出した有機溶剤による土壌の汚染が問題となっている。
(2) 地盤
地盤の沈下は、地下水を過剰に採取することによって生じる。一旦沈下した地盤は元に戻らず建築物への被害などが生じる。古くは戦前、東京都江東区や大阪市西部で沈下が見られ戦後の一時期の経済の停滞により一旦は沈静化したものの昭和40年代には全国的に発生し、年20?を越える激しい沈下もみられた。その後地下水採取規制を行い、地盤沈下は沈静化の方向に向かっている。しかし、平成2年度においても年間4?以上沈下した地域が5地域、14km
2
、2?以上沈下した地域が18地域、360km
2
あり、特に、関東平野北部、千葉県九十九里平野、佐賀県筑後・佐賀平野の沈下が大きい(第1-1-27図)。