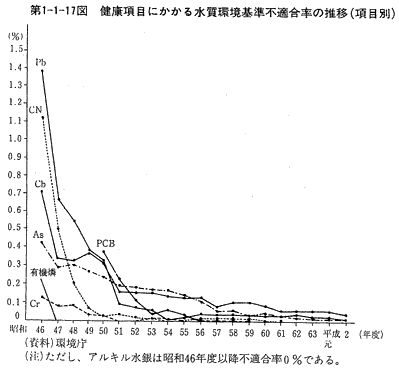
2 水質
(1) 河川水及び海水中の重金属、有害化学物質など
人の健康に害を及ぼす水質汚濁物質のうち、我が国では、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム、(六価)、ひ素、総水銀、アルキル水銀、PCBについて、海域や河川などにおいて、人の健康を保護する上で維持することが望ましい環境濃度として環境基準を設定し、また、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては水質環境目標が設定されている。これら環境基準等を達成、維持し、水質の汚染やこれに伴う公害を防ぐため、「水質汚濁防止法」等の規制が設けられている。
平成2年度全国公共用水域水質測定結果によると、人の健康に係わるカドミウム等の健康項目については、その環境基準を越える検体数の調査総検体数に対する割合は、0.01%と非常に低く、20年前と比較して大幅に減じ、前年度と比較するとほぼ同じであった。また、平成元年4月に水質環境目標が設定されたトリクロロエチレンお及びテトラクロロエチレンについては、その水質環境目標を越える検体数の調査総検体数に対する割合は0.04%と非常に低かった(第1-1-17図)。
「水質汚濁防止法」による規制などが行われていない化学物質についても環境汚染の未然防止の観点から水質中の残留状況について測定が行われている。化学物質環境安全性総点検調査では、水質についても特定の排出源の影響を直接うけない水域(河川、湖沼、海域)の水質中における化学物質の残留状況を把握することを目的に、毎年異なる物質について調査を実施しており、平成2年度は調査した22物質中アニリン等8物質が水中から検出されている。今後一定期間をおいて環境の調査を行い、その推移を監視する必要のある物質はあるものの、直ちに問題を示唆するものではないと考えられる。さらに環境に残留することが確認されている化学物質について、環境汚染の経年監視を目的とする水質モニタリングを行っており、ジクロロベンゼン類等が検出されているため、今後ともモニタリングを継続する必要がある。
また、「化学物質の審査及び規制等に関する法律」の指定化学物質等についても水域(河川、湖沼、海域)の水質中の残留状況を調査しており、有機スズ化合物等が検出されているため、今後とも引続き監視する必要がある。
各先進国の主要河川の鉛及びカドミウムによる汚染の状況は第1-1-4表のとおりであり、特に鉛についてはほぼ各国とも改善を見せている。
(2) 河川水及び海水中の有機物質など
生活環境に係わる水質については、我が国では、河川においては生物化学的酸素要求量(BOD)など5項目、湖沼においては、化学的酸素要求量(COD)など5項目と全窒素、全りん、海域はCOD他の5項目の濃度等について、人の生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境上の条件として環境基準が定められている。これら生活環境項目に係わる環境基準については、水域ごとの利水状況などを踏まえた類型などが設けられて、個々の水域に対し、いずれかの類型の環境基準をあてはめることとなっている。こうしてあてはめられた環境基準の達成、維持に向け、水質汚濁防止法等による排水規制等の対策が行われている。水域の環境は有機物の汚濁によって強く影響を受けることから、有機物による汚濁の代表的指標であるBOD、CODについて生活環境にかかる水質状況の評価を行うと次のとおりである。
BODまたはCODの環境基準の達成率をみると、昭和49年において環境基準を達成している水域は全体の54.9%であり、水域別では河川51.3%、湖沼41.9%、海域70.7%という状況であった。その後、環境基準の達成率は総体的にはわずかずつであるが、上昇してきており、平成2年度では、水域全体で73.1%、水域別にみると河川73.6%、湖沼44.2%、海域77.6%となっている。湖沼については改善はみられるもののなお低い達成状況にある(第1-1-18図)。
湖沼や内湾といった閉鎖性水域の水質では、依然環境基準の達成率は低い状況にある。霞ヶ浦(茨城県)、諏訪湖(長野県)、琵琶湖(滋賀県)などの代表的な湖沼において、CODにかかる環境基準が達成されていない。また、富栄養化の進行により、水道水の異臭味、浄水場の濾過障害、漁業への影響、透明度の低下といった問題も生じ、湖沼の水質が損なわれている。現在、上記の3湖沼を含めた9湖沼については、「湖沼水質保全特別措置法」に基づき指定され、対策が講じられているが、こうした指定湖沼の水質の状況は、改善を示しているものの、環境基準の達成にはなお至っていない。
閉鎖性海域については水質汚濁防止法等に基づき、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について、CODに係る水質総量規制が実施されている。この3海域の環境基準(COD)の達成率を見ると、特に東京湾及び伊勢湾については、なお海域全体に比べて低い状況にあり、瀬戸内海でも大阪湾などは、低い状況にある。また、このような閉鎖性海域では窒素、燐などの栄養塩類の流入により、富栄養化が生じており、赤潮や青潮の発生により、漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭、海浜の汚染といった状況も生じている。このように閉鎖性海域の水質は依然悪い状況にある。この理由は、閉鎖性海域では外部との水の交換が悪く、汚染物質が蓄積しやすいことによる(第1-1-19図)。
また、汚濁の著しい都市内河川の状況も依然改善が進んでいない。都市内河川とその他の主要河川の水質の状況をBODでみると平成2年度においても以前都市内河川の汚濁の状況が著しい。これらの水域の汚染原因に少なからぬ割合を占める生活系の負荷について対策を一層推進する必要がある(第1-1-20図)。
先進国における主要河川、主要湖沼の過去20年間における水質の状況は、第1-1-5表のとおりであり、経年変化をみると水質が改善していない河川も見られる。
(3) 周辺海洋の海水及び底質
我が国の周辺海域で確認された海洋汚染の件数は、昭和48年の2,460件から平成2年には993件に低下した。これは、その大部分を占めていた油による汚染事例が2,060件から583件に低下したことによる。一方、廃棄物投棄など油以外の汚染は、昭和48年の154件から平成2年には354件に増加している(第1-1-21図)。
「海洋汚染防止法」に基づき、廃棄物の海洋投棄は原則的に禁止され、特定の廃棄物に限り、その性状に応じて定められた海域(例えば房総沖、四国沖、三陸沖、日本海)において、排出方法に関する基準に従って行う排出が認められている(第1-1-22図)。海上保安庁が平成2年に実施した排出海域周辺の汚染状況の調査によれば、状況はほぼ従来と同様のレベルであり、特に汚染の進行は認められない。
海上保安庁の調査によると漂流、漂着浮遊物のうち、廃油ボールの状況は、昭和50年代半ばから急激に減少しているが、漂流廃油ボールは南西諸島、本州南海岸で多く、漂着廃油ボールでは、南西諸島、本州南海岸、九州西海岸が多い。また、環境庁は房総沖、四国沖、南西諸島、山陰沖において、漂流物の調査を行っているが、その状況は第1-1-23図のとおりであり、かなりの人工物の漂流が認められる。
水産庁が平成2年に実施した北太平洋全域の海面浮遊物の分布状況調査によると、浮遊汚染物としてはプラスチック類が半数以上を占め(55.4%)、中部太平洋、日本近海に多い。
底質には、比較的多くの化学物質が蓄積していることが考えられる。このため、化学物質環境安全性総点検調査では、特定の排出源の影響を直接受けない水域(河川、湖沼、海域)の底質中における化学物質の残留状況を把握することを目的に、毎年異なる化学物質について調査を実施している。平成2年度には、調査した22物質中、アニリン等10物質が底質から検出されている。今後一定期間をおいて環境の調査を行い、その推移を監視する必要がある物質はあるものの、直ちに問題を示唆するものではないと考えられる。さらに環境に残留することが確認されている化学物質については、環境汚染の経年監視を目的とする底質モニタリングを行っており、クロルデン類及びDDT類等が検出されているため、今後ともモニタリングを継続する必要がある。
また、ダイオキシン等の非意図的生成有害物質及び「化学物質の審査及び製造業の規制に関する法律」の指定化学物質等についても、水域(河川、湖沼、海域)の底質中の残留状況を調査しており、ダイオキシン類及び有機スズ化合物が検出されているため、今後とも調査を継続する必要がある(第1-1-6表)
(4) 地下水
地下水は、良質な水資源として幅広く利用されており、現在でも都市用水の約3割は地下水に依存している。ところが、昭和50年代からトリクロロエチレン等による地下水汚染が顕在化し、広範な汚染が見られるようになり、地下水の質についての懸念が広まっている。これを受けて、「水質汚濁防止法」により有害物質を含む水の地下浸透が禁止されるとともに、地下水の常時監視を実施することになった。平成2年度のモニタリングによればトリクロロエチレンについては0.8%、テトラクロロエチレンについては1.4%、鉛については0.03%、六価クロムについては0.03%、ヒ素については0.2%、総水銀については0.1%、1,1,1-トリクロロエタンについては0.02%、四塩化炭素は0.05%の井戸で、評価基準等を超えていた。汚染範囲を確認するための調査である汚染井戸周辺地区調査や、過去の汚染の継続的な監視等を行う定期モニタリング調査では、さらに高い汚染が見られている。基準を超過した井戸には飲料用の井戸も含まれており、汚染対策が行われているが、新たにこうした井戸を生じさせないよう未然防止対策を徹底する必要がある。
(5) 酸性雨
酸性雨は、水素イオン濃度(pH)5.6以下の雨であり、硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質が大気中で酸化され雨に溶け込むことによって生じる。ちなみに、我が国の国設環境大気測定局(バックグラウンド局)における大気中の硫酸塩、硝酸塩の測定結果では、硫黄酸化物の排出量の減少にともない、硫酸塩は大幅に減少しているが、硝酸塩では減少の傾向は見られない。酸性雨は雨粒として地表に降ってくるほか、霧滴として空気中を漂うことがある。霧状の場合は酸性霧と呼ばれる。
酸性雨は多様な影響を我々の生活や生態系に及ぼす。酸性の雨や霧に直接さらされることによる樹木の衰退、土壌の酸性化による生態系、森林への影響、酸性雨の流入による湖や沼、河川の酸化、これらの湖沼等の生態系の魚類などの減少である。また、都市の文化財、構造物の腐食といった影響も生じる。
我が国では、昭和58年から62年まで第1次酸性雨対策調査を実施した。その結果、年平均でpH4.4-5.5の酸性雨が観測されたが、湖沼の水質では、ほとんどがpH7付近に分布しており、土壌についても酸性化の傾向は見られなかった。しかし、酸性の雨による樹木への直接的な被害が生じている可能性は否定できず、湖沼、土壌が今後徐々に酸性化することも考えられるため、被害の未然防止を目的に現在第2次の調査を平成4年度までの計画で実施している(第1-1-24図)。
諸外国の酸性雨と比較すると、pHの値では内外の差は大きくないが、欧米等では既に深刻な被害が生じている。現在、酸性雨の被害が深刻な地域は、ヨーロッパ、北米、中国大陸であり、広範な地域で酸性度の強い雨が降っており、(第1-1-25図)森林、湖沼への被害が生じている。これは、工場から排出される硫黄酸化物対策の遅れによるものが大きい。欧州では、1985年(昭和60年)のヘルシンキ議定書により、また、北米ではアメリカ合衆国が、1991年(平成3年)に大気浄化法(CleanAir Act)を改正し、抜本的な酸性雨対策として硫黄酸化物排出量の削減に取り組むなど、各国は対策強化を進めている。