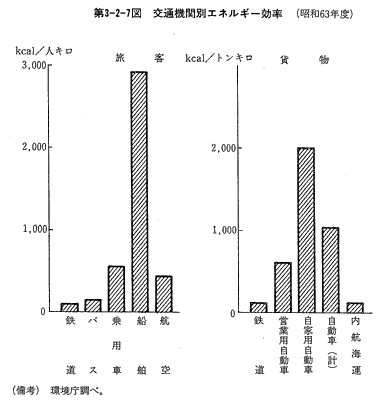
3 多様な交通手段の利用等による二酸化炭素の排出抑制
(1) 交通機関単体からの二酸化炭素排出量の減少
自動車、鉄道、船舶、航空機等の交通機関単体からの二酸化炭素排出量を減少させるための技術の開発・普及が必要である。なかでも交通機関からの二酸化炭素排出の大部分を占めているのは自動車であり、自動車単体からの二酸化炭素排出量を減少させていくことが、運輸部門における二酸化炭素対策の最重要課題である。このため、自動車については、軽量化、走行抵抗の低減により燃費改善を進めるとともに、ハイブリッドエンジン、超稀薄燃焼方式、回生エネルギー利用技術の開発・導入を積極的に推進することによって、二酸化炭素排出量を減少させる努力がなされている。また、二酸化炭素排出量の少ないエネルギーの使用も促進し、電気自動車等の低公害車の導入を積極的に推進するための援助措置も講じられている。さらに、交通機関の間の連携を図りつつ、自動車交通需要を軽減する方策の検討が必要となっている。
(2) 各交通手段別のエネルギー効率
二酸化炭素の排出はエネルギー効率と関係する。交通手段のエネルギー効率は、ロードファクター(旅客においては乗車密度、貨物においては積載効率)、輸送機器の大きさ等により異なるため、一概には言えないが、昭和63年度実績を全体でならしてみると、旅客部門では、鉄道100kcal/人キロ、自家用車で527kcal/人キロ、営業用バスで173kcal/人キロであり、貨物部門では、鉄道121kcal/トンキロ、内航海運120kcal/トンキロ、営業用自動車613kcal/トンキロ、自家用自動車2,009kcal/トンキロとなっている(第3-2-7図)。
(3) 旅客及び貨物別のエネルギー消費の傾向
旅客及び貨物について、輸送シェアとエネルギー消費の割合をみると、自動車は、旅客の49.3%を運び、76.0%のエネルギーを消費し、貨物では51.0%を運び、87.5%のエネルギーを消費している(第3-2-8図)。
自動車の他の交通手段に比べエネルギー効率が良くないが、自動車の輸送量に占める割合は増大している。
旅客及び貨物の推移をみると、貨物は石油ショックの時に輸送量が低下して全体としてもそれ以降低い伸び率となった。経済活動が好調となったここ2〜3年は、経済成長以上の伸びを示している。(第3-2-9図)。経済のサービス化は、商品の軽薄短小化や高付加価値化などにより交通量当たりの価値が上昇すること、情報の高度化により物流や人流の代替が行われて物と人の移動が相対的に少なくなることなど、物流の減少要因として働く一方で、宅配便の成長などが物流の増加要因として働いているものとみられる。(第3-2-10図)。
他方、旅客部門をみると貨物部門でみられるような石油ショック時の輸送量の低下はみられない。全体としても輸送量の低下はみられず、燃料価格の上昇や経済停滞の影響をあまり受けなかったといえる(第3-2-11図)。
(4) 貨物輸送における交通機関の間の連携
ア モーダルシフト(鉄道輸送、内航海運等への誘導)の必要性
現代社会では、自動車は人々の暮らしの中に浸透している。我が国の年間貨物輸送量の総量は、約4,800億トンキロ、これを昭和63年度の輸送トンキロペースのシェアでみると、トラックが51%、内航海運が44%、鉄道が5%となっている。45年度のシェアはトラックが39%、内航海運が43%、鉄道が18%であり、また45年度を100とすると、全体が138、トラックが181、内航海運が141、鉄道が37となっており、トラックが着実に伸びているのに対し、内航海運は51年、52年にシェアのピークを迎えてから減少傾向にあり、鉄道は大きく減少している(第3-2-12図)。
また、これを貨物の距離帯別でみると、近距離では自動車のシェアが圧倒的に多いが、長距離になるにしたがって、内航海運、鉄道のシェアが高くなってきている(第3-2-2表)。内航海運や鉄道は、大量輸送機関として長所をもっているが、トラックはドア・ツー・ドアの輸送が可能で機動性がある。特に都市内の輸送は、トラックなどの自動車に頼らざるを得ない。
二酸化炭素の排出についてみれば、運輸政策審議会答申によれば、トンキロ当たりの二酸化炭素の排出量(昭和63年度)は、トラックが370g、内航海運が35g、鉄道が24gで、トラックは内航海運の10.6倍、鉄道の15.4倍とされている(第3-2-13図)。
したがって、それぞれの交通手段の特性を生かしつつ、可能な限り二酸化炭素排出量を抑制していくためには、輸送機関の間の連携を図りつつ、自動車交通需要を軽減する方策を検討し、二酸化炭素排出の少ない交通体系の形成を図ることが必要であり、貨物輸送については、中長距離の物流拠点間の幹線輸送において、積極的にモーダルシフト(鉄道輸送、内航海運等への誘導)を図るとともに、トラック輸送においても、営業用トラックの利用の促進、共同輸送の推進、情報システム、集約的物流拠点の整備等を推進することにより、輸送効率の向上を図ることが重要である。
モーダルシフトを行っていくためには、鉄道、内航海運とトラックとの協同一貫輸送を推進する必要があり、所要の政策的誘導と、モーダルシフトの受け皿となる鉄道、内航海運の基盤整備を図ることが重要である。
イ 鉄道へのモーダルシフト
鉄道による輸送のほとんどは、日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)によって行われている。JR貨物の輸送量は、昭和61年の200億トンキロを底に増加しており、平成元年では247億トンキロとなっている。JR貨物の主要物資輸送量の推移をみると、石油、セメント、石灰石等が減少傾向にあるのに対し、コンテナが増加している(第3-2-14図)。
コンテナの増加は、モーダルシフトの可能性を示唆するものであるが、その推進のためには、荷物のトラックから鉄道への円滑な移動が必要である。このため、次のような工夫がなされている。
? ビギーパック輸送:集配用4トントラックをそのまま貨車に積載して輸送する方法。トラックはJR貨物のターミナルまで自走して貨車に乗り、運転手はそこで降りてトラックは目的地のJR貨物のターミナルへ行き、目的地で運転手が乗り込んで最終目的地へ行くというものである。列車のトンネル通過等に支障をきたさずにできるだけ多くの荷物を運べるよう、トラックの荷台を丸くした特別仕様車が使われている。現在12の区間で行われて、順調に増加しており、平成元年の輸送トラック台数(往復)は約5万台、平成2年10月の1日の輸送トラック台数(往復)は、300台となっている(第3-2-15図)。さらに10トントラックを輸送できるよう低床コンテナ貨車の開発が行われている。
? コンテナの改良:出荷の積もおろしが容易にできるような工夫や、生鮮食品輸送のためのクールコンテナなどの開発を行い、また、トラックと列車との連携が円滑にいくような配慮もなされている。全国145か所の駅でコンテナ貨物を取り扱っており、全国的ネットワークを形成している(第3-2-16図)。さらに、海上コンテナの大型化に伴い、船舶との協同一貫輸送を図るため、低床コンテナ貨車の開発が行われている。
? スライド・バンボディ・システム:トラックの荷台部分(バンボディ)をそのままコンテナ貨車にスライドさせて積み替える方法。運転手が手作業で行えるため、フォークリフト等の荷役機械を必要としない省力システム。
また、モーダルシフトが軌道に乗っていけば、鉄道貨物の輸送能力を増強する必要が生じる。このため、JR貨物において、現在の20両編成から32両編成へのコンテナ列車の長編成化に必要な基盤の整備の推進と、1,600トンの牽引が可能で、最高速度120km/hの高速大出力機関車の開発等を行っている。
ウ 内航海運へのモーダルシフト
海運は長距離運送に強みをもっており、距離帯501km以上の輸送についてはトラックを上回る貨物を運んでいる。トラックから内航海運へのモーダルシフトを進めるため、自動車をそのまま積み込める内航ローロ・オン・ロールオフ船や内航コンテナ船、長距離フェリー等の整備が必要である。
また、新型式超高速船(テクノスーパーライナー)を活用した物流システムの検討も長期的課題として推進していく必要がある。現在、造船7社によって設立された「テクノスーパーライナー技術研究組合」で、速力50ノット(時速93km)、貨物の積載重量1,000トン、航続距離500カイリ(約930km)以上で荒れた海でも航海できる貨物船(テクノスーパーライナー)を開発している。従来の貨物船の速力は12〜20ノットで、テクノスーパーライナーは2倍以上の速度で航行することになる。
(5) 旅客輸送における交通機関の間の連携
ア 乗用車と公共輸送機関の連携
我が国の年間輸送人員は、約680億人、これを昭和63年度の輸送人キロベースのシェアはでみると、バスが10.7%、乗用車が48.3%、鉄道が36.3%となっている。45年度のシェアは、バスが17.5%、乗用車が30.9%、鉄道が49.2%であり、また45年度を100とすると、63年度は全体が167、バスが104、乗用車が257、鉄道が125となっている。自動車と鉄道のシェアは、自動車の拡大傾向が続き、また、自動車における乗用車の割合は着実に増加している(第3-2-17図)。
我が国の旅客輸送は、大都市では比較的公共輸送機関の利用が多く、郊外や地方都市では乗用車の利用が多いという傾向がみられる。
旅客輸送については、鉄道、バス、新交通システム等の公共輸送機関の整備を推進するとともに、それらの輸送機関におけるサービスの向上等を推進することにより大都市圏をはじめとして公共輸送機関の利用を促進する必要がある。
イ 自転車の利用の促進
自転車は二酸化炭素も地租酸化物も排出しない乗り物である。我が国では、自宅と鉄道駅との間の交通機関をはじめとして、自転車がよく使われている。また、最近では、交通が混雑している都心部において、ビジネスのための移動に自転車で走る光景もみられるようになっている。世界の自転車の大部分はアジアにある。中国に約3億台あり、日本は世界第3位の自転車保有国で約6,600万台である。ヨーロッパは工業国のなかでも自転車が利用されている地域で、一人当たりの自転車保有台数は、オランダ、デンマーク、フィランド、旧西独、スウェーデンの順になっている(第3-2-3表)。
我が国では、自宅から鉄道機関駅や商店街まで自転車を利用する頻度が高く、1970年代には、自転車の路上駐車や放置自転車などの問題が生じた。その後、地方自治体等の努力により駐輪所整備され、これらの問題は緩和されたが、できるだけ駅に近いところに駐輪しようとして、自転車を駐輪場に置かなかったり、災害避難所の入り口等迷惑のかかる場所に駐輪したりする例がみられる。東京郊外の都市である松戸市では、自転車の30%が1km以内の移動であるという調査結果もあり、適正な自転車の利用を促進するためには、歩ける距離は徒歩で歩くという考え方も必要になっている。
また、自転車の利用促進するためには、歩行者等に迷惑をかけず、安全に走行できる自転車道の整備が必要であり、「自転車の整備等に関する法律」に従って都市内における買物、通勤、通学等日常的交通の用に共する自転車道(A種自転車道)と、大規模自転車道のような主として屋外レクリエーションを目的とした交通の用に供する自転車道(B種自転車道)の整備が全国各地で進められている。
自転車の利用は、アジアの開発途上国にもみられるが、自転車は「小さな惑星(地球)のための乗り物」とも呼ばれており、それぞれの国において各種交通手段の中での適切な役割を担うことが望ましい。
(6) 輸送効率の向上及び円滑な走行確保
ア 輸送効率の向上
輸送効率の向上、自動車の円滑な走行によって二酸化炭素排出量を低減できる。貨物輸送におけるエネルギー消費量の構成をみると、トラックの占める割合は、自家用トラックが53%、営業用トラックが36%となっており、全体で約9わりを占めていることから、二酸化炭素排出量低減のためには、トラック輸送における輸送効率の向上を図ることが有効である。営業用トラックと自家用トラックは、それぞれの利点があり、これを反映して使用されているものと考えられるが、自家用トラックから輸送効率の良い営業用トラックへ転換することによって、トラック輸送における輸送効率の向上を図ることが可能である(第3-2-7図参照)。
自家用トラックは、営業活動と物資の配送を合わせて行うことができ、かつ、事業者の都合に応じた活動ができるという利点がある。しかし、輸送効率の面からは、営業用のトラックのように複数荷主の貨物を積み合わせることができず、かつ、片道輸送がほとんどとなってしまうため、営業用トラックより低くなる。自家用トラックから営業用トラックへの転換を図るためには、営業用のトラックが利用しやすい環境を形成していくことが必要である。「貨物自動車運送事業法」の施行により自家用トラックから営業用トラックへの転換が容易となり、その環境は整いつつあると考えられ、物流事業者側においても、複数荷主の貨物の積み合わせ運送の促進、帰り荷の確保等ができるような荷物の情報システムを確立し、物流全体の効率向上に努めることが求められる。
イ 円滑な走行の確保
さらに、立体交差、交差点改良、バイパス、環状道路等の道路整備や交通管制システム等の整備及び高度化によって、渋滞を緩和し、効率的な走行を確保することができる。近時、路上における違法駐車が実質的な道路交通容量を減少させ渋滞問題を招いている。平成2年に警視庁及び大阪府警において行われた瞬間路上駐車実態調査結果によれば、路上の瞬間駐車台数は東京23区内で約20万台、大阪市内で約20万5,000台で、このうち約9割が違法駐車であった。また、東京都と大阪府の主要交差点で実施している1日平均渋滞時間の調査結果によれば、昭和63年は東京都では5年前と比較して13.4%増、大阪府では5年前と比較して22.5%増加している(第3-2-18図)。このため、平成2年5月、交通対策本部において「大都市における駐車対策の推進について」を申し合わせ「道路交通法」及び「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が改正され、駐車違反の防止に関する規定等が整備されたほか、駐車場の整備、公共輸送機関の整備、運転者などのモラルの向上などの対策を講じ、道路交通の円滑化を図ることにしている。