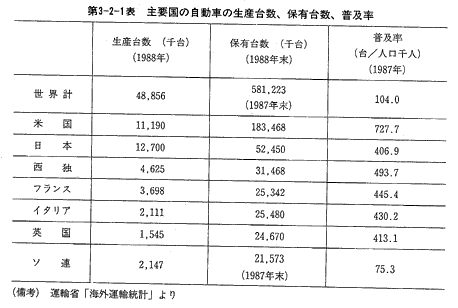
2 自動車と環境問題
(1) モータリゼーション
現代社会の一つの特徴にモータリゼーションの進展がある。
世界の自動車の生産台数は4,886万台(1988年)であり、世界の主要国の自動車の普及率は、0.73台/人と米国が最も高い普及率を示し、我が国も0.41台/人と他の主要国と肩を並べる普及率を示している(第3-2-1表)。また、開発途上国でも自動車の増加傾向がみられる。(第3-2-1図)。
我が国のモータリゼーションの進展は急速である。昭和29年度の道路特定財源制度の設立以来、道路整備は進み、38年の名神高速道路の開通を皮切りに、高速道路時代を迎えた。自動車保有台数は45年には1,900万台であったが平成元年には5,447万台と世帯数を越え、運転免許保有者数は昭和45年の2,645万人から平成元年には5,916万人と免許年齢者の60.3%が運転免許を保有している(第3-2-2図)。
我が国の自動車産業の年間生産台数は、平成元年度で1,296万台であり、この内715万台が国内で販売されている。都道府県別の自動車保有台数をみると大都市に集中している。(第3-2-3図)。また、既に自動車の廃棄が社会問題となりつつある。
現代社会では、自動車が生活の隅々にまで浸透しており、その利便性を全く無視しては我々の生活は成り立たない。そこで、自動車の利便性を享受しながら、自動車から生じる様々な問題をできる限り少なくすることによって、「環境保全型社会」を形成していくことが重要になってくる。
(2) 自動車と環境問題
ア 二酸化炭素
二酸化炭素排出量を環境庁の試算により部門別にみると、運輸部門が占める割合は、日本では23.5%、米国では29.8%、旧西独では22.8%、フランスでは34.8%、英国では25.0%となっている(第3-2-4図)。我が国では産業部門の占める割合が一番大きく、米国では国土が広く、また、自動車用のガソリンの占める割合が高いため運輸部門が最も大きい。ヨーロッパでは暖房用のエネルギーが日本より必要なこともあって概ね民生部門が一番大きくなっている。日本の二酸化炭素排出量に占める運輸部門の割合は4分の1弱であるが、運輸部門においても二酸化炭素の抑制に努めなければならない。
また、我が国の運輸部門からの二酸化炭素排出量の推移をみると、戦後一貫して着実に増加し続けており、運輸部門のシェアも増加している(第2-3-20図参照)。また、その中では、自動車が84.8%とほとんどを占めている。(第3-2-5図)。これは、産業部門の省エネルギーが石油ショックによって格段に進展したのに比べると、運輸部門では、自動車が増加し、かつ自動車の燃費の向上が交通量の急速な増加や渋滞によって相殺されて全体としての省エネルギーがそれほど進まなかったためと考えられる。
イ 窒素酸化物
大都市の大気汚染問題で、最も大きな問題は窒素酸化物による汚染である。硫黄酸化物、一酸化炭素などの大気汚染が改善されてきているのに比べ、窒素酸化物による大気汚染は依然として改善を要する状態にあり、これまでの対策だけでは、自動車排出ガス測定局を中心に環境基準の達成が困難であると予測されている。特に工場・事業場について、窒素酸化物の総量規制を行っている東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域では、多くの自動車排出ガス測定局で環境基準を上回っている(第3-2-6図)。
窒素酸化物の総量規制3地域の発生源別排出量(昭和60年度)をみると、自動車からの排出割合は東京都特別区等地域では67%、横浜市等地域では32%、大阪市当地域では47%となっている(第1-2-1図参照)。
ウ その他の環境問題
騒音については、環境基準が定められているが、道路沿道における環境基準の達成率は依然として低い状況にある。騒音や振動は、身近な環境問題として苦情も多く、平成2年7月の総理府「生活型公害に関する世論調査」をみても、40.7%の人が「自動車やオートバイによる騒音など」の公害による被害を受けたことがあると答えている。
また、積雪寒冷地域においてスパイクタイヤを装着した自動車が道路を損傷することにより発生する粉じんによる大気汚染が深刻な社会問題となっている。一部の都市では、降下ばいじんが100トン/km
2
月近くも測定されており、生活環境の悪化のみならず健康への影響についても懸念されている。この問題を解決するため、平成2年6月、スパイクタイヤの使用規制等の措置を定めた「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が制定され、スパイクタイヤを使わない脱スパイクタイヤ社会の早期実現に向けて各種施策が講じられているところである。
さらに、カーエアコン用の冷媒として使用されているCFC-12は、オゾン層保護の観点からの規制の対象となっている特定フロンの一種であるが、冷媒の入替え時、自動車の廃棄時等において大気中に放出されやすいものである。このため、回収装置の普及を含め、冷媒の回収・再利用システムの整備に努めているところである。