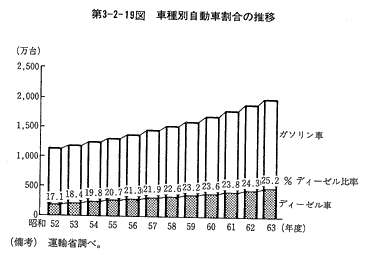
4 多様な自動車の導入等による窒素酸化物の低減
(1) ガソリン車及びディーゼル車への排出ガス規制
我が国では、自動車単体への規制が順次強化され、現在、世界でもっとも厳しいレベルの規制となっているが、この規制の効果を相殺するようなディーゼル車の比率の増大や自動車台数の増加がみられ(第3-2-19図)、大都市を中心とする窒素酸化物汚染は改善の兆しがみえていない。しかしながら、自動車単体への規制が窒素酸化物対策の基本であることには変わりがなく、今後ともこれを強化していく必要がある。
総量規制地域での自動車起因の窒素酸化物汚染を昭和63年度についてみると、例えば大阪市の試算によれば、大阪市では61%がディーゼル車によるものであるが、ディーゼル車による走行は大阪市の全自動車走行量の32%に満たない。このように、走行量に比べ窒素酸化物の寄与割合が大きい原因としては次のようなことが考えられる。
? ディーゼル車の排出ガス対策がガソリン車よりも難しいこと:自動車排出ガス規制の経緯(低減率)をみると、未規制時比べ、ガソリン乗用車で8%、ディーゼル車では21%となっているが、2.5トンを超えるトラックでは、ガソリン車では25%の削減になっているのに対し、ディーゼル車の直接噴射式のものは42%にしかなっていない(第3-2-20図)。
? ディーゼル車が増加していること:ガソリン車とディーゼル車が並存するクラスにおぇる車種の割合もディーゼル車が伸びている。特に、小型トラックで大幅に伸びており、昭和52年度から平成元年度までに、小型トラックで11.6%から53.3%へ、普通トラックで88.9%から97.9%へと増加している。また、昭和60年度から62年度までの2年間にトラックによる燃料使用量はガソリンが約13%減少しているのに対し、ディーゼル車の燃料である軽油は13%減少している(第3-2-21図)。その理由としては、ディーゼル車の方が燃費が良く、かつ、燃料が安いということがある。燃料価格差については、小売価格が平成元年度でガソリンは1リットルあたり120円程度であったのに対し軽油は70円程度と軽油の方が安くなっており、中長期的な観点からこのような経済的要素と環境との関係についても検討を加える必要がある。
? ディーゼル車の中でも直噴式エンジンが増加していること:ディーゼルエンジンには直噴式と副室式とがあり、副室式の方が窒素酸化物が少ないが最近では耐久性、燃費の優る直噴式の生産が増加している。特に中型トラックでは、昭和54年から62年にかけて3割から8割へと増加している。
? 最新規制適合車への代替に時間がかかっていること:ディーゼルトラック・バスの使用年数が延び、実走行しているディーゼル車は54年度規制以前の型のものがバスで4割以上、トラックで2割以上を占めているという状況にある(第3-2-22図)。
自動車単体規制の強化については、ディーゼル車に重点を置いて排出量の一層の削減を行う必要があり、大型ディーゼルトラックの窒素酸化物排出量の15%削減、ライトバンの乗用車並み規制をはじめとする規制強化を昭和63年から平成2年にかけて行っている。また、昭和63年12月には、ディーゼル乗用車について30%低減する規制強化を行い、小型車は平成2年中に、また、中型者に4年中に実施することとしている。さらに、元年12月の中央公害対策審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策の在り方について」に基づき、ディーゼル車を中心に今後10年以内に窒素酸化物排出量を3〜6割低減させていくこととしている。しかしながら、同答申によれば対象となる車両が長期目標値に基づく規制の適合車にほぼ代替した場合においても、これらの自動車排出ガスの低減のみでは、窒素酸化物総量規制地域を中心とする大都市地域における大気環境は、環境基準に対して十分に改善されるものではないと試算されるとされている。
こうした状況を踏まえると、単体規制の強化をできる限り前倒しして実施し、最新規制適合車への代替促進を進めるとともに、低公害車の普及拡大や自動車排出ガス総量抑制の検討を進め、さらには中長期的な観点から燃料価格差などの経済的要素についても検討を加えていく必要がある。
(2) 低公害車の選択
自動車、鉄道、船舶、飛行機、さらに自動車というような多様な交通機関を前に、利用目的に合わせた適切な手段の選択が可能になっている。現在、我が国ではガソリンと軽油を燃料とする自動車が普及しているが、自動車の分野においても、その長所と短所を考慮して多様な自動車を選択する時期に来ている、現在、低公害車としては、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、ソラーカーなどがある。
このような自動車の多様化は、外国においては実行の段階に入っており、米国では1990年11月に成立した大気浄化法の改正に対応して、カリフォルニア州では、独自の自動車公害対策として1998年以降一定の割合の電気自動車の販売を義務づけている(第3-2-4表)。
ア 電気自動車
電気自動車は、バッテリー(蓄電池)に蓄えた電気でモーターを開店させて走る自動車である。最大の特徴は、走行時に排出ガスをまったく出さず、騒音が通常の自動車に比べ低い事である(第3-2-5表)。
電気自動車は、環境に好ましい乗り物である、我が国では、エアーコンディショナーが一般的となっており、その積載も考えなければならないが一充電当りの走行距離は40km/h低速走行で100〜150km程度となっている。また、二酸化炭素低減対策としても有効であり、発電所の効率と送電の効率を含めた全体の効率はガソリン車よりも良い。特に電力をあまり使わない夜間に充電すればより効果的である。性能向上のためには電池の一層の開発が重要であるが、我が国の「NAV」(第3-2-23図)や米国の「インパクト」など、電池は従来のものであっても高性能の電気自動車の開発が進んでいる。
電気自動車の特徴に即した用途への使用を拡大することは、現時点でも十分可能となっている。
英国では騒音が少ないことから早期の牛乳配達者として約2万7,000台が使われており、フランスではごみ収集車として約300台が使われている。スイスのツェルマットでは、貴重な観光資源を排出ガス、騒音などから守るため、電気自動車だけの輸送・移動システムを確立していることは有名である(第3-2-6表)。
我が国では。環境庁において、都市大気汚染対策等の観点から、積極的な普及啓発等により普及拡大に努めているほか、現在「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき公害健康被害補償予防協会に設けられた基金による助成や(財)日本電気車両協会の電気自動車試用制度により普及が進められている。地方公共団体においては、大都市を中心に走る距離があらかじめほぼ分かっているような公害パトロール車をはじめとした業務用車や一定の路線を走るごみ収集車等について導入が進められており、さらに、平成3年度から、環境庁において公害パトロールへの電気自動車導入に対する補助を行うほか、これらの導入を一層進めるため、自治省において地方交付税及び地方債について所要の措置を講ずることとしている。また、民間でも一部の宅配業者によって導入が図られているほか、生活協同組合が自動車メーカーと協力して電気トラックを開発・導入する計画が進んでいる(第3-2-7表)。
イ メタノール自動車
メタノール自動車は、アルコールの一種であるメタノールを燃料として走る自動車である。メタノールは天然ガスから製造されるほか、バイオ技術を利用して製造することもできる。メタノール自動車の排気ガスには黒煙がほとんど含まれておらず、窒素酸化物についてもディーゼルタイプの場合、原型ディーゼル車と比較して約2分の1であり、窒素酸化物の大幅な削減が期待できる。
メタノール自動車の大量普及を進めるに当たっては、燃料によって発生するホルムアルデヒド、未燃メタノールなどを処理する触媒の耐久性などの性能の向上が必要ではあるが、メタノールの性質がガソリンに近いことから、既存のエンジンをベースにして作ることができるという利点がある。現在、大気汚染対策、石油代替エネルギー等の観点から、世界的に研究開発が進められており、早期の工業化を目指して、メタノールの供給体制が十分でない初期の段階でも実用可能なFFV(メタノールとガソリンのどのような混合比の燃料でも走れる自動車)の開発が進められている。
我が国のメタノール自動車の開発は、日本メタノール自動車株式会社及び(財)石油産業活性化センターがその中心的役割を果たしている。環境庁においても、関係省庁、関係団体からなる普及促進のための懇談会を設ける等により普及促進のためのコンセンサスづくりに努めているほか、こう概健康被害補償予防協会に設けられた基金による助成等により普及拡大に努めている(第3-2-8表)。メタノール自動車は動力性能が従来の自動車とあまり変わらないことから、より広い分野への普及が可能であり、特に、現在窒素酸化物で問題になっているディーゼルトラック・バスの分野への普及が期待されている。
ウ 天然ガス自動車
天然ガス自動車は、都市ガス主要原料である天然ガス(圧縮天然ガス・CNG、液化天然ガス・LNG)を燃料として走る自動車であり、黒煙を全く出さず、ガソリン車やディーゼル車と比べて二酸化炭素の排出量が小さく、また、三次元触媒の使用により、ディーゼル車と比べて窒素酸化物を大幅に低減させることが可能である。
CNG自動車は、ガソリンに代わって天然ガスをしようするというところが異なるだけであって、天然ガスでもガソリンのどちらでも知れる自動車が既に実用化されている。諸外国では、イタリアの27万台を筆頭に60万台以上走行している(第3-2-9表)。我が国では、戦後、新潟、千葉などの天然ガスを産出する地方を中心として最大1,000台以上走行していた。天然ガス自動車の普及を進めるに当たっては、ガス充填施設の整備、燃料ボンベ軽量化、ガス充填方式の改善など体制の整備が課題となっている。
エ ディーゼル・電気ハイブリッド自動車
ディーゼル・電気ハイブリッドシステムは、エンジンに新開発のコンピューターの制御の発電機兼モーターを内臓し、発進・加速時のパワーアシスト、減速時のエネルギー回生等の機能を持つシステムである。すなわち、減速時に制動エネルギーで発電・充電し、その電力を発進・加速時に補助的動力として使うものである。我が国の自動車メーカーとエレクトロニクス・メーカーの共同技術開発の成果であり、これにより、都市内走行時の窒素酸化物は約30%削減され、発進・加速時の黒煙は約70%削減される。また、燃費も5〜10%向上する。
ディーゼル・電気ハイブリッド自動車は、平成2年度に試作され、一部の大都市では3年度に路線バスとして試験導入することとなっており、運輸省では、これに対し補助を行うこととしている。今後、その成果を踏まえて大量に導入され、大都市の窒素酸化物大気汚染の改善役立つことが期待されている。
なお、路線バス等の用途として、この他、窒素酸化物及び黒煙の低減を図るためディーゼル・蓄油圧ハイブリッド自動車の研究開発が行われいる。また、使用過程のディーゼル自動車の黒煙の低減を図るため、LPG燃料併用システムの利用可能性調査を行っている。LPG併用システムは、現に使用中のディーゼルエンジンにLPG燃料をコンピューター制御で噴射する装置を取り付けることにより、黒煙の低減を図るシステムであり、エンジン試験では、運転状態により26〜46%黒煙の低減効果がみられている。
平成2年度には、東京都交通局でLPG併用のバス営業運転調査が実施されたところであり、今後実用化が期待される。
オ その他の自動車
ソーラーカーは、太陽電池により太陽エネルギーを直接電気に変換し、モーターで駆動する自動車である。太陽エネルギーを直接利用するので、電気自動車と同様、排出ガスがなく、騒音も低い。ソーラーカーは現在、競技用のものが多数開発されており、これらは国内では公道を走ることはできないが、外国でのソーラーカーレースに出場している。また、最近では、条件つきではあるが自動車登録番号標の交付を受けたソーラーカーも1台開発された。
この他、研究段階の域を大きく出てはいないが、水素自動車、ガスタービン車、スターリングエンジン自動車等の開発が各機関で進められているところである。
(3) 自動車から排出される窒素酸化物の総量抑制
窒素酸化物による大気汚染については、環境基準の達成に向けて、かねてより工上・事業場と自動車に対する規制を逐次強化し、特に昭和57年には、従来の対策のみでは環境基準の達成が困難と認められた東京都特別区等地域、横浜市等地域及び大阪市等地域の3地域において固定発生源に対する総量規制を導入して対策の強化を図ってきたが、達成期限とされた昭和60年度を迎えるに至っても、環境基準を達成することができなかった。
このため、環境庁では、昭和60年12月に「大都市地域における窒素酸化物対策の中期展望」を、さらに63年12月には「窒素酸化物の新たな中期展望」を策定し、自動車単体対策、自動車交通対策及び固定固定発生源対策を3本の柱として各種の対策を総合的に講じてきているが、近年の好景気や大都市集中の進展に伴う自動車交通量の増大や燃料消費量の増大を背景に、未だに大都市地域の道路沿道を中心に環境基準の達成状況ははかばかしくなく、改善の傾向がみられない。
このような状況を踏まえ、平成元年12月には、中央公害対策審議会から、今後10年程度の長期を見通した自動車単体規制強化のためのプログラムを示した答申が出され、今後はこれに基づき、ディーゼル車を中心に自動車排出ガス規制を一層強化していく予定である。
しかしながら、将来においても、各種の開発計画が予定されている東京都等の大都市地域では、現在の着実な経済成長が維持されれば、一層交通量が増加すると考えられる。また、窒素酸化物排出量の多いディーゼル車が増加することも考えられ、これらはいずれも窒素酸化物排出量の増加要因となる。上記の中央公害対策審議会答申に基づく単体規制の強化は一定の環境改善効果を示すものの、これらの窒素酸化物排出量の増加要因により、その効果が相殺され、特に自動車交通が集中する大都市地域では、現時点において予定されている排出ガス低減技術の進展による自動車一台一台の排出ガスの一層の削減のみでは、将来における交通量の伸びに対して、環境基準に照らして十分な環境改善効果を示すことは困難となってきている。
このような自動車排出ガスの問題については、根本的には自動車交通のあり方にまで遡った施策の確立がなされなければならない。すなわち、自動車交通量の増加に結びつく物流方式の改変、自動車に過度に依存しない都市構造の構築、さらには大都市集中の是正等の長期的・計画的な取組が必要である。これらの根本的な対策の確立を視野に置きつつも、大都市地域においては環境基準の達成を図るため早期に実施に移しうる新たな施策が求められている。
こうした観点からの窒素酸化物対策の新たな手法として、特定の地域で排出される自動車排出ガスの総量を抑制することにより一層の環境改善を図ろうとする方策が考えられる。このような自動車排出ガス総量の抑制については、中央公害対策審議会答申においてもその検討の必要性が指摘されている。この方策における検討課題の例としては、窒素酸化物排出量のより少ない自動車の利用、自動車の使用に当たっての効率的な使用方法の採用等による走行量の抑制などが考えられる。
現在、環境庁においては、学識経験者等からなる検討会を設置して検討を進めている。自動車排出ガス総量の抑制の検討当たっては、都市内においては自動車輸送が社会経済活動と密接に関連する物流の中心的位置を占めていることなどから、環境改善効果、必要となる対策費用などを明らかにし、荷主、物流業者、消費者等自動車の使用に関わっている人々の意見を踏まえることとしており、大気環境を早急に健全なものにしていくため、このような方策に対する関係者の理解と国民の支持が是非とも必要である。
(4) その他の窒素酸化物抑制
我が国では、自動車公害対策として自動車排出ガス規制を着実に実行してきたが、増加する自動車を考慮すれば、これのみでは環境基準の達成は困難である。このため、低公害車への転換・導入や自動車排出ガスの総量抑制の検討などを推進しているが、さらにきめ細かな対策が必要となっている。
ア 季節大気汚染暫定対策
気候条件から季節的に窒素酸化物濃度が高くなる冬期においては特別の対策が必要である。冬期には、季節大気汚染暫定対策として暖房温度の適正化や入出荷貨物台数の抑制を国民に呼びかけるほか、窒素酸化物予報や街頭イベントなどを通じて大気汚染防止に関するキャンペーン活動を行っている。
イ ジャスト・イン・タイムの現状の見直し
我が国の物流は、自動車への依存度が高まっている傾向にある。特に都市内では、戸口までいける交通機関として自動車に代替する手段が無い。必要な物を必要なだけ必要な時に納入させるジャスト・イン・タイムと言われる方式を採用した小売店や宅配便などへの需要の増加が促進され、結果として、自動車による少量多頻度輸送が進んでいる。
コンビニエンス・ストア等のジャスト・イン・タイム方式は、現在人々の暮らしの中に浸透している。例えば消費者はより鮮度の高い商品を求め、店の方としては地価が高くなっているから保管のスペースを少なくし、また、チェーンのセンターとしては絶えず商品を供給したい、このような消費者と店の双方のニーズが、これを支えている面があると考えられる。
流通業等においては、共同・計画的配送を行うなどの物流合理化を進める動きもみられるところがあるが、一方では、こした消費者と供給者の構造により、自動車の走行量が増加し、また、道路が渋滞するために早く出発して予定よりも早く着いた場合には、指定の時間まで道路に駐車してまた渋滞の原因をつくるというように、社会生活上のマイナスが生じている。
ジャスト・イン・タイム方式の現状を見直すとともに、都市の自動車交通量を少しでも軽減する努力が必要となっている。