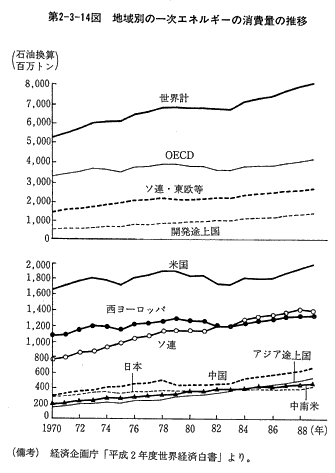
4 エネルギー
ア エネルギーと環境
人口の増加や持続可能な開発に対応していくためには、それに要するエネルギーの需要を満たすことが必要になる。一方、化石燃料の利用は二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物等を排出し、生態系の再生限度を超えた薪炭の過剰な利用は森林の減少や砂漠化を招き、また、大規模な水力利用は熱帯林の水没を招くなど自然生態系に影響を与える。このように、エネルギーの利用の拡大と環境負荷の増大は密接な関係にある。
しかしながら、必要なエネルギー需要を満たすことと、エネルギー供給を拡大することは必ずしも同一ではない。即ち、エネルギーの利用効率の向上により同じ量の最終便益を得るのに必要なエネルギーを少なくすることが可能である。また、エネルギー供給を続けながらも環境負荷を低減していくこともまた可能である。このため、省エネルギー、代替エネルギー、公害防止等の技術を開発するとともに、環境に与える負荷が少ない経済社会へと変革することが必要となる。また、開発途上国での森林の減少による二酸化炭素の排出を抑制し、森林を保護するためには、開発途上国の人々のライフスタイルに即し、身近なエネルギーの大替や効率の向上を図ることも、大きな課題となっている。
イ 世界のエネルギー消費
世界の一次エネルギー消費は、戦後の経済の拡大とともに増加してきたが、石油ショック後、先進国においては、1980年代に省資源・省エネルギー型経済構造への転換を進め、エネルギー依存度のより低い経済体質となった。しかし、1980年代後半の原油価格の低迷と経済活動の好調によって、再び先進国のエネルギー消費が拡大してきている。一方、開発途上国では一貫してエネルギー消費が増加してきており、特に近年その伸びが著しく、世界の一次エネルギー消費に占める開発途上国の割合は、1973年の10.5%から1989年には17.0%と拡大してきている。また、ソ連・東欧等も1973年の28.2%から1989年には32.4%と拡大してきている(第2-3-14図)。
また、1989年のエネルギー消費源の構成をみると、地球温暖化対策において注目しなければならない化石燃料のうち、石油への依存度は、OECD諸国が42.7%であるのに対して開発途上国は50.6%と高く、また、石炭への依存度は、OECD諸国が21.8%であるのに対してソ連・東欧等が42.1%と高いという状況にある(第2-3-4表)。
さらに、GDPのエネルギー消費原単位(GDP−単位当たりの生産に必要なエネルギーの量)でみると、世界全体では低下傾向がみられ、先進国では、1970年の0.45トン(石油換算)/千ドルから1989年には0.33トン/千ドルと低下しているが、開発途上国は、1970年の0.50トン/千ドルから1989年には0.56トン/千ドルと先進国の約1.7倍となっている。さらにソ連・東欧等では、開発途上国をも上回っている状況にある(第2-3-15図)。もちろん、エネルギー消費の原単位は先進国の間でも国によって差異が大きく、日本のように極めて低い水準を達成している国もあれば、米国のように高い原単位を示している国もある。最も人口の多い中国の原単位は、1.9トン/千ドルと先進国の5.4倍にも達している(第2-3-16図)。
世界の一次エネルギーは、IEAによれば、1987年には約77億トンとなっているが、2005年には現在の約1.5倍の約119億トンに達するとされている。また、現在、世界のエネルギー消費の約半分をOECD諸国が占めているが、開発途上国とソ連・東欧等のシェアは1987年の49%から2005年には58%に高まると予測されている(第2-3-5表)。
この他、開発途上国では、多くの人々が燃料として木材を使用している。環境と開発に関する世界委員会の報告書「われら共有の未来(OURCOMMONFUTURE)」によれば、開発途上国の人口の70%以上が、燃料として木材を使用しており、少なくとも毎年350〜2,800?、平均一人当たり700?の乾燥木材をもやしているとされている。
ウ 日本のエネルギー消費
日本のエネルギー自給率は、昭和25年には約90%であった。主力は石炭であった。日本経済の発展は、石炭から石油へのエネルギー転換と石油を中心とする膨大なエネルギーの輸入を1つの条件としていた。石油依存度は、第一次石油ショックの48年度には77.4%であったが、平成元年度には57.9%となっている。また、元年度の日本の一次エネルギー総給量は昭和30年度の7.2倍になっている。なお、エネルギー自給率は、1988年度みると17.7%で主要先進国の中で最も低い(第2-3-17図、第2-3-18図)。
エ 日本の二酸化炭素排出量
エネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量は、単位エネルギー当たりの二酸化炭素排出量(以下「炭素集約度」という。)、GNP当たりのエネルギー消費(以下「エネルギー集約度」という。)、一人当たりのGNP、及び人口の4つ要素に分解できる。
炭素集約度は、単位エネルギー当たりの炭素の割合を表し、エネルギーに占める化石燃料の割合や石炭、石油、天然ガスといった化石燃料の構成に左右される。エネルギー集約度は、単位当たりの経済活動に要するエネルギーの量を表し、エネルギーの利用効率や産業構造のエネルギー依存度、気候条件等によるエネルギー利用度などを代表している。
我が国の二酸化炭素排出量の推移を環境庁の堆計によってみると、つぎのようになっている。
かつて我が国は、目ざましい勢いでGNPを成長させたが、これと軌を一にして二酸化炭素排出量も急速に増大した。しかし昭和48年度の石油ショック以降について見ると、GNPは、その伸び率に大幅な鈍化があったものの年率4〜5%程度の成長を続け、また人口は伸び率が鈍りつつも増加していたが、二酸化炭素排出量は、61年度までほぼ横ばいで堆移していた(第2-3-19図)。これは石油危機を契機として持続的な省エネの努力と産業構造の転換、エネルギー多消費産業における製品の高付加価値化の進展によってエネルギー集約度が48年度から61年度までの間に34.4%も低下(年率約マイナス3.1%)したこと、次いで原子力をはじめとする非化石燃料の導入や天然ガスへの利用推進により炭素集約度が着実に低下(年率約マイナス1%)してきたことによる。61年度以降では、低廉なエネルギーコストと旺盛な経済活動によってエネルギー消費量が増加しており、再び、二酸化炭素排出量は増加傾向に転じて、62年度、63年度の年間伸び率はそれぞれ、5.4%、4.0%であった。
部門別の二酸化炭素排出量の推移をみると、産業部門は石油ショック以降のエネルギー効率向上の努力等により結果として排出削減をも達成してきており、そのシェアは昭和48年度に60.2%であったものが平成元年度では49.5%に低下している。民生部門では、生活水準の向上、人口の増加、業務用床面積の増加等によりエネルギー需要が増加したことに加え、電力化が進化したために、排出量の増加が続き、元年度は昭和48年度の約1.5倍の排出量となった。そのシェアは48年度の18.0%から平成元年度には23.2%と増加している。運輸部門での排出量の伸びはこれより大きく、平成元年度は昭和48年度の約1.6倍となっている。そのシェアは48年度の13.1%から平成元年度の19.4%へと増加した。転換部門の自家消費は送電ロスや燃料精製に伴うエネルギー消費分の排出量を示しているが、送電ロスの低減等により8〜9%のシェアを保概ね横ばいであった。(第2-3-20図)。