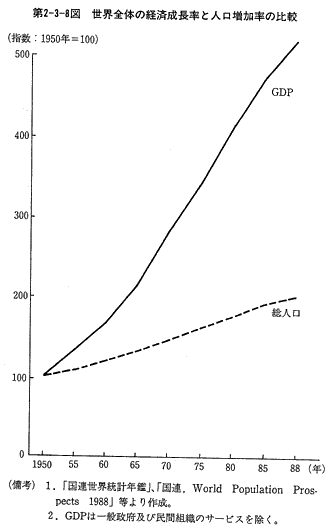
3 経済成長
ア 経済成長と環境
人類社会は、人口も経済も急速に増大してきた。ますます増加していく世界の人々の暮らしを成り立たせるために、経済の安定的成長は必要である。
しかし、現在の経済的価値は、市場に組み込まれていない環境の価値の損失を反映していない。また、経済発展の過程では、適切な公害防止対策を講じることが往々にして怠られがちであり、日本でも、特に臨海部を中心としたコンビナート方式などの密度の高い経済活動が、各地で深刻な産業公害を招いた。
このように環境の価値を適切に反映しないまま経済の成長が続いていけば、産業公害などの地域的な環境問題が世界各地で深刻になるとともに、地球環境破壊の脅威が現実のものとなり、世界経済の成長を阻むおそれもある。
増加していく人口に対処し、開発途上国の人々を含めた人類の共存を図るためには、現在のライフスタイルや経済社会を環境にやさしいものへと転換し、地球の生態系に決定的な打撃を与えることを防ぎ、あわせて地域的な環境問題の発生を防止していくことが重要である。現実には、現在の世代の利益と将来の世代の利益の対立などによって個々の開発の判断においては環境と開発が対立することがあり、その対立の解決の困難性を過少評価してはならないが、持続可能な開発の考え方に基づいて、環境政策と経済政策の連携を強化していかなければならない。
イ 世界の経済成長
世界経済は、第二次世界大戦後、2度にわたる石油ショックを乗り越えて、大きく成長している。1950年以降の世界の経済成長(GDP)と人口増加率の比較をみると、世界全体としては繁栄を生み出しているといえる(第2-3-8図)。しかし、先進工業国と開発途上国の、人口一人当たりのGDPの推移割合をみると、これらの国々の間の格差がますます拡大していることがわかる(第2-3-9図)。また、開発途上国の中には、GDPの伸びが人口の増加率を下回る国もみられ、そのような国では国民の生活水準が低下している。直近のデータでは、世界人口の17%の豊かな国々の人々が82%の所得を得、61%の貧しい国の人々は世界の所得の5%しか得ていないという国際的な貧富の差が浮かび上がってくる(第2-3-10図)。
さらに、注目しなければならないことは、開発途上国全体として食糧の自給率の低下がみられることと、これを補うための食糧輸入の多くは米国一国の農産物に頼っていることである。1990年の世界人口白書によれば、開発途上国全体の穀物輸入は、1968年〜1971年に2,000万トンであったが、1983年〜1985年には6,900万トンに増え、今世紀末までに1億1,200万トンの輸入に頼ることになると予想それている。
ウ 日本の経済成長
我が国は、世界でも有数の経済成長をとげ、GNPでは昭和42年に西独を抜き、世界第2位となった。その後も拡大を続け、現在、旧西独、フランス、英国を合わせた程度のGNPとなっている(第2-3-2表)。さらに、平成元年には一人当たりのGDPも世界第2位になった(第2-3-3表)。都道府県別の県内総生産と世界の国々のGDPを見てみると東京都はほぼカナダと同じくらいの経済規模であり、成長著しい韓国経済といえども愛知県や神奈川県に及ばない。(第2-3-11図)。
我が国は、狭い国土、平地の中で高度な経済活動を営んでいる。我が国に国土は37万8,000km
2
であるが、可住地面積は8万500km
2
にすぎず、1億2,300万人の人口を勘案すれば、日本人一人当たりの可住地面積は、約700km
2
にすぎない。これを米国、旧西独、英国と国際的に比較してみると、我が国は米国の30分の1、旧西独の4分の1などとなっている(第2-3-12図)。また、可住地面積当たりエネルギー消費量をみると米国の12倍、旧西独の3倍などとなっており、いかに小空間において、活発な人間活動が行われているかが分かる(第2-3-13図)。
このように、多数の人々が生活する平地で稠密な経済活動が行われており、適切な環境対策が講じられない場合には、環境問題が生じやすくなっている。