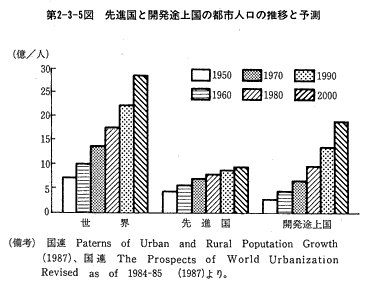
2 都市化の進展
ア 都市化の環境
現在多くの人が都市に住んでおり、都市の環境は、多くの人々の健康にも関わる重要な問題である。
都市が急速に拡大し、都市の経済社会活動の拡大に環境対策が追いつかなかったために、生活排水による水質汚濁や自動車による大気汚染など都市・生活型の公害が大きな問題となり、また、都市から身近な自然が急速に消えてきている。
開発途上国においては、政府の行政サービスの供給能力をはるかに上回る人口の増大に対し、住宅、食糧や安全な水の確保などの生活の基礎条件の確保が困難になっている。また、都市・生活型公害に加えて、開発途上国の経済活動の多くは首都をはじめとする大都市に集中しており、これら大都市では、活発な経済社会活動と不十分な公害防止対策とによって、工場からの排気ガスや排水などによる大気汚染、水質汚濁などの産業公害も深刻になっている。
都市の良好な環境を確保するには、公害防止対策などの対策が必要であり、また、都市の巨大化に対しては、環境破壊が全国に分散しないように配慮しつつ、都市の膨張を抑制するような国土政策も必要である。
イ 世界の都市化の進展
開発途上国の総人口の増加は著しいものがあるが、それよりもなお都市人口の増加は著しい。先進国の都市人口は直線的な増加をたどるが、開発途上国では幾何級数的増加を示すと推計されている(第2-3-5図)。開発途上国の都市人口は、農村地域の増加率よりも60%多い年率3.6%の高い増加率となっている。農村か都市への移住のほか、都市内部での自然増の比率も増大している。
国連の統計によれば人口1,000万人を超える都市は1985年現在11都市あり、このうち7都市が開発途上国にある。これが、2000年には世界全体で24都市となり、開発途上国で18都市となると予測されているが、特に開発途上国の大都市の人口の伸びが著しい(第2-3-6図)。開発途上国の都市人口は1950年には2億8,500万人(開発途上国の全人口の16.9%)、1970年には6億7,500万人(同25.5%)、1990年には13億8,400万人(同33.9%)となっており、2025年には40億5,000万人(同56.9%)と膨れ上がっていくと推計されている。
開発途上国では、農村地域から押し出されてくる人々や都市内で増加する人々を都市における雇用機会の増大によって吸収しきれず、都市のスラム街が膨張するという傾向がみられ、劣悪な環境の中に多くの人々が居住している。
ウ 日本の都市化の進展
我が国の人口について特徴的なことは、戦後の農業人口の急速な減少と人口の都市への集中である。平成元年現在、我が国の人口の76.7%は、都市に居住している。特に三大都市圏には、東京圏25.5%、関西圏14.7%、名古屋圏8.5%の人々が居住している。我が国では、人口の三大都市圏への集中と第一次産業就業人口の減少及び第二次・第三次産業就業人口の増加が同時に起こっているが、これは、大都市における第二次、第三次産業に対する労働力需要が増加したことによると考えられる。(第2-3-7図)
人口の昭和50年半ばからの首都圏への一極集中の傾向は依然として続いており、若年層の都市への流出によって地域的な人口構造の歪みが生じている。