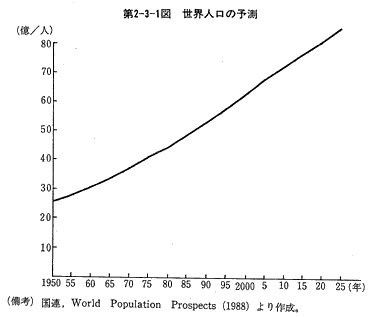
1 人口の増大
ア 人口と環境
環境問題は、人間の経済社会活動と環境との関係において生じる。概念的には、人々の生活様式、所得等によって程度が決定される消費と、これを供給するために必要な経済活動の双方から排出される排ガス、廃水、廃棄物などによって一人当たりの環境への影響度が決まる。一人当たりの環境への影響度は、一般に、先進国が大きく、開発途上国で小さい。この一人当たりの環境への影響度に人口を掛けて全体の環境への影響度が決まる。人口は、一般に開発途上国が多く、先進国が少ない。
もちろん、富の不平等という要素も忘れてはならない。
このように人口の多寡は、一人当たりの環境への影響度と並ぶ環境問題の基本的要素であり、人口政策は環境政策と密接な関連がある。
開発途上国における人口の増加については、貧困とあいまって過度の焼畑等による熱帯林の減少、砂漠化の進行等の環境問題を深刻化させており、持続可能な開発を阻害するような人口増に対処する全国の能力を高めることが重要である。このため、既存農地の生産性向上等により食糧を安定的に供給するほか、家族計画、教育プログラム等の各国の取組を援助するとともに、国連の活動を支援していく必要がある。
イ 世界の人口の動向
世界の人口は、産業革命による近代化により多くの人口を養えるようになって以来増加しているが、特に第二次世界大戦後の人口の伸びは著しい。
国連の統計によると、1650年には世界人口は約5億人であり、年間増加率は0.3%程度であった。20世紀半ばの1950年には世界人口は25億人強、1975年には40億人強、そして1990年には53億人を数えるに至っている。国連や人口急増国の努力にもかかわらず、人口増加のペース(1985〜90年平均で1.73%)は依然として衰えていない。
また、人口予測は上方修正されており、今世紀末には62億5,100万人、2025年には84億6,700万人となるいう推計がなされている。(第2-3-1図)。今後35年間に1960年当時の世界人口に匹敵する31億7,400万人が新たに増加する。そして、従来の推計を超えて、21世紀の世界人口は、110億人へのコースを進んでいる。
2025年までの予測を地域別で見ると、東アジアは13億3,400万人から17億2,900万人に、南アジアは12億200万人から21億7,400万人に、西アジアは、1億3,100万人から2億8,600万人へと増加し、ラテンアメリカでは4億4,800万人らか7億6,000万人に増えるとみられている。アフリカの人口増加は最も爆発的で6億4,800万人から15億8,100万人に増えると推計されている(第2-3-1表)
また、先進国と開発途上国とで比較してみると、新たに増加する人口の5%に満たない1億4,700万人が先進国で、95%以上が開発途上国であり、高齢化する先進国と過密化する開発途上国の図式が浮かび上がってくる(第2-3-2図)
ウ 日本の人口の動向
我が国は、江戸時代は既に3,000万人の人口と、100万人の江戸という大都市をかかえていた。これは当時の世界人口の3%に当たる。
明治維新以降、我が国の人口は増加傾向をたどり、平成2年現在1億2,361万人となっている。(第2-3-3図)
わが国の人口構造については、高齢化が大きな問題となっている(第2-3-4図)これは、近い将来において、日本の経済社会活動の主要な担い手である労働力が少なくなり、高齢者層を支える若年層の負担が増大することを示している。この中で、地球環境問題について、資金や技術のみならず人的な協力の促進など、ますます大きくなっていく我が国の国際的な責任を果たしていかなくてはならない。