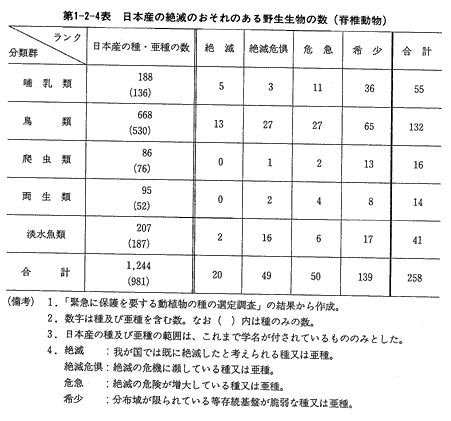
11 野生生物の現状
(1) 我が国の生物相の特徴
我が国の自然が温暖多雨の気候に恵まれ、植生が変化に富んでいることにも表れているように、我が国に生息する野生生物の種類は極めて多様である。我が国に生息する野生生物の種の数は、これまで学名が付けられているものに限ってみても、哺乳類136、鳥類530、爬虫類76、両生類52、淡水魚類187、昆虫類約2万9,000、種子植物及びシダ植物5,565となっている。
しかし、明治時代以降、我が国の人工は急激に増加し、また世界に類のない高度経済成長を達成したことから、狭い国土の中で極めて高密度の土地利用が行われるようになってきた。こうした人間活動の活発化に伴って開発が行われ、野生生物の生存に不可欠である良好な自然環境の改変が進行し、かつて身近に見られた動植物の数が次第に減少し、あるいは、絶滅に瀕するようになってきている。
(2) 絶滅のおそれのある種の現状
野生生物の種の減少は、世界的にみると特に熱帯雨林において急激に進行し、種の多様性の確保や遺伝子資源の保護が重要な課題となっているが、我が国でもこうした野生生物への圧迫は進行している。
オオカミやトキにみられるように、明治以来、多くの種が絶滅し、又は絶滅に瀕している。オオカミが最後まで残っていた北海道では、害獣としての駆除が主な原因となり絶滅した。また、江戸時代には日本各地で観察されたトキも、乱獲や農薬などによる汚染、生息環境の改変などにより、急激に減少していった。こうした有名な例の他にも、ほとんど人に知られることもなく開発に伴って多くの野生生物が絶滅していったものと考えられる。
環境庁が、昭和61年度から3年間かけて日本産の絶滅のおそれのある動植物種を選定するために実施した「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」によると、脊椎動物については、我が国において既に絶滅したと考えられる動物の種又は亜種の数は20、絶滅のおそれのある種・亜種の数は238、また、脊椎動物以外の動物を含めると絶滅のおそれのある種・亜種の数は合わせて600を超えており、脊椎動物についてみれば6種に1種の割合で絶滅の危険があるという結果となっている(第1-2-4表)。
主な分類群について、絶滅に瀕していたり絶滅の危険が増大している種をみると、哺乳類ではニホンカワウソ、イリオモテヤマネコ、ケナガネズミ等が、鳥類ではアホウドリ、イヌワシ、ノグチゲラ、シマフクロウ等が、両生類・爬虫類ではホクリクサンショウウオ、セマルハコガメ等が、淡水魚類ではミヤコタナゴ、ムサシトミヨ、イトウ等が選定されている。
このように、我が国における野生生物の急速な衰退の背景としては、過去においては乱獲も影響していたが、現在における主要な原因は、全国的な開発の進行とこれに伴う森林の伐採、原野・湿地の消滅、河川や小川、海岸等の改変、水質の悪化等と考えられる。これらの開発の進行に伴う環境の変化により、野生生物の生存に不可欠な営巣地や産卵地の消滅、行動圏の縮小・分断、また、エサとなる小動物の減少などが起こり、多くの種が衰退してきていると考えられる。
(3) 渡り鳥の現状
我が国で観察される鳥類のうち渡り鳥は約75%を占める。昭和45年度より全都道府県で観察個体数調査が実施されているガン、カモ、ハクチョウ類は冬鳥を代表する渡り鳥である。本調査は、我が国における冬鳥渡来の傾向を知る手がかりになっている。
平成2年1月の調査によるとガン、カモ、ハクチョウ類の観察総数は、全国で172万1,000羽であつた。昭和45年度の102万6,000羽から徐々に増加している。
そのうちハクチョウ類は昭和45年度から60年度まで1万羽から2万羽内外で推移し、昭和61年度から平成2年度には3万〜4万羽と増加している。ガン類も昭和45年度の5,600羽から62年度までは1万羽内外で推移していたが、平成2年度には2万羽内外に増えた。
一方、国内で繁殖する数種のカモ類は、昭和45年度の100万羽から平成2年度まで150万羽内外で推移し、安定している。