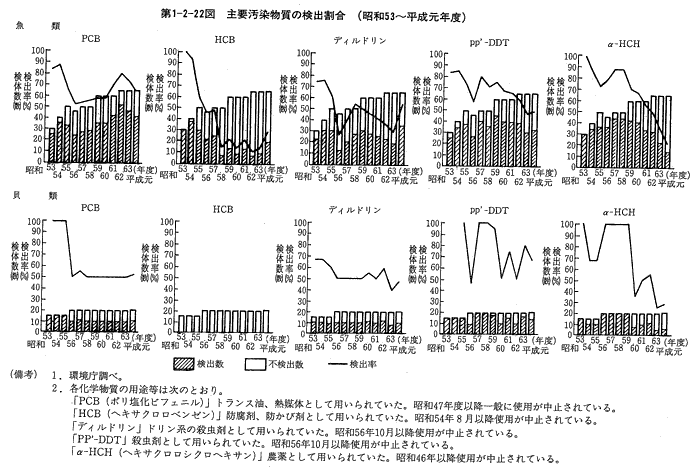
9 科学物質
ア 科学物質に係わる主要な環境問題
科学物質は、その用途・種類が多岐・多用であり、現在、工業的に生産されているだけでも数万点に及ぶといわれている。これらの中には、製造、流通、使用、廃棄等の様々な過程で環境中に排出され、残留し、環境汚染の原因になるものもある。
科学物質の使用や廃棄などを通じて、直感的、間接的に人間社会に悪影響を与えるという新しい問題が顕在化してきたのは比較的新しく、昭和40年代に入ってからである。先に述べた農薬による環境汚染のほか、40年代初めに、ライスオイルに混入したPCB等により発生した油症事件がきっかけとなって全国的に海水や海底等がPCBにより汚染されていることが明らかになり、また母乳からもPCBが検出されるなど、化学物質全般についての環境安全対策の必要性が強く認識されるようになった。
また、昭和50年代半ば以降になると、溶剤として用いられるトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどによる地下水汚染が全国的な規模で進行し、水質・大気等の複数の環境媒体の汚染が明らかになり、50年代末には船底塗料や漁網防汚剤として用いられている有機スズ化合物による環境汚染が明らかになった。
さらに、昭和50年代末には、強い発がん性と催奇形性を有するダイオキシン類が、2・4・5-T等の農薬の不純物以外にも廃棄物の焼却過程などで非意図的に生成することが明らかになり、最近では製紙パルプ工場の漂白工程などでもダイオキシン類が生成することが報告されるなど多くの発生源の存在が指摘されている。
イ 科学物質による環境汚染を防止するための措置
科学物質による環境汚染を防止するため、「水質汚染防止法」により工場・事業場からの排水に含まれるPCBやトリクロロエチレン等の有害物質について公共用水域への排出、地下への浸透の規制が行われている。
また、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、難分解性、高蓄積性、慢性毒性を有する化学物質(第1種特定化学物質)としてPCB、DDT、ドリン剤等が指定され、これらについて許可外製造や輸入が禁止されている。また、難分解性、慢性毒性は有するものの蓄積性は高くない性状を持ち相当広範囲な地域の環境が汚染されることにより人の健康被害を生じるおそれのある化学物質(第2種特定化学物質)として指定されているトリクロロエチレン、有機スズ化合物質等については、製造・輸入定数量の事前届出、必要に応じて製造・輸入数量の制限などの措置が採られるとともに、第2種特定化学物質に該当する疑いのある化学物質(指定化学物質)についても、製造・輸入実績の届出などが義務付けられている。
さらに、これら法律に基づく規制のほか、関係省庁において化学物質による環境汚染防止するための各種指導が行われている。
ウ 環境中の化学物質の状況と環境安全評価
化学物質による環境汚染を防止するためには、化学物質の環境中の安全性を評価することが不可欠である。このため、環境庁では、環境残留性が高いと考えるものについて、水質、底質等の汚染実態そ明らかにするための環境調査を順次行っている。このうち環境中の濃度レベルの推移を長期的に把握していくことが必要な物質や蓄積性が高い物質については魚介類等を指標性物とした生物モニタリング等を行っている(第1-2-22図)。この結果、有機スズ化合物質、PCB類、クロルデン類等は、依然として高い頻度、濃度で検出されていることから、今後とも監視を継続していく必要があると評価されている(第1-2-2表)。
また、指定化学物質及び第2種特定化学物質については、環境中の残留状況を把握するための調査を継続して行なっているが、トリクロロエチレン等9物質は環境中に広範囲に残留していると認められており、引き続き監視する必要がある。
さらに、環境庁では昭和60年度からダイオキシン類による一般環境の汚染状況の調査を行っており、現時点では、人の健康に被害を及ぼすとは考えられないが、低濃度とはいえダイオキシン類は検出されているので、今後とも引き続きその汚染状況の推移を追跡して監視することが重要であると評価されている(第1-2-3表)
これまでに環境汚染が問題となった化学物質は、非意図的に生成するダイオキシン類を除いて、その多くは有用な化学物質として、人の健康影響等に関する知見が十分ないまま大量に生産、使用されて環境へ放出されてきたものである。化学物質による環境汚染を未然に防止するためには、化学物質の人の健康や生活環境への影響に関する化学的知見の集積を図るとともに、環境への排出状況、水質、大気、土壌等のあらゆる環境媒体中の汚染状況の把握等により、化学物質の環境への影響を総合的に評価し、環境への放出を管理していくことが必要になっている。