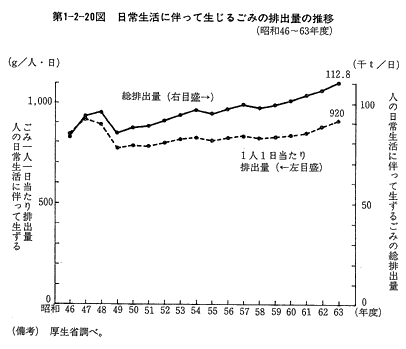
7 廃棄物
廃棄物には、事業活動に伴い排出される汚でい、廃油等の産業廃棄物と、し尿、ごみなど主として国民の日常生活に伴って生じる一般廃棄物がある。
一般廃棄物のうち人の日常生活に伴って生じるごみの排出量は、昭和63年度では、4,117万トン(62年度3,959万トン)となっている。過去20年余りを振り返ってみると、48年度まで急激に増加し、49年度に一旦大きく減少に転じたものの、その後は、消費活動の拡大・多様化等により廃棄物の量・種類とも増加している(第1-2-20図)。
廃棄物処理については、最終処分場の確保が問題になってきており、特に大都市地域においては深刻な問題となっている。
一般廃棄物の発生量、最終処分量について全国の約4分の1を占める東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県)では、最終処分場の残余容量は昭和63年度末において約4年分と評価されており、既に自己の処分場で処分しきれず、処分場を他県の市町村内にもつ民間の処分業者に委託することなどで対処している市町村が全体の30%に及んでいる。
さらに、産業廃棄物についても、最終処分場の残余容量は圏域全体で約1年分しかなく、例えば東京都内で発生する産業廃棄物の埋立量の約64%は他県で処分されている。
これに加えて、近年における廃棄物の性状、排出形態等の変化に伴い、現行の処理技術、システムでは適正な処理が困難な廃棄物が出てくる場合があり、これらの廃棄物の適正処理にさらに努めていくとともに、事業者の協力等により新しいシステムを工夫していく必要がある。
し尿の処分量については、水洗化人口の増加等により数年来減少傾向にあり、昭和63年度は3,751万kl(62年度3,753kl)となっている。減少の原因としては、水洗トイレの普及があげられ、水洗化人口については47年(2,500万人)と昭和63年(7,500万人)を比べると約3倍増加をしており、水洗化人口率についても24.7%から61.8%へとここ20年間で著しく改善されたといえる(第1-2-21図)。