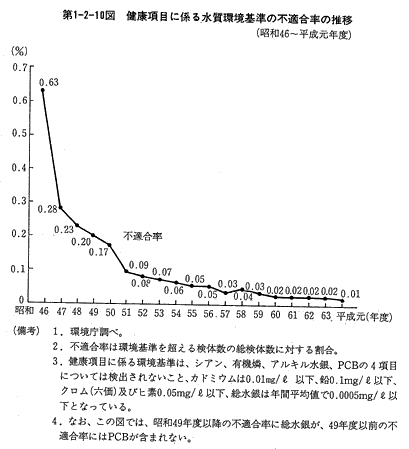
2 水質汚染
水質の汚染に係る環境上の条件については、「公害対策基本法」第9条に基づき「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」が定められている。以下、この環境基準の達成状況などをみる。
(1) 健康項目に係る環境状況
人の健康の保護に関する環境基準は、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、クロム(六価)、ヒ素、総水銀、アルキル水銀及びPCBの9項目について定められている。
これらの基準は、おおむね我が国の「水道法」に基づく水質基準を参考とし、同じ値の基準値となっているが、水銀関係及びPCBについては魚介類の生物濃縮を通じて食品として人体に取り入れられることを勘案して基準値を定めている。また、人の健康は、何物にも優先して尊重されなければならないため、水域ごとに数値に差異を設けたり、一部の水域に限定せず、全公共用水域につき一律に適用されるものとして設定されている。
人の健康の保護に関する環境基準の不適合をみると、昭和46年度においては、0.63%、47年度においては0.28%とかなりの数の地点で基準値を超える値が観測されていたが、その後、「水質汚染防止法」による工業・事業場に対する排水規制の強化・徹底や鉱害防止事業の実施により、現在においてほぼ環境基準を満足するに至っている。平成元年度においても、全国5,267地点において観測された13万6,342(総水銀を除く。)の検体のうち、環境基準に適合していない割合は0.01%(昭和63年度0.02%)となっている。(第1-2-10図)。なお、総水銀については、年間平均値で基準が定められているが、昭和50年度以降環境基準を超えると評価される地点はない。
(2) 生活環境項目に係る汚染状況
生活環境の保全に関する環境基準は、河川においては生物化学的酸素要求量(BOD)など5項目、湖沼においては化学的酸素要求量(COD)など5項目と全窒素及び全燐、海域においてはCODなど5項目について定められている。
生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼、海域別に、各利水目的に応じて設けられた数個の水域類型に分けて定められており、水域の範囲ごとにそれぞれ該当する類型を指定することにより、その水域で保全すべき水準を明かにする方式によっている。生活環境としての望ましい水準は水域における水の利用目的に応じて異なるものであり、それぞれの水域の特性を考慮して基準を設定することが適当であると考えられたからである。
ア 全国の状況
生活環境の保全に関する環境基準は、水域が通常の状態にある場合の日間平均値で定められているが、水域の生活環境は、有機物による汚染により最も影響を受けることから、その量と関連の深い指標であるBOD(河川)又はCOD(湖沼、海域)を代表項目として、年間を通した達成状況の評価を行っている。これによると、昭和49年において環境基準を達成している水域は全体の54.9%であり、水域別では、河川51.3%、湖沼41.9%、海域70.7%という状況であった。その後、環境基準の達成率は相対的にはわずかずつであるが上昇してきており、平成元年では、水域全体で74.3%、水域別にみると河川73.8%(昭和63年度73.3%)、湖沼46.3%(同44.2%)、海域82.4%(同82.7%)となっている。湖沼については改善はみられるもののなお低い達成状況にある(第1-2-11図)。
イ 閉鎖性水域の状況
湖沼、内海、内湾等の閉鎖性水域では、水の交換が少なくて汚濁物質が蓄積しやすく、対策の効果が現れにくいため、依然として環境基準の達成率が低く、中でも後背地に大きな汚濁源がある水域では、水質保全のための条件は厳しい。
湖沼については、琵琶湖(滋賀県)、霧ヶ浦(茨城県)、諏訪湖(長野県)などの代表的な湖沼においてCODに係る環境基準がなお未達成である。湖沼の水質保全に向けては、昭和60年から「湖沼水質保全特別措置法」に基づき対策が講じられてきており、手賀沼(千葉県)等においては、なお著しい汚濁状態にあるものの、徐々に水質改善効果が現れている(第1-2-12図)。
また、広域的な閉鎖性水域については、昭和53年の「水質汚濁防止法」等の改正により、当該水域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制制度が導入され、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、これまで2次にわたって総量規制が実施されてきている。この結果、産業系を中心に流入汚濁負荷量は着実に減少しているものの、環境基準の達成率をみると、東京湾及び伊勢湾については、なお海域全体に比べて低い状況にあり、また瀬戸内海でも大阪湾などは低い状況にある(第1-2-13図)。
このため、引き続き排水規制等の徹底を図るとともに、流入負荷量のうち手賀沼で77%、印旛沼で63%、東京湾で68%など高い割合を占めている生活系の負荷の削減が必要となっている(第1-2-14図)。
また、生活排水、工場排水等に含まれる窒素、燐などの栄養塩類の流入により、藻類その他の水生生物が増殖・繁茂し、いわゆる富栄養化が生じている。このため、湖沼では水道水の異臭味や浄化場のろ過障害の発生、水産における魚類の変化、透明度の低下等による景観の悪化などがみられ、内海、内湾においては、赤潮や青潮の発生などによって漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海浜の汚染など広く生活環境への被害が生じている。
ウ 都市河川の状況
生活における精神的な豊さ、快適さに対する人々のニーズが高まっている中で、都市内河川はそこに住む人々の生活に潤いを与える貴重な空間として見直されるようになってきている。しかし、その状況をみると、汚濁が著しく、悪臭を発したり景観を損なっているもの多い(第1-2-15図)。
河川の水質汚濁の状況をみると、都市河川について汚濁の水準が高く、近年は改善が進んでいない。また、BODで10mg/lを超える汚濁が著しい河川についてみると、その82%は、都市内河川であり、地域別にみると大都市及びその周辺(茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び福岡県)に73%が集中している。
この原因をみると、綾瀬川の例にみられるように、排水規制の実施等により産業系の流入負荷は着実に減少してきているものの、都市内人口の増加により生活系負荷対策の効果が十分に上がっていないことなどが指摘される(第1-2-16図)。
エ 第三次総量規制及び生活排水対策
このような状況を踏まえ、閉鎖性水域の水質保全対策や生活排水対策を強力に進めることが必要となっている。
このうち、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海については、引き続き第三次水質総量規制を実施して、生活排水対策の一層の推進と産業排水対策として総量規制基準の強化等を図ることにより、全体としてバランスをとりつつ、流入負荷量の計画的な削減に向けて最大限の努力を払うこととした。このような基本的考え方の下に平成3年1月には、内閣総理大臣により6年度を目標とする新たな総量削減基本方針が定められ、これに基づき関係都道府県において新たな総量削減計画を策定して、対策を進めている。
また、生活排水による水質汚濁の防止対策については、「水質汚濁防止法」等の法制度に基づき着実に施策が進められてきた産業系の排水規制に比べて制度的な枠組みも整備されておらず、総合的な対策のあり方等が確立されたものとなっていなかった。このため、平成2年6月に「水質汚濁防止法」が改正され、「生活排水対策の推進」の章が設けられ、生活排水対策を進めるに当たっての市町村、都道府県、国それぞれの責務や国民の心がけ等が明確にされるとともに、生活排水対策を重点的に推進する必要のある地域について市町村が生活排水対策推進計画を策定することなど市町村において生活排水による水質汚濁の防止対策に総合的に取り組む枠組みが設けられた。
現在、全国の都道府県において、公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要な地域を生活排水対策重点地域として指定するための作業が逐次進められており、平成3年3月末現在で13地域(28市町)が指定されている。今後、各地域ごとに、下水道、合弁処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備や指導員の育成など生活排水対策に係る啓発に関する事項等を内容とする生活排水対策推進計画の策定の準備が進められている。
(3) 地下水汚染
地下水は良質・恒温な水資源として高く評価され、現在でも都市用水(生活用水及び工業用水)の約3割は地下水に依存している。しかし、昭和50年代後半より、トリクロロエチレン等による地下水汚染が顕在化し、57年度及び58年度に環境庁が全国で実施した地下水汚染実態調査によって広範な汚染が判明した。また、その後、地方公共団体が行った調査によっても汚染が各地域に広がっていることが明らかにされた。
このため、平成元年6月に「水質汚濁防止法」が改正され、有害物質を含む水の地下浸透を規制するとともに、都道府県知事は、地下水の水質汚濁の状況を常時監視するため、毎年、測定計画を策定し、これに従って国及び地方公共団体は地下水の水質の測定を行うこととなった。
平成元年度における概況調査(地域の全体的な地下水質の状況を把握するための地下水の水質調査)では、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀及びPCBの9物質について初めて全国的な調査が行われたが、シアン及びヒ素について一部の地域の井戸で超過が認められ対外は、評価基準を超過する井戸はなかった。また、従来から調査を行っているトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについての超過率は、それぞれ0.9%、1.2%であり、昭和63年度までの過去5年間の地方公共団体の独自の調査に比べ超過率は小さくなっているが、調査地点が異なること等により単純な比較はできない。また、暫定指導指針に基づき行政指導を行っている物質のうち1,1,1-トリクロロエタン及び四塩化炭素について一部の井戸で超過するものがみられた。このほか、汚染井戸周辺地区調査(概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するために実施する地下水の水質調査)や定期モニタリング調査(汚染の継続的監視等継続的なモニタリングとして実施する地下水の水質調査)による過去の汚染がみられた井戸の監視等が行われた。
(4) 海洋汚染
我が国の周辺地域における海洋汚染の発生確認件数は、昭和47年には2,283件であったが、平成2年には993件となっており、元年に比べて59件増加している。このうち油による海洋汚染が全体の59%となっており、これを海域別にみると、油による海洋汚染全体の40%に当たる235件が東京湾、伊勢湾、大阪湾に及び瀬戸内海において発生している。
また、タンカーから排出されるバラスト水などの油分によると推定される廃油ボールの漂流・漂着は、近年、全体として減少傾向を示しているものの、なお南西諸島への漂着が多い状況にある。