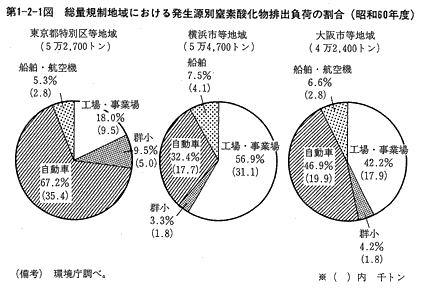
1 大気汚染
大気の汚染に係る環境上の条件について、「公害対策基本法」第9条に基づいて、「人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準」(環境基準)が、現在、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質について設定されている。以下、これらの物質に係る環境基準の達成状況などをみる。
(1) 二酸化窒素(NO2)
二酸化窒素は、呼吸に影響を及ぼすとされている。
大気中の窒素酸化物(NOx)の主たる発生源は、ボイラー等の固定発生源及び自動車等の移動発生源である。固定発生源について窒素酸化物に係る総量規制制度が導入されている東京特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域の大都市では、固定発生源と移動発生源との排出割合をみると、自動車の占める割合は昭和60年度でそれぞれ、67%、32%、47%となっている。(第1-2-1図)。
現行の環境基準は、昭和53年7月にその時点における最新の知見を検討・評価して「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること」と定められたものである。
二酸化窒素の濃度を継続して測定している測定局についてみると、昭和47年度には、一般的状況を把握するために全国に設置されている一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)において年平均値0.020ppm、道路周辺における大気汚染を把握するために沿道に設置されている自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)において年平均値0.034ppmであった。それ以降悪化傾向にあったが、53年度の一般局の年平均値0.028ppm、自排局の年平均値0.043ppmをピークに、54年度以降は改善傾向がみられていた。しかし、61年度から再び悪化傾向を示し、平成元年度は、一般局の平均値は0.028ppm、自排局の年平均値は0.042ppmといずれも昭和63年度に比べて横ばいで推移し、依然として改善を要する状況にある(第1-2-2図)。
全国における環境基準との対応状況を昭和63年度との対比でみると、平成元年において環境基準の上限値0.06ppmを超える局は、一般局で55局(4.1%)から65局(4.8%)に自排局は95局(31.8%)から106局(34.5%)にそれぞれ増加した(第1-2-3図)。また、窒素酸化物総量規制地域の三地域についてそれぞれ環境基準との対応状況を昭和63年度との対比でみると、平成元年度において環境基準の上限値0.06ppmを超える局は、一般局で102局のうち49局から104局のうち49局、自排局は71局のうち63局から72局のうち65局とおおむね横ばいであり(第1-2-4図)、環境基準の達成のためには、なお一層の努力を要する状況にある。
(2) 二酸化硫黄(SO2)
二酸化硫黄は、呼吸器に対する影響などがあり、四日市ぜんそくなどのいわゆる公害病の主な原因物質となった。
大気中の硫黄酸加物(SOx)は、主として硫黄分を含む石炭、石油などの化石燃料の燃焼に伴って発生する。
現行の環境基準は、昭和48年5月にその時点における最新の科学的知見を検討・評価して「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること」と定められたものである。
硫黄酸化物については、昭和43年12月から施行され、順次強化されたばい煙発生施設の排出口の規制(K値規制)や49年11月から導入された総量規制、46年6月から規制が実施され、順次強化された低硫黄燃料の使用など、世界に先駆けて実施された強力な硫黄酸化物低減の対策の実施、及びこれに対応した企業等の公害防止投資などの効果により、大気中の二酸化硫黄の濃度は、一般局における年平均値をみると、42年度の0.059ppmをピークに43年以降減少し、著しい改善を示している。平成元年度は0.011ppmで昭和63年度0.010ppmと比較するとおおむね横ばいとなっている(第1-2-5図)。
また、環境基準の達成状況をみると、長期的評価による達成率は、昭和63年度99.7%、平成元年度99.5%とおおむね良好であり、ほとんどの地域で環境基準が達成されている。
(3) 一酸化炭素(CO)
一酸化炭素は精神神経機能に影響を及ぼす物質である。
大気中の一酸化炭素は物の不完全燃焼によって発生するもので、主に自動車排出ガスによるものとみられている。
現行の環境基準は、昭和48年5月、「1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること」と定められたものである。
自動車に対するいわゆる単体規制が昭和41年に開始され、逐次強化されてきた結果、大気中の一酸化炭素濃度は大幅に改善し、継続して測定している自排局の年平均値は47年度5.4ppmであったものが、平成元年度は2.4ppmと昭和63年度と比べて横ばいで推移している(第1-2-6図)。
また、環境基準の達成状況をみると、長期的評価による環境基準は昭和59年以降、自排局、一般局ともすべての測定局で達成されている。
(4) 光化学オキシダント
光化学大気汚染は窒素酸化物(NOx)と炭素水素類(HC)の光化学反応から二次的に生成されるオゾンなどの酸化性物質によって発生するもので、これらの光化学反応生成汚染物質の指標として、光化学オキシダント濃度が使われている。
地表付近のオゾン等の光化学オキシダントは、粘膜刺激症状、呼吸器への影響等の人への影響のほか、植物への影響も観察されている。いわゆる光化学スモッグ被害である。
大気中の炭化水素類は、自動車の排出ガスや塗装工場、印刷工場等炭化水素類を成分とする溶剤を使用する工場、事業場から排出される。
光化学オキシダントの環境基準は、昭和48年5月に「1時間値が0.06ppm以下であること」と設定された。
光化学オキシダントの測定局は昭和47年に175局、48年に349局となり、全国の監視測定体制も整備されてきた。この結果、「大気汚染防止法」に基づく光化学オキシダント注意報の発令も全国で行える体制が整った。「光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からその状態が継続すると認められる場合」に注意報が発令されることとされており、47年には発令回数は176回であったが、その回数は年によって大きく変動をしている。平成2年の注意報の発令日数は延べ242日で元年の延べ63日と比較して多くなっているが、連絡体制が整備されたことなどから、被害届出人数は2年は58人で元年の36人と比べ大きくは増えていない(第1-2-7図)。なお、地域別にみると、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の関東7都県で117日で約50%を占めており、この他は、山梨県、大阪府、広島県などで注意報が多く発令されている。
(5) 浮遊粒子状物質(SPM)
浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもの、いってみれば空中に漂う微小なゴミである。
浮遊粒子状物質は、大気中に長期間滞留し、その物理的性状からして呼吸器に対する影響がある。
浮遊粒子物物質については、ばいじん、ディーゼル黒煙等人為的に発生するもののほかに、土壌など自然界に起源を持つものがあり、さらにNOx等ガス状物質が大気中で粒子状物質に変化するなど、発生源が多様であり、このうち特にディーゼル車からの黒煙によるものが2〜4割を占めている。
現行の環境基準は、昭和48年5月「1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下であること」が定められたものである。
浮遊粒子状物質の濃度をみると、一般局の年平均値は、昭和58年度までは減少の傾向をみせていたが、ここ数年は横ばいであり、63年度、平成元年度の値は、それぞれ、0.039mg/m
3
、0.039mg/m
3
となっている。また、自排局について、昭和50年度から継続して測定している局の年平均値は、測定開始から大きな変化はなく、63年度、平成元年度それぞれ0.042mg/m
3
、0.047mg/m
3
となっている。(第1-2-8図)
また、一般局における環境基準達成率は、最近は、50%台で横ばいになっていたが、平成元年度は昭和63年度の47.0%に比べ、65.2%と増加した。また、自排局の環境基準達成率も、改善の傾向を示しており、63年度26.1%に比べ、平成元年度37.2%と増加している(第1-2-9図)。
(6) その他の汚染物質
以上のほか、石綿(アスベスト)、水銀、ホルムアルデヒド、ダイオキシン類及び有機塩素系溶剤についてモニタリング事業が行われている。