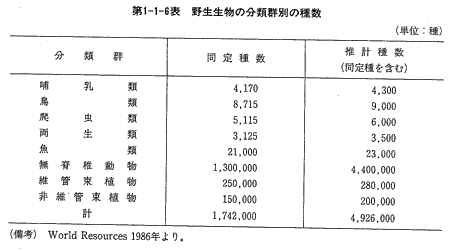
5 野生生物種の減少
地球上の生物種は、地球の歴史ともに進化を遂げてきたが、その過程で絶滅した種もある。しかし、それは、地史的な時間の物差し中で起こったことであって、突然死に絶えたといわれる恐竜でさえ、その「突然」の意味する時間は数百万年のことであったといわれている。今日、百年単位で、いや、十年単位で生物種が絶滅している。猛烈な速さでの数多くの生物種の絶滅は、ヒトというただ一種の生物によるものである。近時、人に人権があるように、他の生物にも生きる権利があるという考え方が出てきたのは、このような実態に直面してのことであると考えられる。
野生生物種の状況をみると、地球上に存在する種の数は500万〜1千数百万種といわれており、3,000万種を越えるという専門家もいる。生物学上種として記録されている種の数は、150万〜170万種であり、多くは同定されていない未知の生物種なのである(第1-1-6表)。
国際自然保護連合(IUCN)によれば、野生生物の分布は、寒帯6%、温帯59%、熱帯35%となっているが、これは、これまでの科学の成果として、生物学上種として記録されているもののみについての数字である。温帯地域の生物については比較的知られていることや、氷河期に多くの生物のシェルターとなった熱帯に多数の生物種がいるということなどから、実際には地球上の種の分布は寒帯1〜2%、温帯13〜24%、熱帯74〜86%と推定されている。特に、熱帯地域の中でも熱帯雨林は、地球表面の7%程度であるが、生物種の約半数がそこで生きていると言われている。熱帯林というと我々は、多くの生物でにぎやかな熱帯のジャングルを想像しがちであるが、種類は多いが意外に生物の数は少ない世界であるといわれている。このような、種類は多いが数はそれ程でもない生物が生息する熱帯林の減少は、多くの野生生物を知らないうちに絶滅に追いやっているおそれがあり、適切な保全が重要である。
また、干潟や浅瀬、サンゴ礁、マングローブ林は、埋立てなどの開発の対象となりやすいが、多様な生物が豊かに生息する場所であり、熱帯林と同様、野生生物の保護の観点からの配慮が必要である。
絶滅の危機に瀕している野生生物は、国際自然保護連合の調査によって分かっているもので1988年現在で動物4,589種(1986年には、動物3,117種、植物1万5,870種)となっている。また、ワシントン条約の規制対象品目は、1990年1月現在1,016品目になっている。これを種に換算すると、およそ動物3,000種、植物3万種といわれる。
野生生物を絶滅から守るため、ソ連、英国、オーストラリアなどの国で絶滅の危機に瀕している野生生物のリストアップを行い、それを国別のレッドデータブックとしてまとめる作業が進んでいる。我が国でも、環境庁が動物並びに維管束植物以外の植物及び菌類に関し、また、(財)日本自然保護協会及び(財)世界自然保護基金日本委員会が維管束植物に関して、それぞれ日本に関するレッドデータブックを作成している。
ワシントン条約などの野生生物保護のための取決めにもかかわらず、現在のままでは、2000年までに50万〜100万程度の種が絶滅するとの予測がされている(第1-1-7表)。我々は、現在よりも遥かに少ない生物種しかいない世界を次の世代に残すことになる。野生生物は、食糧、工業製品、医薬品等の原料となるほか、品質改良や近年のバイオテクノロジーの発展を支える遺伝子資源として有用性が増大してきているが、一方で生息地の破壊等によって、我々はその有用な野生生物種を減少させているのである。
野生生物の保護は、国際的にも今や地球環境保全上緊急に取り組むべき、重要な課題であると認識されており、UNEPでは1992年国連環境開発会議を目指して、生物学的多様性の保全のための国際条約の策定作業が進められている。