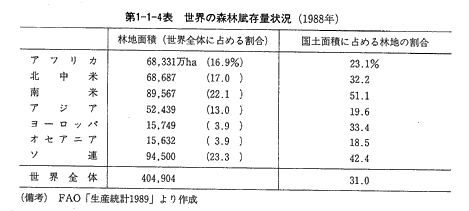
4 森林、特に熱帯林の減少
森林は、地球温暖化抑制の観点から二酸化炭素の吸収源として重視されてきている。しかし、森林は「緑の量」として大切なだけではない。従来、森林は人々の生活の場であったし、農村や都市に住む人々にとって災害を防止したり水を供給するなど国土を保全するものであった。そして、人間以外の多くの生物の住む場所でもあった。森林の保全や整備は、このような森林の多様な価値に留意したものである必要がある。特に熱帯林は、「遺伝子資源の宝庫」といわれるように、地球上の多くの生物種が生息しており、この観点から特別の重要性をもっている。
第2回世界気候会議でも、「我々は、生物学的多様性の保全、土壌安定や水系の保護といった森林の重要な役割に留意しつつ、炭素の貯蔵所としての役割を果たす世界の森林の保全が、他の手段とあいまって、地球の気候の安定化にとって非常に重要であることに留意する。」と述べている。
世界の森林の賦存量状況を見ると、南米及びソ連に多く存在し、これらの地域では国土に占める森林の割合も半分近くなっている(第1-1-4表)。また、世界の森林面積の推移をみると、ヨーロッパ、北中米は横ばいないし増加しているのに対し、開発途上国が多い南米、アフリカなどでは森林面積が減少している(第1-1-10図)。
1981年の国連食糧農業機関(FAO)とUNEPの調査結果によれば、1980年末の時点で熱帯林は全世界で19億3,500万haあるが、1980年から1985年までの間、毎年その約0.6%すなわち約1,130万ha(本州のほぼ半分の面積に相当)減少するとされている(第1-1-5表)。現在FAOでは、世界の森林資源評価調査を行っており、その最終結果はまだ報告されていないが、1990年4月の中間報告では、1981年の調査で予測された年間熱帯林減少面積の約1.5倍の毎年1,700万ha(日本のほぼ半分の面積に相当)の速度で減少しているとされており、さらに、1990年9月に発表されたアジア太平洋地域についての中間報告では、同地域では、1981年調査の予測の2倍以上の速度で熱帯林が減少し続けてきたと警告している。
一般的に、先進国にある温帯林や寒帯林は、造林の技術も確立し、かつ管理も適切に行われているのに対し、熱帯林は、その複雑な生態系のメカニズムについてほとんど未解明であり、熱帯林再生の技術は確立の途上にある。また、これら開発途上国では、急激な人口増加とそれに伴う農地の拡大、生活用燃料の薪炭材への依存、土地所有形態の不明確さからくる計画的土地利用政策の困難性等を背景として森林の管理が適切に行われにくい状況にある。
このような熱帯林のもつ自然的、経済社会的な特徴を踏まえつつ、急激に減少している熱帯林の保全の強化を図ることが緊急の課題となっている。
なお、我が国においては、いわゆる熱帯林は存在しないが、沖縄、小笠原諸島等に亜熱帯植生であるマングローブ林がみられており、その一部は西表国立公園及び小笠原国立公園に指定されている。