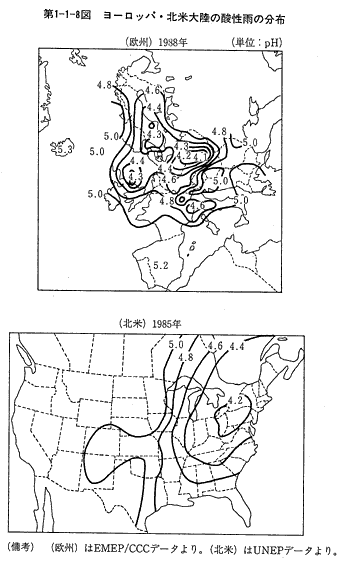
3 酸性雨
酸性雨は、主として化石燃料の燃焼によって生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質を取り込んで生じると考えられている通常pH(水素イオン濃度)5.6以下の雨をいう。
酸性雨の影響としては、雨が直接当ることや土壌が酸性化することによる樹木等の衰退、酸性雨が流入することによる湖沼や河川の酸性化及びそれの伴う魚類の減少をもたらすことなどがあり、生態系に重大な影響を与えているほか、都市の文化財等の腐食などの被害を招いている。最近では、酸性霧等による樹木への影響も指摘されている。
酸性雨は、スウェーデンが国連人間環境会議を提唱する契機にもなった問題であり、ヨーロッパや北米大陸では広範な地域に酸性度の強い雨が降り(第1-1-8図)、これによる被害も甚大で(第1-1-9図)、これらの地域の大きな国際的な環境問題になっている。
一方、我が国においては昭和58〜62年度まで第一次酸性雨対策調査を行い、雨水のpHや酸性降下物の量、湖沼水質への影響及び土壌への影響などを調査した。この結果によれば、雨水の成分については年平均値でpH4.4〜5.5の雨が観測されたが、湖沼の水質についてはほとんどの湖沼がpH7付近に分布しており、土壌についても酸性化の傾向は見られなかった。しかしながら、このような酸性雨が今後とも降り続くとすれば、生態系への影響が現れることも懸念される。このため、引き続き酸性雨についての調査研究を進めることが必要となっており、63年度から大気、陸水、土壌のモニタリング、酸性雨発生予測手法の開発、陸水、土壌への影響予測調査等を内容とする第二次酸性雨対策調査を実施している。また、平成2年度からは酸性雨等による森林への影響調査を行っているほか、地球環境研究総合推進費による東アジアにおける酸性、酸化性物質の動態解明に関する研究等を進めている。
さらに、酸性雨問題については、ヨーロッパや北米大陸の状況に鑑みれば、酸性雨による被害は国境を越えて発生する可能性が大きく、国を越えた地域的レベルでの取組が必要となっている。この観点から、中国、韓国でも一部取組が始まっており、東アジア地域における酸性雨の観測や研究協力の強化が今後の課題となっている。