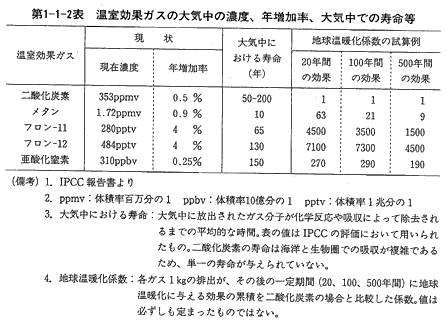
2 地球温暖化
ア 地球温暖化のメカニズム
地球では、大気中に含まれている水蒸気(H2O)、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、対流圏オゾン、亜酸化窒素(N2O)などの温室効果ガスによって地球から宇宙空間へ放射される熱を逃しにくくしており、生物の繁栄に適した気温が保たれている。
地球温暖化は、人間活動により、二酸化炭素、メタン等の排出が増大し、フロン等の人為的な温室効果ガスが新たに放出されているために、大気中の温室効果ガス濃度が上昇して温室効果が強まり、その結果気温が上昇し、人類や生態系がその基盤をおいている気候が変動することをいう。過去、気候は温暖期、寒冷期と変動を続けてきてはいるが、予測されている温暖化は過去1万年の間に例を見ないようなものであり、地球的な物差しからすれば極めて短時間のうちに起こることが特徴である。
温室効果ガスの濃度は急速に増加しており(第1-1-2表)、現在二酸化炭素に換算して産業革命以前より50%増大している。既にこの蓄積だけで地球の平均気温を将来1℃近く上昇させる効果を持つと考えられる。
温室効果ガスの地球温暖化に与える力(放射強制力)はガスの種類や濃度によって異なり、大気中での寿命も異なる。濃度当たりの放射強制力は、二酸化炭素では低く、フロン等で高い。メタンや亜酸化窒素はその中間である。このため、二酸化炭素が地球温暖化への寄与の約半分を占めるものの、フロン等のように大気中にごくわずかしかない物質でも地球温暖化に占める寄与は小さくない(第1-1-4図)。
これらの温室効果ガスの発生源別の温暖化への寄与はエネルギー起源のものが大きいが、他の活動も無視し得ないと考えられている(第1-1-5図)。
イ 地球温暖化の影響
特段の対策が採られない場合、今後も二酸化炭素等の排出量が増大し、2025年には二酸化炭素に換算して産業革命以前の2倍に達する速度で温室効果ガスの大気濃度が上昇し、気温の上昇や降水量の変化等が生じるだろうと予測されている。その影響は、1988年11月に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)とが設置した「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が1990年8月にとりまとめた第一次評価報告書によって「本格的な対策が講じられない限り重大かつ潜在的には破滅的ともいえる変化が生じるだろう。」と結論されている。
IPCCの影響予測の概要は以下のとおりである。
? 農業及び林業
農業については米国南部、西ヨーロッパなどの現在の高生産地域で穀物の生産が減少する。サヘル地域、ブラジル、東南アジア等の特に傷つきやすい地域(これらの地域の多くは開発途上国である。)では、生産減少を含め、深刻な影響を受ける可能性がある。北半球では、高緯度及び中緯度地域の潜在的生産量が増加する可能性があるが、新たに生産地域が拡大する可能性はない。
森林について最も影響を受けやすい地域は、半乾燥地帯など生物学的限界に近い地域である。
? 陸上生態系
今後50年間に気候帯が数百km極地方へ移動する可能性がある。植物や動物はこの急激な変化に適応できず、この移動から取り残され、種の分布や変化の結果、生態系の構造は変化し、幾つかの種は絶滅するだろう。
最も危険にさらされているのは山岳地、島しょ、沿岸地域など適応策が限られているところである。特に地域の社会経済が自然生態系に依存しているところでは、顕著な社会経済的影響がでる。
? 水
比較的小さな気候変動でも、乾燥地帯、準乾燥地帯の多くの地域で水資源上の大問題が生じうる。地域的な影響の詳細はほとんど知られていないが、多くの地域では降水量の増加に伴う様々な変化が生じうるし、他の地域、特にアフリカのサヘル地域のように既に限界状態にある地域では、水の利用可能性が減少し農業や水利用に重大な影響があろう。また、東南アジアのように人為的な調整がされていない河川に依存する地域では、ソ連・米国の西部のように調整された水資源システムを有する地域に比べて水文気象の変化の影響を受けやすい。
? 人間居住・健康
最も影響を受けやすい居住地域は、河川の洪水等の自然災害を受けやすい地域や沿岸である。多くの大都市が臨海部に立地している。最も影響を受けやすい住民は、開発途上国、低所得層、沿岸の低地や島しょの住民、半乾燥地帯の草地の住民、特に大都市のスラムの貧しい人々である。
大都市では、水や食料の欠乏、熱波や伝染病の拡大によって顕著な健康影響が起こりうる。降雨量や温度の変化により、病害虫やウイルスが、より高緯度に移動して、多くの人々を危険に陥れ、大規模な人口移動を引き起こしうる。
? 海洋と沿岸地域
2050年までに予想される30〜50cmの海面上昇は、島しょや沿岸地帯の低地に脅威をもたらす。21世紀末までの1mの海面上昇は、いくつかの島しょ国を居住不可能なものとし、都市の低地等を脅かし、河川への海水の遡上や海岸線の変化をもたらし、何千万人の人々に移住を余儀なくさせるだろう。
沿岸保全は巨大な資金を要する。急激な海面上昇は、沿岸生態系を変化させ、多くの漁業資源を脅かす。
? 季節的積雪、永久凍土
中緯度や高緯度の季節的積雪の地域分布や期間は縮小する。北半球の陸地の20〜25%を占める永久凍土は、今後40〜50年間に著しく減少し、地形の不安定化、侵食や地滑り等が生じる。
1990年10〜11月に開催された第2回世界気候会議では、IPCCの報告を受けて、その閣僚宣言で「気候への危険な人為的干渉を防ぐレベルに温室効果ガス濃度を安定化する」ことが地球温暖化対策の究極の目標であることがうたわれた。IPCCによると、温室効果ガス濃度を現状に安定化するには、寿命の長い二酸化炭素、亜酸化窒素、フロン等の人為的排出量を60%以上、メタンを15〜20%、直ちに削減する必要があるとされており、現状に濃度を安定化させても、温室効果ガスの過去の蓄積により、温暖化や海面上昇は直ちには止らないことも示されている。
したがって、現在の53億人の生活と将来の世代を考えた持続可能な開発を実現するためには、地球温暖化の速度を緩めて影響を緩和するとともに対策を講じるための時間的余裕を得るため、早急に、温室効果ガスの排出の抑制とその吸収源の保全・拡大を推進しなければならない。このため、その第一歩として温室効果ガスの排出量の安定化・削減に向けた取組が多くの先進国で行われている。
IPCCによれば、既に地球の地上平均気温は過去100年間に0.3〜0.6℃上昇しており(第1-1-6図)、平均海面も10〜20cm上昇していることが示されている。これが温室効果の増加によるものかどうかの検証、さらには、気候変動の時期、大きさ、地域的な変動の正確な予測、さらに、海洋や生態系の二酸化炭素の吸収機構と吸収量、気候変動による地域的な影響予測等、引き続き多くの事項についての不確実性を低減するために、観測監視と調査研究を推進しなければならない。
ウ 我が国の温室効果ガス排出の現状
国連の統計を用いたエネルギー起源の二酸化炭素の推計について見ると、1988年現在、世界での年間排出量は約58.9億トン(炭素換算)であり、一人当たりにすると1.15トンに相当する。これは、一人1日当たり12kg近い二酸化炭素を大気に捨てていることになる。排出量の半分以上が米国、ソ連、中国の上位3か国によって占められ、我が国の排出量は世界第4位であり、世界の4.7%を占めている。一人当たりの排出量では我が国は主要先進国の間では低い部類であるが世界平均の約2倍となっている(第1-1-3表)。森林減少に伴う二酸化炭素の排出量は、未だよくわかっていないが、IPCCでは17億トンと見積もられている。
我が国の二酸化炭素排出量については、環境庁の試算では次のようになっている。二酸化炭素は、主にエネルギーの利用によって排出されており、1989年度では、外航船舶や、国際線の航空機の燃料利用も合わせて、約2億8,600万トン(炭素換算、以下同じ。)の排出があった。また、二酸化炭素はセメントや鉄鋼の生産に用いられる石灰石の分解や廃棄物の焼却によっても排出され、石灰石からは1989年度では約1,200万トンが排出されている。廃棄物の焼却による排出の見積もりは困難であるが、一般廃棄物の焼却からは1988年度に約800万トン程度の排出があったと推計され、産業廃棄物の焼却による排出と合わせるとおよそ,1,000万トン程度の大きさと考えられる。しかしながら、この中には、紙、木片、台所厨介など、生物が大気中から固定した二酸化炭素分がかなり含まれていると考えられる(第1-1-7図)。
エネルギー利用に係る二酸化炭素排出量を直接の排出源別にみると、需要分野では、産業部門が9,170万トンを直接排出しており、32.1%を占めている。そのうち3分の2が鉄鋼、窯業土石、化学、紙パルプの4業種で占められている。民生部門では3,380万トン、運輸部門では5,410万トンが直接排出され、それぞれ、11.8%、18.9%を占める。バンカー油分は外航船舶、国際線の航空機用燃料からの排出分であり770万トンと2.7%を占めている。発電や石油精製などを行うエネルギー転換門からの直接排出量は9,840万トン、34.5%と最も大きい割合を占めているが、他の部門の要求する電力や石油製品などの最終需要を満たすための排出が大部分を占めている。
メタンについては、正確な排出量の把握は困難であるが、IPCCによると、世界の排出量は湿地、水田、家畜、天然ガス利用、バイオマス燃焼、白蟻、廃棄物埋立、石炭採掘等から5億2,500万トン(メタン重量)が排出されると推定されている。亜酸化窒素については、さらに推定が困難であり、IPCCでは海洋、土壌、エネルギー、バイオマス燃焼、肥料施用等から440万トン〜1,050万トンの排出があると推定しているが、未解明の発生源の存在も示唆している。我が国におけるメタンの人為的排出量は環境庁の調べでは75万トン〜145万トン程度と見積もられ、亜酸化窒素の人為的排出量は2万7,000〜4万7,000トンと見積もられている。