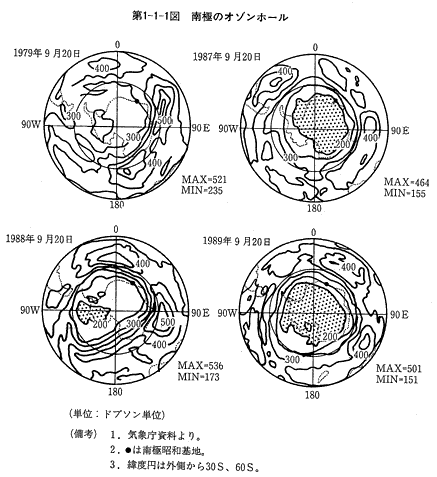
1 オゾン層の破壊
成層圏の(O3)層は、約30億年をかけてつくりだされた地球の生物を守る宇宙服である。一般に紫外線は殺菌作用があることが知られているが、概ね320nm(ナノメーター、1nmは1×10−9m)以下の短い波長の紫外線は生物にとって致命的に有害である。成層圏のオゾン層は、地球に降り注ぐ太陽光線のこの有害な紫外線を吸収して、地球の生物を保護している。地球上の生物は、このオゾン層のおかげで、太陽光線の届かない深海から海面近くへ、そして地上へと進出することができたのである。有害紫外線の増加は、人体に対して皮膚ガンや白内障等の健康被害を発生させるだけでなく、植物やプランクトン等の成育の阻害等を引き起こす。
現在、成層圏オゾン層の破壊が明らかにされており、南極上空では、広い範囲にわたって春先(9月〜10月)頃にオゾン濃度が広い範囲にわたって急激に低下する「オゾンホール」と呼ばれる現象が1980年代に入って観測されている(第1-1-1図)。北極上空では、気象条件が異なることから、オゾンホールの形成には至っていないが、同様にオゾン濃度が急激に減少する可能性があると考えられている。また、北半球中高緯度地域において、1970年以降オゾン全量が減少傾向にあり、この傾向は冬に顕著となっている。1990年3月に得られた人工衛星のデータによれば、特にスカンジナビア半島北方海上から中央シベリア北方海上にかけて、過去11年の平均値より30%を超える減少がみられた(第1-1-2図)。
国内では札幌市、茨城県つくば市等でオゾン層の観測が行われているが、1990年の観測結果をみると(第1-1-3図)、札幌市で平年より少ない月が多く2月および5月には1958年の観測開始以来その月としての最低値を記録した。
オゾン層を破壊する物質は、フロン(厳密にはそのうち塩素原子を含むもの。)、ハロン、1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホロム)、四塩化炭素等である。これらは、対流圏中ではほとんど分解されずに成層圏に達する。そこで太陽からの強い紫外線を浴びて分解し、塩素原子や臭素原子を放出するが、これらが触媒となってオゾンを分解する反応が連鎖的に発生し、その結果、成層圏のオゾン層は破壊されていくことになる。
このため、国際的に、「オゾン層の保護のためのウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」によって、これらの物質のうち一定のものに対する規制を行っている。
オゾン層を破壊する物質の代表とされる5種類のフロンは、1986年現在、世界で約115万トン、日本では約13万トン生産されている。
フロン等は、大気中に放出されてから長期間残存することから、2000年にフロンが全廃された後もオゾン層の破壊は続くことになる(第1-1-1表)。したがって、フロン等の規制を着実に実行するとともに、オゾン層や大気中のフロン等の観測監視及びその変化の将来予測、生物・人体への影響などの調査研究を行って、オゾン層破壊による被害が現実のものとならないよう対処することが重要となる。