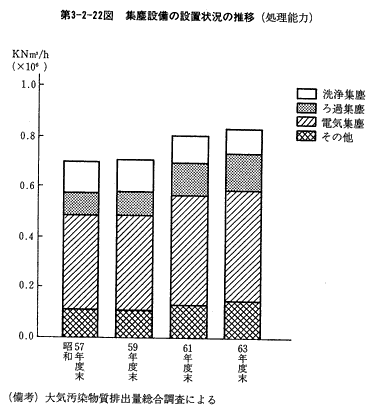
3 取組の状況と検討の方向
(1) ばいじん、硫黄酸化物及び窒素酸化物の対策
ア ばいじん対策
浮遊粒子状物質や降下ばいじんの原因物質の一つであるばいじん(黒煙・すす)に対しては、「大気汚染防止法」に基づき施設ごとに濃度規制が課せられており、電気集塵機等により煙突から排出される排ガス中のばいじんを除去することによって対応が行われている。我が国の集塵設備の設置状況は第3-2-22図のとおり逐次増強されてきており、61年度のばいじんの潜在発生量約529万7千トンのうち約98%に当たる約519万5千トンがこれらの公害防止設備によって除去されていると推計されている。この結果、降下ばいじんについては、大きな改善をみてきている。しかし、浮遊粒子状物質については、依然として改善を要する状況にある。
イ 硫黄酸化物対策
昭和40年代の深刻な硫黄酸化物による大気汚染に対処するため、「大気汚染防止法」に基づく硫黄酸化物の排出規制が課せられた。硫黄酸化物の排出規制には、硫黄酸化物の排出が環境に及ぼす影響(着地濃度)を一定レベル以下に抑え込むために煙突の高さに応じて排出する量を規制するいわゆるK値規制と、K値規制のみでは環境基準の達成が困難な地域において、工場、事業場ごとに排出量の合計を規制する総量規制がある。
硫黄酸化物規制に対応するための方法としては、燃料の低硫黄化、すなわち、輸入原油の低硫黄化や重油の中の硫黄分を少なくする重油脱硫により硫黄分がより少ない重油を使ったり、硫黄分をまったく含まない天然ガスに燃料を転換する方法と、排煙脱硫装置により排気ガスに含まれる硫黄酸化物を除去する方法がある。
K値規制については、1968年の第1次規制から1976年の第8次規制まで二酸化硫黄の環境基準の段階的達成を目標として、ほぼ毎年改定強化された。これに対応するため、エネルギー供給面からも、計画的な低硫黄燃料の供給の確保が図られた。
また、総量規制については、1974年の第1次指定から1976年の第3次指定までに合計24の総量規制指定地域が指定され、規制が実施されている。
硫黄酸化物排出量は、第3-2-23図にみるとおり大きく減少し、その濃度も改善してきている。
ウ 窒素酸化物対策
窒素酸化物の主要な発生源は、工場・事業場の固定発生源と、自動車である。このうち、工場・事業場については、「大気汚染防止法」に基づき、発生施設ごとに排出ガス濃度の規制を行なう排出規制と、硫黄酸化物と同様に地域を限って、工場、事業場の排出総量を規制する総量規制がある。排出規制については、昭和48年の第1次規制以降数次にわたり規制の強化を行なっている。工場・事業場における窒素酸化物対策としては、燃焼方法の改善等により窒素酸化物排出量を抑制する方法と、排煙脱硝装置の設置により窒素酸化物を除去する方法がある(第3-2-24図)。このうち、燃焼方法の改善の基本である空気比の適正化は省エネルギーにも大きく資するものである。また、排煙脱硝装置は、我が国が世界に先駆けて導入したものであり、普及台数も世界の中で群を抜いている。
自動車から排出される窒素酸化物についても「大気汚染防止法」により許容限度が定められており、これは世界でもっとも厳しいレベルにある。とりわけ、ガソリン乗用車については、未規制時に比べて92%窒素酸化物排出量を削減する大幅なもの(アメリカのマスキー上院議員の提案した規制内容にほぼ相当する53年度規制。)であり、規制が発表された当初は、燃費の悪化や自動車価格の上昇により日本経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるといった主張もあった。しかし、結果的には排ガス対策と燃費低減を同時に達成する技術が開発され、我が国の自動車にかかる技術の蓄積が著しく進んだことは周知のとおりである。これは、排出ガス低減の技術予測に基づく環境保全のための適切な目標設定が技術開発を促進し、国民経済上も好影響を与えた典型的な例といえよう。
このような取り組みにもかかわらず、総合的な対策の一層の強化が必要な状況であることは第2章第1節で述べたとおりである。特に、ディーゼル車については、これまでも厳しい規制を実施してきたが、自動車排出ガスによる大気汚染の防止のため、一層の排出基準の強化が必要であることから、中央公害対策審議会は、平成元年12月22日、遅くとも今後10年以内に3割から6割の削減が必要であるとの答申を出しており、これに沿って、今後規制が順次強化されることとなっている。
また、以上のような単体規制を実施しても、自動車の走行量の増大によりある程度相殺されざるを得ない状況にあると考えられる。一方、工場等の固定発生源に対しては、高濃度地域で一律規制に加えて総量規制が実施されている。このような中で、大都市地域における二酸化窒素の環境基準を達成するためには地域全体の自動車排出ガスの総量を抑制していく方策の可能性の検討を行う段階に達していると考えられる。環境庁では、そのような新たな考え方に立った対策についても検討を進めている。
軽油を燃料として使用するディーゼル車は、窒素酸化物や粒子状物質の排出量がガソリン車と比較して多いなどの環境保全上の問題がある。しかし、近年、ディーゼルトラックによる貨物自動車の交通量が著しく増大し、また、ディーゼルトラックとガソリントラックの併存するクラスにおける車種の割合もディーゼル車が増大しており、昭和60年度から62年度までの2年間にトラックによる燃料使用量はガソリンが約13%減少する一方で軽油は13%増大している(62年度の消費量は軽油が約2,120万キロリットル、ガソリンが約560万キロリットル)。これには種々の要因があるが、その一つとしてディーゼル車が経済的にみてガソリン車より優れていることがあげられる。例えば、ディーゼル車はエンジンの耐久性が良く、走行距離当たりの燃料消費量も少ない。さらに、燃料自体の小売価格をみても、63年の平均でガソリンは1リットル120円程度であるのに対し、軽油は1リットル70円程度と軽油の方がかなりやすい。走行距離当りの燃料消費量や燃料価格を総合してガソリン車とディーゼル車の併存するクラスについて燃料に係る費用等を比較して見たのが第3-2-25表であり、走行1キロメートル当りのディーゼル車の燃料費はガソリン車の2分の1となっている。
このような価格差等の経済的要素が、交通手段の選択要因の一つとなることは否定しがたいところである。また、自動車の車種間の選択のみならず、自動車と鉄道、船舶等の他の交通手段との間でも、利便性等の要因の加えて運賃その他の費用の差による選択が生じ得るといえる。したがって、中長期的な観点から、燃料の価格差や運賃などの経済的要素と環境問題との関係についても検討を加える必要がある。
(2) 省エネルギーによる環境負荷の軽減
省エネルギーは、一次エネルギーの大宗を輸入原油に依存している我が国にとって独自の努力によってエネルギー資源の量的制約を緩和しうる手段である。また、省エネルギーは、基本的には硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質の排出の低減に資するとともに、化石燃料の消費の抑制につながることから二酸化炭素等の温室効果気体の排出抑制策としても有力な手段である。
地球環境保全のために二酸化炭素の発生量を削減するための手段は、硫黄酸化物、窒素酸化物等のように技術的な処理を行うことは今後の技術開発に待つべきであり、当面の現実的な対応としてはエネルギー効率の向上により化石燃料の消費量を減らすことと、二酸化炭素の発生を伴わない、もしくは少ないエネルギー源の利用を促進することである。
省エネルギーは、化石燃料の消費量を減らすことに直接資するものであり、地球温暖化対策の有力な手段であることが世界の共通認識となっている。このため、以下では省エネルギーについてこれまでの我が国の経験、諸外国の取り組み及び今後考えられる方策についてみる。
ア 我が国の省エネルギー対策の経験
省エネルギーは、燃料費の節約に直接結びつくことから、これまではコスト節約という純粋な経済行為として行われてきた面が強い。
我が国では、二度の石油危機を契機として産業部門、民生部門、運輸部門及びエネルギー転換部門を通じて省エネルギーのための大きな努力が払われてきた。以下その内容をみてみよう。
工場内における省エネルギー対策は、比較的容易なものから、より高度なものまで次の三段階に分けることができる。
? 従来の設備、プロセスを基本的に変えないで、エネルギー管理を改善・強化し、作業方法、操業条件を見なおす段階
? 本体設備の変更はしないが、小規模の投資により設備を付加したり、一部設備の改善によりエネルギー効率の向上を図る段階
? 従来の設備、プロセスを大幅に変え、高効率型の生産設備、プロセスの導入を図る段階
第一段階は、ソフト面での改善の段階であり、例えば、モーターの空転やスチーム漏洩等の防止、適切な燃焼条件を確保するための空気比管理の強化等がこれにあたる。これらの対策は、比較的地味で小規模のものが多いが、一つ一つの積み重ねが大きな省エネルギー効果を生み出すものである。また、この段階の対策が十分に行なわれなければ、第二段階、第三段階の投資は、無駄になってしまう性格のものであり、省エネ対策の基本といえる重要な段階である。
第二段階は、例えば排熱を回収し利用する装置、熱を捨てないよう貯えておくための蓄熱槽の導入等がこれにあたる。効果的な付加的設備の設置や改良工事の実施により、少しの投資で大きなエネルギー効率の改善が期待できる段階である。
第三段階は、基本的な生産システムそのものが切り変わることから、大規模投資とともに技術開発努力が必要な段階である。これまで実施された例としては、鉄鋼業における連続鋳造設備(工程の連続化)等がある。
これらの対策は、いずれも工場の現場でエネルギー管理を専門に行う技術者が日々常にエネルギー利用設備の維持、点検に努めるとともに、創意工夫を重ねることによって初めて効果の上がる性格のものである。我が国の産業部門の省エネルギーが世界一進んだ最大の理由は、このような有能な技術者が、エネルギーを多く使う工場のほとんどにいて、省エネ努力を行なってきたことに求めることができよう。また、法制的にも、昭和54年に制定された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(いわゆる「省エネ法」)により、一定規模以上のエネルギーを利用する工場には、エネルギー管理の専門職員として国家試験に合格した「エネルギー管理士」を置かなければならないことになっており、省エネルギーを推進するための体制づくりが義務づけられている。この制度は、工場の省エネルギーを推進するための世界の範となるものであるといえよう。
民生部門、運輸部門のこれまでの省エネルギー対策の中心は、個別の機器や建物の性能の向上対策であり、「省エネ法」に基づき、エアコンディショナーと乗用自動車についてエネルギー消費効率の基準が定められるとともに、住宅の断熱基準や事務所の用途に供する建築物等に係る省エネ基準が定められている。
発電部門を中心とするエネルギー転換部門では、これまで、発電効率の向上と、送配電損失率の低減等が図られてきている。
また、省エネルギー設備の設置に対しては、昭和50年度より税制上、金融上の優遇措置が講じられ、特に、56年度からは、省エネ性の高い設備について設備取得価額の7%相当額の法人税額の特別控除又は普通償却に加えて30%の特別償却を選択適用できる制度が続いており、我が国の省エネルギーの推進に大きく貢献した。
省エネルギーの一層の進展を支える省エネ技術の開発も、産業、民生、運輸及びエネルギー転換部門の各部門を通じて積極的に行われきた。特に、省エネルギー効果は大きいが開発リスクが高いため民間企業単独では行うことができない先進的で大型の省エネルギー技術の研究開発については、産業界や大学等の研究機関と密接な連携の下にムーンライト計画として国が実施している。また、個々の企業等においてもさまざまな技術開発が行われている。
イ 諸外国での省エネルギーのための取り組み
諸外国でも、省エネルギーを推進するための様々な取組が行われている。
米国では、運輸部門におけるエネルギー消費が全体の35%を占め(第3-2-10図参照)、そのほとんどが自動車用の燃料である。自動車の燃費の向上を図るため、企業平均乗用車燃費規制(CorporateAverage Fuel Economy(CAFE) standard)がある。これは1978年に創設されたものでありガソリン1ガロン当たり走行距離の基準値を各年度に設定し、各自動車メーカーの販売車の加重平均値がこれを達成しなければならないとするとともに、達成しないメーカーに対しては、未達成の程度に応じた課徴金を徴収するという制度である。(我が国の「省エネ法」に基づく自動車の燃費基準は、乗用自動車を車両重量別に4段階に分け、それぞれの区分について各メーカーの販売車の加重平均値がこれを達成しなければならないとしている。)
また、家電製品についても、1987年、エネルギー効率基準を定める法律が施行されているほか、州によっては独自の効率基準を定めている。
さらに、エネルギー使用効率の向上、再生可能エネルギー源の開発、導入等を目的とした「公益事業規制法」(thePublic Utility Regulatory Policy Act of 1978、いわゆるPURPA法)に基づき、効率等が一定の基準を満たしたコージェネレーション又はバイオマス、太陽、風力等の再生可能資源を利用する小規模発電施設からの電力については、電気事業者が自ら発電する場合あるいは他から購入した場合に要するコスト(回避原価)を上回らない価格で買い取らなければならないこととされている。
英国では、民生部門においては断熱化への補助を、産業部門においては新技術・応用技術の普及促進によるエネルギー効率化実証プロジェクトに対する補助、コージェネレーション、熱回収プロジェクト等に関するコンサルタントサービスに対する補助等を行なっている。
西独では、産業部門においては省エネルギー投資に対する補助を、民生部門においてはヒートポンプ、ソーラーシステム等新型暖房装置に対する省エネルギー投資の割増償却等を行なっている。また、電力会社自身が発電所による大規模なコージェネレーションを導入し、熱は地域熱供給網を通じて一般に供給している。
ウ 省エネルギーによる二酸化炭素削減方策の検討
地球環境保全のための二酸化炭素の削減方策を考えた場合、一次エネルギー投入量をできるだけ小さくしていくことが重要である。
第3-2-26図は、我が国のエネルギーフローを試算したものであるが、一次エネルギー投入量のうち有効に利用されているのは35%に過ぎず65%が排熱の形で直接環境中に捨てられている。これは、例えば火力発電所においては投入エネルギーの4割程度が電気に、ガスコンロにおいては投入したエネルギーの5割程度がお湯の熱に、ガソリン自動車においては投入したエネルギーの2割程度が動力に変換されるに過ぎず、残りはいずれも排熱の形で環境中に捨てられていることにみられるように、エネルギーの持つ熱量を十分に使いきっていないことによる。
一次エネルギー投入量をできるだけ小さくしていく方策は、この65%のロスを有効に活用しロスの比率を小さくしていくことと、有効に活用されているエネルギーの絶対量を小さくしていくことである。その具体的方策としては以下のものが考えられる。
a) エネルギーの段階的利用の推進
エネルギーの一部が使用されることなく捨てられている場合には、エネルギーロスを少なくするため、燃焼によって得られる熱を高温から低温まで何回も使う段階的利用を進めることが重要である。
(環境に配慮したコージェネレーション)
エネルギーの多段階利用を行う設備としてコージェネレーションがある。コージェネレーションとは、燃焼により発生する熱の高温部から動力(発電に用いられる)を、動力がつくられる際の排熱等から熱を同時に取り出すものである。電力需要と熱需要が適切に組み合わされた場合は総合エネルギー効率が70〜80%にまで向上する。この場合、得られる電力と熱の両方を使い尽くせばエネルギー利用の効率化に寄与するものである(第3-2-27図)。
コージェネレーションには、動力部分のエネルギーを作り出す方式として、1,500℃以上の高温領域で燃料が爆発的に燃焼しその高温高圧ガスでピストンを動かす「ピストン内燃機関」方式、約1,100℃程度の高温ガスの中でタービンを連続的に回転させる「ガスタービン」方式及び約500℃の蒸気でタービンを回す「蒸気タービン」方式(一般産業界でよく行われている)等がある。「ピストン内燃機関」方式や「ガスタービン」方式は、「蒸気タービン」方式と比べて熱をより高温段階から利用することができる。
一方、これらは燃焼温度が高いこと等から窒素酸化物を多く発生するという面を持つ。特にディーゼルエンジン等の「ピストン内燃機関」方式の場合は、その燃焼特性から窒素酸化物濃度は非常に高い。したがって、これらの方式を利用しようとする場合には、適切な窒素酸化物対策を講じていく必要がある。
産業分野では、熱需要が相当程度ある工場でコージェネレーションの導入により総合エネルギー効率の向上が期待される。一方、民生分野では、ホテル、病院、業務用ビル等熱需要と電力需要が適切に組み合わされた場合には総合エネルギー効率の向上が期待される。さらに、発電所の排熱を周辺地域に供給する形及び地域熱供給の熱源としてコージェネレーションを導入することも考えられる。
近年、コージェネレーションの導入が進み、ガスタービン、ガスエンジン及びディーゼルエンジンを用いたコージェネレーションの設備能力は、平成元年9月現在、産業用が113万5千kw、民生用が14万8千kwとなっている(我が国の全発電能力は元年9月現在1億8510万kw)。
社会全体のエネルギーロスの縮小のためには、エネルギー効率の向上につながる形でのコージェネレーションの普及の促進を図ることが有効な方策の一つであると考えられる。しかしながら、現在のコージェネレーションについては、環境問題があるほか、取扱の困難さ、運転の安定性、料金負担の公平性、燃料のエネルギー政策との整合性、既存の電力システムとの整合性といった課題があるので、これらの課題を解決すべくシステム作り、技術開発等をさらに進める必要がある。
さらに、社会全体のエネルギー効率を上げるようなコージェネレーションであっても、他方では別の新たな環境負荷を増大させることとなる場合があるものについては、当然のことながらこの面での環境負荷を増大させないようなシステム作り、技術開発等に引き続き取り組む必要がある。
特に、二酸化窒素の濃度の高い大都市地域でのコージェネレーションの導入に対しては十分な対策を講ずる必要があり、地域の環境保全に十分配慮しつつその普及を図っていくほか、コージェネレーションの導入に対応し、排出規制の対象施設の拡大等についても検討していく必要がある。
(コンバインドサイクルによる発電)
現在、火力発電の主流を占めているのは「汽力」方式、すなわち、ボイラーの内で燃料を燃やし、水を熱して蒸気をつくり、この蒸気がタービンを作動し、タービンが発電機を回して電気をつくるという方式をとっている。熱効率を高めるためには、蒸気温度をより高温にしなければならないが、現在の技術では566℃程度が実用的な蒸気温度の上限となっており、熱効率は40%程度がほぼ限界である。一方、ガスの膨張力を利用して発電する「ガスタービン」方式では、タービン入口ガス温度は約1,100℃まで高めることができ、さらに、その排ガスの温度で蒸気をつくり、「汽力」方式の発電を併せて行う「コンバインドサイクル」発電を行なうことができることから、熱効率は約44%程度に上昇する。従来の火力発電方式の熱効率は平均は約37%であることから、このような方式を用いた発電は極めてエネルギー効率の高いものである。「コンバインドサイクル」発電は、現在、世界中で約100基が稼動中であり、我が国でも新規の発電所等で導入されはじめているところであるが、今後一層の導入を促進する必要がある。
(ヒートポンプによる排熱の汲み上げ)
ヒートポンプシステムとは、熱源として低温排熱、外気温等の未利用エネルギーを利用し、電気、ガス等のエネルギーをポンプの駆動エネルギーとして利用することによってより高い熱を得るものであり、投入エネルギー以上の再生エネルギーを生み出すものであることから効率的なエネルギー利用に大きく資する。その仕組みは、冷媒として用いられる液化ガスが蒸発するときはまわりから熱を奪い、液化するときには熱を放出するという性質を利用したものであり、例えば、暖房を行う場合に、冷媒を屋外で減圧し屋外の熱を奪って蒸発させ、これを屋内にもってきて圧力をかけることによって液化し、その液化に伴う熱を発散させようとするものである。このようなシステムを用いると好条件下では、ポンプの駆動に用いられたエネルギーの熱量の3.5倍程度の熱量を得ることが可能である。一方、ヒートポンプは、比較的低レベル温度の産業用需要や民生用需要には対応可能であるが、産業用の高温の熱需要に対応するには適当な熱媒体がないこと等から困難な面がある。
ヒートポンプを利用した熱の供給は、エネルギー利用の効率化に資するものであり、その推進が必要である。特に、ゴミ焼却場、地下鉄、送電線、下水処理場等の排熱、河川水、下水・下水処理水等の未利用エネルギーがある場合は極めて効率的であり、導入の促進が望まれる。
b) 工場の排エネルギーの社会的利用
我が国のエネルギーを多く使う工場では、自工場内で可能な省エネルギー対策は相当進んでいるが、有効に利用されずに捨てられているエネルギーも多い。第3-2-28図は、我が国のある製鉄会社の高炉一貫製鉄所における排熱の状況の一例であり、64%のエネルギーは有効に使われているが、36%は排エネルギーとして捨てられている。しかも、排エネルギーの中には1,500℃程度の高温のものもある。また、セメント産業においても投入エネルギーのうち20%程度が排エネルギーとして捨てられている。これらの排エネルギーの中には、物理的に利用ができないものもあるが、社会全体での利用を進めることにより、個々の工場におけるエネルギー効率はもとより社会全体のエネルギー効率を上げる余地があるものが多く、その利用を進めることが重要である。
工場の排エネルギーを工場外で使う方法としては、熱として使うことと電気に変換して使うことが考えられる。このうち、熱として送る場合は新たな導管を敷設する必要があり、費用面から近接した場所に対するものに限られる。一方、電気として売る場合は、既に一部の排エネルギーを利用した発電所を一般電気事業者と共同で作り、その発電の一部を一般電気事業者に売電することが行われている。
c) 都市の未利用エネルギーの利用
都市の中には、様々な未利用エネルギーが存在する。総合研究開発機構(NIRA)の試算によると、東京23区の下水処理場、ゴミ焼却場、地下鉄、地下送電ケーブル等からの排熱は、年間原油換算1,900万キロリットルであり、東京23区の集合住宅および一般建物の給湯・暖房熱需要の83%に相当し、このうち、熱供給の可能性がある量は熱需要の50%程度であるとしている。清掃工場から出される排熱を利用した発電が既に全国89工場で行われており、総発電設備能力は約25万4千kWとなっている(昭和62年1月現在)。このうち東京都では11の清掃工場に総計で5万6千KWの発電設備を持っており、昭和63年度において約3億7千万kWhの発電を行ない、その52%に当たる約1億9千万kWhを電気事業者に売電している(第3-2-29表)。このような売電は全国各地で行われている。
また、東京都の清掃工場の排熱は地域冷暖房の熱源等としても利用されており、このような取り組みが全国的に展開されることが期待される。
このほか、既に述べたとおり、下水処理場、地下鉄の排熱等の都市内の未利用エネルギーのように外気との温度差が少ないエネルギーは、ヒートポンプによってこれを汲み上げ、地域冷暖房等を通じて地域全体で使っていくことが極めて効率的である。
d) 既存の技術の普及
省エネルギーに関する既存の技術の中には、排熱回収技術に代表されるようにエネルギーロスを小さくするものと、生産設備の合理化に代表されるように、より少ないエネルギーで同じものを作りだすものとがある。
我が国の工場における省エネルギー技術は、既に見たとおり世界的にみても相当進んでいるが、中小企業においては省エネルギー対策が十分に進められている状況にない。(財)省エネルギーセンターが実施している中小企業に対するエネルギー診断においても、約70%の工場において、現状においても十分経済性のある省エネルギー対策の余地があると報告されており、既存の技術の普及による省エネルギーの推進も重要である。また、断熱化の推進等や建て替えの際エネルギー効率のよい建物への建て替えを進めるなどによる省エネも重要な課題である。
e) 交通システムの合理化等の交通対策
エネルギー効率の観点からは、自動車と比べて鉄道をはじめとする大量交通機関の方が優れている。また、都市部においては渋滞により自動車の本来的な機能が十分果たされていない場合があり、相当程度のエネルギー消費量の増加が渋滞により生じていると考えられる。
このようなことから、エネルギー効率改善のため、また、大都市等で問題となっている窒素酸化物対策の観点からも、大量交通機関の活用などによるエネルギー面から見て効率的な交通システムが求められる。例えば、公共交通機関の利便性を高めること等による人流対策、共同輸配送等物資輸送の効率を高めることによる物流対策を一層推進する必要がある。
また、電気自動車等の一層の開発普及などのエネルギー効率の高い新たな技術による対応も必要である。
f) 二酸化炭素の排出量の抑制に資する社会制度の導入
サマータイム制度は、日照時間の長い夏の間だけ時計を標準時間より一定時間進めて昼間の時間を有効に使おうとする制度であり、照明等のエネルギーの節約になること等から我が国とアイスランドを除く全てのOECD諸国、中国等で採用されている。我が国でも、昭和23年から26年まで採用していた。また、第2次石油危機を契機に採用が検討されたが、世論の動向等をも踏まえ導入は見送られた。しかし、照明や空調によるエネルギーを節約できる可能性があることに加えて、自由時間の有効活用を図ることができるというメリットを有していることから、導入の検討を進める必要がある。また、可能な工場、事業場における連続一斉休暇制度の導入や週休2日制の普及の促進等も省エネルギーの推進につながり、二酸化炭素の排出量の抑制に資することから、積極的に進める必要がある。このように、社会システムを二酸化炭素の排出量の抑制に資するように変えていくことも重要である。
g) 個人の行動レベルにおける二酸化炭素の排出量の抑制
国民一人ひとりがエネルギーを大切に使っていくことによりエネルギーの需要を抑制していくことは、二酸化炭素の排出量の抑制のために不可欠の課題である。過剰冷房や過剰暖房はエネルギーの浪費である上、場合によっては快適性を通り越してむしろ身体に悪いことでもあり、まずこのようなことをなくす必要がある。また、使っていない電灯を消すなどいわば人間としての節度ある態度に基づいた省エネや、エネルギー機器の上手な使い方による省エネの推進も必要である。
一人ひとりの身近な省エネルギーに関する心がけは、社会全体では大きなエネルギーの節約につながる。例えば、暖房温度を1℃下げただけで、一家庭で年間約20リットル、日本全体で80万キロリットルの石油を節約できると試算されている(第3-2-30表)。我々のライフスタイルを環境上健全なものに変えていく必要がある。
また、住宅の断熱化の推進や太陽熱を利用した給湯、暖房システムの利用、多機能ヒートポンプを利用した給湯・冷暖房システムの採用など、二酸化炭素の排出量の抑制に資するシステムを家庭のなかに取り込むことも重要である。
さらに、以上見てきた公害防止対策、省エネルギーの推進対策に加え、環境負荷の少ない新エネルギーの開発・導入への取り組み等が行われているが、これらについては次項で述べる。