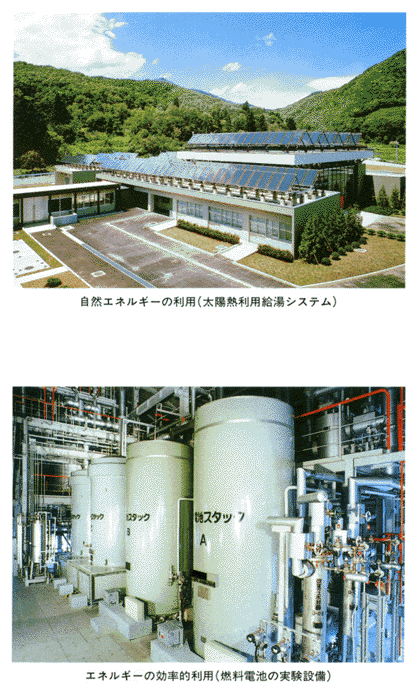
4 環境保全型エネルギー利用への転換を目指して
既に見たとおり、環境問題とエネルギー利用は密接な関係があり、環境保全の観点を考慮したエネルギーの利用が必要である。
(1) 省エネルギー型社会の構築
環境保全の観点からエネルギー利用を考えた場合、環境保全に様々な面で資する省エネルギーの推進施策を抜本的に強化し、社会全体を省エネ型に変えていくことが必要である。
とりわけ、地球温暖化対策としての省エネルギーに対する世界の期待は大いに高まってきている。このため、今後の省エネルギー対策は、地球環境に対する負荷の軽減という観点を踏まえ、従来の枠にとらわれず、広い視野から一層の努力を傾注する必要がある。
今後の省エネルギーの推進に当たっては、前項で示したエネルギーロスを少なくすることと有用エネルギーを少なくてすむようにすることの双方を進める必要がある。
その際、第一に重要なことは、個々の省エネ機器や技術の導入のみならずシステムとしての省エネルギー対策を積極的に推進していくことである。このため、まず、先に記述した課題を解決した上でのエネルギー効率の向上につながるコージェネレーション、コンバインドサイクル発電、ヒートポンプ等の導入促進により効率的なエネルギー需給システムを確立するとともに、工場、都市等の排エネルギーの社会的利用を進めることが重要である。また、交通システムの合理化等都市の構造にまで遡った対応や、サマータイム制度の導入等による省エネルギーの推進策についても、検討を行う必要がある。
第二に重要なことは、これまで進めてきた自動車や家庭電化製品のエネルギー効率向上や生産工程における省エネルギー化を一層推進するとともに、ビル等の断熱化の推進等建物に関するエネルギー効率の一層の向上や建物の中におけるエネルギー管理の向上を進めることである。このため、利用可能な最善の省エネ技術の利用に対する金融、税制上の優遇措置等の促進策を強力に講じていく必要がある。
第三に重要なことは、国民一人一人がエネルギーを大切に使っていくという意識を高めていくことである。エネルギーの最終消費段階で効率的な利用を図らなければ、社会システムや個別の機器の効率化を進めてもその効果は半減しかねず、また、国民の意識の盛り上がりがあって初めて社会システムや個別の機器等の効率化を促進させることができるのである。このため、環境とエネルギーの状況、各家庭で実施できる省エネ努力等に関し、国民各界各層に対する啓発、普及活動を格段に強化する必要がある。
(2) 環境負荷の少ないエネルギーの利用の推進
省エネルギーと並んで、二酸化炭素や硫黄酸化物等環境への負荷の少ないエネルギー源の利用を推進していくことも重要な課題である。
化石燃料のなかでみると、天然ガスは最もクリーンなエネルギーであり、適切な範囲内での天然ガスの導入が望まれる。ちなみに、単位発然量当たりの二酸化炭素発生量は、石炭を10とすると石油は約8、天然ガスは約6である。
原子力については、我が国においては既に総発電電力量の約3割を占めるに至っており、非化石燃料の中で最も実用化の進んだエネルギーである。
原子力については、安全性の確保を前提として、二酸化炭素等の排出量の削減に寄与する代替エネルギーの一つとして、アルシュ・サミットを始め国際的にもその重要性が認識されている。
クリーンなエネルギーである太陽エネルギーの利用方法としては、太陽光発電により光のエネルギーを電気エネルギーに変換して利用するものと、太陽熱を利用するものがある。太陽光発電は、現状では通常の発電方式に比べコストは高いものの、地上のどこでも得られるエネルギーから電気をつくることができるものである。スイス等のヨーロッパ諸国では環境負荷の低減の観点から最近導入が急増している。なお、太陽光発電は昼間しか発電できないため、これを夜間に使う場合は蓄電をしなければならず、蓄電池のコストも大きい。系統連系、コストダウン、蓄電池の長寿命化にかかる技術開発が必要である。また、太陽熱を利用するものとしては、太陽熱によって温められた温水を利用する太陽熱給湯システムがある。我が国における太陽熱給湯システムの利用は第2次石油危機を契機に大きく進んだが、石油価格の低迷に伴い近年減少してきており、その一層の普及のための施策の充実強化が必要である。
また、新エネルギーとしては、上記に述べた太陽エネルギーだけではなく、風力エネルギー、海洋エネルギー、生物の光合成機能を利用する技術によるエネルギー等も、二酸化炭素や硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等を発生しないエネルギーであり、開発導入が期待されている。
(3) 公害防止対策の一層の推進
大都市の窒素酸化物問題をはじめとして、エネルギー利用に伴う身近な環境問題についても改善を図らなければならない分野が多い。
特に、窒素酸化物による大気汚染問題の解決のためには、バス、トラック及びディーゼル乗用車からの窒素酸化物排出量の削減が必要不可欠であり、厳しい規制を実施しているガソリン車とバランスのとれた排ガス規制の強化、最新規制適合車への代替促進、大量公共輸送機関、共同輸配送システム等の形成等の対策の強化が必要であり、さらに、大都市地域における地域全体の自動車排出ガスの総量を抑制する方策の可能性の検討を進め、社会的合意を図りつつ、逐次その具体化を図っていく必要がある。(第2章第1節参照)。
また、エネルギー利用と密接なかかわりあいのある硫黄酸化物、ばいじん等の対策についても、その徹底を図る必要がある。
(4) 技術開発の推進
省エネ技術などの環境保全に資する技術の国内における一層の普及に加えて、より高度な省エネ技術、新エネルギー技術、さらには、二酸化炭素の回収・固定化技術、環境保全型社会システムを構築するための技術等新たな技術開発を促進することにより、自然の大きな循環に人間活動の拡大を融合、調和させることが、特に中長期的には極めて重要な課題である。
当面は、商業化が目前に迫っている燃料電池によるコージェネレーションシステムや、太陽光発電の低コスト化等に関する一層の技術開発が期待される。燃料電池によるコージェネレーションシステムとは、天然ガスを改質して得られる水素と酸素(通常空気が用いられる)を電解液中で結合させ、その際に起こる電子の移動から電気を得るとともに、反応熱をも同時に利用しようとするものである。
低公害車の開発普及も喫緊の課題となっている。電気自動車は、走行に伴う大気汚染物質がなく、騒音も少ない。また、発電段階からトータルに考えても、二酸化炭素を含めて、環境負荷の少ない自動車であるといえる。電気自動車の一層の普及を図るためには、高性能電池の開発による一充電走行距離の延長等について一層の技術開発が必要である。また、メタノール車は、黒煙がほとんど排出されず、触媒の使用により窒素酸化物の排出量がディーゼル車の約半分であり、その一層の普及を図るためには、メタノールにより適合したエンジンを開発し、信頼性の向上等を図ることが必要である。さらに、近年圧縮天然ガス(CNG)自動車が注目を浴びている。CNG車は、黒煙をまったく出さず、触媒の使用によりガソリン者に比べ窒素酸化物、一酸化炭素とも約半分であり、二酸化炭素も約2割少ないとの試算もある。このようなCNG車の環境改善効果に照らし、車両重量の軽量化、一充填走行距離の延長等の面での技術開発が必要である。さらには、ソーラーカーその他の環境負荷が低くエネルギー消費量の少ない低公害車についても積極的に研究開発に取り組む必要がある。
これらの低公害車の技術開発は、使用の拡大に伴って促進されるという側面がある。このため、それぞれの低公害車の特性を生かして、普及に向けての積極的な努力を併せて進めることが必要である。
なお、技術の開発・普及によって環境保全を図るに当たっては、特定の環境問題のための技術的な対応が他の環境問題の拡大につながることとならないように注意する必要がある。
(5) 技術の海外への移転
我が国の進んだ環境保全技術や省エネ技術を開発途上国を中心とした海外に普及することは、地球温暖化防止をはじめとする地球環境保全の上からも、またこれらの国の地域的な環境保全努力を支援する上からも極めて有効である。
とりわけ省エネ技術を開発途上国に移転することは、環境保全ばかりでなく、二重、三重の意味がある。
すなわち、開発途上国においては、今後大幅なエネルギー需要増が予想されることから、開発途上国の省エネルギーを進めることは、世界の二酸化炭素発生量の抑制に大きく寄与する等環境保全に寄与するとともに、当該国のエネルギー需給基盤の強化や世界のエネルギー需要の安定化にも大きく貢献する。さらに加えて、開発途上国の産業部門で省エネルギーを進めることは、そのエネルギーコストの低減や適切なエネルギー管理に伴う製品の安定化等省エネを実施した工場に様々なメリットをもたらし、ひいてはその国の健全な経済発展の基盤となるのである。
開発途上国の省エネルギーを進めるためには、経験豊富な技術者の多い我が国の技術協力がきわめて効果的であり、我が国としては、省エネ分野の技術協力の推進により、国際的な役割を果たす必要があろう。
また、開発途上国に対し、環境保全型のエネルギー利用技術やエネルギー利用に関連する公害対策技術を移転することも、これらの国の環境保全に大きく寄与する。ただし、一般的に環境保全等のための技術の導入は、直接的には個別の工場の生産コストの増大をもたらす等の理由から円滑に進みにくい面があるので、途上国の実情に即した適正かつ安価な技術の開発、移転を進めるとともに、これら技術の援助のあり方についても検討する必要がある。