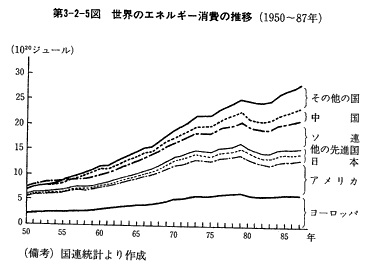
2 エネルギー消費の構造と二酸化炭素の排出量
世界のエネルギー消費の状況をみると、人口の占める割合が24%に過ぎない先進国が75%のエネルギーを消費し、化石燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の発生量も73%を先進国が占めている。今後は、人口増加や工業化の進展を背景として、開発途上国を中心としたエネルギー消費の増大が予測されており、環境保全のための有効な対策を講じなければ二酸化炭素排出量も増加の一途をたどることとなる。
一方、わが国のエネルギー消費は、第二次石油危機の後ほぼ横這いで推移してきたが、1987年以降急増し、二酸化炭素排出量もこれに伴って増大している。
(1) 世界のエネルギー利用構造
第二次世界大戦後、世界のエネルギー消費量は一貫して増大し続け、1950年から第一次石油危機が発生した1973年までの23年間に3.0倍、年率4.9%で増加した(第3-2-5図)。その増加分89%を現在の先進国が占めている。
第二次石油危機の発生した1979年以降、エネルギー消費量は、先進国における需要の減少から世界全体でも減少傾向が続いたが、1983年以降石油価格の低迷と世界的な景気回復を背景として平均年率3.16%で増加している。とりわけ、近年、開発途上国の伸びが大きく、途上国の消費比率は、1973年の15.0%から1987年の25.2%へと上昇している。
また、エネルギー源別の消費割合をみると、石油、石炭、天然ガスの順となっている(第3-2-6図)が、1973年の石油危機以来石油の利用が抑制され、石炭、天然ガス、原子力等の利用が増大している。地域別にみると、開発途上国を含め市場経済の国では概ね石油が50%程度、次いで石炭、天然ガス、原子力の順になっている。一方、ソ連においては天然ガスの比重が4割と最も大きく、中国ではその8割を石炭が占めている。また、開発途上国では薪、木炭、牛糞等の伝統的なエネルギーに多くを依存しており、サヘル以南のアフリカでは約7割を伝統的エネルギーに依存している。このように、エネルギー源は地域によって差が大きい。
今後のエネルギー消費の見込みについては、開発途上国を中心として着実に増大することが見込まれており、1989年9月に開催された第14回世界エネルギー会議の資料によると、2020年の世界の一次エネルギー需要量は1985年の1.51倍〜1.76倍に達する(年率1.18%〜1.63%で増大する)ものと予想されている(第3-2-7表)。
(2) 化石燃料の使用に伴う二酸化炭素発生量
化石燃料である石油、石炭及び天然ガスは燃焼に伴い二酸化炭素を排出する。エネルギー消費による世界の二酸化炭素排出量を推計すると、アメリカ、ソ連、中国、日本の順になっており、エネルギー使用量の大きい先進国や、人口や石炭の使用比率の高い中国が大きな割合を占めている(第3-2-8図)。
国内総生産(GDP)当たりの二酸化炭素排出量は、国によって大きな差がみられるが、経済発展段階が低く、エネルギー使用効率が相対的に低い開発途上国が総じて高くなっている(第3-2-9表)。また、我が国は、先進国の中で最も低くなっている。
人口一人当たりの二酸化炭素排出量は、一人当たりのGDPが高く産業活動が活発な先進国が、エネルギー消費水準が高いことを反映して大きくなっている。しかし、先進国の中でも気象条件、エネルギー源構成、産業構造、省エネルギーの進展度、生活習慣の違いなどによって各国間で大きな差がみられ、我が国や、原子力比率の高いフランスが小さくなってる。
面積当たりの二酸化炭素排出量をみると、当然のことながら狭い国土で高密度の経済活動を行なっている国が高くなっており、我が国は、ヨーロッパ諸国と並んで高い。
(3) 我が国のエネルギー利用構造とエネルギー消費原単位
石油危機以前の我が国のエネルギー消費量は、石炭から石油へのエネルギー転換を伴いつつ経済成長率を上回る割合で増大した(昭和30年から第一次石油危機の発生した48年までの年平均経済成長率9.3%に対し、エネルギー消費量の年平均伸び率は10.9%)が、石油危機以降は増大傾向が抑制され、第二次石油危機の発生した54年から61年までは年によって増減はあるものの全体としてほぼ横這いで推移してきた。しかし、(4)で述べるとおり62年からは大幅に増大している。
我が国のエネルギー利用構造として特徴的なことは、産業部門の割合が相対的に高いことであり、長期的には減少傾向を示しているものの、現在でも全体の過半を占めている。これは、我が国が相対的に暖房用エネルギーの消費が少ないことや、運輸部門において地形等の要因により自動車や航空機と比べてエネルギー効率の高い鉄道及び内航海運に対する依存度が他の先進諸国に比べて高く、運輸エネルギーが相対的に少ないこと等によるものと考えられる(第3-2-10図、第3-2-11図)。
二度にわたる石油危機は、石油価格の大幅な上昇をもたらし、我が国だけでなく各国のエネルギー消費効率の向上をもたらした。第3-2-12図は主要先進国におけるGDPのエネルギー消費原単位(GDP一単位当たりの生産に必要なエネルギーの量)の推移をみたものである。これによると、各国ともエネルギーの効率的な利用が大きく進んだが、特に我が国の進展は大きく、エネルギー消費原単位の改善率は最大であり、かつ、エネルギー消費原単位の値自体も先進国の中で最も小さくなっている。
我が国のエネルギー消費原単位の改善率が高い第一の理由は、産業部門を中心に省エネルギーが大きく進んだことである。産業部門ではほとんどの業種で省エネルギーが相当進展し、わが国の産業部門のエネルギー消費の約7割を占める鉄鋼業、石油化学工業、紙・パルプ製造業、染色整理業、セメント製造業、化学繊維業の主要6業種を例にとってエネルギー消費原単位(48年基準)の推移をみると、62年までに各製造業とも20〜40%の改善となっている(第3-2-13図)。また、我が国産業界の省エネルギーの進展度は、世界の中でトップクラスに達しているものと考えられ、他の先進国のエネルギー消費原単位は鉄鋼業で我が国の1.2〜1.4倍、セメント業で1.5〜1.6倍となっている。(第3-2-14図、第3-2-15図)。
産業部門が我が国のGDP当たりのエネルギー消費効率の改善に貢献した点としては、このような省エネルギーの進展に加えて、製品の高付加価値化、すなわち、同じエネルギーを使った製品であっても、より大きな付加価値を生み出すことができるようになったことがあげられる。
エネルギー多消費型である基礎素材型産業が生み出す付加価値のGDPに占める割合は、昭和50年以降ほぼ横這いで推移しているが(第3-2-2図)、基礎素材型産業自体の付加価値当たりのエネルギー消費原単位は、50年から62年までの間に約53%減少している。第3-2-16図は、基礎素材型産業のエネルギー需要の増減の要因分解を示したものである。これによると、生産物量当たりのエネルギー消費原単位はほぼ常にエネルギー需要を引き下げる方向で働いており、生産物量当たりの省エネルギーが進んでいることがうかがえる。また、GDPの増加はエネルギー需要を引き上げる方向で働いている。GDPの中に占める基礎素材型業種の割合の変化は、景気拡大期には基礎素材型産業がGDPの伸び以上に活発化することからエネルギー消費の増加に、景気の停滞期には減少に寄与していると言える。一方、製品の高付加価値化は、エネルギー消費量の減少に大きく貢献している。
製造業全体のGDPの中に占める割合は、加工組立型産業の増大から一貫して増大しているが、製造業全体の付加価値当たりのエネルギー消費原単位は、製造業全体に占める加工組立型産業の割合の増加の効果もあって昭和50年から62年までの間に約58%減少している。
我が国では、産業分野だけでなく主要民生用機器や、乗用車のエネルギー効率も二度にわたる石油危機を契機に格段に改善してきている(第3-2-17図、第3-2-18図)。
我が国のエネルギー消費のGDP原単位が小さくなっている要因としては、このような省エネルギーに資する努力に加えて、先に述べたとおり我が国は暖房用エネルギーや運輸エネルギーが相対的に少ないことが挙げられる。また、過去の趨勢を見る限り、各国とも産業部門ではコスト意識が強く経済原則が働きやすいことからそのエネルギー消費はエネルギー価格に敏感に反応しやすく、民生部門や運輸部門に比べて省エネルギーが進みやすいと考えられることから、産業部門でのエネルギー消費の比率が相対的に高い我が国は、エネルギー消費原単位の改善率が高めにでやすかったと考えられる面もある。
(4) 近年のエネルギー消費の急増
第二次石油危機の起こった昭和54年度以降、我が国の総エネルギー需要量は、平均的には横這いで推移してきたが、62年度は5.0%、63年度は5.4%と大幅に伸び、平成元年度も同等またはそれ以上の伸びが予想されている。
その主要因としては、石油価格が低迷する中で、内需拡大を背景とした景気拡大が続いていることが挙げられる。第3-2-16図で見たとおり、景気拡大の局面においては、エネルギー多消費型産業の生産が大きく増大する傾向があり、日本全体のエネルギー消費量の増大の大きな要因となっている。また、石油危機以降減少してきた原油の消費量が61年度以降増大しており、今回のエネルギー需要増は石油価格の低迷が大きく寄与しているといえる。景気拡大に伴い、物流の伸びも大きく、運輸部門でのエネルギー消費も増大している。また、第3-2-19図に示すように石油価格が低迷し省エネ投資が頭打ちの状況にある中でエネルギー原単位の改善が停滞していること、家電製品のエネルギー効率についても近年向上が余りみられなくなっていること等も一つの要因である(第3-2-13図、第3-2-17図)。
業務部門においても、業務用床面積の増大や、OA機器の増加によりエネルギー消費が増大している。床面積の増大は冷暖房などの空調を要する面積の増大をもたらし、また、OA機器の増加は、それ自体のエネルギー消費の増加と、OA機器から発生する熱が空調への負担を高めるという効果をもつ。また、第3-2-20図は、ビルにおける冷暖房の設定温度をみたものであるが、冷房温度はより低く、暖房温度はより高くなる傾向があり、業務部門におけるエネルギー消費の増加の一因となっている。
また、近年、小売業等で少量・多品目の頻回注文配達が増加していることが自動車交通量の増加の一因となっている。
さらに、国民のライフスタイルがエネルギー消費を増大させる方向に向かっていることもエネルギー消費量の増加の一つの要因となっている。先に示した新型乗用車の平均燃費をみると(第3-2-18図)、昭和57年以降悪化しているが、これは、同一車種については燃費は向上しているものの乗用車に対するニーズが大型化、高級化していることによる。家電製品についても機器の大型化、高級化、複数所有化が進むとともに、新型機器が登場し、一家庭当たりのエネルギー消費量は48年に比べて3割増となっている(第3-2-21図)。
以上のようなことを背景として、近年エネルギー消費が増大しているが、このような急増傾向が今後も長期間続くとすれば、これに伴う環境負荷の増加が懸念される。