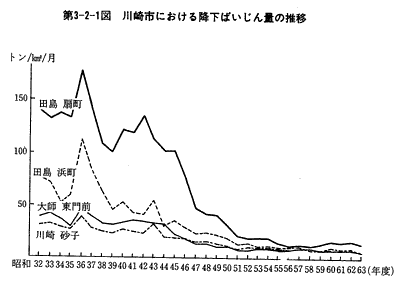
1 エネルギー利用に伴う環境問題
まず最初に、エネルギー利用に伴う主要な環境汚染問題をみてみる。
(1) ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物等による地域的な大気汚染
化石燃料の燃焼は、潜在的にさまざまな大気汚染物質を排出する可能性をもっている。我が国でまず最初にエネルギー利用に伴う環境問題としてクローズアップされたのは、石炭や石油の燃焼に伴い発生するばいじん(黒煙・すす)による大気汚染である。戦後の経済復興に伴い、黒煙、すすなどによる大気汚染が表面化し始め、昭和24年には、早くも東京都が工場公害防止条例を制定している。ばいじんのうち、粒径が大きく地上に降下するものは、降下ばいじんとして測定され、その汚染状況は昭和30年代から40年代の前半にかけて深刻な状況にあったが、その後大きく改善している(第3-2-1図)。また、粒径が10ミクロン以下のものは、大気中に長時間滞留し、気道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼす可能性があることから、浮遊粒子状物質として環境基準が定められているが、その達成率は低い状況にある(第1章第1節1(5)参照)。
石炭、石油等、硫黄分を含む化石燃料は、燃焼に伴い硫黄酸化物を発生する。我が国は、硫黄酸化物による深刻な大気汚染を経験した。1960年代、重化学工業を中心とする鉱工業生産活動がエネルギー消費の増大(10年間で3倍)を伴いつつ急速に拡大した(第3-2-2図)が、エネルギー需要増の大部分は石油であり、特定の工業地帯で集中的に使われたこともあって、深刻な硫黄酸化物による大気汚染にみまわれた。このため、昭和37年には我が国最初の大気汚染防止のための法律である「ばい煙の排出の規制等に関する法律」が制定され、43年にはこれを引き継いで「大気汚染防止法」が制定された。しかし、硫黄酸化物による大気汚染はさらに深刻化し、各地で大気汚染による呼吸器系疾患の患者も増大し、その迅速な救済を図るため昭和44年には「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」が制定され、49年以降「公害健康被害補償法」(昭和63年「公害健康被害の補償等に関する法律」に題名改正。)に引き継がれた。硫黄酸化物による大気汚染はその後著しく改善し、今日においては大気汚染がぜん息等の主たる原因をなすものと考えられないとの科学的評価に基づき、63年3月、大気汚染に係る指定地域を解除した。
化石燃料中の窒素分は燃焼により窒素酸化物になる。また、物の燃焼は高温を発するため、燃焼に際しては、空気中の窒素分が酸化され窒素酸化物が発生する。
環境中の二酸化窒素濃度は、昭和53年度をピークとして、その後改善がみられていたが、61年度以降悪化の傾向がみられ、63年度においても、自動車交通量の多い大都市部で環境基準を上回っているところがみられる。このため、二酸化窒素による大気汚染の問題が重要な課題となっている(第1-1-1図、第1-1-2図)。
この他、燃料の不完全燃焼に伴い発生する一酸化炭素や、窒素酸化物及び炭化水素を原因とする光化学オキシダントによる大気汚染も、エネルギーの利用に伴い発生する地域的な大気汚染問題である。
(2) 酸性雨
酸性雨は、化石燃料の燃焼等に伴って発生する硫黄酸化物、窒素酸化物が雨に溶けることによって生じると考えられており、エネルギー消費と密接に関係している(第1節2(3)参照)
酸性雨は、発生源から数千kmも離れたところに降下することがあり、国境を越えた問題として欧米では国際政治上の課題ともなっている。また、今後、エネルギー需要の急増が見込まれる開発途上国でも被害の深刻化が懸念されている。
我が国においても年平均値でpH4.4〜5.5程度の雨が全国的に観測されており、欧米並かそれ以上の酸性降下物量が観測されているが、森林、土壌、湖沼等において生態系への影響は現時点では顕在化していない(第1章第1節1参照)。
(3) ヒートアイランド現象
都市においては、エネルギーが高い密度で消費されている。これに加えて、都市の土地の多くはアスファルト、コンクリート等の乾いた物質により覆われているため水分の蒸発による温度低下が望めず、また、緑地の場合は蒸散により日射熱をほとんど蓄熱しないのに対しアスファルト、コンクリート等の物質は日射熱を蓄熱しこれを夜間に放出するため夜間の気温低下を妨げるという特徴を持っている。この結果、都心部では郊外に比べて気温が高くなる現象が起こっている。この現象は、等温線を描くとあたかも都市を中心とした「島」があるように見えることから「ヒートアイランド現象」と呼ばれており、東京等の大都市では日常生活で実感できるほどになっている。
また、東京の年平均気温は、1870年代の約14℃からこの100年余りで約15.5℃へと1.5℃程度上昇し、年平均湿度は約77%から約65%へと12%程度下がっているが、ヒートアイランドがその一つの要因となっていると考えられる。(第3-2-3図)。
ヒートアイランド現象が起ると、特に夏の気温上昇が冷房のためのエネルギー需要を高め、その結果ますます都市の気温が高まるという悪循環が起こる。
植物は、葉面から水が蒸発する際に周りの熱を吸収することから気温を調節する機能を有している。ヒートアイランド現象は、このような緑地の効用を都市の中でどのように活かしていくかということと密接に関連しており、都市の生態系循環をいかに構築していくかの問題であるともいえる。
(4) 地球温暖化
地球温暖化問題は、本章第1節2で述べたとおり、人類の生存基盤を直接脅かしかねない問題であり、その対応が世界の最重要課題の一つとなっている。地球温暖化現象は、温室効果気体の排出や温室効果気体である二酸化炭素の吸収源である森林の減少等様々な要因が絡み合って生ずると考えられるが、人為的に排出される温室効果気体のうち、二酸化炭素の大部分とメタンの三分の一程度がエネルギー関連のものであるとの推計がある。また、人間活動に起因する温暖化への寄与のうち、約57%がエネルギーの利用と生産に伴うものであるとの試算がある(第3-2-4図)。したがって、地球温暖化防止対策の実施に当たっては、エネルギー使用に伴う二酸化炭素の排出抑制が鍵だと言える。しかも、世界のどの地域で発生する二酸化炭素も地球環境に同じ影響をもたらすことから、特定の国々の対応のみでは十分な効果が挙げにくく、世界が一致協力して取り組まなければならない重大な問題である。