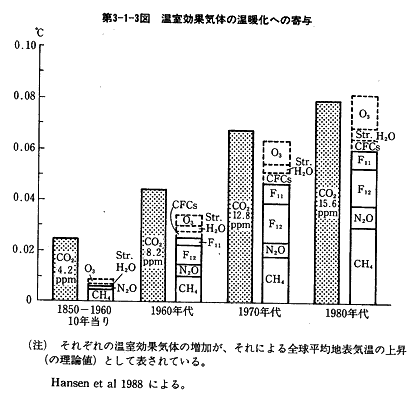
2 広がる地球環境問題
(1) 地球温暖化
大気中の微量ガスが、地表面からの赤外線放射を吸収し、宇宙空間に逃げる熱を大気にとどめることにより、地表面及び大気の温度が暖められ、生物の生存に好ましい気温が維持されている。この現象を温室効果、また、この赤外線を吸収するガスを温室効果気体と呼び、水蒸気(H2O)、二酸化炭素(CO2)、フロン(CFCS)、メタン(CH4)、対流圏オゾン(O3)、亜酸化窒素(N2O)などがこれに含まれている。地球温暖化問題とは、人間活動により、これらの温室効果気体の大気中の濃度が上昇し、その結果温室効果が強まり、今後数10年の間に急激に気温が上昇するおそれがあることをいう。気温の上昇とともに、海面上昇、降水パターンの変化や蒸発量の変化なども起こり、気候と密接に関係している生態系や人類社会に重大な影響が及ぶと考えられている。まず、気温が上昇すると、海水の膨張や陸上の氷の溶解により海水面が上昇し、沿岸地域において浸水、浸蝕被害が発生すると考えられており、世界の臨海都市やエジプトのナイル川河口、バングラデシュのガンジス川河口地域さらにモルジブなど珊瑚礁の上にある国々などに重大な影響が及ぶことになる。また、農作物に対しては、降水量及び降水時期の変化、高温障害、病害虫の発生相の変化、土壌水分の変化等により大きな影響が考えられる。動物や植物などの生態系は、気候と密接な関係にあることから急激な気候の変化に耐えられず、植生が荒廃したり種の絶滅が加速されることも考えられる。また、気候と関係のある感染症の分布変化等を通じて、人の健康にも影響を与えることが懸念される。その他、洪水、台風の増加やツンドラの融解、雪などの観光資源の喪失など影響は広範多岐にわたると考えられる。
温室効果気体の濃度当たりの温室効果の大きさは、気体の種類やその濃度レベルによって異なる。二酸化炭素以外の温室効果気体では、濃度が一定だけ変化したときの温暖化への寄与が、二酸化炭素に比べて非常に大きいものがある。たとえば、二酸化炭素を1とすると、現状から同じ濃度だけ上昇した場合の温暖化への寄与は、メタンで約10倍、亜酸化窒素で約100倍、対流圏オゾンで約1,000倍、フロン類で約10,000倍のオーダーになると計算されている。二酸化炭素は大気中の濃度が他の温室効果気体に比較して高いため、温暖化への寄与という観点から見ると、一番大きな影響力をもっている。しかし、二酸化炭素以外の温室効果気体の寄与は年々高まってきており、その寄与を合わせると二酸化炭素と同程度となってきている(第3-1-3図)。
ここで、二酸化炭素の大気中の濃度の観測値をみると、産業革命以来の石炭、石油などの化石燃料の大量使用や森林の減少等を背景に上昇を続けており、南極の氷に閉じ込められていた空気の分析からの推定によると、産業革命以前においては280ppm程度で安定していたものが、最近では、例えばハワイ・マウナロア山の推計では、1960年に約320ppm、1989年には約350ppmとなっている(第3-1-4図)。エネルギーの多くの部分を化石燃料の燃焼に頼っていることから、何の対策も採らない場合、エネルギー消費に伴って今後とも二酸化炭素の排出が続くと考えられ、二酸化炭素の濃度は今後とも増加を続けることになると思われる。また、その他の温室効果気体も増加を続けている。メタンは、湿地や湖沼、水田、家畜等の消化器官、廃棄物処分場における微生物活動や天然ガス等の化石燃料の生産等により発生するが、その大気中濃度はここ200年間でほぼ倍増し、現在は年約1%程度で上昇している。その上昇の原因としては、人為的発生源の増加や、メタンの大気中での分解を妨げる一酸化炭素等の人為的な排出の増加が考えられている(第3-1-5図)。亜酸化窒素については、土壌や海洋、森林の減少、窒素肥料の使用、化石燃料の燃焼などが発生源として考えられており、現在大気中の濃度は年約0.3%程度で上昇している。フロン(CFCS)に関しては、先に述べたように全廃へ向けて動いているが、対流圏では極めて安定した気体であり、全廃されても大気中濃度が低下するまでにはかなりの時間を必要とする。また、代替フロンが使用された場合、その温室効果による影響も心配される。温室効果気体の増加が現在の趨勢のまま推移したとすると、2030年までに、温室効果気体全体でも産業革命以前の二酸化炭素濃度の2倍に相当する濃度に達し、その後も加速度的に増加していくことになる。
また、その時の影響については、例えば、気象庁の気候問題懇談会温室効果検討部会の報告(「温室効果気体の増加に伴う気候変化」)によれば、温室効果気体の濃度が現在の増加率で推移すれば、2030年代には地球全体の平均気温が1.5〜3.5℃、海面水位が20〜110cm上昇するとされている。温暖化の将来予想については、地域的な気候変動の様子や具体的な温度上昇の時期に関して未だ分かっていない面があるが、地球の平均気温が半世紀足らずの間に数度上昇し、一部の地域ではそれよりも高い温度上昇になるおそれのあることは概ね共通の認識となりつつある。気候変動のメカニズムについては、例えば、化石燃料の燃焼より発生している年間約55億トンの二酸化炭素(炭素換算)のうち約58%は大気中の二酸化炭素濃度の増加分に相当すると言われているが、残りの二酸化炭素濃度の吸収メカニズムの解明(第3-1-6図)、さらに、様々な温室効果気体の大気中での挙動の解明、雲の発生量とその影響の解明、陸地における水の蒸発散の正確な推定、海洋の深層循環も考慮に入れた海洋大循環の大気モデルへの結合などに関して世界中で精力的に研究が行われており、今後とも科学的知見を一層深めていく必要がある。しかし、地球温暖化が生態系や世界の経済活動、人々の生活等に与える影響は極めて大きく、また、地球温暖化による影響が明白に認識されるようになった時点で初めて対策をとっても、大気中の温室効果気体を急に削減させることはできず、また一旦生じた気候変動や海面上昇を回復させることは著しく困難であることから、上記のような不確実性があっても、今から対策を講じていかなければ、将来取り返しのつかない事態をもたらすことになると考えられる。したがって、アルシュ・サミットの宣言でうたわれたように、幾つかの問題について不確実性が残っているからといって、我々の行動が不当に遅延されてはならず、手遅れにならないうちに、必要な対策を実行していくことが重要である。
このような、温暖化問題の深刻性に対する認識は我が国においても、また世界においても急速に高まってきており、各国及び国際機関において、その研究、対策の検討が精力的に行われてきている。
まず、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の協力のもとに設けられたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)においては、専門的見地からの検討、討議を行うための3つの作業部会を設置し、1988年11月の第1回会合以来検討作業を続けている。第1作業部会においては、気候変動のメカニズム、予測と不確実性などに関する科学的知見の評価を行い、第2作業部会においては、気候変化によってもたらされる環境への影響、農業、水資源、エネルギーなど社会・経済への影響などの検討を行い、さらに、第3作業部会では、法制、技術移転、財政、教育そして経済的措置の在り方など、気候変化に対処するための政策や戦略を検討しており、1990年8月のIPCC全体会合でそれらの検討結果をとりまとめ、10月末から11月初めにかけての第2回世界気候会議に中間報告として提出されることになっている。
その他に、前述のように、ハーグ環境首脳会議、UNEP管理理事会、ノールトヴェイクにおける環境大臣会議等が開催され、特にノールトヴェイク会合では、世界経済の安定的発展を確保しつつ、温室効果気体の排出を安定化させる必要性が認識されるに至っている。
(2) オゾン層の破壊
大気に存在するオゾンは、30億年程度をかけて植物の光合成により放出された酸素に基づいて形成されたもので、その多くがオゾン層として成層圏に存在し、太陽から放射される生物にとって有害な紫外線のほとんどを吸収する非常に大切な役割をはたしている。このオゾンが近年急速にフロン等によって破壊される恐れが強まっている。フロンは、洗浄剤、冷却剤、発泡剤などに広く使われてきたが、化学的に安定的な物質であるため、使用後大気に放出されたフロンガスは、対流圏では分解されずに成層圏に達する。そこで太陽からの強い紫外線を浴びて分解し塩素原子を放出するが、この塩素原子を触媒としてオゾンを分解する反応が連鎖的に発生し、その結果成層圏のオゾン層は破壊されていくことになる。フロンは、毒性がなく、燃えない、油をよく溶かす、他の物質と化学反応をおこしにくいという便利な性格をもっていたことから広く利用されてきており、我が国での使用量は昭和61年で約13.3万トンであり、これは世界の使用量の1割強を占めている。また、オゾン層を破壊する物質としてフロン以外にもハロン、メチルクロロホルム、四塩化炭素などが問題となっている。ハロンは消火剤などに使用され、フロンに比較してその使用量は少ないものの、オゾン層を破壊する程度ははるかに大きい。一方、メチルクロロホルムは、オゾン層を破壊する程度はフロンより小さいもののフロンと同様に多量に使用されている。
オゾン層が破壊され地上に降り注ぐ紫外線が増加すると、皮膚ガンや白内障が増加するなど人の健康への悪影響の他、農作物等の生育の悪化をもたらし、また海洋のプランクトンに影響を与えることにより海洋生態系にも悪影響をもたらすなど、全地球的規模で、人間、動植物、材料(合成樹脂など)等に多様な影響を及ぼす。
成層圏におけるオゾンの減少に関して、近年急速にその科学的知見が進展している。まず、極地におけるオゾンの状況に関しては、南極において毎年春先にオゾン濃度が急激に減少する現象(オゾンホール)が観測されており、北極においてもオゾン濃度が急激に減少するおそれがあることがわかってきた。また、全球的なオゾン変動の傾向としては、1969年から1988年の20年間に北半球(北緯30〜64度)の冬季において、オゾン全量が3〜5.5%の減少を示していることが確認され、その原因が既知の自然現象では説明がつかず、少なくとも部分的には大気中のフロン等の濃度の増大に起因することが確認されている(第3-1-7図、第3-1-8図)。
このような知見の深まりを受けて、前述した通り、国際的な取組が行われてきている。様々な要素を考慮に入れなければならないため、定量的な評価は難しいが、特定フロン全廃による利益は損失を大きく上回っているとの基本的な結論に達しており、フロンの早期全廃に向けて代替品の開発が進められている。
ウィーン条約及びモントリオール議定書への加盟国は、1989年11月現在、我が国を含め、それぞれ54か国及びヨーロッパ経済共同体(EEC)、48か国及びEECである。今後は、ウィーン条約及びモントリオール議定書に対する各国の理解を深め、その参加国を増やし、オゾン層保護のための様々な取組を世界的に推進することが重要である。
(3) 酸性雨
酸性雨は、主として化石燃料の燃焼によって生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質を取り込んで生ずると考えられているpH(水素イオン濃度)5.6以下の雨をいう。酸性雨は、大気汚染物質の発生源から数千キロも離れた地域にも降下する性質があり、国境を越えた長距離を移動する大気汚染問題として、特に欧州、北米において深刻な問題となっている(第3-1-9図)。ヨーロッパにおける各国間の硫黄酸化物の降下状況をみると、多くの国で自国で発生する硫黄酸化物の半分以上が他国に降下している。
酸性雨の被害としては、雨が直接葉にあたることによる農作物への直接的影響に加え、土壌が酸性化することにより有害な金属が溶け出し根を痛めることなどによる森林への影響、さらに酸性雨が流入することにより湖沼や河川が酸性化し、そこに住む魚類の減少をもたらすことなどがあり、生態系に重大な影響を与えている。ヨーロッパにおいては、多くの国で半分以上の森林が被害を受けていると報告されている(第3-1-10図)。また、ベルギー、チェコスロバキア、フィンランド、西ドイツ、イタリア、オランダ、ノールウェー、スウェーデン、アメリカ、カナダにおいて湖沼や河川が酸性化していることが確認されている。ノールウェーやスウェーデンの南部の湖沼は強く酸性化しており、ノールウェー南部の湖沼では70%が酸性化し、そこに住む魚の数が減少し、さらに絶滅する被害が発生している。
このような酸性雨の被害に対処するため、欧米諸国では、1979年に長距離越境大気汚染条約が締結され、1985年のヘルシンキ会議において硫黄酸化物を1980年の排出量から30%以上削減することを同条約の議定書として採択した。さらに、1988年には窒素酸化物の排出量を1994年時点で1987年レベルに凍結することなどを内容とするソフィア議定書に25か国が署名した。
森林の衰退の原因としては、酸性雨を主因とする考え方の他に、葉に吸収された大気中のオゾンや硫黄酸化物が直接的に植物の生理的機能を阻害し成長を抑制するという説、窒素の供給が過剰で他の栄養塩類が欠乏した栄養障害及びそれに伴い気象害や病虫害への抵抗力が低下しているという説などもあり、必ずしも森林の衰退の機構が十分に解明されているわけではない。しかし、酸性雨による森林の衰退のメカニズムとしては概ね以下の現象が複合したものと考えられている。まず、酸性物質によって土壌のカルシウム、カリウム、マグネシウムなどの栄養塩類が流出することから土壌の肥沃度が低下し、一方、有害なアルミニウムなどの金属イオンも溶出し根を痛める。また、土壌中の微生物、特にバクテリアの活力を低下させ有機物の分解が遅れ物質循環が乱れることになり、葉に付着した酸性物質は葉からの栄養塩類の溶脱をもたらす。
酸性雨問題は、当初ヨーロッパで問題となったのであるが、中国においても酸性雨が降っていることが分かってきた。中国において酸性雨は「空中鬼」とも呼ばれ、特に中国南西部において酸性の強い酸性雨が発生している。中国における酸性雨の原因としては、硫黄分の多い石炭を大量に使用することによる硫黄酸化物の排出であろうと考えられている。
(4) 森林、特に熱帯林の減少
第3節で詳しくみるように、森林は木材や薪炭材、果物などの供給源であるとともに、野生鳥獣の生息の場でもあり、また、水源をかん養し、山崩れ等の災害を防止する働きも有している。さらに、近年では温暖化の原因物質である二酸化炭素の吸収源として、その重要性が再認識されているところである。
このような森林資源の世界の賦存量を地域別にみると、第3-1-11表のとおりであり、アマゾン川流域を中心として広大な熱帯雨林を抱える南米や寒帯針葉樹林が広く分布するソ連において豊かであることがわかる。また、第3-1-12図は、増減の傾向をみたものであるが、西欧や北米などではほぼ横ばいで推移しているのに対し、ラテンアメリカやアフリカなどの開発途上国においては森林の減少傾向が見られている。
中でも熱帯林は、熱帯地方の人々の食糧や燃料の供給源であるだけでなく、世界全体にとっても生物種のうち約半分が生息すると推定される「生物種の宝庫」として、また、地球規模での気候の緩和などの環境調節機能を有するものとして、その貴重性の認識が高まっている一方で、急激に減少しつつあることが明らかとなり大きな問題となっている。
熱帯林としては、熱帯地域に存する森林が広く扱われ、マングローブ林を含む広葉樹閉鎖林、針葉樹林、竹林のほかアフリカの樹木の混ざったサバンナやインドシナの疎林なども含められている。世界の熱帯林のの状況については、国連食糧農業機関(FAO)が1981年に調査結果を発表しており、これによると全世界の熱帯林は1980年末で約19億4,000万haあり、熱帯アメリカに9億ha、熱帯アフリカに7億ha、熱帯アジアに3億4,000万haが分布しているが、1980年から5年間に年平均で約1,130万ha(本州の約半分に相当する。)が減少していると推測されている。地域別にみると熱帯アメリカで560万ha、熱帯アフリカで370万ha、熱帯アジアで200万haが減少している。なお、FAOの報告における熱帯林の「減少(deforestation)」は、「非森林化の目的のために、林地の転換あるいは譲渡を示すもの」と定義されおり、移動耕作を目的としない伐採跡地などは、「減少」とみなされず、「荒廃(degradation)」とされている。また、米国政府が1980年に発表した「西暦2000年の地球」では世界の森林は年間1,800万〜2,000万haの割合で減少しており、この純減少速度は今世紀末まで続くであろうとの予測がなされている。
また、その後の状況については、民間の研究所や研究者による調査結果が発表されており、見解に幾分の相違がみられるものの、FAOの推計に比べて熱帯林減少のスピードが速まっているとみるものも多く、衛星による観測データによって、ブラジルのアマゾンでは1987年だけで800万haと80年代初めに予想されていた面積を500〜600万haを上回る量の森林が減少していることが明らかにされている。
熱帯林の減少の要因は、地域によって違いがあるが、自然回復力を無視した焼畑移動耕作が最大のものであるといわれており、熱帯アフリカにおいては閉鎖林の減少の70%、熱帯アジアにおいては49%、熱帯アメリカにおいては35%がこれによるものと推定されている。このほかにも、熱帯アメリカにおいては、過放牧が重要な要因となっており、熱帯アフリカにおいては定住農業やダム等の建設が要因にあげられている。また、熱帯アジアでは低地を追われた農民による奥地への移住やパーム油やゴムなどのプランテーションへの転換の比重が大きいことも指摘されている。また、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の報告によれば、南アジア(バングラデシュ、ブータン、インドネシア、ネパール、パキスタン、スリランカ)では薪炭材の採取と過放牧が、東南アジア大陸部(ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム)では焼畑移動耕作がそれぞれ熱帯林の減少・荒廃の主要因であり、東南アジア島しょ部(マレーシア、インドネシア、フィリピン、パプアニューギニア)では商業用伐採が熱帯林の荒廃の、また間接的に減少の主要因であるとされている。
焼畑移動耕作とは、一般的には小面積の森林を伐採焼却した肥沃な跡地に作物を耕作し、これを続けて肥沃度が低下すると、他の森林に移動するという耕作法である。開墾初年から耕作を継続する期間は普通2〜3年であり、放棄された開墾地は次第に森林へと回復していくが、再び耕作を可能にするまでに地力を回復するには少なくとも10年の休閑期が必要とされる。このような耕作法は、森林農民が伝統的に行ってきたものであり、東南アジアにおいては2000年以上の歴史をもつ。ところが、近年の開発途上国を中心とする人口増加により耕作地が不足し、十分な休閑期をとらずに焼畑が行われるため土地の生産性が低下して(第3-1-13図)、さらなる耕地需要を生み出し、これが森林減少への圧力となっている。
また、1980年における開発途上国の絶対的貧困者約7億8,000万人(中国とその他のアジア中央計画経済国を除く)のうち90%が農村住民であるとの推定がなされるとともに、3,000万戸の農家が土地無しであり、1億3,800万戸が土地無しに近い状態であった。特にラテンアメリカでは耕地の93%が7%の地主の手に集中し、何百万人という農民は土地無しの状態におかれている。こうした農村地域における貧困等の問題にみるように、熱帯林減少の背景には、開発途上国の人口増加や貧困、土地配分の状況等の経済社会問題が存することに注意しなければならない。
また、「荒廃」している熱帯林の面積を明らかにすることは容易ではないが、その要因としては木材の切り出しや薪炭材の採取、過放牧に加え、火災があげられている。このうち木材の切り出しについては、一般的には熱帯林を構成する樹種数は極めて多く、そのうち一定の径級以上で市場価値のあるものだけを伐採することから、森林の再生等に十分な注意が払われれば、森林の減少や著しい荒廃をもたらすものではない。しかし、FAOの熱帯林資源評価プロジェクト報告書によれば、東南アジアのフタバガキ科を中心とする熱帯混交林のように有用木の密度の高い森林では強度の伐採が行われており、伐採の目的とされない樹木も切り出し作業によって傷つけられている。さらに、フィリピンやマレーシアのサバ州での調査によると、トラクターなどの搬入のために開発地域面積の14%が裸地にされている。強度の伐採によって原生林のうちのいくつかの有用樹種は林地伐開後の更新が困難なために消失してしまう場合もあると考えられ、また、トラクター道跡地などの裸地では植物が再生されにくいために丘陵地域において土壌の侵食が起こり土地崩壊が助長されるなど、深刻な影響がもたらされている。
さらに、木材の搬出のための道路の整備は、奥地への不法耕作農民の侵入の誘因となっている場合もあり、むしろ伐採後引き続いて行われる自然回復力を無視した焼畑移動耕作が森林減少の主要な要因であるといわれている。
また、熱帯や亜熱帯の潮間帯に生育するマングローブ林も減少している。マングローブ林は熱帯、亜熱帯地方の人々の炊事用の燃料、家屋の建材として不可欠であるとともに、薬用になる樹種も多くある。また、マングローブ林は満潮時には稚魚の隠れ家となり、落葉は腐食してプランクトンの餌となることから多くの海生生物の繁殖地となっており、沿岸に根をはったマングローブ林は海岸河岸の侵食を防止する働きも有している。こうした有用なマングローブ林においても水田造成や木材やパルプ材としての商業目的等のために大規模な伐採が行われ、研究機関等によればインドでは現存するマングローブの4倍以上の160万haが、バングラデシュでは2.5倍の100万haが今世紀になって消滅したとの推定もなされている。また、「ENVIRONMENTAL ANDSOCIO-ECONOMIC ASPECT OF TROPICAL DEFORESTATION IN ASIA AND THEPACIFIC」(国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)1986年)によると、バングラデシュ、タイ等では、マングローブ林を切り開いてエビの養殖が行われ、マングローブ林の減少の一因となっているとされている。
北米や欧州等の温帯林は、先に見たように大気汚染や酸性雨によって甚大な被害を受けている。また、北米では森林資源の成長量を上回る伐採が行われていることが明らかになってきていることやニシアメリカフクロウ等の森林に棲む野生生物保護の観点から森林保護の声が高まってきている。
(5) 砂漠化、土壌侵食
砂漠化とは、世界の乾燥地、半乾燥地における土地生産力の低下をいう。砂漠化問題について特に世界の関心が集まるようになったのは、1968年に始まったサハラ南縁サヘル地帯の干ばつが1972〜73年に前半のピークを迎え、環境の顕著な荒廃と多数の死者と難民の発生をもたらしたことが契機となっており、1977年には第1回の国連砂漠化防止会議(UNCOD)が開催されるに至った。
UNCODは世界的な砂漠化の状況が初めて明らかにされた場であり、世界のすべての乾燥・半乾燥地域並びに半湿潤地域で砂漠化が進行しているか又はその危険のあること、毎年600万ha(九州と四国の合計の面積に相当する。)の土地が砂漠化により不毛となっていることが報告された。さらに7年後の1984年には、UNCODで採択された砂漠化防止計画の実施状況を評価するための調査が行われたが、これにより、?砂漠化により不毛となった土地の面積は、なお毎年600万haの割合で増加し続けていること、?ネットの経済生産性がゼロないしマイナスになった土地の面積は、年々2,100万haの割合で増え続けていること、?放牧地の約8割(31億ha)、降雨依存農地の約6割(3億3,500万ha)、かんがい農地の約3割(4,000万ha)が既に中程度以上の砂漠化により被災していること、?砂漠化した農地の合計面積34億7,500万haは、乾燥地域における全生産地域面積(45億ha)の75%を占めること、?深刻な砂漠化による被災農村人口は、1977年の5,700万人から1983年の1億3,500万人へと増加していることが明らかにされた(第3-1-14表)。
砂漠化の人為的要因としては、家畜の過放牧(植物の成長限界以上に家畜による消費がなされることにより植生が破壊され、裸地化した土地の土壌が風食や水食により失われる)、過耕作、薪炭のための伐木、不適切なかんがいによる塩類集積等が挙げられるが、その背後には社会情勢、政治情勢、鉱工業開発による影響等の問題が存する。
今後とも開発途上国においては人口圧が増大することが予想されるので、適切な防止対策が講じられなければ、放牧地では現在とほぼ同じ速度で、降雨依存農地では加速度的に砂漠化が進行すると予想されており、特にサハラ砂漠南縁のサヘル地方、南米のアンデス地方、南アジアのインド、ネパールなどの熱帯地方の降雨依存農地における危険度が最も高いと予測されている。
また、世界の砂漠化の進行・深刻化の現状については不明な点が多く、最新のデータに基づく新しい評価が必要とされている。このため、FAOにおいて人工衛星を利用したリモートセンシングによる観測システムの整備が図られているところである。また、UNEPにおいても評価手法の検討を進めており、それをもとに1992年までに世界全体の砂漠化の進行状況をまとめることとしている。
また、砂漠化と密接に関係のあるものに土壌侵食がある。土壌侵食とは土地から雨や風によって表土が失われてしまう現象であり、乾燥地においては砂漠化を進行させ乾燥地以外でも農業生産等に被害を与える。土壌侵食の原因としては、傾斜地での耕作、不適切な樹木の伐採、不適切な農業方法等が挙げられる。土壌侵食の状況については、世界全体で年間に新しく生成される土壌よりも260億t多い土壌が失われており、そのうち半分は世界の主要な穀物生産国である米国、ソ連、インド、中国が占めていると推定されている。また、ネパールの山岳地方における森林減少によってもたらされている土壌侵食は、毎年バングラデシュをみまう洪水の原因の一つとなっているといわれている。
(6) 野生生物の種の減少
地球表面は生物圏と呼ばれ、人類の生存できる唯一の空間である。野生生物は、このごく薄い層である生物圏の物理的環境の中に、切れ目のない多様な生態系を構成し、総体としてエネルギー循環、物質循環等自然環境のバランスの維持に寄与している重要な存在で、人類に生物学的生存の基盤を提供し、かつ芸術、科学及び文化上の恩恵を及ぼしている。野生生物の直接的、実利的な面だけ見ても、それ自体食料や燃料、衣料品、装飾品や医薬品の原料として人間の生活上不可欠な資源である。ところで、一例として農作物をみれば、実際に栽培されているイネや野菜等多くのものは栽培品種であり、野生生物のみを食べている訳ではないことも確かである。しかし、すべての栽培品種は品種改良の出発点や過程において野生種の遺伝子が利用されていることを認識すべきであり、今後の地球人口の増加、気候変動等の環境変化、新しい病気に対応する医薬の開発等を可能にするためには、地球上の生命の進化の過程の所産である野生の遺伝子、種及び生態系の多様性を残す以外に賢明な方法はないといえよう。また、資源的な見方をしない場合でも、野外レクレーション、愛玩の対象として人間の生活に潤いを与えていることも直接的利益である。
約40億年前に地球上に生命が誕生して以来、進化の過程において多くの種が出現し、その一方で気象や地形の環境変化により、あるいは種間競争に敗れ多くの種が姿を消していった。このように種の絶滅は、自然のプロセスの中で絶えず起こってきたのであるが、今日、地球の歴史が始まって以来と指摘されるようなスピードで絶滅が進行しつつある原因は、自然のプロセスによるものではなく、人類の多様な行動に起因するものである。
野生生物種の絶滅の直接的な原因は、IUCNの報告(1986年)(第3-1-15表)によれば、生息環境の悪化、乱獲、侵入種の影響及びその他の順である。このうち、生息環境の悪化については、熱帯林、珊瑚礁、湿地、島しょ部等において深刻であり、中でも、野生生物種の宝庫といわれる熱帯雨林の減少は、野生生物種の減少に大きな影響を与えていると考えられている。
また、今後、種を脅かす新たな要因として、オゾン層の破壊による有害紫外線の増加、温室効果気体濃度の上昇に伴う気候の変化等も指摘されている。これまでの種の保護に対する国際機関等の考え方をみると、既に、1972年の国連人間環境会議における人間環境宣言の中で、「祖先から受け継いできた野生生物とその生息地は、今日種々の有害な要因により重大な危機にさらされており、人はこれを保護し、賢明に管理する特別な責任を負う。野生生物を含む自然の保護は、経済開発の計画立案において重視しなければならない。」との原則を示した。1973年にワシントンで作成されたワシントン条約の前文にも「野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものである。」との基本認識が示されている。その後、1987年に公表された「環境と開発にかかる世界委員会」の報告書「OurCommon Future」では、「野生生物の種とそれに含まれる遺伝子材料は、今後の人間社会の発展の中でますます重要な役割を果たしていくことは確実であり、それが野生生物保護に対する従来の倫理的、美的、科学的根拠に加え、強力な経済的根拠をも与えようとしている。」とし、作物の品種改良、医薬品原料、その他の産物としての資源としての重要性を指摘し、「種と生態系という地球の基本財産は、近い将来全人類の利益のため保護され、管理されるべき資産と見られるようになるだろう。このためには種の保護を国際的な政策上の議題として加えることが必ず必要となるであろう」と述べている。
野生生物種の現状を見ると、いくつかの調査があるが、科学的に同定されている種(学名が与えられたもの)の数は、150万〜170万種とされているが、地球上に存在する種の数は一般に500万種〜1千数百万種といわれており、3000万種を超えるとする専門家もいる。第3-1-16表は、IUCN等の調査によるものである。地球上の種の総数は、近年の昆虫類や深海底の生物の研究が進んだことなどにより増加してきたが、500万から3000万という推定値の差は、主に昆虫類の種数の推定値の差によるものである。さらに、地球上に存在する種数の分布を気候帯別に見ると、寒帯6%、温帯59%、熱帯35%となっているが、熱帯地域の分類学的研究の進捗率が極めて低いため、同定種のみで気候帯別の分布をみることは危険である。推定種でみると、寒帯1〜2%、温帯13〜24%、熱帯74〜86%である。なお、熱帯地域の中でも熱帯雨林は、世界の地表面の7%程度を占めるに過ぎないが、地球上に存在する種の約半数がそれに依存していると考えられている。
現在絶滅に瀕しているとして確認されている種数についてみると、IUCNのレッドリスト等の調査によれば1986年現在で動物3,117種、植物15,870種となっている。また、ワシントン条約の規制対象品目を種に換算すると、およそ動物3,000種、植物30,000種といわれる。今後の種の減少については、N・マイヤースの「沈みゆく箱船」、IUCNの「世界保全戦略」(1980年)、米国国務省の「西暦2000年の地球」(1980年)(第3-1-17表)他が、いづれも西暦2000年までの種の絶滅の予測を行っているが、いづれも50万〜100万種程度、あるいはそれ以上としている。これらの絶滅の予測が、IUCNのレッドリストやワシントン条約の規制対象種数を大幅に上回っているのは、小型動物、特に軟体動物、昆虫及び珊瑚等の非脊椎動物の消滅を一定の手法で予測し、消滅の対象に含めているためである。
目下、地球上に現存する野生生物の種については、一旦絶滅すれば再現不可能であることから、それらが再生産可能な状態に保全され、それを前提にして利用が図られていくことが人類生存にとって不可欠であるとの認識が支配的になりつつある。絶滅のおそれの高い種については、IUCNのレッドリストやワシントン条約の規制対象品目に示されており、少なくともこれらの種については、国際的な理解と協調のもとで絶滅を食い止める必要がある。我が国においては、ワシントン条約等に加盟するとともに、その効果的な実施を図るため、昭和62年12月より「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」を施行し、過度の国際取引により絶滅のおそれのある野生動植物の国内における流通についても規制を行うとともに、その保護を図るための規制を講じてきている。
しかしながら、現在、種の減少が最も進行しつつあるのは、最も種の多様性の高い熱帯地域であり、特に野生生物の宝庫といわれる熱帯雨林の減少が野生生物の種の減少に拍車をかけている。熱帯地域での種の大幅な減少は、急速に進行しつつある森林の減少や劣化が主たる要因であり、開発と種の保全等の調整には、解決すべき困難な問題が多い。
このため、UNEPにおいて、生物学的多様性の保護のための総合的な政策を推進するため、条約を含む新たな法的取組についての検討が開始されている。
(7) 海洋及び国際河川の汚染
海洋には、河川を経由したり、沿岸から直接流入するもののほか、船舶の航行やこれに伴う事故、海底油田開発等により各種の汚染物質が排出されている。1982年に公表されたIOC(政府間海洋学委員会)とWMO(世界気象機関)による調査結果によれば、油による汚染は、そのほとんどがメキシコ湾内、欧州、日本のタンカー航路及び米国と欧州間のタンカー航路に沿って見受けられる。油による海洋汚染は鳥類、海洋哺乳動物等の野生生物、観光産業、漁業等に大きな被害を与えることがある。また、地球全体でみた場合の影響についても、海面に広がった油膜により地球の水循環、大気循環に影響を及ぼす可能性があるといわれている。
また、近年、プラスチック類の生産量の増大に伴ってプラスチック廃棄物による海洋汚染が国際的に問題となってきている。気象庁では1976年から西太平洋において海洋漂流物の目視調査を行っており、調査海域のほぼ全域で漂流物が見いだされている。また、1987年に水産庁が日本近海・沖合域において行った海洋漂流物の目視調査結果によれば、調査海域のほぼ全域で漂流物が見られており、このうち発泡スチロール類が22%、その他のプラスチック類が23%を占めプラスチック廃棄物による汚染が目立っている。また、1970年から1987年の間に北太平洋において行った調査によれば、ハイイロミズナギドリ218個体中193個体(88.5%)、ハシボソミズナギドリ324個体中265個体(81.8%)の胃中からプラスチック類が抽出されており、繁殖能力の減退や異常行動を引き起こすこと等が懸念されている。
さらに、化学物質による海洋汚染の状況については、最近の調査によりBHC、DDT、PCB等による外洋の汚染やクジラ等の野生生物の汚染状況が報告されている。BHCとDDTについての調査によると、化学物質の生産と使用が集中している北半球中緯度地域で高い値が観測されており、南半球での汚染はあまり進んでいないが、今後は、低緯度・熱帯域へも汚染が進行するおそれもある。
このような状況に対し、海洋汚染防止のため、主として陸上で発生した廃棄物の海洋投棄を規制する「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン・ダンピング条約)と船舶からの油や有害液体物質などの排出を規制する「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が作成されており、MARPOL73/78条約については、1983年からは油に関する規則が、1987年からはばら積みの有害液体物質に関する規則が実施され、さらに1988年には、船舶からの廃物による汚染の防止のための規則を定めた附属書?が発効した。
また、1989年3月には、アラスカ湾で座礁したタンカーから大量の原油が流出し、流出油の防除対応の遅れから大規模な海洋汚染事故を招き、ラッコなどの哺乳動物、海鳥、魚類に深刻な被害をもたらした。このため、アルシュ・サミットでは国際海事機関(IMO)が油濁防止活動のための案を提示するよう求められ、これをうけて10月に開かれたIMO総会においては、大規模な油汚染事故への対応のための国際協力の確立を目的とする新条約を採択すべき旨の決議がなされ、本年11月採択に向けて策定作業が進められている。
いくつかの国に囲まれた地域海の汚染も国際的な環境汚染として問題となっており、特に世界有数の工業地帯に囲まれた北海では、従来より各種の重金属、化学物質、油、栄養塩類等が流入し生態系への影響が懸念されていたが、1988年夏には魚やアザラシが原因不明のまま大量に死滅する事件が発生した。また、北海以外にもバルト海、地中海等における汚染が問題となっている。こうした地域海の生態系を保全するため、UNEPはその海域を共有する国々に共同行動をとるよう働きかけを行ってきた。この結果、現在までに世界の11地域で130以上の国と14の国連機関・地域機関の参加により地域海の保全計画が策定され、研究、モニタリングや陸上汚染源からの汚染負荷の削減等の取組が行われている。
さらに、海洋汚染と並び河川の水質汚濁も重要な問題であり、特に国際河川の水質保全のためには沿岸諸国を中心とする国際協力が行われてきている。例えば、西ヨーロッパを流れるライン川は、流域の経済発展と人口の増加を背景に水質の悪化をまねき、1970年代の初めには溶存酸素の欠乏によって魚が浮かび上がるなどの被害が生じるとともに、重金属や有機化合物の排出も増大し飲料水への影響が懸念されるようになった。このため、スイス、フランス、西ドイツ、ルクセンブルク、オランダの沿岸諸国は、国際ライン川水質汚濁防止委員会を結成し、1976年には欧州共同体の参加を得て、ライン化学条約及びライン川の塩素による汚染防止条約を成立させた。こうした国際協力の結果、水質は溶存酸素量については正常値の80%にまで改善され、重金属濃度もほとんどすべての金属について減少した。しかし、ライン川の浄化のためには今後ともさらなる努力が必要とされている。
(8) 化学物質の管理と有害廃棄物の越境移動問題
ア. 化学物質の適正管理
化学工業の発展に伴い、数万種にのぼる化学物質が工業的に生産され、その製造数量も飛躍的に増加している。また、市民生活に密接な分野を含む種々の分野で多様な化学物質が利用されるようになってきた。このような化学物質の使用の増加等に伴って、化学物質が環境中に排出される機会も増加し、PCB等の有機塩素系化学物質のように世界的規模の汚染が認められるものもあり、化学物質による環境汚染問題は国内だけでなく世界共通の大きな問題となっている。
化学物質による環境汚染は、健康や環境に対する影響を十分評価しないまま大量・広範に使用されていたことが原因の一つであり、化学物質の影響評価及び製造、流通、使用、廃棄等の全過程における管理等の徹底が重要となっている。我が国を含め欧米各国で新規の化学物質について製造、輸入又は市場化前に安全性を評価するため届出を義務づける制度が整備されてきている。また、米国では、化学物質に係る大規模事故に鑑み、事故時の対応や化学物質の貯蔵量の届出等についても制度が整備されてきている。さらに、OECD等の国際機関でも新規化学物質の届出制度、大規模事故対策、化学物質の安全性評価手法、各国の化学物質規制や調査研究状況等の情報交換、既存化学物質に対する各国分担による環境安全性試験データの整備事業活動等の活動が行われている。また、開発途上国等に対する適切な情報提供の観点等から、厳しく製造等が規制されている化学物質の輸出入の際の情報提供等についての勧告も出されている。
世界的な大量の化学物質の生産や使用、国際流通が増加していることや化学物質による環境汚染は徐々に進行し地球規模に広がる場合があること等を踏まえると、化学物質による環境汚染の未然防止を図るためには、各国レベルでの対応に加え、国際的な環境汚染状況の監視、化学物質の安全性に関する情報の整備、国際的な協力による化学物質管理等の強化が重要な課題となっている。
イ. 有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物の越境移動は、各国が陸続きで接しているヨーロッパでは、従来より容易に行われてきた。現在でもヨーロッパのOECD加盟国全体で200万tの有害廃棄物が国境を越えて処分されており、東ドイツ、ハンガリー、ユーゴスラビアといった外貨不足に悩む東欧の国々への輸出に加えて、最近では中東やトルコといった国にも越境移動していることが判明している。
有害廃棄物について越境移動が生じる原因としては、?自国における処理費の高騰、?自国における特定の廃棄物の処分容量の減少、?自国において陸上処分した場合それによって将来起こるかもしれない環境汚染による被害の補償の可能性、?有機溶剤等特定の廃棄物の処理に関する法規制等の強化、?排出事業者による廃棄物の発生場所での処理に関する法規制等の強化、?経済成長による廃棄物量の増大、?数か国が利用できる処理施設の存在、?本来なら最終処分されてしまう廃棄物から回収しうる物質が取り引きされる市場の存在、?自国よりも外国の処理施設が近接していることが挙げられており、特別な施設による高度な処理を行わなければならない有害廃棄物がより規制が緩く処理費用もかからない開発途上国等へと輸出されているものと考えられている。
有害廃棄物の越境移動は、ヨーロッパ域内においては、イタリアの農薬工場の爆発事故(セベソ事件)の際に発生したダイオキシンによって汚染された土壌が行方不明になり、8か月後に北フランスで発見された事件の発生等により1980年代前半から問題とされはじめ、OECDやヨーロッパ共同体(EC)により、有害廃棄物の輸出に当たって事業者等は事前に輸出国、輸入国の政府機関に連絡し、許可をとるべきことなどを内容とする決定・勧告や指令等を採択する等の取組が行われてきた。
しかし、1980年代後半になって欧米から有害廃棄物が適正な処分が確認されないままアフリカや南米の開発途上国へ輸出されたり、不法に搬入、放置される事例がたび重なるようになり、地域を越えた世界的な問題となってきた。代表的な事例としては、イギリスの会社が対外債務の返済に苦しむギニアビサウに1,500万tの有害廃棄物を負債額の倍に及ぶ契約額で持ち込もうとしたり、イタリアの会社がPCB等を含む有害廃棄物をナイジェリアに投棄した事件などがある。
このような状況に鑑みて、1987年、UNEPは有害廃棄物の適切な管理のための基本的事項をとりまとめた(カイロガイドライン)。また、アフリカ統一機構(OAU)は、1988年、外国政府や企業との間で有害廃棄物をアフリカにおいて処分する協定や契約を結ぶことを禁ずる決議をした。こうした動きを踏まえて、1989年3月、UNEPや各国政府の努力により、輸出入に伴う通報制度や違法な越境移動行為が行われた場合の措置等を規定した「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」(仮称)が採択された。これを受けて、我が国においても、条約への早期加入をめざして所要の検討を進めている。
(9) 開発途上国における環境汚染
開発途上国では経済発展のために工業化を進め、その生産量は飛躍的に増加してきた。当初は軽工業を中心として工業化が進んできたが、次第に石油化学、金属などの重化学工業化が進行し、これら環境負荷の大きい産業の立地が増加するにしたがって、産業公害も顕在化してきている。また、開発途上国では人口が高い伸び率で増加を続けており、それが熱帯林の減少の一因となるとともに、農村地域で生活することができなくなった人々が都市へ大量に流入することから、都市人口の急激な膨張、集中が進んでいる。この結果、スラムが広範に形成され、生活環境、衛生状態は悪化、生活公害が増大することとなっている。NIES諸国では、これら工業化と人口集中がより急激であったことから公害も広く認められるようになってきている。一方その他の途上国では、これら工業化による環境悪化に加え、貧困による劣悪な衛生環境の問題が重要な問題として存在している。
まず、大気汚染についてみると、UNEP/世界保健機関(WHO)のモニタリング・ネットワークにより、世界の主要都市の二酸化硫黄の濃度を見ると、開発途上国の都市では先進工業国と同程度かそれ以上の濃度となっており、上位10都市のうち7都市は開発途上国の都市である(第3-1-18図)。また、浮遊粒子状物質も同様であり、例えば、メキシコシティでは、一日に吸引する量は40本の煙草を吸うのと同じレベルにある。また、先進工業国の都市では次第に改善する傾向を示す都市が多いが、開発途上国の都市では逆に次第に悪化する傾向にある都市が多くなっている(第3-1-19図)。
また、水質汚濁に関しては、不十分な汚水処理、あるいは農薬の地下水浸透や河川流入による問題等が発生している。UNEP「世界の環境の状況」(1989年)よると、UNEP/WHOのモニタリング・ネットワークによる観測地点の中で、有機化学物質による水質汚染が1μg/リットル以上の高い数値を示した河川として、タンザニアのルフィジ川(ディルドリン3.0μg/リットル)、コロンビアのカンカ・ジャンチト川(DDT3.0μg/リットル)、マレーシアのゴムバク川(ディルドリン30.6μg/リットル)そしてインドネシアのすべての観測地点(PCBS、0.4〜6.9μg/リットル)と開発途上国の河川があげられている。
このような開発途上国における環境汚染の解決に協力するために、我が国はすでに円借款、無償資金協力、専門家の派遣、研修員の受入れ、開発調査等を行ってきているが、高い技術力と資金を有する我が国が今後一層環境協力を推進していくことが望まれている。