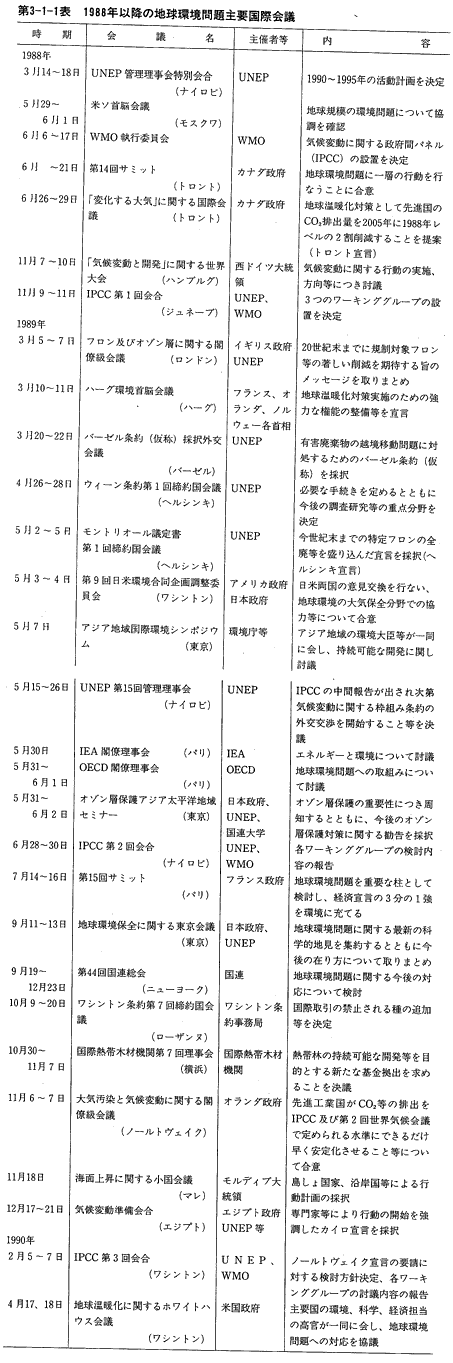
1 地球環境問題をめぐる内外の動向
1989年は、世界においても、日本においても地球環境保全のための大きな一歩を踏みだす年となった。以下では、ここ一年間を中心に、地球環境問題に関連する内外の状況をみてみる。
(1) 世界の動向
1989年は、地球環境が重大な危機に瀕しているという世界の共通した認識が強まり、持続可能な開発に向け一致協力していかなければならないという合意が形成されるとともに、国際協力のための枠組みづくりに向けて大きな前進をみた年となった。1989年以降、国際的な合意形成に向けて次のような国際的協議が行なわれた(第3-1-1表)。
? ハーグ環境首脳会議
1989年3月、オランダのハーグ市でフランス、オランダ及びノールウェーの三か国の首相の共催により、地球温暖化に対する国際的取り組みのあり方を論議するための首脳会議(ハーグ会合)が開催され、我が国からは、環境庁長官が政府を代表して出席した。
この会議では、「今日、大気の温暖化とオゾン層の破壊という地球の大気に対する激しい攻撃により、地球上の生存条件そのものが脅威にさらされている。これは地球レベルの協力によってはじめて解決できる」という基本的な認識に立ち、地球温暖化対策の実行のために有効な決定を行ない得るような制度的権限の整備を検討すること等を内容とする「ハーグ宣言」を採択した。
? オゾン層保護のためのウィーン条約第1回締約国会議等
オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「ウィーン条約」という。)は既に1985年に採択され、これに基づき各国の具体的な規制内容等を定めたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)が1987年に採択されるとともに、それぞれ1988年9月及び1989年1月に発効している。ウィーン条約は、各国がオゾン層保護のために適切な措置をとること、研究協力や情報交換を行うこと等を定めたものである。また、モントリオール議定書により、オゾン層を破壊しやすい特定フロンの生産量及び消費量を1986年の水準に比べ、各一年間について1989年7月から100%以下、1993年7月から80%以下、1998年7月から50%以下とするとともに、特定ハロンの生産量及び消費量については1992年1月から1986年の水準以下に凍結することとされている。
最新の科学的知見によれば、このような規制スケジュールではオゾン層の保護が十分でないとの懸念が強まったことから、1989年3月、イギリス政府とUNEPの共催により、「フロン及びオゾン層に関する閣僚級会議」(ロンドン会議)が開催され、「全ての先進工業国は、20世紀末までに規制対象フロン等の著しい削減を達成するものと期待される」とする議長メッセージがとりまとめられた。
このような状況のなかで、ヘルシンキにおいて1989年4月末ウィーン条約第1回締約国会議が、引き続き5月にモントリオール議定書第1回締約国会議が開催された。
モントリオール議定書第1回締約国会議では、特定フロン等に関する規制強化問題と途上国に対する援助の充実に関する問題が焦点となり、特定フロンの今世紀末までの全廃等を合意する「ヘルシンキ宣言」が採択された。この宣言で合意された主な事項は次のとおりである。
a) ウィーン条約及びモントリオール議定書に未だ参加していない国に対して、参加するよう要請すること。
b) 遅くとも2000年までに特定フロンを全廃すること。
c) 実現可能な限り早く、ハロンを全廃すること及びその他のオゾン層破壊物質を規制し削減すること。
d) 各国は、その能力等に応じ代替品や代替技術の開発に全力を尽くすこと。
e) 開発途上国に対する情報提供や訓練の機会の提供に努めるとともに、技術移転等を促進するための適切な資金援助の仕組みの整備に努めること。
また、規制強化等に関する議定書改正案の作成、途上国に対する財政的支援のメカニズム等に関するワーキンググループが設置され、1990年6月に開催予定のモントリオール議定書第2回締約国会議に向けて検討が行われている。第2回締約国会議では、特定フロンの全廃等を内容とする議定書改正案が採択される予定である。
? UNEP管理理事会
UNEP管理理事会は、UNEPの最高意思決定を行う機関であり、2年に1回開催されている。1989年5月に開催された第15回UNEP管理理事会では、地球温暖化防止に関する枠組み条約づくりに関し、1990年秋に取りまとめられる予定の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の中間報告が出され次第、枠組み条約についての外交交渉を開始することとし、その準備をUNEPがWMOと協力して行うことが決定された。
また、「国連人間環境会議」の20周年に当たる1992年に「環境と開発に関する国連会議」を開催し、地球温暖化、オゾン層保護、森林保全、生物学的多様性の維持等を主要な環境問題として掲げつつ、地域レベル及び地球レベルでの環境保全のための戦略づくりを行うこと等を決議した。さらに、地球上の生物学的多様性を保護するための条約を含む新たな法的取組を行うため、技術的、法制的な検討結果をまとめた報告書を前記「環境と開発に関する国連会議」の準備会合に提出することになった。
本会議をも踏まえて、1989年12月の第44回国連総会において、1992年にブラジルで「環境と開発に関する国連会議」を開催することが正式に決定された。
? アルシュ・サミット
主要先進7ヵ国とECの首脳の集まる主要国首脳会議(サミット)では、1981年のオタワ・サミット以来その経済宣言において地球環境の保護について触れられてきたが、1989年7月パリ郊外のアルシュで行われたアルシュ・サミットは、地球環境問題を中心的な課題の一つとして経済宣言の三分の一強をこれに割くという画期的なサミットとなった。
この経済宣言では、「成層圏オゾン層の破壊、将来気候変動をもたらし得るCO2及びその他の温室効果気体の過剰排出等、我々の環境に対する深刻な脅威の存在が科学的研究により明らかになった。環境保護のためには、断固とした協調的な国際的対応を行うこと及び持続可能な開発に根ざした政策を世界的規模で早急に採用することが要請される。」と謳った。また、「環境問題に関する科学的研究に一層の弾みを与え、必要な技術を開発し、環境政策の経済的な費用と効果につき明確な評価を行うようすべての国に対し要請する。これらの問題のいくつかについて不確実性が残っているからといって、我々の行動が不当に遅延されてはならない。」と明確に述べるなど、地球環境保全のための様々な基本原則について合意を行った。さらに、地球温暖化問題については、「気候変動に関する一般原則あるいは指針を定める枠組みまたは包括的条約の締結が、……早急に求められている。」とし、「科学的根拠により必要とされ、また許容される場合には、具体的責務を盛り込んだ特定の議定書をこの枠組みの中に組み込むこともできよう。」とした。
我が国は、このサミットの機会に、地球環境問題の取り組みに当たっては途上国における環境保全努力の支援が必要であるとの観点から、今後3年間に環境分野における二国間・多国間援助を3,000億円(約22.5億ドル)程度を目途として拡充強化に努めることを国際的に表明した。
? 地球環境保全に関する東京会議
1989年9月、日本政府の主催により「地球環境保全に関する東京会議」が開催された。本会議は、地球環境問題のうち、地球温暖化、熱帯林の減少及び開発途上国の環境汚染問題を重点的な検討テーマとして取り上げ、最新の科学的知見の集約と今後世界のとるべき行動についての提言を行うことを目的として、世界23か国から多数の有識者の参加を得て行われたものである。討議の結果を取りまとめた議長総括では、地球環境問題に関する不確実性を減少させるため調査研究やモニタリングが不可欠であること、すべての国において生活様式を改めることを含む「環境倫理」が確立される必要があること、開発途上国の持続的開発のため国際的な資金づくりへの革新的なアプローチが必要であること、以上のような国際協力の進展のためUNEP等の国際機関の強化が必要なこと等が述べられている。本会議の成果は、その後の各種の国際会議等における重要な参考資料として生かされることとなった。
? ワシントン条約第7回締約国会議
野生動植物の国際取引を規制することにより野生生物の保護を図ろうとする「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が、1973年に採択され、1975年に発効し、1980年に我が国についても発効ている。本条約により、絶滅のおそれがある種で、取引により影響を受けるものとして附属書?に掲げられた動植物については、商業目的のための国際取引は禁止され、現在は必ずしも絶滅のおそれはないが取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れのある種となり得るものとして附属書?に掲げられた動植物については、商業目的の国際取引は可能であるが輸出国政府の発行する輸出許可書が必要とされている。ただし、各国は、規制対象品目であってもなんらかの理由により留保すること(当該品目につき非締約国扱いとなること)ができることとなっている。
1989年10月、スイスのローザンヌで開催されたワシントン条約第7回締約国会議では、象牙の取り扱いが大きな問題となり、全てのアフリカゾウ個体群を附属書?から附属書?へ移行することとなったほか、シーラカンス、ラン科パフィオペディルム属全種等についても附属書?から附属書?へ移行すること等が合意された。また、我が国は、附属書?の動植物の中で留保している11種のうち、イリエワニについては同年11月末までに留保を撤回すること、インドオオトカゲ及びアカオオトカゲについては次回締約国会議までに留保を撤回する方針であることを表明した。また、次回の締約国会議は、1992年春に日本で開催されることが決定された。
? ノールトヴェイク会合
1989年11月、オランダ政府の主催により、「大気汚染及び気候変動に関する閣僚会議」がオランダのハーグ郊外のノールトヴェイクで開催され、我が国をはじめとするサミット参加国はもとより、ソ連、東欧諸国や中国、インド等の開発途上国を含め67か国の環境大臣及び11国際機関の代表が出席した。この会議は、地球温暖化はこのまま放置すれば地球の未来を脅かす重大な問題であるとの認識のもとに、地球温暖化対策の推進のため、世界各国の一致協力した取組を促進することを目的として開催されたものである。
会議の結果は「大気汚染及び気候変動に関するノールトヴェイク宣言」として取りまとめられた。この宣言には、
a) 世界経済の安定的発展を確保しつつ、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出を安定化させる必要性を認識し、先進工業国は、このような安定化がIPCC及び1990年11月の第2回世界気候会議によって検討される水準で、先進工業国により可能なかぎり早期に達成されるべきことに合意する。多くの先進工業国の見解によれば、二酸化炭素のこのような安定化は、第一段階として、遅くとも2000年までに達成されるべきである。
b) 森林の増減を地球的規模でバランスさせ、来世紀の初めに年間1,200万haの世界の森林面積の純増を暫定的目標とし、IPCCに対し、この目標達成の実現可能性を検討するよう要請する。
c) 開発途上国に対する資金供給については、既存の資金援助を活用するとともに、クリアリングハウス(援助を行なう側と援助を受ける側の仲介を行なう仕組み)構想や新たな国際基金の可能性を含め、追加的な資金供給の仕組みについて、更に検討がなされるべきである。
d) 気候変動に関する枠組み条約を可能であれば1991年、遅くとも1992年の「環境と開発に関する国連会議」において条約が採択されるよう、最大限の努力を払う。
こと等が盛り込まれた。温室効果ガスの排出量を先進工業国がIPCC及び1990年11月の第2回世界気候会議によって検討される水準で安定化させることに合意したことや森林面積の回復について具体的な目標が掲げられたこと等により、本会合は地域温暖化対策の推進に向けて大きな前進を促すものとなった。
また、1990年2月に開催された第3回IPCCでは、この宣言でIPCCに要請された検討を行なって8月に予定される中間報告にその結果を盛り込むことが決定された。
こうした国際的な動きに続いて、今後も重要な国際的な会議が次々に開催される予定である(第3-1-2表)。このような動きは、1992年の「環境と開発に関する国連会議」をひとつの節目としており、この会議に向けて、国際的な協力の枠組みづくりを目指し、世界の叡知を集めた議論が行われることとなっている。
(2) 我が国政府の取組
ア 地球環境保全に関する関係閣僚会議の設置
平成元年5月12日、政府は、地球規模で深刻な影響を与える環境問題に対応するための施策に関し、関係行政機関の緊密な連絡を確保し、その効果的かつ総合的な推進を図るため、「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置し、これを随時開催することとした。
そして、6月30日に第一回会合を開催し、「地球環境保全に関する施策について」申合せを行った。
この申合せでは、地球環境問題が顕在化し、国際的取組の気運が急速に高まってきている中で、高度な経済活動を営み、地球環境に大きなかかわりを持つと同時に、公害防止等の分野で優れた技術力を有する我が国としては、今後更に、国際的地位に応じた役割を積極的に果たしていく必要があるとしたうえで、当面、我が国が講ずべき施策の基本的方向として、次の6項目を示した。
1) 地球環境保全のための国際的な枠組みづくりに積極的に参加し、地球的視野に立った施策の推進を図ること。
2) 人類の諸活動が地球環境に及ぼす影響等を科学的に解明することにより、地球環境保全のための基盤づくりを進めるため、地球環境に関する観測・監視と調査研究を推進すること。
3) 地球環境保全に資する技術の開発、普及に努めること。
4) 開発途上国の環境保全に積極的に貢献するため、環境分野の政府開発援助の拡充、開発途上国の実情に応じた技術の開発・移転及び環境分野における人材の育成等に努めること。
5) 政府開発援助等の実施に際しての環境配慮を強化すること。
6) 省資源、省エネルギーの推進等地球環境への負荷がより少ない方法で経済活動が行われるよう努力し、また、国民各界各層への普及・啓発を推進すること。
また、地球環境問題の解決のためには、長期的視野に立って科学的知見を集積することが必要であり、我が国としては、世界に率先して直ちにこれに努め、内外の研究者等の総力を結集して取り組む必要がある。このような観点から、10月31日には第二回の関係閣僚会議を開催し、「地球環境保全に関する調査研究、観測・監視及び技術開発の総合的推進について」申合せを行った。これは、第一回会合の申合せの第二項目及び第三項目の具体化に向けたものであり、その内容は次のとおりである。
1) 地球環境に関する国際共同研究計画への積極的参加等により調査研究を推進すること、大気、海洋、生態系等の広域的な観測・監視及び人工衛星による観測・監視並びに国際的な観測・監視ネットワークの充実等により観測・監視を推進すること及び民間とも協力しつつ広範な分野で技術開発を推進すること
2) これらを着実に推進するため、閣僚会議は、各年度の調査研究、観測・監視及び技術開発についての総合推進計画を定めるとともに、同計画の実施状況及びその結果に関する報告を受け、さらに環境庁を全般的窓口とし関係省庁においても地球環境保全に関する情報の窓口を定めること。
イ 地球環境問題担当大臣の指名
また、政府は、地球環境問題に対応するための施策を政府一体となって円滑に推進するため、平成元年7月11日、地球環境問題に係る行政各部の所管する事務の調整を担当する「地球環境問題担当大臣」を置くこととし、爾来、環境庁長官が指名されている。
地球環境問題担当大臣は、各省にまたがる事務の調整の一つとして、政府全体の平成2年度の地球環境保全関係予算を取りまとめた。
政府全体の平成2年度の地球環境保全関係予算は、前記閣僚会議の申合せを踏まえた関係省庁の積極的な政策努力を反映して、総額4,523億円で対前年度比6.3%増、このうち特に政策経費については600億円で対前年度比35.9%増と著しい伸びを示している。