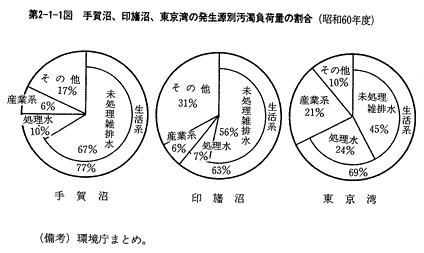
2 生活雑排水対策の推進
第1章でみたとおり、人の生活環境の保護に関わる有機物質等による水質汚濁は、近年、改善が進んでおらず、依然として水道水の異臭味等の被害を生じさせている。
こうした水質汚濁の要因をみると、生活系の排水による汚濁負荷の割合が高く、手賀沼で77%、印旛沼で63%、東京湾で69%などとなっており、首都圏の都市河川のうち特に汚濁の著しい河川についてみても非常に高い割合となっている(第2-1-1図)。生活系の負荷のうち、し尿については未処理で公共用水域に排出することが禁止されているが、調理や洗濯、入浴等に伴って排出されるいわゆる生活雑排水については、未処理で放流される場合が多く、水質保全上見過ごすことのできない問題となっている。このため、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁問題への取組が急務となっており、これまで家庭等からの汚濁負荷の抑制に向けて生活雑排水対策の強化を図ってきた。
生活雑排水対策の中心の一つは、下水道等の集合処理施設や各家庭に設置される合併処理浄化槽といった生活雑排水を処理する施設の整備等により未処理排水の排出を抑制することである。下水道の処理人口は近年毎年約200万人ずつ伸びてきているが、現在の普及率は全国の人口の約4割であり、その他の生活雑排水処理施設を加えてもかなりの国民の生活雑排水は未処理で排出されている(第2-1-2図)。そのため、これらの施設の一層の整備・普及を進めているところである。もう一つは、台所での水切り用ろ紙袋の使用や地域での廃食用油の集団回収等の日常生活において身近にできる対策の普及、啓発の推進である。このため環境庁では昭和56年から地方公共団体による普及・啓発活動の進め方について指針づくりを行うとともに、昭和59年から毎年5地域を選定してモデル事業を実施してきている。住民による実践活動は、その主体や地域的な広がりを異にする様々な形態で実施されており、各地区の住民によるリーダーを中心とする協議会を設置する等により顕著な効果をあげている事例もみられる。
しかしながら、生活雑排水対策としては、下水道の整備が行われているほか、地域の実情に応じ、コミュニティプラント(地域し尿処理施設)、農業集落排水施策等の整備及び各家庭向けの合併処理浄化槽の設置に対する助成等の諸施策が講じられてきているが、これらの施設は事業の進め方、建設等に要する費用、管理主体等にそれぞれ特徴を有しているため、それぞれの施設を踏まえて、地域の実情に合った計画的な整備を図っていくことが必要となっている。さらに、生活雑排水についても極力負荷の抑制を図らねばならないことについて、今後とも国民への啓発が必要な状況にある。
このような状況を踏まえ、また中央公害対策審議会からの答申を受けて、環境庁としては総合的な対策推進のための制度化に関し所要の対応を図ることとしたところである。