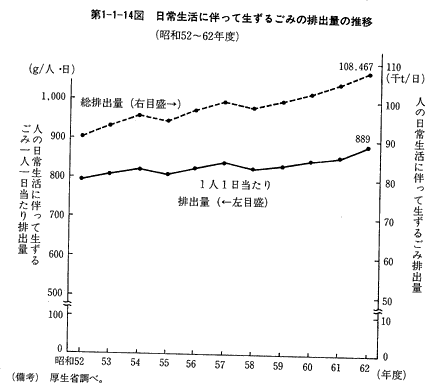
8 廃棄物
廃棄物には、事業活動に伴って排出される汚でい、廃油等の産業廃棄物と、し尿、ごみ、生活雑排水など主として国民の日常生活に伴って生ずるもの及び事務所から出る紙ごみなどの一般廃棄物がある。一般廃棄物のうち人の日常生活に伴って生ずるごみ排出量は、近年一貫して増加傾向にあり、昭和62年度で、3,959万t(昭和61年度3,808万t)となっている(第1-1-14図)。近年の消費活動の拡大・多様化によって排出される廃棄物も多様化しており、その適正な処理が課題となっている。また、オフィスのOA化等に伴って紙類のごみなどが急激に増加している。
くみ取りし尿量については、水洗化人口の増加等によってここ数年微減傾向にあり、62年度では3,764万kl(61年度3,815万kl)となっている。
産業廃棄物の排出量は昭和60年度3億1,200万tと昭和55年度の2億9,200万tに比較して7%増加している。
廃棄物処理については、最終処分場の確保が問題になってきており、特に大都市地域においては深刻な問題となっている。とりわけ、一般廃棄物の発生量、最終処分量について全国の約4分の1を占める東京圏(1都3県(埼玉県、千葉県、神奈川県))では、最終処分場の残余容量は昭和62年度末において約5年分と評価されており、既に自己の処分場で処分しきれず、処分場を他県の市町村内にもつ民間の処分業者に委託することなどにより対処している市町村が全体の36%に及んでいる。また、現在は自己処分場で処分している市町村でもその約9割が平成7年以前に埋立てが完了する見込みとなっている。さらに、産業廃棄物についても、最終処分場の残余容量は圏域全体で約1年分しかなく、例えば東京都内で発生する産業廃棄物の埋立量の約65%は他県で処分されている。こうした状況にあって、地方公共団体の中には、地域外で発生した産業廃棄物の搬入について事前協議を求める措置をとったり、産業廃棄物処分場設置反対の議会議決を行うなどの動きがみられており、最終処分場の確保が一層重要かつ緊急の課題となっている。
また、最終処分場については、処分後の跡地を含めその適切な管理を行うことが重要であり、性状の変化、排出形態等の変化に伴って出現するおそれのある処理困難な廃棄物については適正処理を行うとともに、減量化・再生利用に努めていく必要がある。