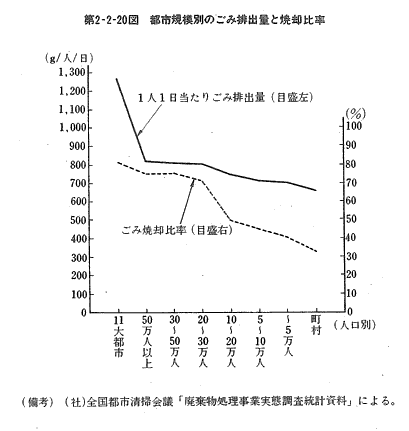
4 都市の物質循環と廃棄物
技術革新の進展、都市活動の活発化、消費物質の多様化等により、都市における物質代謝は巨大かつ複雑なものとなっており、それに伴って廃棄物の発生量も膨大になるとともに、その処理について様々な問題を引き起こしている。
(1) 都市の人間活動と廃棄物
戦後、我が国の廃棄物は、経済活動の活発化・高度化を背景として、量的に増大するとともに質的にも多様化してきた。都市規模別のごみ発生量をみると、事業系一般廃棄物の寄与もあって、都市規模が大きくなるにしたがって1人当たりの発生量も増加している(第2-2-20図)。また、廃棄物は質的にも多様化してきており、それに対応することが重要となっている。
ここでは、消費の多様化、情報化、建築活動の活発化等による土木・建設事業の増大といった都市活動の新たな展開と廃棄物とのかかわりについてみてみる。
ア 消費の多様化と廃棄物
消費活動の拡大・多様化や技術革新の進展等を反映して、排出される廃棄物も多様化し、適正な処理の困難な廃棄物がみられる。
全国の地方公共団体・事務組合を対象として行われた調査によると、地方公共団体によって異なるが、適正処理の困難な廃棄物としては、最も困難度の高い乾電池をはじめとして、タイヤ、農薬、自動車、電気冷蔵庫、注射器・輸血バッグ、テレビ等が挙げられており、理由としては、粉砕が困難、有害物質が発生すること等が指摘されている。また、近年伸びの著しく処理・再資源化が困難な廃棄物としては、電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビ等が指摘されている。
乾電池の国内流通量は年々増加し、昭和62年には約20億個となっている。これに対し、乾電池全体としての水銀使用量は、乾電池1個当たりの平均水銀含有量が削減されてきたこともあってここ数年減少しており、62年では約44tとなっている。
冷蔵庫、テレビ等の家電製品は、普及率が年々高まるとともに、大型化が進んでいるものも多く、その廃棄物は量的にも容積・重量的にも増大している。
さらに、我が国では、少量多頻度流通に対するニーズが高く、販売に際しプラスチック容器や包装紙の使用が多くなっており、それが、ごみへのプラスチックや紙の混入を高めている(第2-2-21図)。また、外食産業、特にファーストフード店の急成長にみられるような消費のサービス化もこうした動きに寄与している。
その他、近年、ガラスびんや金属びんにかわって合成樹脂びん(ペット(PET)ボトル)が増加しており、中でも飲料用の容器が増大している。(第2-2-22図)。
イ OA化と廃棄物
我が国では、現在、技術革新に支えられて急速な情報化が進んでおり、それが情報機器の普及・高度化によるオフィス・オートメーション(OA)化の進展となって表れている。例えば、コンピューター及び端末の設置台数は、いずれもこの5年間で約2倍と大幅な増加となっている。また、日本語ワープロの販売台数をみても、昭和60年代に入って急速に増加している。こうしたOA化の進展は、オフィスの「ペーパーレス化」を通じてごみの減少につながることが期待されるが、近時では、逆に紙類のごみの増加が指摘されるようになっている。第2-2-23図はコンピューターの打出用紙等のOA機器関連の紙類の国内出荷量をみたものであるが、いずれもここ数年高い伸びとなっている。また大都市における主なオフィスビルからのごみ発生量を調査した結果からは、床面積1?当たり月間で1kg前後にものぼっていることがわかる。
ウ 建設活動と廃棄物
近年、都市域における住宅・オフィスビル需要の増大等を背景として土木・建築工事が盛んになっており、それに伴い建設廃材等の発生量も増加している。全国の産業廃棄物発生量に占める建設業の割合をみると、昭和55年度の10.4%から60年度の18.4%と大きく増加している。また、東京都における建設工事に伴う廃材等の発生量を57年度と61年度で比較してみると、アスファルト廃材1割増、コンクリート廃材6割増、汚泥3割増、残土3割増と増加している。(第2-2-24図)。
(2) 廃棄物の処理と環境問題
廃棄物は、その発生から排出、収集・運搬を経て処分に至るまでの様々な過程の中で環境とのかかわりをもっている。特に近年では、廃棄物が量的に増大するとともに質的にも多様化しており、様々な問題が生じてきている。
ア 廃棄物の処理に伴う問題
ごみは、昭和61年度では全体の71.8%が焼却されており、都市規模が大きいほど焼却比率も高くなっている(第2-2-20図)。近年、ごみの焼却過程におけるダイオキシンの発生や有害物質を含むごみの混入による環境汚染が懸念されていることから、環境庁等では、59年度にはごみ焼却処理施設や最終処分場におけるダイオキシン及び水銀について調査を行った。その結果、現在のところ問題になるレベルの汚染はみられなかったが、その動向については、今後とも十分留意していく必要がある。また、ごみへのプラスチック類の混入の増大は、焼却時の発熱量を高め、焼却炉によっては炉の劣化につながるおそれがある。
一方、建設活動の活発化等から、今後も建築物の解体が増大するとみられるが、その現場やそこから発生する廃材の処理について、量的な面に加え質的な面でも課題が生じている。我が国では、国内で消費される石綿の約7割が建造物材料として使用されてきたが、大量に石綿含有材料の使用されている建築物の解体や廃材の処理は、石綿発生源となりうる。環境庁が昭和56〜58年度に行った調査結果によると、廃棄物処分場周辺や解体ビル周辺等での石綿濃度が他の地域と比べ高くなっている。
医療廃棄物についても、医療サービスの増大、医療技術の進歩、使い捨て注射針の普及等医療形態の変化等から、量的に増加するとともに質的にも多様化しているが、これらの廃棄物からの感染等の危険性が指摘されており、その適正な処理が課題となっている。
イ 最終処分場の確保の問題
さらに、廃棄物量の増大に伴い、その最終処分に必要な処分場の確保が問題となっている。特に、大都市圏とその周辺地域においては最終処分場の確保が極めて困難となっており、東京圏、大阪圏については海面埋立ての割合が高まっているが、これらの閉鎖性水域においては、貴重な自然や水面の確保に留意していく必要がある。なお、東京都では、産業廃棄物について処分量の8割を他県に依存しており、首都圏域においても最終処分場の確保は容易でない状況となっている。
ウ 処分跡地管理の問題
今後も増加していく最終処分場の跡地管理も重要な課題となっている。環境庁が都道府県及び水質汚濁防止法の政令市を対象として行ったアンケート調査によれば、市街地土壌汚染が報告された事例63件の汚染の原因については、「廃棄物の埋立又は埋立地からの溶出」を原因とするものが14件で全体の2割強を占め、工程中の設備の破損・漏出に次ぐ2番目に大きな原因となっている。
また、工場移転等に際して跡地の土壌汚染も問題となっており、地方公共団体レベルでは、横浜市、東京都等において、企業に土壌汚染の有無の確認を義務づけるための要綱等が制定されているが、まだ全体としては取組が遅れている。なお、公害防止事業団では、汚染土壌の除去等の対策の実施について低利融資を行っている。
(3) 廃棄物の再生利用
都市における廃棄物問題に対応するためには、廃棄物発生量の削減、再生利用等による減量化、廃棄物処理施設の整備による処理機能の強化等を図る必要がある。特に、廃棄物の再生利用(リサイクル)は、健全な物質循環と再生するという意味で重要である。そこで、ここでは、我が国における廃棄物のリサイクルの状況とその問題点をみてみる。
ア リサイクルの現状
故紙、ガラス、金属など資源として再利用できるものが廃棄物の中に多く含まれており、以前から故紙や金属等については、民間の資源回収業者や集団回収等により回収され資源化されてきている。また、市町村においても、資源ごみの分別収集等により資源回収が図られている(第2-2-25図)。(財)クリーン・ジャパン・センターが地方公共団体を対象に行った昭和61年度の調査結果によると、何らかの再資源化を行っている地方公共団体の割合は、市では約73%、町村で約48%となっている。
集団回収については、実施していると答えた地方公共団体は市で約90%、町村で74%となっている。また、厚生省のまとめた調査によると、資源化率については、都市規模が大きくなるほど概して小さくなっている。
イ リサイクル推進上の問題点
廃棄物のリサイクルを推進するに際しての問題点としては、製品の質の変化、廃棄物の量・質の不安定性、排出時における分別の不徹底、収集・運搬に係わるコストの増大、再生資源市場の不安定性等がある。
冷蔵庫、テレビ、洗濯機等の家電製品は、小売店、地方公共団体、あるいは資源回収業者と通じて回収と廃棄または再資源化が図られてきた。冷蔵庫、洗濯機等の再資源化率の高い(80%以上)ものもあるが、テレビのように(6〜9%)依然として低いものもある。また、近年、製品の素材としては金属類の使用割合が減少し、プラスチック類やガラス類の使用割合が増加するなど製品の質的変化が起こっており、再資源化が難しくなっている。
一方、消費ニーズの多様化等を反映して、使い捨てびんやペット・ボトルの販売・消費量が増加しており、廃棄物のリサイクルの阻害要因となっている。
さらに、再生資源の価格は、市況や、品目によっては為替レートに左右される。例えば、近時の円高による安価な原材料輸入の増大は、故紙価格の低迷につながり、それが紙類のごみへの混入増大の要因ともなっている。また、再生技術や流通市場が確立されていないこと等から、資源として回収されても、再資源化された製品の需要が拡大されにくいものもある。