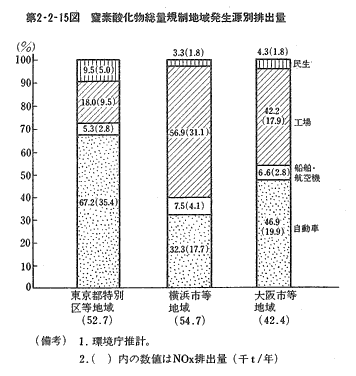
3 都市における人と物資の移動と自動車交通
都市の諸活動、都市と都市の間の人的・物的交流を支えているのが交通である。交通は,都市内の生産、生活等の都市機能の分化を可能にするとともに、都市活動の地域的広がりをもたらし、物資等の供給について他地域への依存を高めている。自然の生態系においては、物資等の移動は水や大気の流れがつかさどり、自立・安定的、循環的な系を形成している。
都市交通に起因する環境汚染については、昭和40年代から自動車単体からの排出ガス等の規制が逐次実施されているが、都市活動の規模、密度の拡大、産業構造の高度化等に伴い増大する交通量に対応した都市の構造、交通体系等が形成されてこなかったこともあり、大都市を中心とした窒素酸化物による大気汚染等の問題の大きな要因の一つとなっている。特に、二酸化窒素の濃度は近年悪化しており、対策が現状のままでは環境基準の達成は困難であり、対策の充実・強化が求められている。
(1) 自動車交通と窒素酸化物問題
窒素酸化物対策としては、工場に対する排出規制の強化、規制対象施設の拡充及び東京地域等3地域における総量規制、自動車単体に対する排出規制の強化を行ってきているほか、自動車交通対策として、物資輸送の効率を高めることによってトラック走行量の抑制を図る物流対策、公共交通機関の利便性を高めること等によって乗用者利用の抑制を図る人流対策及び環状道路等を環境保全に配慮しつつ整備することや交通管制システムの整備、交差点構造の改良等によって交通流の円滑化等を図る交通流対策を講じてきたところである。また、電気自動車等の低公害車の普及促進、最新規制適合車への代替促進等が行われてきている。特に、二酸化窒素の環境基準の達成期限であった昭和60年には、環境庁は「窒素酸化物対策の中期展望」を策定し、これらの諸対策を関係省庁、関係地方公共団体等の協力を得て総合的に推進してきたが、第1章でみたように、61年度、62年度と続けて特に大都市地域を中心にして環境濃度が悪化し、環境基準の非達成局が増加している。
一方、環境庁が昭和63年12月に新たに策定した「窒素酸化物対策の新たな中期展望」によると、総量規制3地域についての平成5年度までの窒素酸化物の排出量の予測結果等から、濃度についてはある程度の改善が期待できるものの、これまでの対策だけでは、特に、自動車排出ガス測定局においては、一部の測定局を除き、環境基準の達成は全体的には困難であると推計されている。
同「中期展望」によると、?自動車、特にディーゼルの普通貨物自動車の走行量が増大し、自動車排出ガス規制による一台ごとの排出ガス量が低減されても、自動車全体としては排出量の削減が進みにくいこと、?これらの地域は、世界的にみても最も過密な地域の一つであり、自動車走行が集中すること、等がその理由として挙げられている。
窒素酸化物について、その発生源別の排出量を窒素酸化物の総量規制を実施している東京都特別区等地域、横浜市等地域、大阪市等地域において推計してみると、自動車からの排出割合は昭和60年度においてそれぞれ67%、32%、47%となっており、大きなウェイトを占めていることがわかる(第2-2-15図)。
(2) 都市交通の実態
ア ますます高まる自動車利用
都市における人や物の移動は、交通機関を利用して行われる。交通機関のなかでも、自動車の占める割合が傾向として高まっている。第2-2-16図にみられるように、主要都市地域で実施されているパーソントリップ調査によると、いずれの都市圏においても、人の移動に利用される自動車の割合は増大していることがわかる。
また、物の移動についても、最新の都市圏物資流動調査(第2回中京都市圏物資流動調査(昭和61年))でみると、10年前と比較して自動車の分担の割合が高まっている(第2-2-17図)。
イ 自動車による貨物輸送の少量多頻度化等
物の移動は自動車の分担する割合が増しているが、自動車が輸送している輸送トン数は経年的にはそれほど増加していない。
昭和51年から61年までの10年間の輸送トン数の年平均伸び率は、1.3%となっている。
一方、トンキロでみると、同じ期間の年平均伸び率は、5.0%であり、輸送の距離が大きく伸びていることがわかる。これは、少量多頻度輸送や輸送距離の長距離化が進んでいることが関係していると考えられる。
例えば、前出の中京都市圏物資流動調査によると、10年前と比べて、貨物自動車の使用台数が1.37倍、運行台数が1.20倍へと伸びているのに対し、1回当たりの平均積み荷重量は0.95倍、平均卸し重量は0.87倍へと減少しており、少量多頻度化の傾向がうかがえる。また、自動車輸送による貨物1トン当たりの平均輸送キロは、昭和40年度22.1km、50年度29.5km、61年度43.5kmと大きく延びてきている。
(3) 自動車交通増大の背景
ア サービス経済化、生活様式の変化等とトラック輸送
こうした貨物輸送の少量多頻度化や長距離化の背景には、産業構造の高度化、サービス経済化、生活様式の変化がある。
全国でこの10年間に、トラック輸送品目のうち鉄鋼、セメント、木材、揮発油等の産業活動の素材等の輸送トンが減少し、野菜・果物、水産品、日用品等の消費者関連の生活物資の輸送トンが増大している。また、宅配便の個数はこの5年間で6倍近くにまで急激に増大し、昭和62年度には7億6,000万個を超えている(第2-2-18図)。
昭和61年度のトラック輸送の品目別に平均輸送キロの長い品目をみると(括弧内は51年度の数字)、取り合わせ品272km(217km)、水産品90km(72km)、日用品89km(65km)等となっており、生活物資の輸送キロが一般的に長い傾向があるとともに、10年前よりもその距離は延びている。
このように、生活物資のトラック輸送は大きく増大し、都市の生活物資は、トラック輸送によってますます遠距離から供給されていることがわかる。
一方、都市内において、消費者サービスの向上、生活様式の変化は、思わぬところで自動車交通を増大させている。
例えば、宅配便は急激に伸びているが、これに伴う都市間の大型トラックや都市内の集配車の運行の増大のほかに、女性の社会進出等に伴う留守宅の増加により、持帰り、再配達回数の増大が生じているとみられている。
また、単身世帯の増大、夜間活動の増大等に伴い、24時間営業のコンビニエンス・ストアーが増加しているが、コンビニエンス・ストアーはほとんど保管施設をもたず、店頭の品数が減るとそのつど配送車が納品する。また、近年、デパート、スーパーの営業時間も延びてきている。
新鮮な食品に対する消費者の要求の強さもある。例えば、賞味期間が6か月のものでも、製造年月日から1か月以上経ったものは売れないから返品になるということが起きている。
こうしたところにも、自動車の多頻度運行の背景がみられ、この傾向は今後ますます高まるものと考えられる。
イ 業務ビル等の整備と自動車交通
都市においては、業務ビル、住宅施設、文化施設等が整備されているが、こうした施設には人や物が出入りし、自動車交通の発生や集中がこれに伴う。また、建設工事中には、廃材、建材、残土等を輸送する必要も生ずる。
総合研究開発機構の行った予測(「東京都都心部におけるオフィススペース需要動向」)によれば、2000年度までの東京都都心3区のオフィス需要は、1985年度に比し、1.3ないし1.6倍になると推計されており、こうした床面積需要の増大に対応して、今後とも自動車交通の増大が予想されるところである。
(4) 都市の自動車交通の密度
サービス経済化・生活様式の変化、業務ビル等の整備の観点から自動車運行の増大の背景を探ったが、次にこれらの活動が顕著である大都市の自動車交通の密度をみてみる。
昭和60年度道路交通センサスによる東京都特別区及び10大市の12時間走行台キロ(高速道路、一般国道及び都道府県)から、1km
2
当たりの12時間走行台キロ(同)をみると、大阪市、東京都特別区において極めて高く、以下名古屋市、横浜市、川崎市等と続く。大阪市、東京都特別区では、全国平均の25〜30倍、広島市や札幌市の10倍程度の密度となっていることがわかる(第2-2-19図)。
また、昭和55年度道路交通センサスと比較すると、全国平均、大都市とも密度は高まっており、横浜市、広島市、福岡市、札幌市等においてその伸びが大きい(第2-2-19図)。
高密度の自動車利用は、都市における自動車の走行速度を低めており、昭和60年度道路交通センサスによる高速道路、一般道路、都道府県道のピーク時旅行速度をみると、東京都特別区及び川崎市17.7km/h、大阪市19.8km/h等と全国平均(35.9km/h)の半分程度となっている。
これまでみてきたように、サービス経済化・生活様式の変化、業務ビル等の整備等都市における自動車の運行を派生させる要因は今後も増大するとみられる。こうした中で、大都市地域において窒素酸化物の排出総量を削減するためには、自動車一台ごとの排出ガス規制の強化に加え、一極集中の是正、交通流の分散・円滑化を図るとともに、物流対策、人流対策による交通量の抑制等の自動車交通対策を強力に推進する必要がある。また、自動車について排出ガスの総量を抑制していく方策の可能性の検討、都心部への自動車乗入れ抑制に係る各種対策について、その効果、実施上の問題点等の検討、さらに、ディーゼル車の利用を抑制する方向に誘導するための経済的政策手段の導入の検討等を新たに行う段階に達していると考えられる。