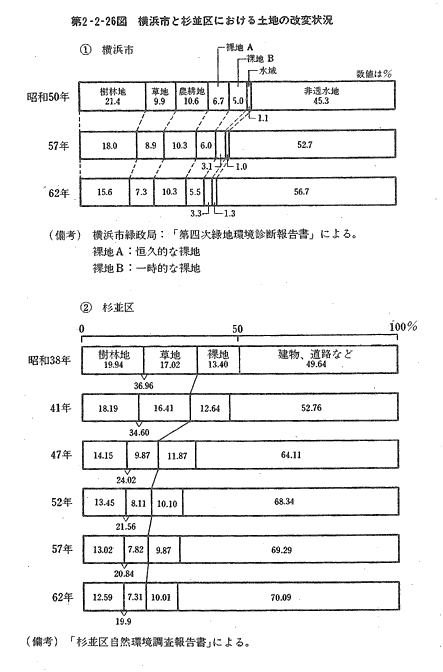
5 都市の緑と生物環境
都市及びその周辺の自然は工業化、都市化の進展に伴い、変ぼうしてきている。以下、その状況をみる。
(1) 都市の自然をめぐる状況
ア 都市周辺の自然の変ぼう
かつて農業を経済社会の基盤としていた我が国においては、河口または臨海部の平野や山に囲まれた盆地を中心として都市が広がっており、周辺の農村部、里山等との間に安定した一種の循環構造を形づくっていた。しかし、急速な工業化の進展と人口の都市集中は都市内の自然はもちろんのこと、周辺部の自然をも大きく変えていった。また、エネルギー革命の進行等による生活様式の変化を背景に、これまで連綿と続けられてきた薪炭材やカヤの採取のような自然利用が衰退し、都市周辺の雑木林や野原は他の用途に転換していった。
イ 土地の改変と緑地の減少
いくつかの都市を例にとって土地の改変状況をみてみると、年を追って樹林地、草地等の緑地が減少し、それにかわってコンクリートやアスファルトなどで覆われた人工の不透水地が増加するという結果になっている(第2-2-26図)。裸地等の透水性の地表面(非舗装地)の減少も著しい。
不透水地の増加はヒートアイランド現象による都市気温の上昇をもたらしたり、都市の水循環に悪影響を与えていることは既に述べたとおりであるが、土壌生物等生きものの生息の面からも好ましくない結果をもたらしている。
次に、緑地の減少をみると、鎮守の森、防風林、民家の屋敷林等が比較的良好な状態で維持され、また、その地域のシンボル、歴史的遺産、ランドマークとして巨樹や巨木林が保存されているところもある。しかし、これらの貴重な森林や樹林も都市化の進展に伴う無秩序な宅地開発やゴルフ場建設等により失われるおそれがある。
ことに大都市地域では、近年の地価高騰と急斜面での建築技術の進展を背景として、これまでかろうじて開発を免れてきた丘陵地帯や傾斜地の雑木林などの樹林地の開発が急速に進みつつある。
市民団体や地方公共団体の中には、例えば埼玉県の「緑のトラスト基金」のように土地を買い取ったり、横浜市のように地主から土地を借り上げて「市民の森」等として一般に開放しているところもあるが、その多くは高騰した地価により土地の取得が困難になったり、相続税負担等の問題に直面している。
また、緑地の量のみならず、緑地の種類、質の問題や分布状況も、都市の自然を考えるうえで重要である。
例えば、東京及びその周辺における植生についてみてみると、都市の中心部では公園、墓地等の緑地以外の自然はほとんど認められず、周辺部をとりまくのは、雑木林(二次林)、植林地、農耕地などであるが、平野部や丘陵部では宅地化等により、それらは散在するような形となっている。また、ある程度の規模の自然林は都市から遠く離れた山地部に残るのみであることがわかる。(第2-2-27図)。
また、自然に対する人為の影響を示す指標となる帰化植物(外来植物)の割合を東京都についてみると、第2-2-28図のようになっており、都市化の進んだ都心部に近いほど帰化率が高くなっている。
ウ 都市内農地等
農地は人間によって厳しく管理され、単純化されており、純粋の自然生態系とはいえないが、作物が耕作されている間は都市に残された数少ない緑のオープンスペースを提供するとともに、地下水をかん養し、さらに水田等にあっては一種の遊水池として都市の水循環の維持にも寄与している。
都市の市街化区域内農地についてみると、昭和57年に20万2,530haであったものが62年には17万7,058haと5年間で約13%減少している。市街化区域内の農地のうち、一定の要件に該当するものについては、「生産緑地法」に基づく「生産緑地地区」として指定され計画的な保全が図られ、62年末現在、全国で約702haが指定されている。
大都市においては、地方公共団体が農家などから土地を借りてそれを市民農園として一般に開放したり、子供広場や公園として活用しているところも多い。昭和60年に総理府が行った「食糧及び農業、農村に関する世論調査」によると、非農家の約6割の人が家庭菜園(貸農園を含む)に関心をもっており、都市内農地のレクリエーションや子供の教育の場としての価値は高くなっている。
エ 都市の生きもの
都市化の進行に伴って、身近な生きものの分布に変化が生じている。
樹林地、草地、水辺などの環境を必要とする身近な生きものの分布域の多くが後退していく一方で、人工的な環境にも強い生物はそのまま生き残り、あるいは勢力を拡大し、その結果として生物相の単純化が生じている。
第2-2-29図は、環境庁の第3回自然環境保全基礎調査(「緑の国税調査」)の一環として行われた身近な生きもの調査の結果から作成したものであるが、都心部では、大面積の緑地を除くと身近な生きものの多くが、ほとんどみられなくなっており、また、第2-2-27図と比較すると、多摩丘陵や狭山丘陵などのように雑木林や農耕地等からなる地域が、豊かでまとまりのある身近な生きものの生息地となっており、これらの地域が都市住民の自然とのふれあいの場所としても重要であることがわかる。
また、底生生物、魚類、鳥類などが数多く生息して豊かな生物相を形成している干潟の喪失も問題である。東京湾では、昭和40年から62年までの23年間に、埋立てによって約1万7,200haの干潟、水面が失われている。これは、明治初期以来昭和40年までに行われた埋立ての約2.5倍の面積に相当する。
また、河岸の人工化や瀬と淵の消失等が進んだことにより、河川の魚類が貧弱化してきている。多摩川はかつては「鮎の川」といわれたほど、多数のアユやサクラマスの遡上が見られたが、現在では、横断工作物ができたこと等により、天然のアユの遡上は減少し、サクラマスの遡上は見ることができない。
(2) 都市の緑の多様な価値
緑には多種多様の機能があり、しかも、ひとつの緑によって同時にいくつもの効用を得ることができるという特質を有する(第2-2-30図)。
ここでは、特に都市における緑の効用についてみていくこととする。
ア 大気浄化
樹木には、呼吸や付着によって大気汚染物質であるNO2、SO2等を浄化する能力がある。大阪府の行った調査によると、樹木の浄化能力を樹種別にみると第2-2-31表のようになり、例えば、胸高直径15cmのイチョウ(約5kgの葉量生産)では一日当たりSO2を212mg、NO2を846mg吸収することができる。自動車交通量が6万5,000台/日、NO2濃度0.032ppm(8月平均)である大阪府の御堂筋の延長3kmのイチョウ並木について、そのNO2の吸収量を計算してみると自動車からのNOx排出量の4.5%となる。
イ 地下水のかん養、土壌の保水力
都市における不透水地の増加による様々な悪影響については既に述べたが、緑地の持つ雨水の浸透能力は極めて大きなものがあり、都市の健全な水循環の維持に役立っている。
ウ 気候緩和
既に本節1,2でみたように緑地の多いところでは気温の較差が少ない。樹木は水分の蒸発散作用を盛んに行って多量の気化熱を消費し、気温が高温になることを防いでいる。また、樹木の蒸散作用は空気中に絶えず水分を供給し、湿度を高め、乾燥化を防いでいる。木陰による直射日光を遮る効果や、人々に快適感を与えるものも重要な働きである。
エ 騒音軽減
樹木は、音の広がりを遮ることによって騒音を低減させる効果を有する。また、森林によって騒音源が覆い隠され見えなくなること、樹木の風にそよぐ音等による心理的な効果も大きい。
オ 生物生息
野鳥やリス、セミ、トンボなど身近な小動物の存在は、人々の生活にうるおいややすらぎを与えてくれる。一方、地中の土壌生物は、動植物の遺体等を分解するなどして、土地を肥沃なものとし、植物の生育に必要な栄養分を供給するなど極めて重要な働きをしている。
カ 土壌保全と防災
裸地に比べると樹木等の植生の覆われた緑地は、土壌保全にも大きな役割を果たしている。特に、森林の土壌浸食防止能力は大きい。これは、樹木が地表面を雨などから保護するとともに、雨水を地下に浸透させて地表面の流出水を減少させるからである。そのほかにも、樹木は難着火性、輻射熱の遮断、飛び火捕捉等多くの防火能力を有している。
キ アメニティ
木々の緑に代表される樹木や緑地が人々にうるおいとやすらぎを与えることは改めて言うまでもない。昭和63年に総理府が行った「まちづくりと水辺空間整備に関する世論調査」によると、快適な生活環境づくりに重要な要素として「豊かな緑」を挙げた例が一番多い(第2-2-32図)。そのほか、都市住民が自然とのふれあいを求める場あるいは豊かな自然の中でスポーツやレクリエーションを楽しむ国民の余暇指向を満たす場としても、緑地の保全・創出は重要である。
なお、都市内に残された貴重な自然として鎮守の森に代表されるような社寺林の価値が高まっている。それは、鎮守の森が宗教的な理由により古くから伐採や立ち入りなどが制限され、自然のままの緑を残しているからである。そこでは、自然植生が保たれた結果として、豊かな生物相を形成している。また、鎮守の森に巨木が多いこともその価値を高めている。巨木は景観的にも優れており、やすらぎ感も大きい。さらに、こうした風格のある樹木は都市のシンボルともなる。また、社寺林などにおける巨木とともに丘陵地や崖地などの傾斜地に残る斜面林が景観的な面等から果たす役割も大きい。
また、緑を支える土とのふれあいも人々にうるおいとやすらぎを与える。環境庁が環境モニターを対象として行ったアンケート結果によると、住環境のまわりに土がたくさんあったほうがよいとする理由として、緑が多くなることと並んで、自然の遊び場が多くなる、子供と土のふれあいが大切ということが挙げられている。
これまでみてきたように、都市の緑は多様な価値をもつものである。
住民の緑に対する欲求や満足度の観点から、都市にどのくらいの緑があるのが望ましいのかということについては、いつくかの調査から30ないし40%の緑被率が望ましいという結果がでており、都市において緑とオープンスペースの総合的な整備のあり方を示した「緑のマスタープラン」(昭和51年都市計画中央審議会答申)も、確保すべき緑地の量を市街化区域面積の30%以上としている。都市緑化の推進状況についてみると、公共施設については、第3次都市緑化のための植樹等5か年計画に基づき、昭和62年〜平成3年の間に高木1,300万本を植栽し、61年度末現在の約3割増とすることを目標に緑化が進められている。
また、都市公園の面積については、長期的な目標としての都市公園の整備水準を20?/人とし、西暦2000年までに、この半分の10?/人を確保することとしている。しかし、我が国の現状をみると1人当たりの都市公園面積は5.1?(昭和61年度末現在)で、諸外国と比べてはるかに低い水準にあり、引き続き整備を進めていくことが必要である。
今後、こうした緑地の整備とともに、身近な生きものも豊富にみられ、自然とのふれあいの場としても重要な雑木林、鎮守の森、斜面などに残された自然林等の保全と活用を図っていかねばならない。