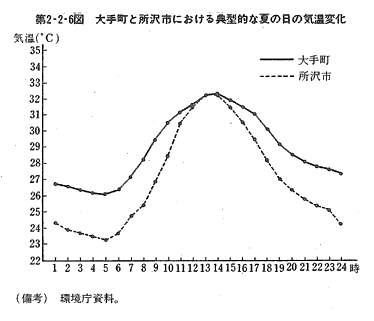
2 都市のエネルギー代謝
都市においては、主に他の地域でつくられたエネルギーが、高い密度で消費されている。一般的に、原油、石炭等の一次エネルギーを電気、ガソリン等の二次エネルギーに転換する際や二次エネルギーを最終消費段階で消費する際に、熱や汚染物質を排出する。汚染物質の排出は各種の環境汚染問題を、熱の排出は微気候等に変化をもたらす。
(1) 都市のエネルギー消費等と都市の環境
東京都全域における1?当たりのエネルギー消費量は、昭和62年度において263.1kcal/日であり、全国平均の13倍となっている。
このような高密度のエネルギー消費や地表面の改変等により、都市の気候にはいくつかの特徴がみられる。
まず、都心部と郊外部では気温の差がみられる。ヒートアイランド現象である。例えば、昭和58年から62年の間で典型的な夏の日を抽出し、東京大手町と埼玉県所沢市の気温の日変化をみると(第2-2-6図)、最高気温はほぼ同程度であるが、そのほかの時間は所沢が低く、最低気温では、約3℃の差がみられる。
また、1880年代からの東京における真夏日(最高気温が30℃を超える日)と熱帯夜(最低気温が30℃を超える日)の日数の経年変化をみると(第2-2-7図)、真夏日の日数は緩やかに増加しているが、熱帯夜の日数は大正末期から昭和の初めを境として急激に増加していることがわかる。
さらに、東京の1月の平均湿度をみると、昭和20年代までは60%程度で推移していたが、その後急激に低下し50%を割る年が多くなっている(第2-2-8図)。
ここで、緑地率、エネルギー消費に伴う人工熱の量、舗装面の状態が都市の気温に与える影響を推測してみる。
? 緑地率の影響
東京都区部の緑地(田畑、草地、平地林)割合は昭和62年度において5.6%であり、この割合を高めた場合(30%、50%の2ケース、いずれにも緑地の増加分だけ屋根が減少すると仮定)の東京都心部の気温を推計すると、日中から夜間にかけての気温が、最高でそれぞれ0.7℃、2℃程度現状より下がる(第2-2-9図)。
? 人工熱の影響
人工熱を削減した場合(1/2、ゼロの2ケース)には、夜中から夜明けにかけての気温が、最高でそれぞれ1℃、2℃程度現状より下がる(第2-2-10図)。エネルギー消費に伴う人工熱は、都市において夜中から夜明けにかけての気温を高めていることがわかり、これが熱帯夜の主な要因であると考えられる。
? 舗装面の影響
舗装面からの水の蒸発効率を高めた場合(10%、30%の2ケース)には、日中の気温が、最高でそれぞれ0.5℃、1℃程度現状より下がる(第2-2-11図)。
また、エネルギーの利用は、環境への負荷を伴う場合が多い。
東京都における化石エネルギーの消費に伴う二酸化炭素の排出量は、昭和62年度において約28,780千t/年であり、東京都特別区等地域における窒素酸化物の排出は、60年度において52.7千t/年である。第1章でみたように、二酸化窒素による環境汚染は、50年代は横ばいで推移していたものが、61年度に悪化し、62年度はさらに悪化した。特に、大都市及びその周辺地域において悪化の傾向が著しい(第2-2-12図)。
(2) 都市のエネルギー消費の現状
我が国では、昭和62年度において原油換算308百万klの商業エネルギーを消費している。
我が国のエネルギーフローをみると昭和62年度において、最終消費段階で消費される量は、一次エネルギー総供給量の67.4%である。これは、エネルギー転換部門等でのロスがあるためである。最終消費段階でのエネルギー効率も、例えば、自動車では20〜30%程度であり、本来の目的に利用されるエネルギー量の一次エネルギー供給量に対する比率はさらに低いものとなる。
都市のエネルギー消費を東京都の例でみると、第2-2-13図のとおりであり、次のような点が指摘できる。
? 昭和62年度の総エネルギー消費量は、50年度からみると年率0.2%で増加しており、この5年間では年率2.4%の増加となっている。
? 用途別のエネルギー消費(昭和62年度)をみると、全国では産業が50.2%と大きな割合を占めるのに比し、東京都では24.3%と低い。運輸が28.8%と高く、業務23.7%、家庭23.3%と続く。
また、用途別のエネルギー消費量の昭和50年度から62年度までの伸び率をみると、産業がマイナス5.0%であり、業務4.8%、家庭2.2%、交通2.4%となっている。
? エネルギー種類別の消費の割合は、石油57.0%、電力21.9%、都市ガス13.7%、LPG7.4%となっている。昭和50年度からの伸び率でみると、石油は、マイナス1.8%であるが、石油のうち軽油5.2%、ガソリン2.0%となっており、自動車、特にディーゼル自動車の運行が相当増大していることがわかる。自動車は、他の交通機関に比べてエネルギー効率が低い(第2-2-14図)。また、同じ自動車のなかでも。営業用が自家用よりもエネルギー効率が高くなっているが、これは、営業用の方が輸送効率が高いことによる。
(3) 都市のエネルギー資源
都市においては、高密度のエネルギー利用が行われているが、都市のなかには、最終消費段階でのエネルギーの利用の結果排出される排熱等様々な都市活動に伴うエネルギーが賦存する。総合研究開発機構(NIRA)の試算によると、東京23区の下水処理場、ごみ焼却場、地下鉄、地下送電ケーブル等からの排熱は、年間原油換算1,900万klであり、東京23区の集合住宅及び一般建物の暖房・給油熱需要の83%に相当し、このうち、地域供給の可能性がある量は熱需要の50%程度であるとしている。
また、都市においても、太陽エネルギー等の自然エネルギーが賦存する。例えば、太陽エネルギーは東京では2,950kcal/?・日であり、商業エネルギー消費の現状の密度の10倍程度に匹敵する。
都市におけるエネルギー消費は、交通、業務、家庭における伸びが高く、これらの分野におけるエネルギー利用の効率化を一層推進することが重要である。併せて、エネルギー転換部門におけるエネルギー利用効率を高めること等によりエネルギーロスを低減するとともに、未利用の排熱等を利用することにより全体でみたエネルギーの効率的な利用を図り、環境への負荷の少ない健全な都市のエネルギー代謝システムを形成する必要がある。