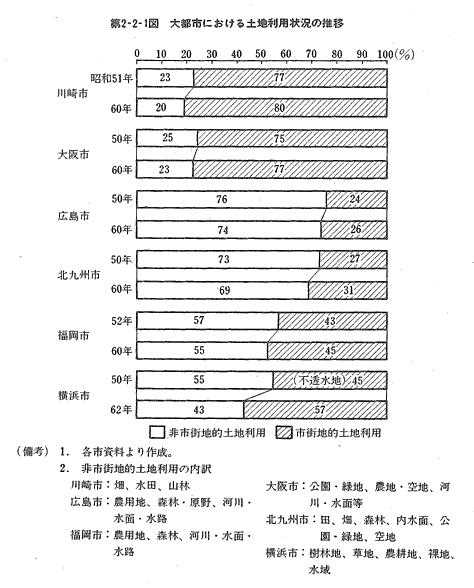
1 都市の水循環と水質汚濁
都市においては、諸活動の集中、高密度化等により、自然の生態系にみられる水の循環が損なわれ、河川等の水質汚濁も著しい。水は、都市の中において諸活動を支える基本的要素であるのみならず、存在そのものが都市気候等都市の環境に安定性をもたらす。
(1) 水循環の変化とその影響
ア 不透水地の拡大等
都市化が進んだことによる最大の変化の一つは、市街地が拡大し、農地、山林、草地などの土地がコンクリートのビル・住宅地やアスファルトの道路などに変えられていったことである。第2-2-1図は、いくつかの大都市における土地利用状況の推移を表すものであるが、ここ10年間でみても各都市において森林、農地等が減少していることがわかる。横浜市においては、特に土地の透水性という観点から土地利用状況の推移をみたものであるが、最近の12年間で樹林地などの透水地が減少し、不透水地の割合が45.3%から56.7%へと大きく増加している。このような不透水地の拡大に加え、都市では浸水の防除を行うことを目的の一つとして下水道の整備が進められ、雨水は速やかに都市より排除されるようになった。
イ 地下水収支の変化
一方、都市においては上下水道、地下鉄等による地下空間の利用が進んでいるが、これらは地下水収支に大きな影響を及ぼしている。例えば、東京都が昭和56年に発表した調査によると、52年時で一日25万m
3
の地下水が管の継手等から下水管へ浸入しており、この量はその後の下水道管渠の延長により62年には一日39万m
3
にのぼると推計された。また、地下鉄、洞道等へは一日2万m
3
以上の地下水が浸出し、排水ポンプで下水道等へと排出されている。さらに、地下街の開発、地下鉄建設のための掘削工事により、大量に地下水が流出、排除され一年で26cmを超える地盤の沈下が記録された事例も報告されている。逆に、水道管からは大量の水が地下へと漏出しており、東京都においては昭和62年時で56万m
3
/日にのぼると推計された。
このように、都市における水循環は様々な人間活動により変化しており、東京都においては昭和52年から62年までの10年間で雨水のうち地表面や排水路を通して海へ排出される量が6%程度増加する一方で、地下へ浸透する量は6%弱減少し、地表面から蒸発したり植物から蒸散する蒸発散量も4%程度減少すると推計された。
ウ 都市気候への影響
こうした、都市における水循環の変化は、都市気候に影響を与える。
都市に存在する水はその気候を和らげる。すなわち、水は大地に比べ温まり方、冷め方が遅いため、温度を安定させる要因として重要な働きをする。また、水分の蒸発は地表面からの熱放出に少なからず寄与し、都市気温の上昇を防いでいる。ところが、緑地の減少、地表面のアスファルト等による被覆、地中への地下水補給量の減少等は、地表面及び樹木等からの水の蒸発散量を減らし、真夏の都市中心部の気温を高める原因の一つとなっている。(都市のヒートアイランド現象については、「2 都市のエネルギー代謝」を参照。)
エ 湧水の枯渇、河川水量の減少
また、雨水の地下浸透量の減少は、都市における湧水の枯渇、都市内河川に平常時流量の減少をもたらす。例えば、東京都における調査によれば神田川の沿岸にはかつては水源の井の頭池など多くの湧水があり、河川水量も2〜3万m
3
/日あったが、現在ではまとまった湧水は2か所のみとなり河川流量への寄与も小さくなっている。また、目黒川の沿岸においては30地点以上あった湧水が現在では半数に減り、新河岸川の沿岸でもかつては多くの湧水があったが、名主滝湧水が停止し現在の湧水は限られているなど、多くの都市内中小河川の流域において都市化の進行により湧水が枯渇し、河川の固有流量を減少させていることが報告されている。
オ 水需要の増大
都市における雨水の地下浸透、保有量が減少していく一方で、地下水は良質・恒温で容易かつ安価に取得できる水資源として工業用、ビル用水用等に使用され、さく井技術の進歩等に伴い大量に採取されるようになった。このため、都市域を中心として地盤沈下が起こり、建造物等に被害を生じさせるとともに、水害による被害を拡大させる要因となった。そこで東京、大阪、名古屋など都市域では地下水採取の規制が行われ、現在では工業用等の地下水揚水量は減少している。
都市化に伴う水需要の増大に対しては、上流域でのダム開発等が進められている。
(2) 都市化と水質汚濁の進行
ア 都市河川等の水質の現状
都市内の河川等には、急速な都市人口の増加と産業の飛躍的な発展に伴って大量の汚水が不十分な処理のまま放流されたため、悪臭を発するなど深刻な水質汚濁を招いた。その後、排水規制の実施等によりかなり改善がなされたが、第1章でもみたように特に大都市圏の中小河川においては、依然として著しい汚染が続いている。
こうした状況を、一級河川における水質調査において8年連続ワースト1にあげられている綾瀬川についてみると(第2-2-2図)、急激な人口増加等都市化の進展に伴って水質が著しく悪化し生物の生息を不可能とするまでに汚濁が進んだこと、そして水質汚濁防止法が施行された昭和40年代後半以降、排水規制の強化等により水質の改善が図られてきたことがうかがわれる。しかし、その後は排水規制を強化・徹底し、53年からは東京湾についての水質総量規制制度が導入され、これに基づき総量規制基準の設定、下水道の整備、小規模排水対策等の諸施策を推進してきたにもかかわらず、全体として改善が進んでおらず、環境基準の達成には程遠い状況にある。
また、湖沼についてみても手賀沼、印旛沼など流域の都市化が進んでいる湖沼では、下水道の整備等の対策が追いつかず、著しい汚濁が続いている。
水質の汚濁は上水道の水源においても進んでいる。第2-2-3図は東京都の総配水量の4分の1近くを占める金町浄水場における原水の水質の状況をみたものであるが、近年は悪化の傾向がみられており、水道水の異臭味等の原因となっている。
イ 生活排水の大量流入
都市における水質汚濁の最大の要因は、流域への人口集中とそれに起因する生活排水の大量流入である。
例えば、首都圏の代表的な都市河川のうちで汚濁の著しい不老川(埼玉県)、空堀川(東京都)、春木川(千葉県)について最近の水質及び発生源別の負荷割合をみると第2-2-4図のとおりであり、いずれも生活系の割合が非常に高い。また、汚濁の著しい湖沼、海底についてみても、汚濁負荷量全体に占める生活系の割合は手賀沼で77%、印旛沼で63%、東京湾で70%など、生活排水が汚濁の主因となっている。
また、前述の綾瀬川についてみても、この10年で4分の1程度発生負荷量を削減したもののなお全体の36%を占める産業系の負荷とともに、生活系の負荷、特に生活雑排水が大きなウェイトを占めている。ことに綾瀬川については、流域人口の伸びに下水道の整備が追いつかない(流域の埼玉県の主要都市の下水道普及率をみると、現在においても1割程度と非常に低い。)ことなどにより、10年前に比べ生活系の発生負荷量はなお増加しており、発生負荷量全体に占める割合も55%から63%へと上昇している。
ウ 生活様式等の変化
これら生活系の負荷の増大の背景には、なお都市化の進展により人口集中が進んでいることとともに、風呂を持つ家庭が増えたこと、電気洗濯機を持つ家庭が増えたこと、洗剤の使用量が増えていること、台所での食用油の使用量が増えていることなど生活様式の変化が指摘される。また、人々の外食頻度が増加し、都市部を中心にレストラン等の数が増えているが、それに伴って飲食店業からの排水量も大きくなっている。
エ 自浄能力を失った都市河川
また、都市内河川の水質汚濁の背景には、(1)でみたような河川の固有流量をなす湧水の枯渇・減少も大きく影響している。東京都内をみても白子川、柳瀬川、仙川など、かつては清らかな水を流していた川が固有流量の減少により、生活排水がそのまま流されるいわゆるドブ川へと変わっていっている。また、水質測定結果における汚濁の著しい河川についても、その原因として生活排水対策の遅れとともに流量の少ないことが共通して挙げられる。流量の少ない河川に生活排水等から有機物が過剰に排出されると、大型生物の生息は困難になり微生物類のみが増殖し、捕食が追いつかなくなる。
さらに、河川のコンクリート水路への改修は微生物等による自浄機能を減退させた。すなわち、河川等に汚水が流入した場合、その水質は一時的には悪化するが、河川等を流下するうちに、細菌類、原生動物や微小動物などによる自浄作用により、汚水の流入にする以前の状態にまで回復する。浅瀬の河床では接触酸化作用による水質浄化が行われ、淵において浮遊物質の沈殿及び沈殿物中の有機物の消化分解による浄化が行われるのであるが、こうした浄化作用はコンクリート張りの水路では起こりにくいとされている。
(3) 地下水の汚染
地下水は、恒温かつ水質が良好であるとされ、飲み水を含む生活用水はもちろん、工業用水、農業用水として広く用いられているほか、建築物用水(ビル用水)としても使われている。これを全国の水使用量全体に占める割合でみると約7分の1であり、都市用水(生活用水と工業用水)に限ってみると約3割を占める。
ところが、昭和50年代後半より、地下水がトリクロロエチレン等の有機塩素系溶剤によって汚染されていることが顕在化してきた。57年度に環境庁が全国の15の都市で地下水の汚染実態調査を実施したところ、トリクロロエチレンとテトラクロロエチレンについて、調査した井戸の3割近くで検出され、そのうちそれぞれ約3%、4%の井戸ではWHOが定めている飲料水の暫定水質ガイドライン値を超える濃度で検出された。また、その後の調査の結果からも、地下水の汚染が各地でみられていることが確認されている。
汚染物質のうちトリクロロエチレンは主として金属部品の脱脂洗浄剤として使用され、テトラクロロエチレンはドライクリーニング用洗浄剤のほか金属の脱脂洗浄剤、フロン系溶剤の原料として使用されているが、ともに不燃性で脱脂力が大きく、回収も容易なことから現在でも多くの事業場で使われている。
(4) 水循環の変化と水辺
都市の河川の中には、水量が減少し、降雨時においては雨水をできるだけ早く海へ排出するとともに、平常時においては固有の流量を失い下水を流すだけのものとなり、かつてせい息していた魚等も見られなくなったものである。
また、都市化及び都市的生活様式の拡大により、身近な河川で洗濯をするなどの光景はほとんど見られなくなり、都市内の水面は無用のスペース、子供たちにとって危険なところ、衛生上好ましくないものとみなされるようになった。そのため、汚濁の進んだ中小河川を中心に、埋立てないしは暗渠化が進み、道路などへと変わっていくものが多くあった。例えば、大阪市についてこれをみると、この20年間で河川・水面の面積が2割程度減少している。また、第2-2-5図は、とりわけ東京の都区部において水域の減少が著しく進んでいることを表している。
こうした河川の姿の変ぼうは、人々の水辺とのふれあいを失わせた。川崎市内を流れる二ヶ領用水及び平瀬川流域に在住する市民(世帯主)を対象にしたアンケート調査によれば、昭和19年以前からの居住者では90%近くが子供の頃川で遊んだ経験を持っているのに対し、40年以降の居住者で川で遊んだ経験を持っているものは6人に1人程度であり、子供たちが直接に水と親しむ機会が失われていったことがうかがわれる。
また、東京都内の中小河川の一つである石神井川について行われた調査によれば、切り立ったコンクリート護岸とフェンスに遮られ全体の46%の川岸からは川の水を見ることさえできない状況である。
こうした状況に対して、都市内にも豊かで清らかな水環境を回復するためには、個々の家庭も含めた汚濁負荷の発生源において排出抑制対策を徹底するとともに、雨水の地下浸透を促進し、地下水、湧水等都市に残された貴重な水源、水域の保全を図り、あるいは雨水、下水処理水等の有効利用を進めることにより、都市の水循環を再生していくことが必要である。