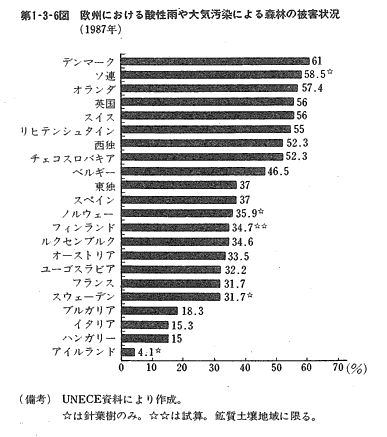
3 国境を越える環境問題の動向
(1) 酸性雨
酸性雨は、化石燃料の燃焼によって発生する硫黄酸化物、窒素酸化物が原因となって生じると考えられているが、発生源から数千キロも離れたところに降下することがあり、欧州や北米では国境を越えた問題となっている。酸性雨は、森林や農作物に直接的に、あるいは土壌の変化を通じて間接的に被害を与えたり、湖沼や河川を酸性化させ魚類の減少をもたらす等生態系に影響を与えるとともに、建物や文化財へも被害を及ぼしており大きな社会問題、国際問題になっている。
こうした中で1988年11月に「越境大気汚染に関するソフィア会合」が開かれ、窒素酸化物の排出量を1994年時点で1987年レベルに凍結することなどを内容とする「長距離越境大気汚染条約」の新しい議定書に25か国が署名した。会議では欧州や北米における大気汚染による河川、湖沼や森林の被害状況についての報告がなされた。そのうち森林の被害状況については第1-3-6図のとおりである。
(2) 有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物の越境移動は欧州等においてかねてより問題とされてきたが、近年はむしろ欧州からアフリカ・中南米諸国への有害廃棄物の輸出として大きな問題となっている。1988年6月に発覚したナイジェリアでのココ事件はその代表例である。これは、1987年8月から1988年5月まで、3,884tにのぼる有害廃棄物が化学品の名目で、イタリアからナイジェリアのココ港に搬入され、近くの船荷置場に野積みにされたものである。ナイジェリア政府は、現場を封鎖し、関係国際機関や友好国の協力を得て現地の調査を行う(日本からも2次にわたり調査団が派遣された。)とともに、イタリア政府に投棄有害廃棄物の撤去等を要請した。その後、撤去された廃棄物は船に積まれイタリアに向かったがイタリアの各港をはじめ、フランス、スペイン、英国、オランダ等でも入港を拒否され、長い間、地中海及び大西洋をさまよった。こうした問題に対し、アフリカ諸国はアフリカ統一機構(OAU)等の場で早急な対策を求めてきた。
こうした動きの結果、1989年3月、スイスのバーゼルで開催されたUNEP外交会議において、有害廃棄物は発生した国で処分されることを原則とすること、本条約に定められる手続により輸入国、通過国の同意が得られた場合にのみ越境移動が許可されること等を定めた有害廃棄物の越境移動及び処分の管理に関するバーゼル条約(仮称)が採択された。
(3) 地域海の汚染
世界有数の工業地帯に囲まれた北海では、これまでも各種の重金属、化学物質、油等が流入し、生態系への影響が懸念されていたが、1988年6月頃より魚やアザラシが原因不明死を始め、最終的には北海に生息するアザラシの3分の1にあたる1万5千頭が死滅した。沿岸各国では、この背景には北海の汚染があるとみて北海における廃棄物の洋上焼却の全面禁止等、水質浄化に向けての規制強化の動きが活発化している。
また、米国では、1988年夏には北東海岸で医療系廃棄物の漂着と有機性汚濁によって海水浴場が閉鎖される事件が発生した。このため、医療系廃棄物及び下水汚泥の海洋投棄の禁止等の措置がとられた。