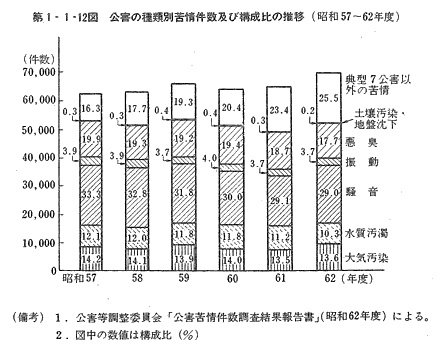
3 騒音
騒音は日常生活に関係の深い問題であり、発生源も多種多様であるため、例年、地方公共団体に寄せられる苦情件数は各種公害の中で最も多く、昭和62年度では全体の29.0%を占めている(第1-1-12図)。
騒音の発生源の種類ごとの苦情件数は、工場・事業場によるもの、建設作業によるものが多い。また、深夜営業店からのカラオケの音、家庭からのピアノ、クーラーの音などのいわゆる近隣騒音に関する苦情の件数は、昨年より増加しており、騒音苦情全体に占める割合は37.4%を占めている(第1-1-13図)。
一方、一部の交通施設周辺においては、自動車、航空機、新幹線鉄道等の運行に伴って発生する騒音が交通公害問題の大きな要素となっている。
このうち、自動車騒音についてみると、都道府県等が当該地域の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点で昭和62年中に測定した自動車交通騒音の結果では、4,298測定点のうち、朝、昼、夕、夜の4つの時間帯のいずれにおいても環境基準を達成している地点は14.4%(617地点)と低い。また、58年から5年間継続して同一地点で測定している測定点における環境基準の達成状況をみると、4時間帯のすべてで基準を超過している地点が過半数を占め、前年度よりやや悪化しており、要請限度(騒音規制法第17条第1項の限度)の超過状況においても、改善がみられない状況にある(第1-1-14図)。
新幹線騒音については、東海道・山陽新幹線においては昭和60年7月に、東北・上越新幹線(大宮以北)においては、それぞれ62年6月及び11月に環境基準の達成目標期間が経過している。騒音の状況は、対策実施によりかなりの改善が認められるものの、未達成の地域も相当みられるため、引き続き環境基準の達成に向けて努力が必要な状況にある。
航空機騒音については、昭和58年12月末に環境基準の達成期限又は10年改善目標の達成期限が到来している。主要な空港については大幅に改善されてきているが、すべての地点で環境基準を達成している空港は少ないことから、なお引き続き環境基準の達成のための努力が必要な状況にある。