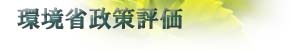1.日時: 平成20年6月18日(水)10:00~12:15
2.場所: 環境省第1会議室
3.出席者
|
-委員- |
(委員長) | 須藤 隆一 | 埼玉県環境科学国際センター総長 |
| 井村 秀文 | 名古屋大学大学院環境学研究科教授 |
| 大塚 直 | 早稲田大学法学部教授 |
| 河野 正男 | 中央大学経済学部教授 |
| 崎田 裕子 | ジャーナリスト・環境カウンセラー |
| 堤 惠美子 | 株式会社タケエイ 取締役 |
| 藤井 絢子 | 滋賀県環境生活協同組合理事長 |
| 細田 衛士 | 慶應義塾大学経済学部教授 |
| 三橋 規宏 | 千葉商科大学政策情報学部教授 |
| 鷲谷いづみ | 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 |
| | | |
| [欠席] | |
| 山本 良一 | 東京大学生産技術研究所教授 |
|
-事務局(大臣官房)-
|
小林大臣官房長、鷺坂大臣官房審議官、小林大臣官房審議官(秘書課長)、
三好総務課長、阿部会計課長、清水政策評価広報課長、他 |
|
-環境省各局部-
|
紀村企画課長(廃棄物・リサイクル対策部)、角倉総務課長補佐(総合環境政策局)、
森本企画課長(環境保健部)、梶原総務課長(地球環境局)、
岡部総務課長(水・大気環境局)、奥主総務課長(自然環境局) |
4.議題:
(1)平成19年度環境省政策評価書(事後評価)(案)について
(2)その他
|
5.議事録要旨 |
〔議事録要旨〕 |
|
|
|
(各委員紹介)
(大臣官房長挨拶)
(須藤委員長選任)
(事務局より資料説明)
【須藤委員長】
委員の先生方にご意見を伺うが、大塚先生、井村先生の順でお伺いしたい。
【大塚委員】
まだ完全に意見はまとまっていないが、2点お伺いしたい。
1つは、P.35にある目標6-2環境リスクの管理の「①既存化学物質及び既審査新規化学物質について、生態毒性試験を実施する数」の目標について、生態毒性試験が終わると既存化学物質の審査がどの程度終わったことになるのか。
既存化学物質の審査がなかなか進まないことは昔からあるが、生態毒性試験が終わったことにどの程度の意味があるのかをお伺いしたい。
もう1点は、P.16にあるように、リサイクルに関する指標の多くが達成されていて大変よいと思うが、例えば家電リサイクルについて、現在使用している「再商品化率」だけを指標としていてよいのか、指標について検討する必要がさらにあるのではないかという点である。
具体的には、資源有効利用促進法との関係で、再商品化率だけではなく、新商品に再生部品をどれだけ使用しているかという議論も必要ではないか。
指標として以上の2つのもの(環境リスク管理について生態毒性試験を実施する数、家電リサイクルについて再商品化率)がそれだけで適当かということをお伺いしたい。
評価書全体として分かりやすくなり、読みやすくなったと思う。
【井村委員】
全体的に数年前と比べて読みやすくなり、分かりやすくなっている。地球温暖化対策などについては、環境白書よりも全体像が分かりやすい部分もあると思う。
P.6であるが、平成19年度における地球温暖化対策予算のうち、「6%削減約束の達成に直接の効果のあるもの」が5,093億円、うち環境省予算が304億円とある。「直接の効果のあるもの」の意味を教えて欲しい。
P.15の循環型社会については、循環型社会の今後の展開として、「低炭素社会や、生物多様性の保全に配慮した自然共生社会に向けた取組と統合的に展開する」との記述がある。
循環型社会を統合的に展開するという発想は大事なものであると思う。一方で、低炭素社会に例示しているものが廃棄物発電のみで、いまだ廃棄物処理の考え方から抜け出ていない感がある。
循環型社会と低炭素社会、生物多様性などとの統合的な関係性をさらに重視し、もう少し内容的に改善されてはいかがかという感じを持った。
P.24の浄化槽の整備によるし尿及び雑排水の適正な処理がリサイクルのところに入っている。水との関係も深いので、組織上は仕方ないと思うが、少し違和感がある。
環境政策の基盤整備については、全体的にインパクトのある内容が見当たらないのかなという印象を持った。指標としては作りにくい分野なので、インターネットのアクセス件数などの指標しかまだ書けていない。
基盤のところなので仕方ないかなとは思うのだが。
化学物質については、中国や途上国における化学物質問題、農薬などの問題等々、国際的な問題がどこで取り上げられているのか知りたい。
【須藤委員長】
井村委員が指摘した「低炭素社会を目指して」のような課題は、各課でまとめるとその担当部分だけでまとめてしまう。
例えば、地球温暖化とのつながり、自然共生とのつながりというのが出てこなくなるので、相互関連している部分で、環境省全体の評価をやらなくてはいけないのだろう。
【河野委員】
感想が2つある。
1つは、地球温暖化については、各省にまたがった政府全体の対策の結果が指標に表れている。
書き方が難しいが、希望としては、政府全体としての立場で、他省の政策にも踏み込んだ記述をしていただけるとありがたい。
P.6の効率性のところで、全体の予算が5,093億円で、環境省はこのうち304億円という書き方になっているが、このような書き方をしてもらえると、環境省の分担がわかるのかもしれない。
P.21浄化槽については、確かに記載する場所がおかしいと思う。目標の普及率11%はかなり低いと感じる。公共下水道などとも関連しているとは思うが、どうしてこのように低い目標になっているのかを質問したい。
P.51環境情報の整備について、ホームページ上に外国語のページを設置し成果が得られた、としているが、これは環境省の情報だけで実施しているのか。
他省庁も含めて集めた情報として発信することにより、諸外国から見れば、環境省というよりも、日本の情報という形で理解されるのではないか。
【崎田委員】
全体的に分かりやすくまとまっているのに加え、目標が達成できそうもないというようなネガティブ情報も分かりやすく記載されているのはよいと思う。
全体的なところで言うと、これだけ環境分野が大事だと言いながら、予算について、特に循環型社会と化学物質について、前年より予算額が下がっているようである。
できれば環境省全体の予算をもっと増やしてほしいが、今この大事な時期を乗り切れるような予算を是非確保してほしいと思う。
「福田ビジョン」など、国としての動きは素晴らしく、こうした急速な動きに対応して、地域が変化していく加速度を上げていくことが必要である。
そのためには国の動きを自治体、地域社会へうまく活かす施策が必要と考える。
例えば、P.5の地球温暖化対策のところで、一酸化二窒素については、目標値に比べて削減が十分に進んでいないのは、自治体の下水処理施設で下水汚泥の一酸化二窒素の高度焼却が進んでいないということだと思う。
国土交通省の温暖化対策の中でも一番実現が難しいというのがこのポイントであった。このあたりも強調しながら、地域の温暖化対策を進めていって頂きたい。
下水汚泥のみならず、生ごみ、畜ふん、木質など地域のバイオマス資源利用も交え、地域が自発的に2050年エネルギービジョンを考えていく動きを強めていくことが必要ではないかと思う。
そのためにも、P.51の目標9-4「環境情報の整備と提供・広報の充実」であげている「研修」については、今後さらに重要な役割を占めることをもう少し明確に言及してほしい。
と同時に、この施策を展開し、評価していってほしいと思う。
循環型社会づくりについては、循環基本計画、あるいはリサイクル法の見直しなど非常に進んでおり、リデュース、リユースを明文化するなどの流れになってきている。
今後の展開としては、より大きな視点で、例えば2050年の温暖化対策の将来ビジョンの中で、資源とどうつき合い、どういう暮らしや社会になるのかということを具体的に描き、施策を進めていくことが大事ではないかと考える。
【堤委員】
評価報告書を眺めていたが、PDCA的な考え方で評価しようと思うと、1枚1枚の書かれた指標を見る限り、新米委員としては、これにどうコメントすべきか戸惑った。
自分の専門分野については、指標を羅列されただけでもその背景にある見えない部分が大体推測することが可能であるが、評価書全体を見て何が問題であるのか捉えかねたのが正直な感想である。
18年度の資料では、個体識別措置推進事業という、危険な動物とか、犬猫の飼い主が印をつけるという努力規定のモデル事業があったが、自身でペットを飼っているがまったく知らなかった。
そういう意味で、知られていないことがたくさんあると感じた。
地球温暖化については、情報として入ってくるので、何が問題であるかは判断もしやすい。しかし、リサイクルについては、実際に裏で何が起きているか、普通は分からない。
ネガティブ情報を含めた裏の情報を知らされないまま、表だけの情報ではパブリック・コメントを募集しても意見が集まる展開にならないように感じた。
感想であるが、低炭素社会、循環型社会、生物多様性、これらを一体的に環境として捉えようと思うと、省庁同士の連携が必要になるが、そういう場合に全体的に目標をどう表現していくのかが気になった。
【須藤委員長】
委員になられて、全て読んで頂いての感想で、新鮮な意見だろうと思う。
特に、リサイクルとか廃棄物の問題で、知られていない、見えないところを見えるようにすることが大事であるという意見もあったかと思うので、後で廃棄物・リサイクル対策部から付け加えて頂きたい。
【藤井委員】
今日は、浄化槽についてだけ申し上げる。
P.24の浄化槽について、達成状況の中で「生活排水対策が着実に進展している」とあるが、全体を見て1987年に合併浄化槽に補助金がついたときから、浄化槽普及率は10%前後のまま全く伸びていないと言える。
その中で浄化槽ビジョンが取りまとめられたが、浄化槽ビジョンを含めたフォーラムにはまったく予算もついてない。
滋賀県13市13町の財政分析を5年間の比較で実施してきた。特別会計の中で、下水道による財政の圧迫は相当のものである。
例えば、彦根市で言うと、一般会計の赤字が470億円ぐらいだが、特別会計が500億円ということで、その多くを下水道が占めている。今こそ下水道、浄化槽に光を与えるべきである。
下水道には税金が相当投入されているが、なぜこれだけ転換率が進捗しないかというと、イニシャルコストの一部補助はあるとしても、ランニングコストが問題で、これが100%個人負担であることも導入を難しくしている。
維持管理を含めて、制度設計を相当見直さないと、浄化槽の普及率は上がっていかないだろうというのが率直な意見である。
【細田委員】
3点申し上げる。
P.31の化学物質対策について、例えば欧州のREACHが進んでいて、日本企業も対応をしている。
日本政府としてこのREACHの考え方に国内で対応することをしなくてよいのか。
上市(欧州域内において有償、無償にかかわらず第三者に渡すこと)される製品についての管理を考えるべきかを検討すべきときが来ていると思うが、その点どう考えているかをお伺いしたい。
2点目は、P.71の大気・水・土壌環境の保全で、複合的な環境犯罪を重ねている企業に対して、性善説のような大防法、水濁法等の措置だけでいいのか。
公害時代から今まで、ほとんど体質が変わっていない企業がまれにあるが、そうした企業に対応しきれていない。
3点目は、P.86の土壌環境について、市街地のブラウンフィールド対策がまだまだ不十分であると考える。
用途変更しない、土地の売買がなく放置されている汚染地の問題に対して、検討しているのであれば、途中経過でもよいので教えてほしい。
【三橋委員】
1つは温暖化対策について、環境省は本当にリーダーシップをとっているのか気になる節がある。「福田ビジョン」をつくるにあたって、環境省が関与しているのだろうか。
2020年までの中期目標が、福田ビジョンでは、EUは90年対比20%減、現状対比14%減、これに対し日本は現状対比14%削減が可能という数字を打ち出している。
現状と比べて14%として、日本の場合は上がっていて14%であるので、90年対比に換算すると4%削減にすぎないということになる。
実現可能な現状対比14%減に落ち着いたからくり、欺まん性を感じる。
本日の委員会の助言の対象は、20年度の事後評価(平成19年度施策の評価)の内容であり、ここに書かれている地球温暖化対策はすばらしいと思うが、環境省の役割とは何かということが非常に気になる。
P.4の温暖化の「国際交渉等」という部分について、日米、日中、日印、アジア太平洋地域等々の各種セミナーの開催に触れているが、これらのセミナーを開催しただけでフォローアップをしないと、実施だけで実績とすることにはあまり意味がないように感じる。
もちろんセミナーの実施は大切であるが、今後の温暖化対策、国際的協力における意味・意義は何なのか、どのような形で活かしていくのか、さらに踏み込んで記載してほしい。
P.5の⑥「指標の名称及び単位」について、例えば①のエネルギー起源二酸化炭素には問題があり、②非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素、③代替フロン等3ガスについては成果がみられたのならば、
①は手法に問題があるから達成できないのではないか、②③は手法が正しかった、等の分析を行い、問題点を指摘すべきではないか。
あとはP.25の循環型社会について、各種個別の法律について、運用後に制定時に想定していなかった課題が生じているはずである。分析・経過・問題点等を指摘した評価も必要だと考える。
【鷲谷委員】
政策の評価の視点について、必要性、有効性、効率性の観点から指標を重視して評価するという点に関しては、年を追うごとに洗練され明瞭になってきている。
ただ、ここにきて、統合性や連関性の視点が重要である気がしてきた。
特に環境への取組に関しては目標間でトレードオフが生じたりする。ある目標に対してオルタナティブな手法があって、それを選択することがある。その時に、一元的な指標であれば誤ることがあるだろう。
温暖化は既に明瞭な一元的指標があるが、落とし穴がないとは言えない。その一元的指標だけに基づいて選択と集中を行うと、他の社会的な目標達成に問題が生じることがある。
ある取組を進めた時に、その指標で見ると量的な効果が少なくても、他の政策に対してメリットがある場合には、そちらを選択する方が社会にとってよい場合も少なくない。
国民にとって分かりやすい、他の目標との関連の評価を含めて多次元的に分析しつつ、よりよい政策を選択していく形がよい。
明瞭になって対策が進むことはよいことだが、指標を一元的に集中しすぎていることには問題があるように思う。
必要性、有効性、効率性の3つの観点に加えて、統合性や連関性といった指標を加えて評価していくとよいように思う。
【須藤委員長】
「福田ビジョン」を中心に、地球温暖化関係を小林大臣官房長からお願いする。
【小林大臣官房長】
毎回出席させて頂いて、本当に有用な会議であると思っている。個々の政策の評価を超えて、大変高い見地から意見を頂いている。私からは2点だけ申し上げる。
1つは、今、鷲谷委員に最後まとめて頂いたが、統合目標を持っている場合とか、連関的な関係にある政策については、そういう目で評価が必要だという話で、これは本日共通してあった話だと思う。
方法論の開発を検討する必要があると考えている。
一番簡単なやり方は、もともと複眼的な目標を持っている施策をモデル的に取り上げて、そういった複数目標をどう達成しているかを調べることだろうと思う。
あるいは、いろいろな政策が合わさって、CO2の排出量を減らす効果を発揮しているようなものについては、個々の施策を切り刻んで見るのではなく、かけ算で相乗効果が出ているのか、あるいは足を引っ張っているのかを見てみるというのがあるだろう。
それでもまだお手盛りなので、環境政策のバウンダリーを超えて、何か副作用を及ぼしているというケースもあるかもしれないので、ネガティブな影響も評価するといったことが考えられる。
それぞれの施策について、統合的な作用も定性的に分析するなど、検討させて頂きたい。
環境省のリーダーシップ、他省への働きかけをどう評価するかということの典型例が、「福田ビジョン」がどうだったのかということだと思う。
「福田ビジョン」については、環境省としては、大臣まで含めて、言うべきことは総理にインプットをしている。現状比14%の問題も、私の解釈では正しいかどうかという問題ではない。
単純に今から実現可能という数字が、偶然欧州と同じ14%削減であっただけで、いずれにせよ、中期的に望ましい目標は来年に発表すると言っている。
ご批判も踏まえて、これからも環境省として影響力を発揮していきたいと思う。
【地球環境局】
まず1点目、井村委員、崎田委員からご指摘の6ページの温暖化関連予算の部分であるが、「直接的に効果のある」ものとして、5,093億円、これは何かというお話である。
京都議定書目標達成計画については、目標関連予算として関係省庁の予算をとりまとめている。
温暖化対策関連予算には、直接的に削減が見込まれるもの、すぐに効果が発現しない研究開発の長期的に効果があるようなもの、温暖化対策が直接的な目的でないものの結果として副次的な効果が期待できるもの、制度管理のような横断的なものなどがある。
ここに書いてある5,000億円、環境省の300億円強というのは、1番目の直接的に削減が見込まれるものの予算である。
それから、一酸化二窒素のご指摘については、全体として排出量が最も多いのは、アジビン酸の製造過程に伴う一酸化二窒素であり、この分野については対策を進め、効果が現れており、全体としては目標レベルまで行っている。
地域発の対策に関して、例えば2050年のエネルギービジョンなど、地域発のイニシアティブがいろいろ出てきている。
温対法の改正の目玉として、中核市、特例市以上の自治体は、地域の温暖化対策についても計画を作ってくださいということにしている。
その中で、再生可能エネルギーについては、地域事情に応じてローカルエネルギーとして取り組んでいただくこと、また、例えば都市計画や農振計画といった土地利用の面で工夫をこらしていただくこと、の2点をポイントとしている。
「福田ビジョン」の件については、先ほど官房長からご説明申し上げたとおりである。
総理の発言内容を読むと、先ほどの14%の話をした後、「国別総量目標の設定に当たりましては、こうしたセクター別積みあげ方式について各国の理解を促進してまいりたいと思います。具体的には・・・」という形で、セクター別アプローチの一つの考え方の例として説明しているところもある。
積み上げ方式に対する各国の評価等も踏まえて、共通の方法論を確立するとともに、来年のしかるべき時期に我が国の総量目標を発表したいと考えているということである。
P.4にある、日米セミナー、日中セミナーなどのセミナーの話については、やるだけではなく、今後どういう形で貢献していくのか、評価していくのかというお話であった。
中には古くから行っているものもあり、時によって中身を変えて実施しているものである。
最近は、日米、日印、日中間の場合には、環境担当部局だけでなく、自治体、開発部局、民間の方々なども入ってもらって温暖化の議論をしている。
【廃棄物・リサイクル対策部】
廃棄物、3Rとなると、政策分野として非常に大きく、評価書の限られたスペースでどの部分までとらえて書いていくか、書ききれない部分もあることがまずベースにあるかと思う。
とはいえ、循環型施策全般について、中身を抜本充実しなくてはいけないということで、今年3月に第二次循環型社会形成推進計画を閣議決定している。
第一次計画の5年間の進展も踏まえて、各法の施行上の問題点を踏まえた抜本改定となっている。
範囲の問題となると、低炭素社会、自然共生に加えて、健全な水循環や資源問題にもスコープを拡充させるとともに、さまざまな取組指標も充実させている。
大塚委員からご指摘のあった指標関係だが、家電リサイクルの再商品化率目標については、新規追加品目分も含めて、定期的に見直しを行い、検討を行っているところである。
また、主として経済産業省の所管する資源有効利用促進法の関係についても、適宜再商品化率の見直しを行っている。
再生品をどの程度使っているかということについては、どこまで指標化するかは別の問題であるが、しっかり把握しながら進めていく方向になっている。
井村委員からご指摘のあった温暖化対策との関係で書いてあるのは廃棄物発電だけであるというお話については、循環型社会形成推進基本計画では廃棄物発電に加えて、
生産工程、バイオマス系資源の有効活用、静脈物流システム、レジ袋削減などの国民運動の類も含めて盛り込んでいる。
自然行政の観点からも、生物多様性に配慮した再生可能な資源の利用促進、環境保全型の農林水産業なども射程に入れるべきだということを盛り込んで、幅広く具体的なものを盛り込んで計画を作り込んでいる。
崎田委員からご指摘のあった廃棄物関連の予算が減っているということについては、特に廃棄物・リサイクル全般については、公共事業関係の予算のウェイトが約9割ということで高い分野である。
高濃度PCB処理施設整備が大分進んできているので、公共事業に伴う予算は自然減の部分が非常に大きい。
他方、非公共と言われる部分を見てみると、地域循環圏とか、発生抑制とか、国民運動等の予算は大幅増額させている。
温暖化との関係では、様々なコラボレーション効果を測ったような施設整備に関するモデル事業も増額している。
また、国際的に3Rをどんどん進めていこうということで、国際関係の予算も抜本拡充している。資源全体の話については、資源を有効に確保することを念頭に施策体系を組んでいきたい。
堤委員からご指摘のあった、表だけでの議論だけではなくてというお話については、全体的な流れで行くと、廃棄物関係のものがどういう風に流れているのかを正確に把握していこうということが第二次循環型社会推進基本計画にも盛り込んでいる。
また、循環資源の観点から、モノの動きを正確に把握しようということで、統計情報の整備、分析の高度化に取り組むことにしている。
また、容器包装リサイクル、家電リサイクルのフローもできるだけ見える化に取り組んでいきたい。
浄化槽全般については、普及率の現状に関するお答えは難しいが、とにかく光を当てていこうという意識で、浄化槽ビジョンを作って頂いており、大々的な政策展開をしていきたい。
特に普及率の観点では、中山間地域にはもっと入る余地があると思っている。
少なくとも浄化槽ビジョンの検討会の中では、1つは地域住民の意識啓発が大きな鍵ではないかということで浄化槽フォーラムを実施するとともに、浄化槽の整備区域を積極的に指定していこうという中身も入っている。
また、国際的にも、浄化槽、し尿施設などについて大きな需要があるのではないかということで、国際的にも打って出られるよう施策展開していきたい。
もちろん、公共事業の予算の性格があり、メンテナンス費用を支援することは難しい部分があるので、ビジョンが進むような予算を担保して進めていきたい。
なお、国交省、農水省との関係においても、汚水処理施設整備交付金があり、相互に全体を調整しながら整備を進めるというスキームができている。この分野でも連携強化を進めていきたい。
三橋委員からのご指摘については、個々のリサイクル法の問題点については、それぞれ法律の個々の見直しを徹底して進めているところである。
評価書にどこまで入れ込むかの問題であるが、各省庁間で相互連携をするように施策展開をしていきたい。
【環境保健部】
大塚委員からのご指摘について、P.35~36にある生態毒性の検討結果の取扱いであるが、平成16年度から調査をしており、既存化学物質2万、新規化学物質1万の中から、リスクの高いところから順次対象として調査試験を行っている。
平成19年度の109物質のうち約半数の物質についてリスクがある可能性があるとされ、それら物質は法律上で第三種監視化学物質と位置づけられることになった。
これらの物質については、さらにリスクの分析を進めて、化審法上、より厳しい規制を課していく仕組みとなっている。
第2点目として、井村委員からの途上国の化学物質対策についてお尋ねがあった(P.38~39)。
基本的には、各国で国際化学物質管理戦略(SAICM)に基づいて国内戦略を策定し、化学物質の審査・管理を行っている。
残念ながら、途上国に対する二国間の直接的な支援は環境省ではそれほどできていないが、現時点では、日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ等による日中韓三ヵ国での情報交換・連携、東アジア地域におけるPOPsモニタリングに対する支援等があり、H20年度からはブータン及びタイを支援予定である。
評価シートの今後の展開にあるとおり、途上国の公害問題、化学物質の汚染問題については、被害者の対策も含めて取り組むべき時期にきていると認識しており、検討していきたい。
第3点目に、細田委員からご指摘頂いたREACHへの対応であるが、化審法の見直しが5年以内という法律の規定になっており、来年の通常国会で化審法、化管法を見直しするために、中環審などで検討を行っているところである。
REACHの考え方も参考にしつつ、上市後化学物質への対応は、その中での論点の1つに入っている。
【総合環境政策局】
井村委員から、目標9-3.調査・研究・技術開発について、書きようはこれしかないのは分かるが、何をやっているかわからず、インパクトが弱いというご指摘を頂いた。
国民に分かりやすいという観点からするとご指摘の通りの部分もあるかと思うので、どのような工夫があるかを検討していきたい。
外国語の情報発信を他省庁の施策も含めて幅広くすべきとのご指摘について、現状は環境省の日本語版ホームページを下敷きにして作成している。
但し、関係省庁とのリンクも外国語で張っているので環境施策情報は最低限発信できるようになっている。
諸外国の方が日本の環境政策を見るときに、まず環境省のホームページを見るだろうという観点からすると、なお工夫ができるか、担当部署とも相談していきたい。
3点目、崎田委員から、研修の重要性についてご指摘頂いた。
国レベルの急速ないろいろな動きを地方公共団体の担当者に直に伝え、一緒に連携し、関係者を巻き込んでいくような形で大きな流れを作り出していくためには、研修が1つのツールであると思う。
環境調査研修所で環境省職員のみならず、地方公共団体の職員向けの研修を行っているが、ここで国レベルのさまざまな動きを説明し、ご理解いただいている。
また、地方公共団体等のご希望等の声も、そういう機会を通じて吸い上げて、国・地方公共団体が全体として大きな流れを作り出していけるように、頑張っていきたい。
【水・大気環境局】
細田委員からお話のあった、問題企業への対応であるが、罰則に該当するようなことをやっている企業には、関係省庁相互で、現行法の最大限の活用で対処していくが基本である。
2点目としては、大気汚染防止法の改ざん問題や製紙業界の方の問題などに対し、地方自治体に、立入検査の実施を要請している。
ただ、都道府県も実施体制に限界があるため、立入検査の実施ついては、重点的にやる必要がある。
メリハリをつけて、問題のあるところについては経過観察的に見ていくという運用はしていくべきであろうと認識している。
企業行動の情報開示が求められる世の中であり、環境省としては情報開示の環境整備に努めていくべきと考えている。
株主、顧客、取引銀行などのステークホルダーから評価されるようにすることが、即効性はないかもしれないが、じわじわと効いてくることになるかもしれない。
土壌汚染対策について、いわゆるブラウンフィールド問題と現在の土壌汚染対策法で必要な調査、対策を押さえ切れていないのではないかというご指摘を頂いた。
土壌汚染対策法の施行の問題は、全くこの2点がポイントと思っている。この3月に有識者懇談会でまとめていただいた報告の柱でもあった。
1つは、土壌汚染対策法の対象範囲の見直しを考えていきたい。もう1つ、ブランウンフィールド問題は、今後の政策のあり方として、リスクの程度に応じた合理的な対策を推進し、対処していきたい。
浄化槽問題は、環境省だけでなく都道府県、関係各省との連携が重要である。
浄化槽の整備にあたっては、現実に改善をどのように進めていくかが問題であり、都道府県の整備計画の支援をするなど情報を聞きながら足並みをそろえて進めていきたい。
また、地域再生基盤交付金のようなベースがあるので着実に進めていきたい。
POPs関係は、P.88の中ほどにある枠組みにあわせて、利用可能な最良の技術の普及に取り組んでいきたい。
農薬取締法の体系もあるが、OECD諸国の動向に応じた陸上生物を含めたリスク評価を行っているので、今後とも国際調和を考えながら取り組んでいきたい。
【自然環境局】
個体識別の施策について、「マイクロチップを知っていますか?」という表題でマイクロチップのパンフレットを作り、獣医師会の協力を得ながら普及啓発に努めている。今後も積極的に進めていきたい。
【政策評価広報課長】
前回に山本委員から、日本の温暖化対策のパフォーマンスが国際比較で下ではないかというご指摘をいただいた。
平成21年度の予算において、世銀の評価手法などの本格的な勉強をはじめていきたい。
政府全体で政策の棚卸しをしようとしており、無駄ゼロの政府を目指している。環境省としてもプロジェクトチームを発足して、無駄を排除する観点からも対応している。
各9分野の政策評価を相互にどのように考えるかは、大変に大きな課題となっていきている。環境基本計画の評価・見直しとの関係も見ていく。
環境省の政策を評価するのだが、環境省の調整機能を政策評価面からどのように捉えることができるかは、政策評価の問題として検討したい。
個別の政策評価の体系に関して、浄化槽の場所について意見があった。政策体系を見るときに、部局で見るのがよいか、検討を深めていきたい。
書き方の面でも、例えばセミナーなど議論があったが、実績をさらに詳しく踏み込んで、より分かりやすい評価となるように努めていく。
ご意見を踏まえて、充実した政策評価書としていきたい。
【須藤委員長】
これをもって本年度の第1回政策評価委員会を終了させていただく。
以上
|