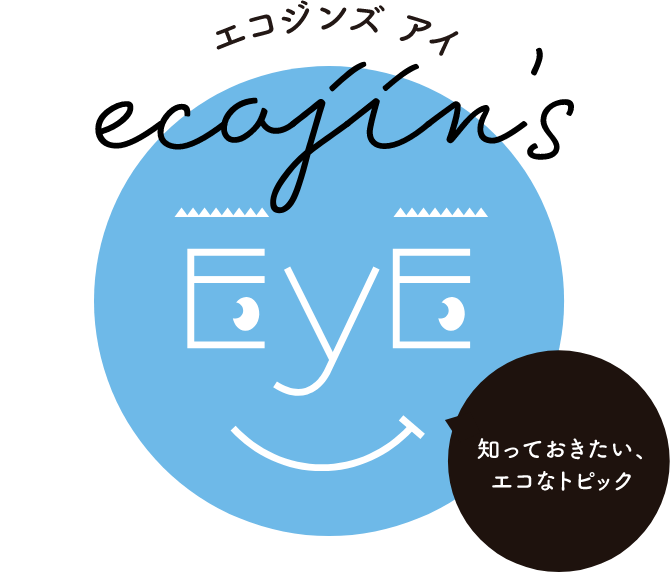環境のことをもっと知りたくなる、
注目のキーワードや
ニュースをお届けします。
今月のキーワード 鳥獣保護管理法

ポイント!
近年は自然環境や社会環境の変化──里山環境の変化、人口減少、過疎高齢化など──により、野生鳥獣が畑や市街地に姿を現すようになったり、生息数が急速に変化したりしてきています。そうした中で、人と鳥獣が共存できる世界の実現に向け、重要な役割を担うのが鳥獣保護管理法です。
1. 鳥獣保護管理法とは?
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、その名の通り、鳥獣の「保護」と「管理」を柱とする法律です。「保護」とは、野生鳥獣の生息数を適正な水準に増加または維持し、その生息地を適正な範囲に拡大・維持すること。もう一方の「管理」は、生息数を適正な水準に減少させ、その生息地を適正な範囲に縮小させることです。
法律の背景として、豊かな生物の多様性を将来にわたって確保するために、鳥獣を保護する必要がある一方で、生息数の増加や生息地の拡大によって人に被害をもたらしている鳥獣も存在することがあげられます。人と鳥獣の適切な関係の構築を通じて、両者の生活をできるだけ乱すことなく問題の解決を目指すことが求められているのです。鳥獣保護管理法は、「保護」と「管理」の両面からアプローチすることで、生物の多様性を守ると同時に、人の暮らしの充実や社会の健全な発展を目指しています。
2. 地域の実情に即した「保護」と「管理」の仕組み
鳥獣保護管理法では、国や地方公共団体、民間団体や市民、専門家などが、それぞれの役割を果たしながら、互いに連携して鳥獣の「保護」と「管理」に取り組むよう定められています。まず国は、国際的、全国的な鳥獣の「保護」及び「管理」の見地から、国全体としての基本的な指針を示すとともに、これに沿った取り組みを促進します。これを受けて、都道府県は地域の実情を踏まえ、科学的かつ計画的な鳥獣の「保護」及び「管理」の基本的な枠組みを作り、施策を実施します。特に、広い地域で集中的な「管理」が必要とされる動物として環境大臣が定める指定管理鳥獣(ニホンジカ、イノシシ、クマ類)については、市町村などとも調整しながら、目標達成のために必要な捕獲に取り組みます。
一方、民間団体や市民は、行政との連携を十分に図りながら、人と鳥獣との適切な関係について理解を深め、鳥獣の「保護」と「管理」に関わる活動に自主的・積極的に参加することが期待されます。また、専門的な知識及び技術を持つ専門家や民間団体は、科学的な観点から必要に応じて地方公共団体などに助言・指導を行います。
3. 人と鳥獣のすみ分けを図るためにできること
生息数が著しく増え、生息地が拡大している鳥獣に関しては、鳥獣保護管理法に基づく取り組みによって増加が抑えられるなど一定の成果が上がっています。
一方で、近年はクマやイノシシなどが畑や市街地に出没する問題が深刻化しています。これを受けて2025年には法律の一部改正が行われ、一定の条件を満たす場合には市町村長の判断で、人の日常生活圏での猟銃の使用を可能にする緊急銃猟制度が創設されました。
今後こうした問題を改善していくためには、地域住民が一体となって未収穫の作物や生ごみの適切な管理などに取り組み、鳥獣を畑や市街地に誘引しないようにする必要があります。また、鳥獣への餌やりは、鳥獣の行動が変化して人への被害につながる場合があるのでやめましょう。鳥獣が豊かな自然の中で暮らせるよう、自然環境の保全への取り組みも大切です。まずは、私たちの日常生活の中でできることから考えてみませんか。
なお、クマが駆除された際に、行政機関に過度な苦情電話が寄せられることも問題となっています。行き過ぎた苦情電話は、自治体の活動を制限し、ハンターの活動を委縮させ、新たな事故につながりかねません。クマが連日出没して不安な生活を送る人々の状況などもご理解いただき、節度を持って行動しましょう。

原稿/久保寺潤子
イラスト/丹下京子