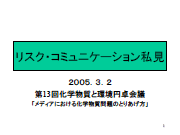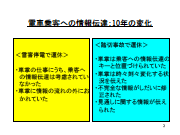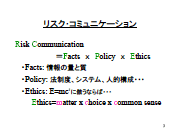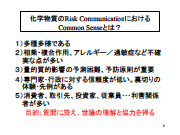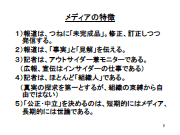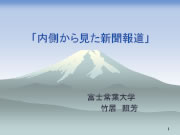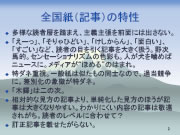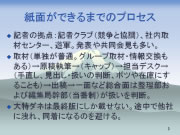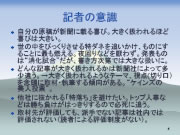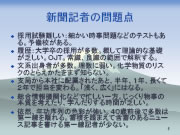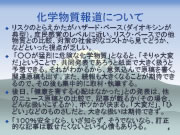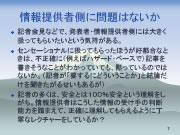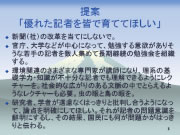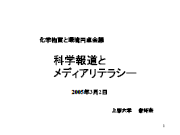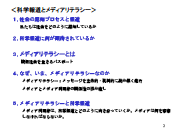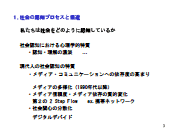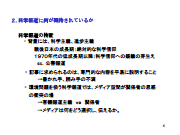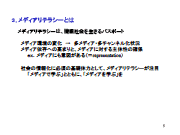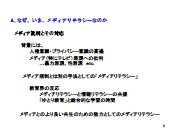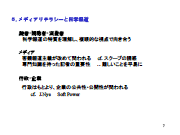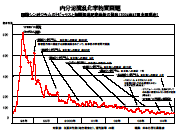■議事録
1.開会
(荒木) 本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。時間がまいりましたので、開催させていただきます。本日は、原科さんに司会をお願いしています。原科さん、よろしくお願いします。
(原科) それでは、ただ今から「第13回化学物質と環境円卓会議」を開催します。今回は、メンバーの皆さんとご相談させていただき、「メディアにおける化学物質問題の取り上げ方」について意見交換を行うこととなっています。これにあたり、大妻女子大学教授でNHK解説委員の小出五郎さん、富士常葉大学流通経済学部教授で元日本経済新聞社論説委員の竹居照芳さん、上智大学文学部新聞学科助教授の音好宏さんからそれぞれ20分程度のお話を頂きます。まず、事務局から本日のメンバーの出席状況等と資料の確認などをお願いします。
(荒木) まずはメンバーの交代をお知らせします。産業側の田中康夫さんが岩本公宏さんに交代しています。岩本さんは(社)日本化学工業協会、環境安全委員会の委員です。次に代理出席についてお知らせします。産業側の山下光彦さんの代理で八谷道紀さん、行政側の染英昭さんの代理で菊地弘美さん、当省、滝澤秀次郎の代理で上家和子が出席します。本日のご欠席は、市民側の中下裕子さん、産業側の西方聡さんです。
次に配布資料の確認を行います。資料1は小出さん講演資料の「リスク・コミュニケーション私見」、資料2は竹居さん講演資料の「内側から見た新聞報道」、資料3は音さん講演資料の「科学報道とメディアリテラシー」です。次に、参考資料1は「第12回化学物質と環境円卓会議議事録」です。これは本円卓会議のメンバーのみに配布しているものですが、既にメンバーに御確認いただき、環境省HPに掲載しています。参考資料2は「化学物質と環境円卓会議リーフレット」です。リーフレットは毎回必要に応じて改訂しながら配布しています。以上です。
2.議事
(原科) それでは早速議事に入りたいと思います。今回の議題は「メディアにおける化学物質問題の取り上げ方について」ということで、冒頭にもお話ししましたとおり、3人の専門家からお話しを頂きます。はじめに、小出さんから「リスク・コミュニケーション私見」についてお話を頂きたいと思います。
(小出)


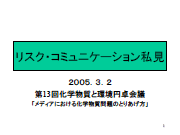
 小出です。よろしくお願いします。私は長年NHKで科学番組のディレクターをやっていました。その中でもリスクコミュニケーションの問題は非常に大きなテーマで、私もいろいろと考えることがありましたのでそういった経験的なことをまとめてお話したいと思います。
小出です。よろしくお願いします。私は長年NHKで科学番組のディレクターをやっていました。その中でもリスクコミュニケーションの問題は非常に大きなテーマで、私もいろいろと考えることがありましたのでそういった経験的なことをまとめてお話したいと思います。
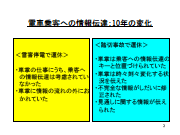
 まず、「電車乗客への情報伝達:10年の変化」です。これは私が小田急電車内で体験した2つの事例です。<雪害停電で運休>の方は10年前に雪が降って、駅のホームに長い間、電車が止まっていたという話で、<踏切事故で運休>の方は、昨年踏切事故があり、やはり駅のホームに長い時間、電車が止まっていたという話です。10年前に雪が降って電車が止まったときは乗客に何の情報も与えられないままそのままの状態に置かれていました。車掌や駅員に聞いても何も分かりませんでした。当時、携帯電話がはやり始めた頃で、携帯電話で自分の家や職場に電話をする人が出てきて、逆にその方からNHKのニュースでこんなことを言っている、復旧する見通しはまだないことを教えてもらいました。そして、それを車掌に教えるという逆転現象が起きたこともあり、印象に残っていました。ところが昨年踏切事故で電車が止まった際に車掌室の様子を見ていましたら、5分おきぐらいに車掌のところにコントロールセンターから情報が入り、復旧の進み具合や開通の見通し時間、トラブルの処理状況等といったかなり正確な情報が時々刻々と入ってきました。そしてそれを随時乗客にアナウンスしました。同じセリフではなく少しずつ内容が違うため頻繁にアナウンスが流れても乗客はうるさいという感じがしないようでした。ここで、状況の変化、つまり情報伝達の重要性における変化がこの10年で起きてきたのだと思いました。また、そういう情報を収集し伝達するシステムやポリシーというものが鉄道会社に浸透してきたということでしょう。復旧することが最も重要な仕事であることは今もかつても変わりませんが、乗客への情報伝達や不安解消が重要視されてきたという大きな変化を感じました。この変化の中には、コミュニケーションの本質が入っていると思います。
まず、「電車乗客への情報伝達:10年の変化」です。これは私が小田急電車内で体験した2つの事例です。<雪害停電で運休>の方は10年前に雪が降って、駅のホームに長い間、電車が止まっていたという話で、<踏切事故で運休>の方は、昨年踏切事故があり、やはり駅のホームに長い時間、電車が止まっていたという話です。10年前に雪が降って電車が止まったときは乗客に何の情報も与えられないままそのままの状態に置かれていました。車掌や駅員に聞いても何も分かりませんでした。当時、携帯電話がはやり始めた頃で、携帯電話で自分の家や職場に電話をする人が出てきて、逆にその方からNHKのニュースでこんなことを言っている、復旧する見通しはまだないことを教えてもらいました。そして、それを車掌に教えるという逆転現象が起きたこともあり、印象に残っていました。ところが昨年踏切事故で電車が止まった際に車掌室の様子を見ていましたら、5分おきぐらいに車掌のところにコントロールセンターから情報が入り、復旧の進み具合や開通の見通し時間、トラブルの処理状況等といったかなり正確な情報が時々刻々と入ってきました。そしてそれを随時乗客にアナウンスしました。同じセリフではなく少しずつ内容が違うため頻繁にアナウンスが流れても乗客はうるさいという感じがしないようでした。ここで、状況の変化、つまり情報伝達の重要性における変化がこの10年で起きてきたのだと思いました。また、そういう情報を収集し伝達するシステムやポリシーというものが鉄道会社に浸透してきたということでしょう。復旧することが最も重要な仕事であることは今もかつても変わりませんが、乗客への情報伝達や不安解消が重要視されてきたという大きな変化を感じました。この変化の中には、コミュニケーションの本質が入っていると思います。
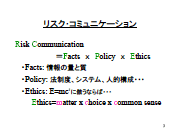
 私は、Risk Communication=Facts×Policy×Ethicsだと理解しています。これはリスクに関わらずコミュニケーションすべてについて言えることだと思います。もちろんこの他にもTiming(タイミング)などいろいろな要素がありますが、代表的なものはFacts(事実)、Policy(施策・方針)、Ethics(倫理)でしょう。
私は、Risk Communication=Facts×Policy×Ethicsだと理解しています。これはリスクに関わらずコミュニケーションすべてについて言えることだと思います。もちろんこの他にもTiming(タイミング)などいろいろな要素がありますが、代表的なものはFacts(事実)、Policy(施策・方針)、Ethics(倫理)でしょう。
Factsは情報の量と質の問題であり、量だけでも質だけでも駄目です。質の良い、ある一定量の情報がFactsです。Policyとは、システムや法制度がどうなっているか、どういう人々がその中に関わっているかといったことです。どちらかといえばSystemという方が良いのかもしれませんが、Policyとしています。また、Ethicsの要素もあります。
ものを伝えるときに、このようないくつかの要素のかけ算になっていることがコミュニケーションの非常に重要な点です。かけ算ということは、どれかがゼロであると成り立ちません。仮に、Factsがいかに正確無比であっても、それに対する法制度やシステム、また、関わる人々に対して信用がおけないということになるとかけ算の結果としてゼロになるため何も伝わりません。Ethicsについても同様です。中でも1番重要なのは、Ethicsだと思いますので、ここからEthicsについて取り上げます。
「E=mc2 Ethics=matter×choice×common sense」。これは、アインシュタインの相対性理論が公表されてからちょうど100年にあたるということで、Ethicsを相対性理論の根幹になる式である「E=mc2」に当てはめて遊んでみました。ですから、「E=mc2」にあまり意味はありません。
Ethicsで考えられる要素にも同様に3つあると思います。事柄(matter)と選択肢(choice)、さらに世の中の一般的な常識(common sense)のかけ算であるということがいえます。ですから、これもどれか1つがゼロであれば、結果としてゼロになります。
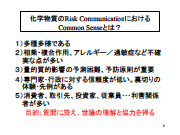
 化学物質問題を考える上ではCommon Senseが大変重要であると思います。化学物質のRisk CommunicationにおけるCommon Senseは5つあります。
化学物質問題を考える上ではCommon Senseが大変重要であると思います。化学物質のRisk CommunicationにおけるCommon Senseは5つあります。
1つ目は、「多種多様である」。2つ目は、「相乗・複合作用、アレルギー/過敏症など不確実な点が多い」。例えば、現在はやっている花粉症に化学物質が関係しているといいますが、何がどう関係しているかが分からりません。これは典型的な例だと思います。3つ目は、「量的質的影響の予測困難、予防原則が重要」。4つ目は、「専門家・行政に対する信頼度が低い。裏切りの体験・先例がある」。これは専門家のみならず、行政や企業を含めて、信頼が非常に低い。また、専門家といえどもよく分からないことがたくさんあるという両方の要素が入っています。過去に日本が体験してきた水俣病やイタイイタイ病といった公害病や世界で起こる様々な問題、事例を見ると、専門家が期待を裏切ったという経験がかなりあります。ですから、専門家の言葉が本当かな、と眉唾で考える傾向があります。そして5つ目は、「消費者、取引先、投資家、従業員・・・利害関係者が多い」。利害関係者が非常に多いため余計に意味不明で、真実を述べているのか、それとも、利害を大事にして述べているのかがよく見えないということもしばしば起きます。そういった様々なものを抱えながら化学物質問題等については質問に答え、世論の理解と協力を得る努力が基本的に必要であるように思います。具体的な事例を挙げる時間がありませんので、話が少々抽象的で恐縮です。
以上のことは、元々の情報の発信者のみならず、ジャーナリズムやメディアのメンバーについても同様です。ものを伝えるにあたっては、さまざまな要素を踏まえながら伝えていかなければ、いくら努力してもほとんどのことは伝わらない。どれか1つが欠けても伝わらないということを改めて述べておきたいと思います。
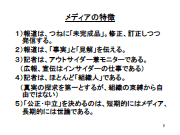
 次にメディアの特徴についてお話しします。今回の発表に際し「メディアは危険なことは報道するが安全な情報を報道しないのはなぜか」ということ、そして「専門家が見ても分かりづらいようなことを一般人に分かりやすく報道する際に情報の齟齬が生じてくるのではないか」ということについて意見を述べて欲しいと言われましたのでそれらを踏まえてお話します。これも化学物質に限ったことではありません。ありとあらゆる事柄の情報伝達に共通するように思います。
次にメディアの特徴についてお話しします。今回の発表に際し「メディアは危険なことは報道するが安全な情報を報道しないのはなぜか」ということ、そして「専門家が見ても分かりづらいようなことを一般人に分かりやすく報道する際に情報の齟齬が生じてくるのではないか」ということについて意見を述べて欲しいと言われましたのでそれらを踏まえてお話します。これも化学物質に限ったことではありません。ありとあらゆる事柄の情報伝達に共通するように思います。
1つ目は、報道は、常に「未完成品」であるということです。テレビの受像器は完成品を売らなければならないのは当然のことです。しかし、報道する中身に関しては完成するまで待つことはできません。時々刻々の変化を伝えるのが報道の役割ですから、すべて分かってから報道するということはまず有り得ません。スピードが1つの勝負です。また、常に未完成品ですから修正、訂正しつつ発信するという性質を持っています。そして、その間に、これは業界用語ですが、私たちは“裏”をとります。1つのことが分かると必ずそのことが正しいかどうかということを複数の情報源でチェックし、傍証を集めます。ものによっては日本でチェックができないことも数多くあります。その時はインターネットも活用します。また、外国の文献や研究者を通じて直接チェックすることも少なくありません。それらを踏まえつつ修正、訂正しつつ発信するという流れです。ときにはチェックを省く者がいて、大騒ぎになったりします。それは否定しません。ここで私が言いたいことは、報道とは未完成品を発信しつつ時間の経過とともに修正、訂正していくという性質のものだということです。
2つ目に、報道は、「事実」と「見解」を伝えるものであるという点です。もちろん事実を伝えていますが、当然のことながら新聞やテレビには途中で編集作業が入ります。ある一定の時間や字数の中に情報を収め、他のニュースとのバランス等も考慮しながら編集を行います。その中で事柄に重み付けの判断が行われます。つまり、見解が入ります。事実と見解を合わせて伝えるという性質も報道の特徴です。
3つ目に、記者はアウトサイダー兼モニターであるということです。私はディレクターですが記者もディレクターと同じと考えてください。取材者の代表としての「記者」と考えてください。取材される側の企業や行政は、しばしば記者を自分たちの立場に立つ広報・宣伝マンであるかのように、あるいは仲間内の者と誤解している向きがあります。インサイダーのように思われていますが、これは実に悲しいことです。ジャーナリストは、もともとアウトサイダーであり同時にモニターである、つまり、監視者です。発信者の広報室に所属しているわけではないのですから、いろいろな事柄に対して厳しい見方をするのは当たり前です。記者の大きな役割とは、モニターとしての視点、つまり科学技術というものは暴走するものだということを踏まえてものを見るということであり、これはメディアに属する人間の基本的常識といっても良いでしょう。
4つ目は、記者もディレクターもフリーランスであっても、ほとんどが「組織人」であるということです。ジャーナリストは「真実の探求を第一とする」と言いましたが、組織人であるということは同時にビジネスマンでもあります。ビジネスマンであれば利益追求を第一に、行政であれば社会貢献を第一に考え、他のことは第二、第三に考えるのが当然です。そういう意味では、ジャーナリストは真実の探求を第一に考えなければいけません。しかし、組織の束縛から逃れることはできません。人事異動や予算的制約などもあります。フリーランスも同じです。何かを発表する際にはメディアを使わなければいけないので、そういった組織の束縛を受けざるをえない事情があります。そうした中でメディアそのものも随分過ちを重ねてきた事実もあります。同時にそれはメディアが反省してきた部分でもあります。組織人としての記者、ディレクター、そしてジャーナリストとしての記者、ディレクターは常に対立関係や葛藤の中で仕事をしています。
5つ目として、「公正・中立」を決めるのは短期的にはメディアで長期的には世論であるように思います。メディアは変な形で自己規制をしてはいけないということは基本であり、長期的にはそれが利益になると考えます。
化学物質のリスクコミュニケーションで考えると、メディアは化学物質の安全性を伝えるのが仕事ではありません。このことを誤解してほしくありません。緊張関係の中でこそメディアは良い仕事ができていくと私達は考えます。それに応じて行政や企業の方がどのように発信していけば良いのか。その点に関する一般的な手段を、説明はしませんが参考までにスライドの6~10に載せています。私の発表は以上です。ありがとうございました。
(原科) ありがとうございました。小出さんのお話に対し、メンバーから質問等はありますか?
(瀬田) 最後に化学物質の安全を伝えるのはメディアの仕事ではないとおっしゃいましたが、これに対して若干のこだわりが感じられます。1つは危険であると報道した後の修正の問題、もう1つは安全ということを伝えないという姿勢があるように感じることです。この辺を詳しくご説明いただきたいと思います。
(小出) これはニュースバリューの問題になると思います。報道は1度でおしまいではなく次々に修正、訂正を行います。完成品を目指してなるべくバランスのとれた良い報道をしたいと思っています。例えば、事件の場合、最初は「危険」から始まりますが、報道をしているうちに報道のバランスを取るように努力します。ですから、安全情報も実際に出しています。一方、安全ということを特に取り上げてニュースにするかといえば、それは極端な場合に限られると思います。例えば、ダイオキシンを舐めると身体に良いとか青酸カリを舐めると元気になるというような安全情報があれば、それは大ニュースになります。しかし、そうではない形で、「これまでの報道で強調した危険度を少し差し引いてくれ」というようなことをを取り上げるということはなかなか難しいと思います。発信側にとっては、第一報の印象と報道を修正していく過程の中での印象とでは違うという理由から、改めて報道すべきだと思われるでしょうが、これはなかなか難しいと思います。
(瀬田) 途中で報道内容が変わっていく場合、それに対する説明が入るのかどうかという問題です。例えば、段々と報道のバランスがとれていくとおっしゃいましたが「危険」というものは最初のニュースで視聴者に刷り込まれます。ニュースとしては徐々にバランスがとれるかもしれませんが、聞く側としてはバランスがとれていない可能性もあります。つまり、最初の印象が残ってしまう、というわけですが、そういった聞く側のバランスをどうとればよいとされているのでしょうか。
(小出) 聞く側のバランスをどうとるかということは非常に難しい問題です。ケースバイケースです。最初は非常に衝撃的に情報が入り、それが刷り込まれて後で変わらないというふうに不満に思われる方がいるのは当然だと思います。しかし、それを戻す手段というものはなかなか無いように思います。これは極端な例ですが、例えばダイオキシンが身体に良いというような新たな発見があるとすれば話は別です。しかし、そうでなければ、何を持って偏っているかどうかの判断をするのかは難しいところがあります。
(原科) 安井さんどうぞ。
(安井) 報道は常に未完成品でその修正、訂正をしつつ、というのは当然のことだと思います。しかし、サイエンスの場合、思わず報道してしまうということも有り得ます。何かを報道してしまったときに組織的に報道のチェックを行うような機構というものはあるのでしょうか? なぜこのようなことを聞くかというと、平成11年9月30日にJCOの臨界事故が起きた際、NHKは当初放射性物質が漏れたという表現をとりました。確かに微量の放射線は漏れましたがあれは中性子線が漏れたのであって、そのことが訂正されるまでにだいたい48時間かかっています。放射性物質が漏れるというよりもっと重要な中性子線が漏れたという報道に変わるまで48時間かかったというのはちょっとどうかと思っていました。その辺りを組織的にチェックする機構などはあるのでしょうか?
(小出) 組織的に報道をチェックするということはありません。ただ、私はあの日の夜中の放送を担当していた当事者でしたが、当日の夜中の時点で中性子線と放送しましたので、48時間経っていたというのは違うように思います。組織的なチェックに関しては、おっしゃるような意味での組織的な機構はありません。内部的に報道をチェックすることもありますが、チェックしきれないことがあります。テレビ局は個人企業のようなところがあり、個人的にはいろいろな繋がりを持っていて、放送を見てくれている人が放送内容に対する訂正や意見を言ってくれます。各人そういうネットワークを持っていることによって何とか報道のバランスをとりながらやっています。自分が報道の間違いに気付いて担当のセクションに伝えるということもありますが、これは個人的な関係であって組織的ではありません。実際問題として組織的に報道をチェックするのは無理だと思います。
(安井) ありがとうございました。
(原科) 今のようなクレームがついた場合に対応する部門などはあるのでしょうか?
(小出) 特に窓口はありません。安井さんはおかしいなと思われたときにどなたかお知り合いの方にそのことを伝えられましたか?
(安井) いえ、特に伝えていません。
(小出) 是非、伝えていただきたいと思います。これはおかしいと言っていただければ効果があると思います。
(原科) 中塚さんどうぞ。
(中塚) 化学物質のCommon Senseのところで常識とおっしゃいましたが、これは一般市民が持っている常識なのか、小出さんがお持ちの常識なのかをお聞きしたいと思います。
(小出) 簡潔にいいますとこれは私がこう思うという常識です。「私見」というタイトルでやっていますので。
(中塚) 小出さんの個人的常識という感じでしょうか?
(小出) そうです。ただジャーナリストであろうとする人には志があり、各人それぞれが「常識」というものを持っているはずであると理解しています。
(中塚) スライド4の2つ目の「相乗・複合作用、アレルギー/過敏症」は全て化学物質が原因でこういうことが起きているとお思いのように受け止められますが。
(小出) 化学物質のリスクコミュニケーションにおいては多分こういうことが関係しているだろうなというくらいの意味です。
(中塚) 現在はアレルギーテストで原因物質がかなり特定できます。それから、先ほどメディアの特徴のところで「科学技術は暴走するものであるというのは当然の見方である」とおっしゃっていましたがこれも小出さんご自身のお考えでしょうか? それともメディア全体がそのようなスタンスなのでしょうか?
(小出) 組織として決めたことはありません。ただ、メディアの仕事に従事する人間は将来どのような範疇でものを考えていけば良いかということについて、ある程度の認識を持つべきであると私は思います。
(原科) 岩本さんどうぞ。
(岩本) スライド5「メディアの特徴」の1)報道は、常に「未完成品」であり、修正、訂正しつつ発信するということは報道のかなり根本的なことに関係すると思います。具体的な話になりますが、例えばNHKの場合、1998年当時内分泌撹乱化学物質に関する報道が次から次へと行われました。内容を見ると若干恣意的な報道もあったように思います。その後、いろいろなことも分かってきましたが過去に放送した内容について修正、訂正という報道が可能なのかどうか、マスメディアの仕組みとして可能なのかどうかについてお伺いしたいと思います。
(小出) もちろん可能です。ニュースで考えた場合、とにかく第一報が大事です。しかし、第一報の時は何だかよく分からないものです。しかし、次から次へといろいろな情報が入ってきて、それをまた発信すると、それに対するリアクションも当然入ってきます。そのルートを作っていく時間がある程度かかります。それがまず第一次的な修正の時間になります。もう1つは、テレビの場合には番組というものがあり、これはある程度情報をせき止めて作る方式のものですから1年目2年目という時点で分かってくることが多少変わってきます。環境ホルモンの問題については長期間にわたって放送し、節目の時期やコルボーンさん(注、Theo Colborn;「奪われし未来」の著者の1人)が来日した際などにも放送しています。それぞれについて、新しい情報が入りニュアンスが変わってきている情報なども含めて報道を修正、訂正しています。
(岩本) 特にこのような比較的新しいサイエンスの問題の場合、単なる事実が真実ではなく、真実から見れば随分かけ離れたところにある事実だったりします。いろいろな事実や研究成果が積み重なってきて段々と真実に近づいてくるということだと思います。あるところで放送された内容は時間が経つと随分違ったものになり、そういう意味で、以前特集番組で報道された内容を今ビデオで見るとかなり内容が古くさいなと思います。そういう場合に、ここに書いている修正、訂正という機能は働くのでしょうか?
(小出) 機能が働くというか、報道はそういう性質のものです。おっしゃるようなことももちろんあります。科学一般についても全く同じことが言えます。ちょっと前に科学論文で出てきたことが今から見ると陳腐だということはたくさんあります。
(原科) 時間になりましたので、続いて竹居さんから「内側から見た新聞報道」についてお話を頂きたいと思います。
(竹居)


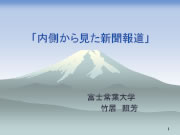
 竹居です。よろしくお願いします。初めにお断りをしておかなければいけないことがあります。1つは、私は新聞社に40年いましたが新聞社を離れてから3年と少し経っています。ですから今の状況がどうなっているのかについてはお答えできません。私の体験したことや考えたこと、見たことをベースにお話ししたいと思います。
竹居です。よろしくお願いします。初めにお断りをしておかなければいけないことがあります。1つは、私は新聞社に40年いましたが新聞社を離れてから3年と少し経っています。ですから今の状況がどうなっているのかについてはお答えできません。私の体験したことや考えたこと、見たことをベースにお話ししたいと思います。
私は新聞社に入ってからずっと経済記者として経済に関する記事を書いてきました。論説を担当する部署にも16年ほどいました。1990年頃に廃棄物に関心を持ち始めたことから環境問題の一端に足を踏み入れ、化学物質についても多少のことは知っています。しかし、化学物質の問題そのもので攻められると答えることはできません。それから、私が日本経済新聞社(以下、日経)にいたから日経の話をするというのではなく、記者クラブ等で各社と競争しながらやってきたことを踏まえて、新聞全体という観点でお話ししたいと思います。また、記事のごく一部に問題があるとすれば、その原因はきっとこういうことだろうと日頃思う点についてお話しします。
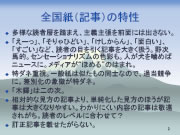
 私は現在の新聞は客観報道だと思います。つまり、発表者が発表したことを全部そのまま書いても責められることはない、自分のリスクはないという観点で書かれることが非常に多いです。ですから、自分の意見や考えよりも第一報をそのまま丸写しにして書くということはごく当たり前に行われています。
私は現在の新聞は客観報道だと思います。つまり、発表者が発表したことを全部そのまま書いても責められることはない、自分のリスクはないという観点で書かれることが非常に多いです。ですから、自分の意見や考えよりも第一報をそのまま丸写しにして書くということはごく当たり前に行われています。
また、センセーショナリズムというものがどんどん強くなってきています。週刊誌の影響を相当受けるようになっています。したがって「面白い」とか「それはひどい」というところにパッと飛びつく傾向があり、「とても良い話だな」というような話題はあまり大きく取り上げられません。
それから、記事を書くときに詳しく調べていろいろな角度から問題点を切ると、一体この記事は何を言っているのだということになります。ですから、記事はなるべく単純化してどこかに焦点を当てて書いた方が大きくなるという傾向があります。調べれば調べるほど記事が小さくなるというのが私の経験則です。
また、「訂正記事を載せたがらない」という傾向があります。これは極端な例でありすべてに通じることではありませんが、私が一度だけ経験したことです。私が同僚の記事について訂正記事を載せる必要があるとデスクに話したところ、「君、その記事について相手が抗議してきたのか?」とデスクに聞かれ、「いえ、してきていません。私が読んで明らかに間違っていると思うから言っているのです。」と答えました。すると「それなら訂正記事は載せなくて良い」ということをデスクから言われました。これには非常にカッとなりました。
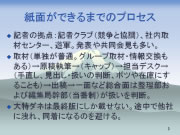
 新聞の場合、記者はいろいろな形で取材をします。まず記者クラブですが、これは競争と協調の関係にあります。発表ものなどはもっぱら協調して扱います。新聞社によっては社内に遊軍なるものがあり、そこから動員するというような形態もあります。発表や共同会見もたくさんあり、定期的に行われるものもあります。例えば、大企業のトップや役所の事務次官の会見などの共同会見は非常に多いです。取材も多様です。ベースは一人で取材し、一人で記事を書くというものですが、政治のように様々な政治家の断片的な情報をつなぎ合わせて一本の記事にしていくというような形もあります。そして原稿を書き、デスクがそれをどういう扱いにするかの判断をして出稿になります。したがって、載せるか載せないかということや記事の扱いをどうするかということにおいて、デスクの役割は一線にいる記者以上に大きなものです。また、大特ダネは最終版にしか載せません。他社に漏れないようにこれ以上ないところまで溜めておいてから載せます。日経の朝刊でいえば14版にあたります。記者は満足していますが、通勤電車で通うほとんどのサラリーマンはその記事に気付かず、朝、テレビで聞いたNHKの特ダネだと錯覚することも多いようです。
新聞の場合、記者はいろいろな形で取材をします。まず記者クラブですが、これは競争と協調の関係にあります。発表ものなどはもっぱら協調して扱います。新聞社によっては社内に遊軍なるものがあり、そこから動員するというような形態もあります。発表や共同会見もたくさんあり、定期的に行われるものもあります。例えば、大企業のトップや役所の事務次官の会見などの共同会見は非常に多いです。取材も多様です。ベースは一人で取材し、一人で記事を書くというものですが、政治のように様々な政治家の断片的な情報をつなぎ合わせて一本の記事にしていくというような形もあります。そして原稿を書き、デスクがそれをどういう扱いにするかの判断をして出稿になります。したがって、載せるか載せないかということや記事の扱いをどうするかということにおいて、デスクの役割は一線にいる記者以上に大きなものです。また、大特ダネは最終版にしか載せません。他社に漏れないようにこれ以上ないところまで溜めておいてから載せます。日経の朝刊でいえば14版にあたります。記者は満足していますが、通勤電車で通うほとんどのサラリーマンはその記事に気付かず、朝、テレビで聞いたNHKの特ダネだと錯覚することも多いようです。
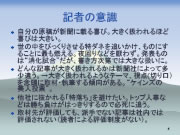
 記者の喜びは、書いた原稿が活字になり大きく扱われることです。ですから、他社と同じ条件となる、発表や共同会見で出てきたものはそれほど重視しません。やはり、特ダネを狙うことがベースにあります。どんな記事が大きく扱われるかは新聞社によって多少違います。この新聞はこういう調子で記事を書くと大きく扱われる、例えば、企業を徹底的に叩くと扱いが大きくなるといったように同じ記事でもデスクに媚びるような形で書く傾向があります。つまり、自分の意見で徹底して書くより、こう書いた方が大きく扱われてよく仕事をしているように見られる、自分自身も大きく扱われて満足するということがあるようです。記者は会社やデスクの判断や価値観に合わせて原稿を作り上げる傾向があるように長年の経験を通じて感じています。
記者の喜びは、書いた原稿が活字になり大きく扱われることです。ですから、他社と同じ条件となる、発表や共同会見で出てきたものはそれほど重視しません。やはり、特ダネを狙うことがベースにあります。どんな記事が大きく扱われるかは新聞社によって多少違います。この新聞はこういう調子で記事を書くと大きく扱われる、例えば、企業を徹底的に叩くと扱いが大きくなるといったように同じ記事でもデスクに媚びるような形で書く傾向があります。つまり、自分の意見で徹底して書くより、こう書いた方が大きく扱われてよく仕事をしているように見られる、自分自身も大きく扱われて満足するということがあるようです。記者は会社やデスクの判断や価値観に合わせて原稿を作り上げる傾向があるように長年の経験を通じて感じています。
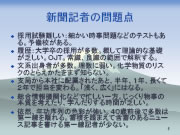
 新聞記者の問題点として感じることを挙げます。まず、新聞記者には大学卒、文系が非常に多いことです。皆さんもご自身を振り返られるとそう思われるかもしれませんが、文系の学生で4年間ものすごく勉強して社会に出てきたという人はそうはいないと思います。ですから、例えば、博士論文を書き基本的な学問の基礎を身につけて社会に出てくるというよりは、社会に出てその場で鍛えられていく、OJT(注、on-the-job-training)で学んでいくことが多いと思います。実は私自身もそうでした。文系の人は理数系のことには非常に弱いです。社会部の記者というと理数系の人はほとんどいないでしょう。したがって、世の中のいろいろな事件で化学物質等が関わった場合、理系の知識があれば当然そのような馬鹿なことは書かないであろうということをうっかり書く可能性があります。文系の新聞記者は、化学物質のリスクの捉え方が庶民感覚である、つまり「こわい」や「危険」、「ダイオキシンと聞いただけで危ない」というふうに思っています。これが普通の文系の新聞記者の感覚でしょう。ですから、化学物質は毒にもなれば薬にもなるというような相対的な評価、あるいは観点をいろいろと設けてみることは、理数の経験者でないとなかなかできないと思います。さらに今の新聞記者は猛烈に忙しいです。最近ではIT関連の仕事も増えてきていますので段々と考える時間が少なくなってきたように思います。昔は暇なときに麻雀ばかりやっていた時代があり、そういう記者がたくさんいました。今はそんな雰囲気は全くありません。皆必死に仕事をしていて、無駄な時間がなくなっています。これは非常にまずいと思います。ですから、自分の関心あるテーマを掘り起こしてさらに勉強するというのは、よほど優秀な方(かた)か、特に自分で志を立てている方を除くとなかなか難しい状況であると感じます。もう1つ、日本の場合、新聞社は依然年功序列の色彩が強いです。ですから、ある年代になると、だいたい一線の記者クラブ等の仕事を離れてデスクになります。私の場合は、記者を14年やってからデスクの仕事に就きました。14年といえば30代半ばです。ちょうど脂がのってきてこれから面白くなるというところで皆卒業しデスクになります。ですから、40代50代になっても記者会見に出て生のニュースを書くというような形の記者は、会社によっては例外的にはいますが、ほとんどいません。このように経験の蓄積が活きてこないという問題がある気がします。
新聞記者の問題点として感じることを挙げます。まず、新聞記者には大学卒、文系が非常に多いことです。皆さんもご自身を振り返られるとそう思われるかもしれませんが、文系の学生で4年間ものすごく勉強して社会に出てきたという人はそうはいないと思います。ですから、例えば、博士論文を書き基本的な学問の基礎を身につけて社会に出てくるというよりは、社会に出てその場で鍛えられていく、OJT(注、on-the-job-training)で学んでいくことが多いと思います。実は私自身もそうでした。文系の人は理数系のことには非常に弱いです。社会部の記者というと理数系の人はほとんどいないでしょう。したがって、世の中のいろいろな事件で化学物質等が関わった場合、理系の知識があれば当然そのような馬鹿なことは書かないであろうということをうっかり書く可能性があります。文系の新聞記者は、化学物質のリスクの捉え方が庶民感覚である、つまり「こわい」や「危険」、「ダイオキシンと聞いただけで危ない」というふうに思っています。これが普通の文系の新聞記者の感覚でしょう。ですから、化学物質は毒にもなれば薬にもなるというような相対的な評価、あるいは観点をいろいろと設けてみることは、理数の経験者でないとなかなかできないと思います。さらに今の新聞記者は猛烈に忙しいです。最近ではIT関連の仕事も増えてきていますので段々と考える時間が少なくなってきたように思います。昔は暇なときに麻雀ばかりやっていた時代があり、そういう記者がたくさんいました。今はそんな雰囲気は全くありません。皆必死に仕事をしていて、無駄な時間がなくなっています。これは非常にまずいと思います。ですから、自分の関心あるテーマを掘り起こしてさらに勉強するというのは、よほど優秀な方(かた)か、特に自分で志を立てている方を除くとなかなか難しい状況であると感じます。もう1つ、日本の場合、新聞社は依然年功序列の色彩が強いです。ですから、ある年代になると、だいたい一線の記者クラブ等の仕事を離れてデスクになります。私の場合は、記者を14年やってからデスクの仕事に就きました。14年といえば30代半ばです。ちょうど脂がのってきてこれから面白くなるというところで皆卒業しデスクになります。ですから、40代50代になっても記者会見に出て生のニュースを書くというような形の記者は、会社によっては例外的にはいますが、ほとんどいません。このように経験の蓄積が活きてこないという問題がある気がします。
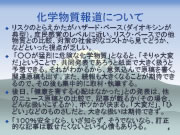
 化学物質に関する報道についていえば、先ほども述べた通り記者は物事を非常に単純に捉えがちです。実は私もそうでした。しかし、いろいろな方の考えを伺ったりしているうちに段々とこれは違うということが分かってきました。その1つには、本があります。例えば、安井さんが中心になって出された本や中西準子さん(注、産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター センター長)がお書きになった本で、リスクについての考え方などが出てきました。私も審議会等でいろいろな大学の先生方と同席してお話をする機会がありましたが、そのようなことについて率直に教えていただくことは残念ながらありませんでした。したがって、単純な考え方をしていた時間が相当長く続いていました。
化学物質に関する報道についていえば、先ほども述べた通り記者は物事を非常に単純に捉えがちです。実は私もそうでした。しかし、いろいろな方の考えを伺ったりしているうちに段々とこれは違うということが分かってきました。その1つには、本があります。例えば、安井さんが中心になって出された本や中西準子さん(注、産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター センター長)がお書きになった本で、リスクについての考え方などが出てきました。私も審議会等でいろいろな大学の先生方と同席してお話をする機会がありましたが、そのようなことについて率直に教えていただくことは残念ながらありませんでした。したがって、単純な考え方をしていた時間が相当長く続いていました。
新聞では真実かどうかは別にして、それが世の中を動かすような記事であれば大きく扱うというところがあります。しかし、記事を載せた後、何年も経ってから、あれは実は問題なかったという発表があってもそのときには担当記者も変わっています。また、問題意識を持って継続して勉強している人はほとんどいません。まず、記者にそういう傾向があると思います。
次に、仮に記事に書いたとしてもそれがニュースとして紙面で大きく扱われるかといえばそうではないでしょう。素人的な感覚では、安全といえば100%安全かということを聞きたがります。例えば、デスクに「そんなことを記事に書いて大丈夫か?100%大丈夫か?」と聞かれ「100%ではありません。」と答えると「それでは危ないじゃないか」ということになり、そこで終わりになります。今のBSE問題ではありませんが、どのように考えるかが非常に難しいところです。実はこういう考え方に日本国民もメディアも慣れていないように思います。
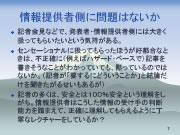
 次に、あえてスライドに書かせていただきますが、「情報提供者側に問題はないか」と言いたいと思います。例えば、最初に役所が「これは大変だ」と発表する際に、発表する人は大きく扱ってもらいたいという意識が無意識にありますから、理解してもらおうとくわしく説明すると思います。しかし、記者もよほどの者でない限り化学物質等についてはよく知りません。ですから、記者は根掘り葉掘り聞いた上で分かりやすい表現にするために話を単純化する、そうすると話の前提条件等が端折られることもあり、ポイントとなる部分だけが大きく載ってしまうということになりかねません。それでも発表する側は大きく扱われればそれで良いということもあり、結果としてオーバーに報道される傾向があるように感じています。
次に、あえてスライドに書かせていただきますが、「情報提供者側に問題はないか」と言いたいと思います。例えば、最初に役所が「これは大変だ」と発表する際に、発表する人は大きく扱ってもらいたいという意識が無意識にありますから、理解してもらおうとくわしく説明すると思います。しかし、記者もよほどの者でない限り化学物質等についてはよく知りません。ですから、記者は根掘り葉掘り聞いた上で分かりやすい表現にするために話を単純化する、そうすると話の前提条件等が端折られることもあり、ポイントとなる部分だけが大きく載ってしまうということになりかねません。それでも発表する側は大きく扱われればそれで良いということもあり、結果としてオーバーに報道される傾向があるように感じています。
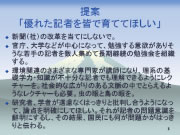
 それから、記事を書くのは新聞記者であり、デスクからこれを書けと言われて出る記事はほとんどありません。普通のコラム的な囲み記事や単独のニュース等も記者が言い出しっぺで書いています。したがって、記者に問題意識があって、長期間フォローしていくということであれば、化学物質の問題に限らず、もう少しメディアのレベルは上がっていくでしょう。それから、現時点でリスクコミュニケーションの話に絡めていうのであれば、新聞社側の改革を当てにしない方が良いと思います。それは百年河清を待つようなものであり、とても無理だと思います。むしろ現実的には、官庁、大学、企業などが中心となって、勉強する意欲がありそうな若手の記者を育てるということをぜひやっていただきたいと思います。新聞記者には勉強する場を提供されれば勉強したくないという人はほとんどいません。ですから、是非長い時間をかけて勉強会をやっていただければと思います。
それから、記事を書くのは新聞記者であり、デスクからこれを書けと言われて出る記事はほとんどありません。普通のコラム的な囲み記事や単独のニュース等も記者が言い出しっぺで書いています。したがって、記者に問題意識があって、長期間フォローしていくということであれば、化学物質の問題に限らず、もう少しメディアのレベルは上がっていくでしょう。それから、現時点でリスクコミュニケーションの話に絡めていうのであれば、新聞社側の改革を当てにしない方が良いと思います。それは百年河清を待つようなものであり、とても無理だと思います。むしろ現実的には、官庁、大学、企業などが中心となって、勉強する意欲がありそうな若手の記者を育てるということをぜひやっていただきたいと思います。新聞記者には勉強する場を提供されれば勉強したくないという人はほとんどいません。ですから、是非長い時間をかけて勉強会をやっていただければと思います。
また、理系の人が新聞記者になることはなかなかありません。ひと昔前は大学を卒業して新聞記者になろうとすると恩師に破門されたというぐらいです。現在の入社試験の問題があまりにも時事問題やひねくれた問題が多いため、理数系の人が普通に入社することが非常に難しいように思います。そこにも問題があるように思います。やはり、理数系の人たちがもっとメディアを志すというように普段から大学の先生にご指導いただければと思います。また、環境問題は実に広い話であり、非常に広範囲のものを多角的に見るという視点が育つような勉強会等を作っていただくと良いと思います。私は経済記者ですが、経済記者としても環境問題は非常に重要であり、環境問題を扱うということは経済問題を扱うのと同じようなところがあります。
最後に、日本では学者の方々は誉めあい、けなすことをしません。書評をみるとだいたい誉めまくっているためあまり意味がないなと感じます。おかしいことはおかしいというふうにきちんと言わなければ、我々国民にも新聞記者にも論点が見えてきません。したがって、何が問題かということを新聞記者が知りたくても分からないという状況があると思います。例えば、ダイオキシンはそんなに危険なものではないとある立派な大学の先生が話されていたので「どうして対外的にそのことを言わないのですか?」と質問したところ、そういうことをいえば後が大変だという回答でした。何が大変かといえば、まずあちらこちらから抗議が来ること、手紙や電話で脅しや何やらがたくさん来るということでした。これは中西準子さんも何かの記事に書かれていていたように思います。ですから、うかつに批判的なことを言うと世の中から叩かれ、それが邪魔になって一時的に仕事ができなくなるという状況に追い込まれることがあるようです。このような点では、日本は成熟していないなと感じます。ですから、研究者や学者の方々がもっとはっきりと批判し合うようになっていただければ、我々記者は問題が分かってくるように思います。以上です。ありがとうございました。
(原科) ありがとうございました。竹居さんのお話に対し、メンバーからの質問等はございますか? 後藤さんどうぞ。
(後藤) 若手の新聞記者に教えてあげようと思っても、勉強もせずに聞きに来て、また、勉強しようというスタンスも全然ないという方が多いのが実情です。今後、インターネット等により大メディアである新聞等がなくなってくる可能性が非常に強いように思いますが、そういう危機感を持って若手を育てるということが経営者の中なら出てこなければ新聞社は潰れてしまうのではないだろうかと思いました。
(原科) 北野さんどうぞ。
(北野) 化学物質の情報については新聞やテレビ等のマスメディアを通じて得ることが多いです。そういう意味でマスメディアの力というものは非常に大きく、重要だと思います。同じ活字メディアでも、例えば雑誌と新聞を比べると、雑誌はだいたいゲラ(下版)を送ってくれるので後で校正ができますが、新聞の場合は一方的にインタビューしただけで記事が書かれてしまいます。それほど緊急性のないものでもゲラを見せてくれないことがあります。また、記者の考えていることがあたかも私の意見のように書かれてしまうことがあります。例えば、記者に「これは開き直りですよね?」と質問され、私が「そういう見方もできますね」といったら「北野は開き直りと言っている」というようになってします。一度ゲラを見せてくれればその辺のニュアンスが変わるように思います。ゲラを見せないということがマスコミ、特に新聞の基本姿勢なのでしょうか?
(竹居) 全体のことは分かりませんが、私の経験ではゲラを見せていませんでした。なぜなら、紙面を作るときには行数等いろいろなことを考えて作るので、見せてコメントを頂いた方に全文を載せろといわれても困ってしまいます。ですから、記者の方で必要な量に圧縮して記事を載せていました。今、北野さんがおっしゃったような要求が多くなれば変わるかもしれませんがそういうことがない限り今まで通りだと思います。
(原科) 私も時々新聞の取材を受けますが、取材前に1回はゲラを見せてほしいと言っておくと、どの新聞社も概ねファックスなどで送ってきてくれます。これが一般的なのかどうかは分かりませんが必ずしもゲラを見せてくれないというわけではありません。ケースバイケースでしょう。崎田さんどうぞ。
(崎田) 私も大学を卒業してから出版社に勤務したので、いろいろなことを勉強する時間もなく働いていた若い頃を思い出しながらお話を伺っていました。スライド8の最後に「優れた記者を皆で育てて欲しい」と提案してくださっていて大変有り難いと思います。しかし、昔のことを思い返してみると、メディアにいるとメディアの自立を尊ぶような気持ちが記者や編集者自身に強かったと思います。どこかからの情報よりも自分が調べてきた情報を大事にするというところがあったような気がします。このように皆で育て合うような状況にするにはどのような主体がこのようなことを企画すれば良いのか、ご提案やご意見があれば教えてください。
(竹居) 以前、(社)日本環境教育フォーラムの理事長をしている岡島成行さんとお話をしていたときに、彼がこういう問題に関心を持ったのは勉強会がきっかけであるとおっしゃっていました。それはある方が主催する勉強会で、他にも今日、著名な方が参加していたようです。皆が最初から環境問題について関心を持っていたというよりも、そういう勉強会をやろうとおっしゃった方がいたことがきっかけとなり、彼らは今日につながるような勉強をされたと聞きました。もちろん優秀な方に声をかけられたのだと思いますが。私がここで提案していることは、岡島さんの話が記憶にあったので書きました。実際、私が論説などを書いていた時もいろいろなところで勉強会がありました。しかし、それらは私がかなり年をとってからの話であり、もっと若いときにやる気のある人間を集めて勉強会をするということはとても良いことだと思います。やる気のある人間を見抜くのは皆さんです。どういう主体がこのようなことを企画すれば良いのかといえば、例えば、後藤さんの団体は優れた仕事をされていますので後藤さんの団体がベースになっていろいろな方を講師に集め、何人かの若手の記者たちに勉強会を開いていただくと、彼らはいろいろな問題に目が見開かれていくように思います。
(原科) 中塚さんどうぞ。
(中塚) 質問ではありませんが、記者を育ててほしいということに関連して、最近お茶の水女子大学で始まった講座についてご紹介します。パンフレットは部数の都合もありメンバーにのみお配りしています。(化学・生物総合管理の再教育講座 http://www.ocha.ac.jp/koukai/saikyouiku/index.html#)
講師には環境・安全に関わる行政や企業、NPOなど多岐にわたる方々をお招きしています。学生や社会人その他市民の方などどなたでも参加できますのでぜひご検討ください。
(竹居) 私が言う勉強会は少人数、つまり自分が話を聞いておかしいと思うことをその場で質問できるという形態です。取材の中で分からないことを質問し、自分のロジックの中に取り込み納得し、自分の世界を作るというものです。ですから、今おっしゃったような大人数の勉強会とはちょっと違うかもしれません。数人ぐらいの少人数の勉強会でなければ効果は上がらないように思います。
(原科) それはきっと小さなゼミのようなものですね。有田さんどうぞ。
(有田) 消費者団体にも記者の方が取材に来られます。なかには、取材をかねてお勉強に来られているような方もいます。何時間もかけるのであれば自分の足でいろいろなところで勉強してくださいというふうに最近も言いました。ですから、わざわざ勉強する方がいらっしゃるのかなというような疑問を持ちます。
もう1点は、専門家の方々にはいろいろなところで堂々と議論をしていただいて、それを参考に消費者は判断したいと思っています。しかし、言葉がすれ違ってコミュニケーションがとれず、時には単純に喧嘩腰になってしまい、科学的な内容とは関係のないところで議論が始まってしまうこともあります。どういうところで正々堂々と議論をすれば良いとお考えでしょうか?
(竹居) 勉強していない記者がたくさんいることはその通りです。それは否定しません。だからこそ、よく人を見て成長株だと思う人間を選んでいただければと思います。勉強していないということは随分私もいろいろな方からいわれました。しかし、それは今私がお話ししたことで解決していただければと思います。もう1点の専門家間のコミュニケーションの云々については、新聞記者はいろいろなところを回ってくるので、ある意味でそれぞれの専門家の話をある程度理解できる素地があります。浅く広くですが、いろいろな問題についていろいろな観点で考えることができます。専門家の中には話を聞いていると必ず専門用語が入ってきて素人には何を言っているのかが分からないということがあります。つまりコミュニケーションのしかたが分かっていないということです。やはり、相手に分かってもらうということが第一であり、いかに分かってもらえるかということを考えながらお話をすることが基本だと思います。そういう意味では、縦割りで、たこつぼに入って、みんな他人のことは関係ないという日本の風土を変えなければいけないと思います。ですから、そういうコミュニケーションについてももっと他流試合をやって厳しく切磋琢磨しなければこの社会はあまり発展しないように思います。
(原科) ありがとうございました。今のお話はこれからにもつながる問題ですね。この円卓会議自体もそういうものだと思います。それでは続いて音さんから、「科学報道とメディアリテラシー」についてお話をいただきたいと思います。
(音)


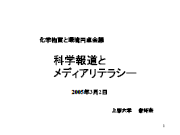
 上智大学の音です。本日はお招きいただき、ありがとうございます。私自身は、化学物質や化学物質情報の専門家ではありません。専門はメディア・コミュニケーション、特にメディアとオーディエンスの関わりを専門としています。ですから、本日お話する内容もやや広い領域の話になるかと思います。これまでお二方のご発表やご質問を伺っていて、何となくこそばゆい感じでした。記者たちが専門家に取材し、その専門家の話を噛み砕いて普通の人々に分かるように説明することがメディアの役割であり、専門家が専門的な知識を持っていることは当たり前のことです。記者に求められるのはその知識を噛み砕き、多くの人々に理解させる仕掛けだと思います。化学物質情報とメディアとの関係を考える時、専門家の方々の話を広く世間に広げるためのプロセスが非常に大事だと思っています。私の話はその領域からです。
上智大学の音です。本日はお招きいただき、ありがとうございます。私自身は、化学物質や化学物質情報の専門家ではありません。専門はメディア・コミュニケーション、特にメディアとオーディエンスの関わりを専門としています。ですから、本日お話する内容もやや広い領域の話になるかと思います。これまでお二方のご発表やご質問を伺っていて、何となくこそばゆい感じでした。記者たちが専門家に取材し、その専門家の話を噛み砕いて普通の人々に分かるように説明することがメディアの役割であり、専門家が専門的な知識を持っていることは当たり前のことです。記者に求められるのはその知識を噛み砕き、多くの人々に理解させる仕掛けだと思います。化学物質情報とメディアとの関係を考える時、専門家の方々の話を広く世間に広げるためのプロセスが非常に大事だと思っています。私の話はその領域からです。
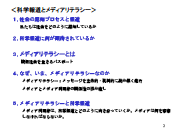
 メディアとコミュニケーションの関わりの中で私たちは社会をどう認知するのかということですが、現代社会では、私たちが世の中で起こっているすべてのことを知ることは無理です。多くの場合、特にメディアを通じて社会の様子を知ることになります。しかし、注意しなければいけないことがあります。例えば、読者は、新聞記事を見たとき、たくさんの記事の中から見出しを見てこれを読もうとステップして新聞記事の内容に入っていきます。事前に自分で知識を持っているところであれば、読んでいる内容についてプラス、マイナスの評価をする作業を行います。逆に自分があまり知らないことについては関心がないといって読み飛ばすかもしれませんし、またはその記事から新しいことを知るかもしれません。ただ最初に読者が記事を読むときには予備知識がなければ分からないことがたくさんあります。このように世の中のことを同じような形で情報として接したときに読者は何でも情報を手に入れるわけではありません。自分が特によく知っている部分から入っていきがちですし、そうではない部分に関しては最初の段階でスキップしてしまうことも随分あります。
メディアとコミュニケーションの関わりの中で私たちは社会をどう認知するのかということですが、現代社会では、私たちが世の中で起こっているすべてのことを知ることは無理です。多くの場合、特にメディアを通じて社会の様子を知ることになります。しかし、注意しなければいけないことがあります。例えば、読者は、新聞記事を見たとき、たくさんの記事の中から見出しを見てこれを読もうとステップして新聞記事の内容に入っていきます。事前に自分で知識を持っているところであれば、読んでいる内容についてプラス、マイナスの評価をする作業を行います。逆に自分があまり知らないことについては関心がないといって読み飛ばすかもしれませんし、またはその記事から新しいことを知るかもしれません。ただ最初に読者が記事を読むときには予備知識がなければ分からないことがたくさんあります。このように世の中のことを同じような形で情報として接したときに読者は何でも情報を手に入れるわけではありません。自分が特によく知っている部分から入っていきがちですし、そうではない部分に関しては最初の段階でスキップしてしまうことも随分あります。
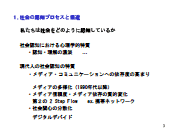
 「第2の2 Step Flow」について、「第2」については後ほど説明します。2 Step Flow、つまり2段階の流れとは、ラザースフェルド(注、Paul Lazarsfeld;米国の社会学者)が1940年代にマス・コミュニケーションのメッセージを受け手がどのように受け取るのかという研究で用いた用語です。当時は、ラジオや新聞といったマスメディアが大衆社会の中に広く拡がり始めた時代でした。私たちはメディアからどのようにメッセージを受け止めるのかについてですが、例えば新聞記事を例に挙げると、新聞で手に入れたニュースをより噛み砕いて説明してくれる人がとても大事になります。私たちは日頃から新しい情報を手に入れると、それにはどういう価値があるのかということを、特に感度の優れた人に聞くことがあるかと思います。例えば、ファッションで考えてみましょう。この背広はかっこいいかどうかを自分の配偶者に聞くというのもその1つかもしれません。先ほど、小出さんが自分で科学番組を作ったときにそれがどういう反応をするのかというアンテナになる方が知り合いにいると話されましたが、それも当てはまります。このように、自分である種のアンテナ(意見を決めるのに影響力を持つ人)を持っているということをラザースフェルドは1940年代に話しました。その後、1960年代に入りテレビが非常に普及しました。テレビのメッセージは非常に感覚的な部分があり、また、チャンネルをひねればすぐ見えるということでストレートに情報が入ってきやすいという状況ができました。感覚的にこれが良い、あちらが良いと思ってしまいます。例えば、ニュースキャスターの顔が何となく好きなのでそのチャンネルを見てしまうというような話が分かりやすいかと思います。では、現代はどうかというと、私はここにお集まりの皆さんより相当年齢が低い学生たちと日頃付き合っています。学生たちの様子を見ると彼らはひょっとして「第2の2 Step Flow」という形のメディア・コミュニケーションをしているのかもしれません。私の隣の研究室の先生はある研究をしました。それは「学生たちは安室奈美恵が離婚をしたニュースをどういうふうに手に入れたのか」というものでした。結果はラジオやテレビよりも携帯電話でそのメッセージが先に流れたということでした。つまり、先ほどの話でいえばマスメディア、マス・コミュニケーションで報道機関がメッセージを提供するというような形の流れではない情報の流れが広がっています。そこには、既存のマスメディアが提供していたような情報を流してくれる新たなシステムが生成しつつあるのかも知れません。それが第2の2stepと表記した意味です。
「第2の2 Step Flow」について、「第2」については後ほど説明します。2 Step Flow、つまり2段階の流れとは、ラザースフェルド(注、Paul Lazarsfeld;米国の社会学者)が1940年代にマス・コミュニケーションのメッセージを受け手がどのように受け取るのかという研究で用いた用語です。当時は、ラジオや新聞といったマスメディアが大衆社会の中に広く拡がり始めた時代でした。私たちはメディアからどのようにメッセージを受け止めるのかについてですが、例えば新聞記事を例に挙げると、新聞で手に入れたニュースをより噛み砕いて説明してくれる人がとても大事になります。私たちは日頃から新しい情報を手に入れると、それにはどういう価値があるのかということを、特に感度の優れた人に聞くことがあるかと思います。例えば、ファッションで考えてみましょう。この背広はかっこいいかどうかを自分の配偶者に聞くというのもその1つかもしれません。先ほど、小出さんが自分で科学番組を作ったときにそれがどういう反応をするのかというアンテナになる方が知り合いにいると話されましたが、それも当てはまります。このように、自分である種のアンテナ(意見を決めるのに影響力を持つ人)を持っているということをラザースフェルドは1940年代に話しました。その後、1960年代に入りテレビが非常に普及しました。テレビのメッセージは非常に感覚的な部分があり、また、チャンネルをひねればすぐ見えるということでストレートに情報が入ってきやすいという状況ができました。感覚的にこれが良い、あちらが良いと思ってしまいます。例えば、ニュースキャスターの顔が何となく好きなのでそのチャンネルを見てしまうというような話が分かりやすいかと思います。では、現代はどうかというと、私はここにお集まりの皆さんより相当年齢が低い学生たちと日頃付き合っています。学生たちの様子を見ると彼らはひょっとして「第2の2 Step Flow」という形のメディア・コミュニケーションをしているのかもしれません。私の隣の研究室の先生はある研究をしました。それは「学生たちは安室奈美恵が離婚をしたニュースをどういうふうに手に入れたのか」というものでした。結果はラジオやテレビよりも携帯電話でそのメッセージが先に流れたということでした。つまり、先ほどの話でいえばマスメディア、マス・コミュニケーションで報道機関がメッセージを提供するというような形の流れではない情報の流れが広がっています。そこには、既存のマスメディアが提供していたような情報を流してくれる新たなシステムが生成しつつあるのかも知れません。それが第2の2stepと表記した意味です。
先ほどのやりとりをお聞きしていて非常に興味を持ったことがあります。それは、ここにいらっしゃる多くの方々がひょっとするとオーソドックスなジャーナリズムやマスメディアのある種の無謬性に対して、非常に高い価値を置いているのではないかなということです。私も既存のマスメディアの社会的機能に非常に高い価値を置いています。ただ、今のメディアの状況から考えてみると、私たちの身の回りには相当違うものがたくさんあるあります。例えば、放送では24時間、新聞ではその日の紙面、40ページなら40ページという限定された中でニュースバリューを決めています。一方、インターネットでは大量に情報を流しても全然かまいません。米国では24時間のコートチャンネル(注、裁判中継を放送する番組)があります。こういった状況がもたらした結果の1つとして、メディアに対する信頼度や依存度が質的に変化してきたという見方ができるのではないかと思います。2つ目には、携帯ネットワークに見られるようなメディアの利用などメッセージの受け取り方が変わってきたことが挙げられます。3つ目に、社会関心が明らかに分散化していることは間違いありません。重要なことは社会関心が分散化しているときの共通認識、つなぐ装置としてオーソドックスなジャーナリズム、例えば、新聞や放送などはますます意味を持ってくる部分があるように思います。デジタルデバイド、これには2つの意味があります。新しいメディアに対する接触のしかたや使い方が分からない人たち、使える人と使えない人の差が出てきたということが1つです。もう1つは関心のない情報をあまり入手しようとしないという人たちが増えてきていることもまた間違いありません。このような状況があります。
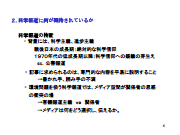
 そのような中で、科学報道に対して何が期待されているのかということを考えてみました。背景には科学主義、進歩主義があるのかもしれません。これは私の若干感覚的なところですが、戦後日本の高度経済成長期には科学報道に対するある種の科学信仰が付随していたように思います。それが1970年代の低成長期以降は、特に公害報道に見られるように科学信仰に対する疑義の芽生えがメディアの中でも非常に強くなったと思います。そんなこともあって記事に求められるのは、作り手たち、書かれ手たちの熱き思いを噛み砕き、多くの人々に分かりやすく説明することだと思います。専門的な内容を平易に説明することがメディアに求められています。先ほどの皆さんのやりとりを聞いていると書かれ手側にも読み手側にも不満が渦巻いており、メディアは今そこで批判を受けているのかなという印象を持ちました。ただ私からすれば、別の見方もできるように思います。環境問題を扱う科学報道については先ほどのお二人の発表から今のメディアが持つ内部的な問題をご報告していただけたと思います。一方、メディア空間をどのように捉えるのかということでいえば、メディア政治学を研究したハロルド・ラスウェル(注、Harold D.Lasswell;米国の政治学者)はメディアの社会的機能を3つ挙げています。Teacher(ある特定のことを教える)、Watcher(環境監視、社会監視)、これはジャーナリズムの機能として非常に分かりやすいと思います。もう1つは、Forum(話し合う、議論をやりとりする)です。言うなれば、環境問題1つにしても多くの人がそこでぶつかり合ってやりとりをするという形になっているのかということは議論する必要があります。そこで議論する人々にはそれぞれバックグラウンドがあり、ある種の力のぶつかり合いがそのForumの中で行われていると思います。先ほど、お二人が率直にお話してくださったメディア自体が持っている特色がその表現においてはいろいろな形で出てくると思います。例えば、竹居さんが「新聞はニュース価値が大事である」とか、「やはりスクープはとりたい」とおっしゃっていましたが、メディアが持っている特色が、Forumの中でぶつかって出てくるという状況がでていると思います。
そのような中で、科学報道に対して何が期待されているのかということを考えてみました。背景には科学主義、進歩主義があるのかもしれません。これは私の若干感覚的なところですが、戦後日本の高度経済成長期には科学報道に対するある種の科学信仰が付随していたように思います。それが1970年代の低成長期以降は、特に公害報道に見られるように科学信仰に対する疑義の芽生えがメディアの中でも非常に強くなったと思います。そんなこともあって記事に求められるのは、作り手たち、書かれ手たちの熱き思いを噛み砕き、多くの人々に分かりやすく説明することだと思います。専門的な内容を平易に説明することがメディアに求められています。先ほどの皆さんのやりとりを聞いていると書かれ手側にも読み手側にも不満が渦巻いており、メディアは今そこで批判を受けているのかなという印象を持ちました。ただ私からすれば、別の見方もできるように思います。環境問題を扱う科学報道については先ほどのお二人の発表から今のメディアが持つ内部的な問題をご報告していただけたと思います。一方、メディア空間をどのように捉えるのかということでいえば、メディア政治学を研究したハロルド・ラスウェル(注、Harold D.Lasswell;米国の政治学者)はメディアの社会的機能を3つ挙げています。Teacher(ある特定のことを教える)、Watcher(環境監視、社会監視)、これはジャーナリズムの機能として非常に分かりやすいと思います。もう1つは、Forum(話し合う、議論をやりとりする)です。言うなれば、環境問題1つにしても多くの人がそこでぶつかり合ってやりとりをするという形になっているのかということは議論する必要があります。そこで議論する人々にはそれぞれバックグラウンドがあり、ある種の力のぶつかり合いがそのForumの中で行われていると思います。先ほど、お二人が率直にお話してくださったメディア自体が持っている特色がその表現においてはいろいろな形で出てくると思います。例えば、竹居さんが「新聞はニュース価値が大事である」とか、「やはりスクープはとりたい」とおっしゃっていましたが、メディアが持っている特色が、Forumの中でぶつかって出てくるという状況がでていると思います。
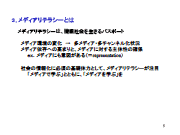
 おそらく、すこしは聞いたことはあるけれども、あまりよく知らないというのがこれからお話しする「メディアリテラシー」という言葉かもしれません。皆さんに手を上げていただきたいのですが、「メディアリテラシー」という言葉を以前から知っているという方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。周りを少し見渡していただけますか?ありがとうございます。手を上げていただけたことは、それぞれの方に意思表明をしていただけたということですし、周りを見ていただいて、この部屋の中での世論がどのように分布しているのかということをご覧いただきました。多くの方々はメディアリテラシーという言葉を聞いたことがないということが分かりました。私は日頃、メディア・コミュニケーションの領域で授業をやっていますし、そういうことを学び、研究している学生たちとやりとりをしていますので、多くの場合はメディアリテラシーという言葉を学んでいる人たちと付き合っています。つまり、今日私はそうではない社会に遊びに来ているということだと思います。そうなると何をしなければいけないかといいますと、より噛み砕いてこの言葉を説明しなければいけないということです。ここはおそらく科学報道や化学物質に関する情報を非常によく知っている世界であり、メディアリテラシーに関してあまり知らない世界です。あまり知らない方向けに説明をしなければいけないということが既存のマスメディアに問われる役割です。メディアリテラシーの定義は研究者によっても違いますが、私は「メディアから伝えられるメッセージというものを批判的、主体的に読み解く能力」と定義しています。研究者によってはこれを「運動」だと捉える方もいますし、「表現能力」と捉える方もいます。
おそらく、すこしは聞いたことはあるけれども、あまりよく知らないというのがこれからお話しする「メディアリテラシー」という言葉かもしれません。皆さんに手を上げていただきたいのですが、「メディアリテラシー」という言葉を以前から知っているという方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。周りを少し見渡していただけますか?ありがとうございます。手を上げていただけたことは、それぞれの方に意思表明をしていただけたということですし、周りを見ていただいて、この部屋の中での世論がどのように分布しているのかということをご覧いただきました。多くの方々はメディアリテラシーという言葉を聞いたことがないということが分かりました。私は日頃、メディア・コミュニケーションの領域で授業をやっていますし、そういうことを学び、研究している学生たちとやりとりをしていますので、多くの場合はメディアリテラシーという言葉を学んでいる人たちと付き合っています。つまり、今日私はそうではない社会に遊びに来ているということだと思います。そうなると何をしなければいけないかといいますと、より噛み砕いてこの言葉を説明しなければいけないということです。ここはおそらく科学報道や化学物質に関する情報を非常によく知っている世界であり、メディアリテラシーに関してあまり知らない世界です。あまり知らない方向けに説明をしなければいけないということが既存のマスメディアに問われる役割です。メディアリテラシーの定義は研究者によっても違いますが、私は「メディアから伝えられるメッセージというものを批判的、主体的に読み解く能力」と定義しています。研究者によってはこれを「運動」だと捉える方もいますし、「表現能力」と捉える方もいます。
メディアリテラシーが世界的に注目されるようになったのは、私たちが社会を知るにあたってその情報を自分の目や耳で直接見たり聞いたりするよりも、圧倒的にメディアを通じてその情報を得ているという状況があるからです。もう1つは、メディアということ、つまり、携帯電話でいえば最近は映像も出ますが圧倒的に音声ですし、テレビでいえば、映像と音声となります。新聞は文字だけです。となるとメディアによって表現の違いが当然そこにでてきます。例えば、臭いをテレビで表現するとか温度を表現するということは非常に難しいというようにメディアもそれぞれの特色を持っています。その特色を理解しながらメディアメッセージを受け取らなくてはいけません。そういう情報化が進んでいく社会が今日私たちが住む社会であるということがメディアリテラシーという考え方の背景にあるのです。ドイツにおいて、メディアリテラシーというのは情報社会を生きるパスポートだという言い方がされています。当然のことですが、メディアにはメディアの独特なメッセージの伝達手法があります。それは、お二人に紹介していただいた部分とも重なっているように思いますが、メディアメッセージもある種の表現の意図があるということです。ニュース価値のあるものを一面に載せたいとか長く取り上げたいというようなことは意図的ですが、意図的ではない、つまり送り手側が意図しないけれども意図的になってしまうものがよくあります。
竹居さんのお話にありましたように、新聞記者には圧倒的に四大卒が多いのが事実です。このことから、メディアで提供されるメッセージがある特定の層の教育や思考が反映される場合があります。私は「メディアにも意図がある(=representation)」と書きましたが、representationには意図的な表現だけではなく、社会的なバックグラウンドで意図しないうちに表現してしまう場合が起こります。例えば、メディアの1つの機能である「社会の環境監視=watcher」から考えた場合、スクープはとらなければいけないという社会的な機能を使命として持っているときに、もう片方でスクープに非常に傾斜する場合というのは、当然あるように思います。逆の言い方をすれば、メディアとはそういうものだと突き放して考える方がより良いのではないか、メディアリテラシーはこのような意図も持っているように思います。つまり、情報化社会が進む中で基礎体力としてメディアリテラシーが注目されたのはメディアで社会を学ぶということだけでなく、メディア自体がどのようなものなのかを学ぶ必要があるということです。つまり、私たちが世の中を知るときにメディアを通じて知るのであれば、そのメディアにどのような特性があるのかということを知って付き合っていくことが大事なのだと思います。
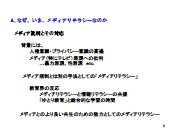
 この10年の間、日本の中でもメディアリテラシーの重要性が非常に活発に論じられるようになりました。それは、人権意識やプライバシーの高揚、メディア表現、特にテレビへの批判が高まった一方で、メディア規制をするのではなくメディアメッセージを受け取る一人一人の抵抗力を高める必要があるということがきっかけでした。そして、教育の中でメディアリテラシーを取り入れようという活動が起こりました。日本ではカナダ、オーストラリア、英国等の事例を学びながらメディアリテラシーの論議が進んできたという状況があります。
この10年の間、日本の中でもメディアリテラシーの重要性が非常に活発に論じられるようになりました。それは、人権意識やプライバシーの高揚、メディア表現、特にテレビへの批判が高まった一方で、メディア規制をするのではなくメディアメッセージを受け取る一人一人の抵抗力を高める必要があるということがきっかけでした。そして、教育の中でメディアリテラシーを取り入れようという活動が起こりました。日本ではカナダ、オーストラリア、英国等の事例を学びながらメディアリテラシーの論議が進んできたという状況があります。
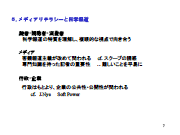
 最後に、メディアリテラシーと科学報道ということをつなぎ合わせて考えてみます。読者、視聴者、消費者側にとって大事なことは、科学報道の特質を理解し、複眼的な視点で向き合っていくことだと思います。言い換えると、分かりにくい科学報道に対しては拒否反応すべきだということです。また、ある特定の視点だけで記事を読むのではなく、複数のものを見ていく、つまり、メディアの特性やメディアメッセージがどういうふうに作られているのかということを理解しながら、それと向き合っていく必要があるように思います。言うなれば、記事やニュースに対して感激しながら見る一方で、冷めた視点も持つ必要があるということです。それから、メディアの側では、改めて客観報道主義というものが問われると思います。もちろん客観報道主義というものは完全無欠だということではありません。記者一人一人にも意思はありますし、新たな視点を提供しようとするでしょう。しかし、もう片方で事実に基づいた形でメッセージを提供することが問われるように思います。また、専門知識を持った記者の重要性が出てきています。NHKも日経もそうでしょうが、大学を卒業して記者になり、まずは支局で記事を書く練習をする。そして何年か経つと一人前の記者になるというようなトレーニングをしています。それをOJT(注、on-the-job-training)といいます。私が所属している上智大学には新聞学科があります。新聞とは、Newspaperの新聞ではありません。メディア・コミュニケーションの方です。もともとは戦前に記者養成としてできた学科です。今私たちが議論していることは、例えば米国のジャーナリズムスクールと同じような形でミッドキャリアのジャーナリストを養成することが大事なのではないかということです。つまり、専門職の記者が養成される必要があるように思います。これは米国ではよく行われています。先ほど、40代でデスクになり現場から離れるという話がありましたが新聞社や放送局を見ていますと30代半ばで海外留学を希望する記者の方々が随分いるように思います。日本は遣隋使以来の外国信仰があり、米国の大学院留学をして箔を付けるというようなことがあります。しかし、そうではなく例えば、総合大学のようなところに籍を置き、それぞれの記者が専門性をより高められるような再トレーニングの場を大学が提供しなければいけないのではないかということです。大学のなかでも、少なくとも今までとは違ってもう少し社会に広く公開し、そこで情報の受信、発信ができることが大事なのではないかという議論が、しばしば行われるようになっています。
最後に、メディアリテラシーと科学報道ということをつなぎ合わせて考えてみます。読者、視聴者、消費者側にとって大事なことは、科学報道の特質を理解し、複眼的な視点で向き合っていくことだと思います。言い換えると、分かりにくい科学報道に対しては拒否反応すべきだということです。また、ある特定の視点だけで記事を読むのではなく、複数のものを見ていく、つまり、メディアの特性やメディアメッセージがどういうふうに作られているのかということを理解しながら、それと向き合っていく必要があるように思います。言うなれば、記事やニュースに対して感激しながら見る一方で、冷めた視点も持つ必要があるということです。それから、メディアの側では、改めて客観報道主義というものが問われると思います。もちろん客観報道主義というものは完全無欠だということではありません。記者一人一人にも意思はありますし、新たな視点を提供しようとするでしょう。しかし、もう片方で事実に基づいた形でメッセージを提供することが問われるように思います。また、専門知識を持った記者の重要性が出てきています。NHKも日経もそうでしょうが、大学を卒業して記者になり、まずは支局で記事を書く練習をする。そして何年か経つと一人前の記者になるというようなトレーニングをしています。それをOJT(注、on-the-job-training)といいます。私が所属している上智大学には新聞学科があります。新聞とは、Newspaperの新聞ではありません。メディア・コミュニケーションの方です。もともとは戦前に記者養成としてできた学科です。今私たちが議論していることは、例えば米国のジャーナリズムスクールと同じような形でミッドキャリアのジャーナリストを養成することが大事なのではないかということです。つまり、専門職の記者が養成される必要があるように思います。これは米国ではよく行われています。先ほど、40代でデスクになり現場から離れるという話がありましたが新聞社や放送局を見ていますと30代半ばで海外留学を希望する記者の方々が随分いるように思います。日本は遣隋使以来の外国信仰があり、米国の大学院留学をして箔を付けるというようなことがあります。しかし、そうではなく例えば、総合大学のようなところに籍を置き、それぞれの記者が専門性をより高められるような再トレーニングの場を大学が提供しなければいけないのではないかということです。大学のなかでも、少なくとも今までとは違ってもう少し社会に広く公開し、そこで情報の受信、発信ができることが大事なのではないかという議論が、しばしば行われるようになっています。
先ほどから既存のメディアに対して批判的なご意見がありましたが、逆に私の知っている情報をいいます。おそらくメディアにおける採用システム自体は随分変わってきていると思います。中途記者が随分増えています。終身雇用制ではない形、自分の専門的な知識を持ってステップやスキップしていく人々が増えてきています。このような状況が今すでに起こっています。そんなこともあり専門知識を持った記者の重要性を申し上げましたが、もう片方で将来性は真っ暗ではないようというふうにも思っています。
最後に、行政や企業はもとより、企業の公共性や公開性が問われる時代です。クリントン政権時に国防次官補だったジョセフ・ナイ(注、Joseph S. Nye, Jr.;米国の国際政治学者)が「Soft Power」という本を出版し世界的に話題になりました。彼はこれからの政治学においてハードのパワーではなく、ソフトのパワー、つまり文化が非常に重要だと論じています。もう片方でそこで非常に問われることは公開性であるとも言っています。誰にでも説明ができるようにオープンにすることが問われます。その説明のしかたについては、先ほどジャーナリズムは批判ばかりするという言い方がありましたが、逆の言い方もできるように思います。それは、メディアに対してうまく説明することが大事なのではないかということです。もちろんメディア側も謙虚に聞くことが大事です。オーディエンス側はメディアから伝わってくるものに対してちょっと愛を混ぜながらこれは大丈夫かなと見ることも大事だと思います。そのことを論理的に示している言葉がメディアリテラシーだとご理解いただければと思います。私の発表は以上です。
(原科) ありがとうございました。音さんのお話に対し、メンバーからの質問等はございますか?岩本さんどうぞ。
(岩本) お話の中にあったTeacher、Watcher、Forumに非常に感銘を受けました。竹居さんのお話に訂正記事は載せないとありましたが、言ってみれば従来のマスメディアは一方通行だったわけです。私は以前おかしいなと思った記事に対して、受取人証明書付きで編集局長宛に数回手紙を出しましたが一度も回答をもらえませんでした。今後メディアが多様化していく中で、双方向の議論というものが必要になっていく、そういう意味でForumの位置づけは有意義だと思います。それが互いの緊張感を保ち、また、社会のいろいろな意見が読者にも伝わっていく、そういう試みがこれからのメディアのあり方かなと思います。何十年も続いたメディアのやり方を少しずつ変えていかなければいけないというのが私の感想です。
(原科) 後藤さんどうぞ。
(後藤) 私も大学で非常勤講師をしていますが、新聞を読んでいる学生がほとんどいません。例えば、京都議定書が発効したという話をしても誰も知らないという状況です。「第2の2 Step Flow」という話がありましたが、第1の2 Step Flowのときに、First Stepがラジオやテレビ、新聞でそれから別のメディアになったとおっしゃいました。今でもサラリーマンなどあるレベルの人々は新聞を読んでいますが、そうではないもっと若い人々のFirst Stepが携帯電話や口コミ等であるとすれば、それらの人々にとっての次の2 Stepは何なのでしょうか?
(音) おそらく今までは信頼する装置、社会を束ねる装置がオーソドックスなマスメディアだったように思います。それが今は分散したという状況です。例えば、先ほど安室奈美恵さんの話を出しましたが、安室さんが離婚したということを新聞や雑誌の芸能ニュース等を通じて手に入れるのではなく、その情報について詳しい人が知らせてくれるということが出てきました。これは、メディアが多様化したということだと思います。ですが、だからこそオーソドックスなマスメディアが持っている意味はすごく重要になってくると思います。フロム(Erich Fromm;ドイツの精神分析学者)の著書「自由からの逃走」に、私たちは自由ですと言われると不安になり、世の中のことを少し知っていたいという気持ちになることが書かれています。オーソドックスなマスメディアの接触率は相対的に下がるかもしれませんが、ある種の信頼度が全くなくなるわけではありません。だからこそオーソドックスなジャーナリズムは専門性がすごく問われてくるでしょう。学生たちに何かを調べてくるようにいいますとまずインターネットを利用します。しかし、それは信頼できる情報なのかと聞きますと、彼らは新聞や本を調べます。世の中にそういうものが全く存在しないと思っているわけではありません。小出さんや竹居さんがいらっしゃったマスメディアはすごくきっちりした取材能力があり、トレーニングを受けた記者たちがいることは間違いありません。そのことは若い学生たちもよく分かっています。
(原科) 塚本さんどうぞ。
(塚本) 行政は、日々さまざまなプレスリリースや記者会見等を行い、情報提供の対応をしています。その際、広範囲に及ぶことや専門的なことを極力分かりやすく説明するために努力していますが、なかなかうまくいかないという感じもしています。しかし、情報提供側の立場として、客観性や分かりやすさという点をさらに心がける必要があると思いました。一方、行政の場合は利害関係者が直接関係する場合が多いため、情報提供のやり方が慎重にならざるをえない場合があります。例えば、物不足という問題がある場合、不足しているという事実があまりにも強調されすぎるとその事実を加速化してしまい、大規模な不足状態を起こしかねません。しかし、逆に慎重な言い回しにすると分かりづらくなることもあります。マクロベースでいえば足りていますが、局部的に品不足になっていることを発表すると次は個別攻撃になり、そうなると全体がおかしくなり、その対応に苦労します。しかし、以前記者の方5、6人に集まってもらい、2時間ほどかけて徹底的に状況説明等をしましたら、記者の理解度が極めて高くなり、客観的な報道がなされるようになりました。あおるような話にならなかったので良かったなと思っています。
メディアの責任という問題について、Teacher、Watcher、Forumの中で、特に行政として期待したいことはWatcher、社会への監視です。行政に対する監視も含めて、適切な機能が働くと我々も緊張感を持ってやることが大事だということを再認識します。しかし、ある1つのものに極端化するようなことになると魔女狩り的な話になり、非常に先導的で社会をあおるような状態になりかねません。そうなってしまったときにはいろいろな影響を受ける方がたくさんいます。そういう状況になったときに、メディアの責任というものも若干あるように思います。その点については皆さんのお考えをお聞かせください。
(音) おっしゃることはよく分かります。ただ、オーディエンス側の位置付け方はいろいろあるかと思いますが、私は戦後60年の間にオーディエンスは相当優秀になってきていると思います。例えば、「2ちゃんねる」(注、インターネット上の匿名掲示板)によく接触している子どもたちでも、2ちゃんねるの情報には信頼性がないものも多いということもよく分かっています。そのメディアの持っているある種の信頼度や情報の正確度にグラデュエーション(階級)を付けて接触していると見た方が良いと思います。逆の言い方をすれば、信頼度の高さを売りにしようと考えるオーソドックスなメディアは、そこを自分たちの商品価値だと強く持ってやっています。また、ますますやらざるをえないという状況になってくると思います。極端にいうと、英国などでは他の新聞よりも値段も高い分信頼度も高い情報を提供する「高級紙」があります。それを支える社会があります。日本のメディアにも少しずつそういう状況が出始めているように思います。
(原科) ありがとうございます。ここで10分程度の休憩を挟んだ後、「メディアにおける化学物質問題の取り上げ方」について意見交換を行いたいと思います。
|