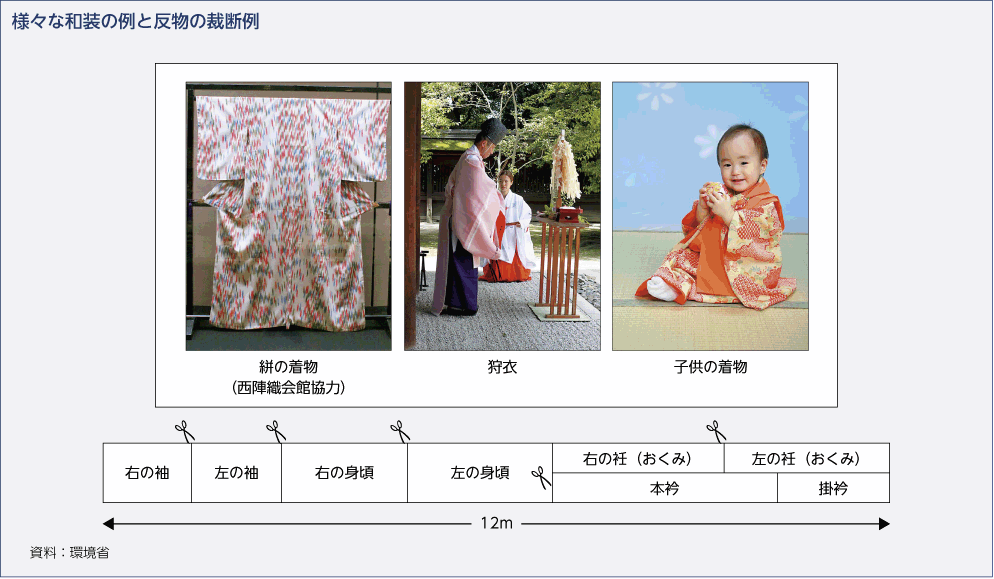
我が国の伝統的な衣服である和服は、反物と呼ばれる長さ12m、幅36cmほどの1枚の布(身長160cmの女性の場合)を裁断し、その直線的なパーツを組み合わせて仕立てられています。
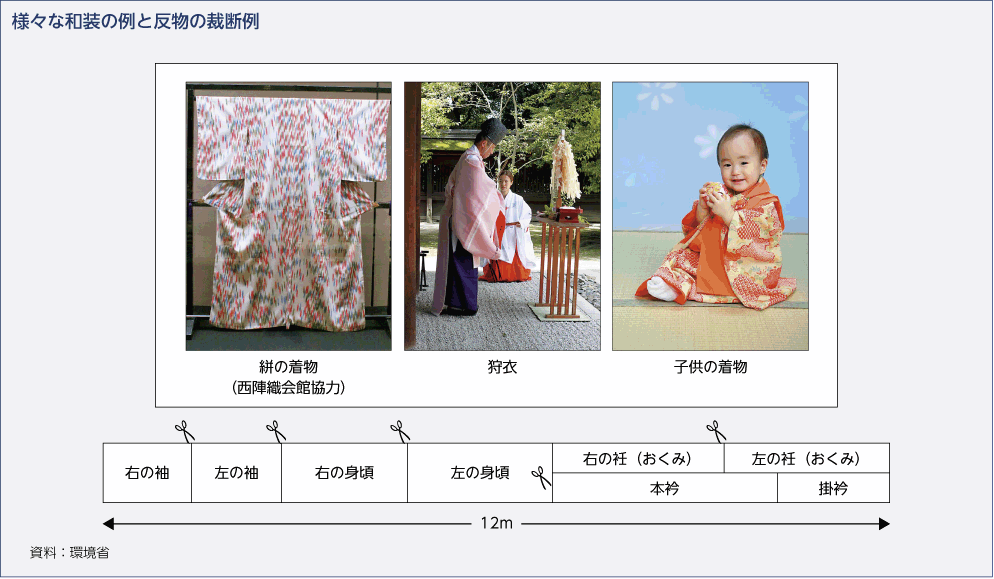
和服は、製品としての和服から、仕立てた糸をほどいて元の反物の状態に戻すことが比較的容易です。また、和服の生地に用いられる素材の一つである絹は、カイコが体内で作り出すとても丈夫な繊維であり、適切な管理をすれば非常に長い年月の使用に耐えるとともに、好みに合わせて色抜きや染め直しもすることができます。
これらの特長から、親の世代に仕立てた和服を、好みや体型に合わせて仕立て直し、子の世代に引き継ぎ、場合によっては孫の世代まで大切に引き継がれることもあります。その後、ついに衣類としての使用に耐え得なくなった生地は、子供の人形や財布などの小物といった身の回りのものに再利用され、絹という貴重な生物由来の資源は最後まで余すところなく使われます。
このような着物の再利用は、江戸時代においては当然のように行われていたとされています。一般的に、非常に高価であった着物を、どうにかして長く着続けようとすることは、モノが持つ本来の値打ちや役割を最後まで使い切ろうとする精神の表れであると考えられます。これは「もったいない」という言葉に集約され、資源の持続可能な利用のための重要な生活の知恵の一つであるといえます。
食品としての農林水産物は、生物多様性を基礎とする生態系サービスがもたらす恵みの重要なものの一つです。私たちは、気候風土にあった食物を手に入れ、料理し、それを食してきました。また、栄養源としての食料だけではなく、春にはふきのとうやタケノコ、夏にはカツオ、秋には栗や柿、冬にはなめこや猪肉など、海や山で季節ごとに手に入る食材を用いた食事を通じて、四季の移ろいを味覚に感じとることも、暮らしの中の楽しみの一つと考えられます。

それぞれの地域でとれた農産物をその地域で消費しようとする取り組みを地産地消、季節の産物をその季節に消費することを旬産旬消といい、近年、環境問題への対応や消費の安心・安全という側面から注目されています。これまで遠隔地まで輸送され消費されていた農産物が、生産者の周辺で消費されるようになると農産物の輸送距離が短くなるため、輸送にかかっていたエネルギーの消費を抑えられます。また、その地域の気候に適した野菜を、適切な時期に栽培することで生産に要するエネルギー消費を抑えることができます。消費者にとっては、農作物の生産が近くで行われることから、いわゆる「顔の見える農業」によって安心を得られるなどのメリットもあります。
現代の建物においては、空調機器などによって室温を人工的に制御するため、建物全体を高断熱・高気密の構造にし、省エネルギーでありながら快適な生活空間を維持しようとする傾向が見られます。
一方、この現代的な設計の方向性は必ずしも我が国の全ての地域に適しているものではなく、たとえば、亜熱帯気候の沖縄においては、戦後、台風による災害やシロアリなどに強い鉄筋コンクリート造りの建築物が主流となり、暑蒸への対応を空調機器による冷房に頼って進められる一方で、建物の気密性が高まったことから室内のカビの発生等の問題を誘発するようになりました。
一方、沖縄の伝統的な住宅は、開放的で風通しのよい構造となっているため、室温の変動は、外気温の変動に機敏に反応して連動する傾向にあります。沖縄においては、このような風通しのよい伝統的な住宅のよさが見直され、近年では、鉄筋コンクリート造りで台風などの災害に強い構造でありながら省エネルギーに配慮した住宅建築のため、吹き抜けの多いピロティ建築や空調機器によらないパッシブクーリングシステムを導入した設計などが注目されています(図2-3-2)。
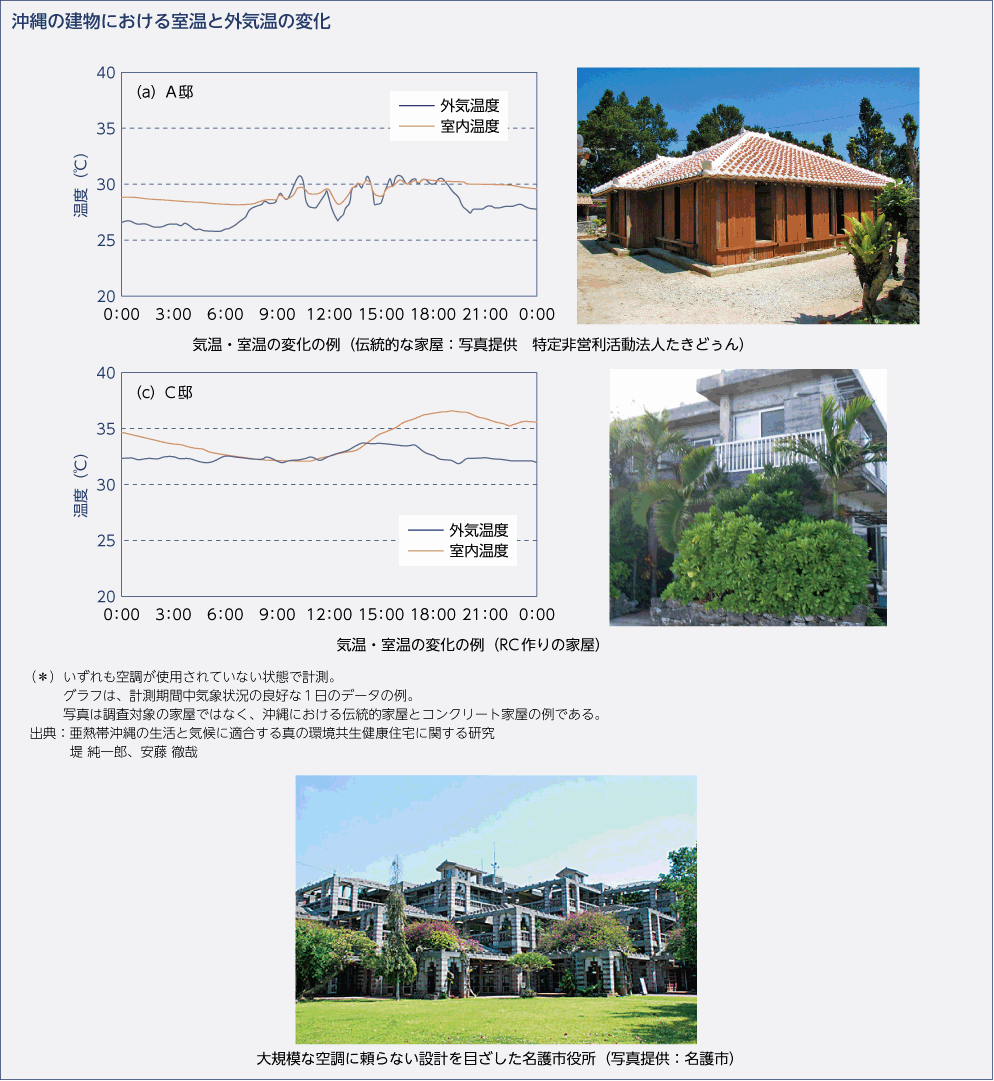
私たちの暮らしは、風土という地域独特の環境条件の中で営まれています。その風土の中で培われた生活の知恵は、その地域にあった伝統的な生活スタイルを形成してきたと考えられます。戦後急速に発達した大量生産、大量流通、大量消費という生活は、必ずしもその地域の風土条件に適したものではなく、環境に負荷を与え、地域の独自性を奪ってきた側面も否定できません。持続可能な社会の実現に向けて現代の生活スタイルを見直すためには、ここで見たような伝統的な生活の知恵が役に立つ可能性は大いにあると考えられるのです。
かつて、我が国には、農耕地、人工林や二次林、ため池や用水路、草原、集落など、長年にわたる農林業などを通じて大小様々に人の手が入った環境で構成される二次的な自然地域が広がっていました。そのような自然地域は里地里山と呼ばれ、私たちは生活に必要な物資をその身近な自然から得ていました。
私たち日本人は、里地里山での暮らしの中で、自らの生活基盤である資源を消費し尽くすことなく、持続可能な利用を続けてきました。こうして育まれた里地里山は、全国一様のものではなく、地域独自の生態系と景観を形成しています。

先の項で見たような生活の知恵は人と自然との関わり合いの中で育まれ、地域の共同体において文化や伝統的な技術として広く根付いていると考えることができます。自然環境の容量や自然の復元力の範囲の中で自然資源を持続的に利用し、また、地域の伝統や文化を伝承してきた例として、大型の獣を捕獲する技術と組織をもち、狩猟を生業としてきたマタギの集落での暮らしが挙げられます。
マタギ集落に住んでいた人々は、通年で狩猟を行っていたわけではなく、夏期の農耕と冬期の狩猟を使い分けながら生活を営んでいたと考えられています。マタギにとっての最大の獲物はツキノワグマをはじめとする大型動物であり、冬期に行われる命がけの仕事でもあったため、山神信仰と厳しい戒律や禁為によって、必要以上の乱獲をしないように自制されていました。
自然と共生した狩猟文化を育んできた東北地方のマタギ集落での人々の暮らしの様子は、昭和の初期頃に全国的に知られるようになったものの、近年では、生活様式の近代化とともに伝統的なマタギの暮らしは姿を消しつつあります。秋田県の阿仁地方では、伝統的なマタギの暮らしを伝承する取り組みが進められています。
北海道では、近年、エゾシカが急激に増加し、道内の社会経済に大きな影響を与えています。そのエゾシカの保護管理を進めるために、地方公共団体と地域住民が協力しながら、エゾシカ肉を高級食材であるジビエとして有効活用し、狩猟者等に捕獲のインセンティブを与えるとともに、エゾシカを地域資源ととらえた地域の活性化を図る取り組みが行われています。
神奈川県においては、豊かな水源環境を保全し、山林と河川と都市域の統合的な管理を推進するため、丹沢における植栽作業(株式会社キリンビール)、間伐作業(株式会社鈴廣かまぼこ)、自然観察(本田学園つくの幼稚園)等、民間団体や民間企業と連携した水源林パートナー制度を推進しています。
一方、山林の自然と最も近いところで日々の生活を営みつつ、自然と直接向き合っている林業者や農業者の数は年々減少しています。林業家戸数は1980年代から2000年代にかけて約2割減少し、農家戸数は約半数になりました。また、野生鳥獣を捕獲するという狩猟行為を通じて、野生生物に直接的な働きかけを持つ狩猟者の数も、ピークであった1970年代の約50万人から現在では半数以下となっています。
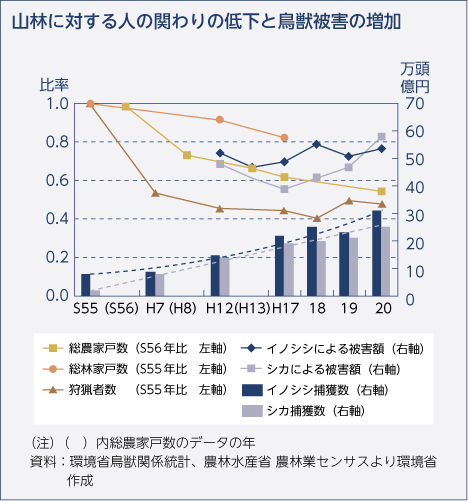
このような山林に対する人間の働きかけの減少や山林の管理の担い手の減少は、生物多様性に大きな影響を与えています。近年のシカやイノシシ等の野生鳥獣の増加はその顕著な例の一つであり、その結果、農林業に対する被害や高い食圧による自然植生の損失が高い水準で発生し続けています。
このように、地域に暮らす人々との協働は、生物多様性の保全を考える際にはかかせない要素です。そのため、その担い手をどのように育成・確保するのかが大変重要な課題となっています。
これまでみたように、日々の暮らしや地域ごとに固有の風土の中で培われてきた知恵からは、持続可能な社会の実現に向けた示唆に富んだ様々なヒントを得ることができます。健全な地球環境が維持され、すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる世界を目指す国際的な動きを踏まえた地球資源の持続可能な利用を考えるためには、これら伝統的な知恵を活かしつつ、科学的な知見や知識と組み合わせて取り組みを進める必要があります。このような知恵や知識は、生物資源を持続的に利用し、保全しようとする人々の間で共有され、実際の行動に活かされることが重要です。
生態系に関する科学的な情報は十分ではありませんが、現在ある知見を集約して生態系の状態や損失の状況の全体像を総合的に評価する取組が行われるようになってきています。国際的な取組としては、国連の主唱より1,000 人を超える専門家の参加のもと2001 年(平成13年)から2005 年(平成17年)にかけて行われた「ミレニアム生態系評価(MA)」や、生物多様性条約事務局により3回にわたり行われた「地球規模生物多様性概況(GBO)」(2001年、2006年、2010年)などの事例があげられます。
わが国においては、環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会が、過去50年間の国土全体の生物多様性を評価した「生物多様性総合評価(JBO: Japan Biodiversity Outlook)」を2010年(平成22年)に公表しています。これらの結果については、第3章において詳しく見ていきたいと思います。
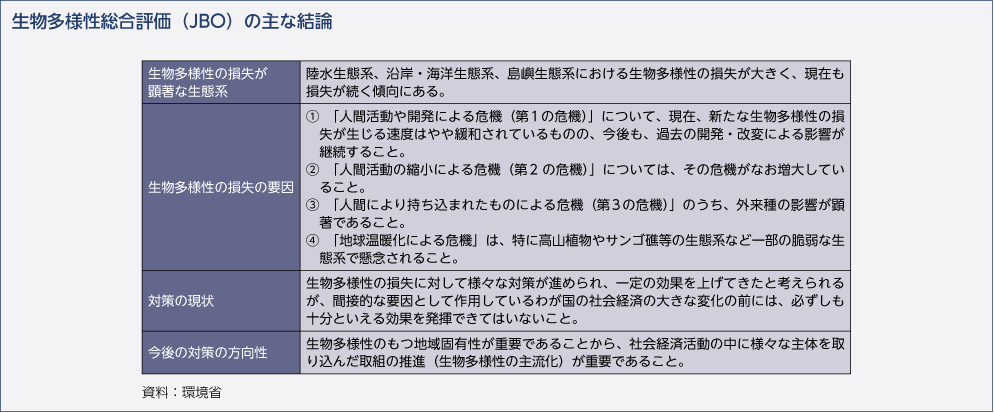
近年、生物多様性の劣化や生態系サービスの損失を軽減し、生物多様性への配慮をあらゆる意志決定の中に位置付けるための取組や政策オプションのツールが提言されてきています。具体的には、生物多様性や生態系サービスの経済価値を市場メカニズムに内部化する手法などがあげられます。
生物多様性条約第11条においては、「締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、生物の多様性の構成要素の保全及び持続可能な利用を奨励することとなるような経済的及び社会的に健全な措置をとる」とされており、世界の国々や国際機関により、市場メカニズムを用いた生物多様性の保全や持続可能な利用に向けた取組や試みがなされています。これらの市場メカニズムを活用した生物多様性の保全と持続可能な利用にあたっては、生物多様性に関する定量的な評価が重要となります。
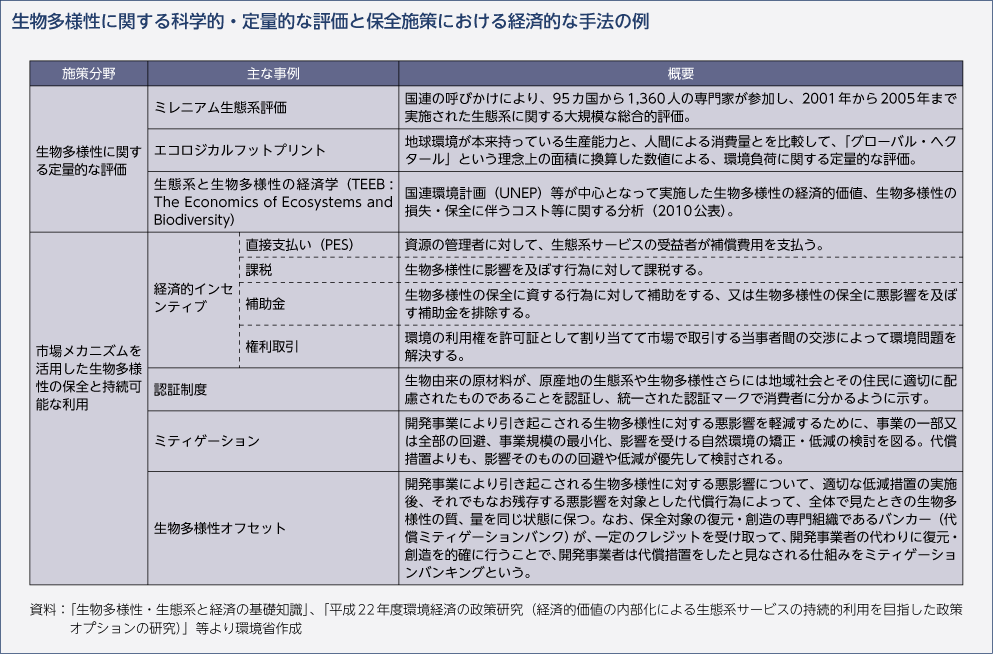
| 前ページ | 目次 | 次ページ |