
「パリ協定は人類、そして我々の惑星にとっての歴史的な勝利である(“The Paris Agreement is a monumental triumph for people and our planet.”)」。これは、フランス・パリで行われた気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21、於:フランス・パリ。以下、気候変動枠組条約締約国会議を「COP」という。)でパリ協定が採択された直後、国連の潘基文事務総長が発したメッセージです。交渉をリードした締約国の閣僚から、交渉を陰で支え続けた気候変動枠組条約の事務局長に至るまで、交渉に携わった人々は今回のパリ協定を「世界にとっての転換点(“a turning point for the world”)」や「信念と連帯の合意(“an agreement of conviction, an agreement of solidarity”)」といった表現で賞賛し、喜びを分かち合いました。
パリ協定は、産業革命前からの世界の平均気温上昇を2℃より十分低く保つことなどを目標とし、この目標達成のため、今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡等を目指すことが規定され、全ての国に削減目標・行動の提出・更新が義務付けられるなど、地球温暖化対策の新たなステージを切り開くものです。各国政府、民間企業、地方自治体、NGO等、あらゆる主体の人々が、従来にも増して気候変動問題に立ち向かう必要性を強く認識し、後押ししたことにより、パリ協定の採択に至りました。
この章では、パリ協定の内容や歴史的な意義について概説するとともに、今後の世界がいかに気候変動問題に立ち向かっていくべきか、その道しるべとなる様々な先進的取組についても紹介します。
COP21は、フランス・パリにおいて、2015年(平成27年)11月30日~12月13日の14日間、開催されました。初日には首脳会合(Leaders Event)が行われ、約140か国もの首脳級が新たな国際枠組みの採択に向けた各国の政治的な決意を表明しました。
予定より会期を延長して厳しい交渉が行われた結果、12月12日(日本時間13日未明)、交渉はついに合意に至り、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました(写真1-1-1)。

今回合意に至ったパリ協定(表1-1-1)は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、附属書Ⅰ国(いわゆる先進国)と非附属書Ⅰ国(いわゆる途上国)という附属書に基づく固定された二分論を超えた全ての国の参加、5年ごとに貢献(nationally determined contribution、以下「NDC」という。)を提出・更新する仕組み、適応計画プロセスや行動の実施等を規定しており、国際枠組みとして画期的なものと言えます。
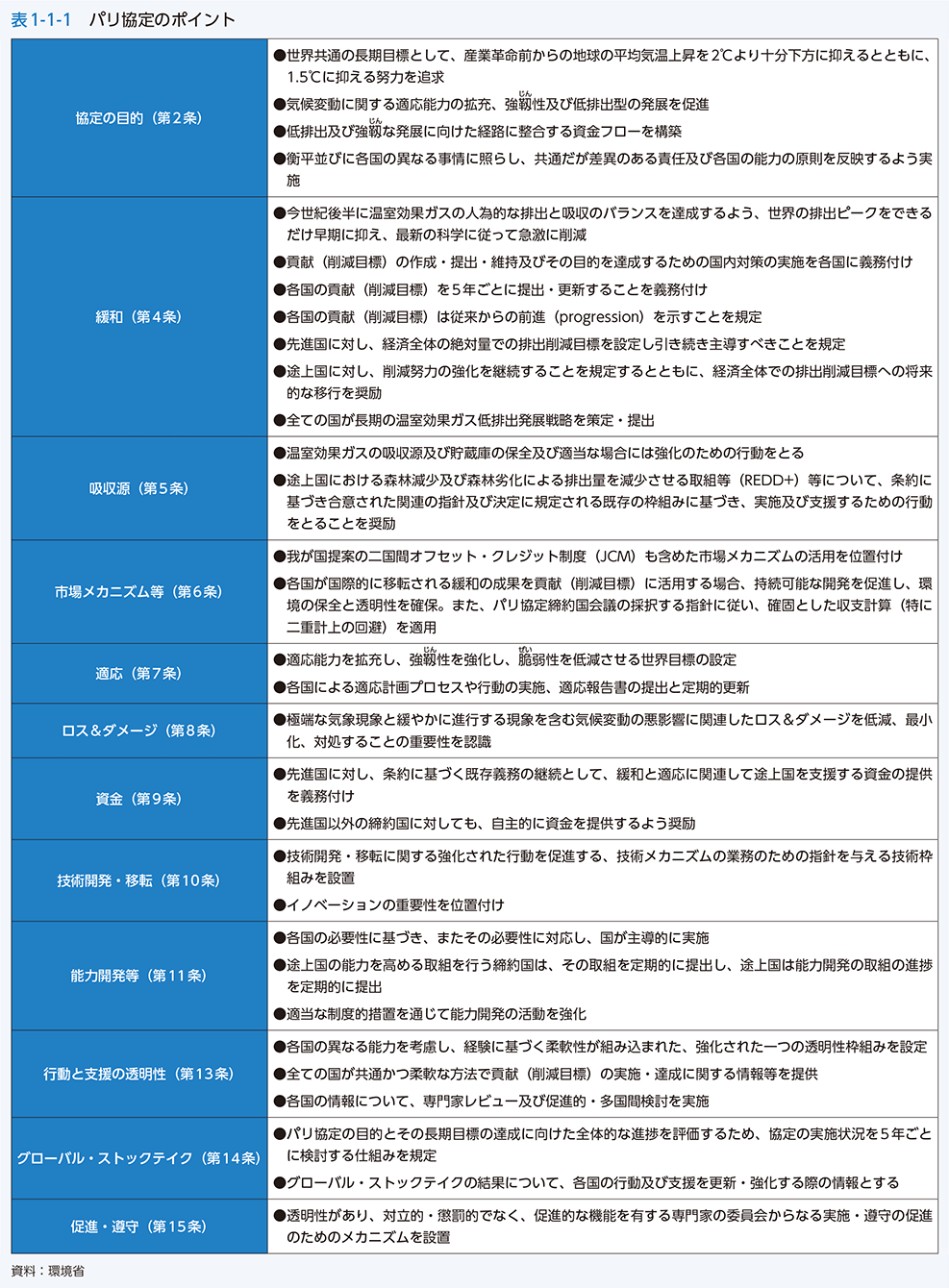
また、世界が協力して気候変動対策を推進する体制や野心の向上を図る方向性を共有したことが今までにない特徴であり、今後どのような社会像を目指すべきか明確なメッセージを提示しました。すなわち、気候変動枠組条約や京都議定書を経て積み重ねられてきた取組を踏まえた世界の気候変動対策の転換点であり、新たな出発点と言うことができます。
我が国は、「新たな国際枠組みは、全ての国が参加する公平かつ実効的なものであるべき」との立場を従来より継続的に発信してきました。
2015年(平成27年)11月30日のCOP21首脳会合開会式において、安倍晋三総理はこの方針を改めて表明するとともに、新たな国際枠組みに長期目標の設定や削減目標の見直しに関する共通プロセスの創設を盛り込むべきと示しました(写真1-1-2)。また、「美しい星への行動2.0(以下「ACE2.0」という。)」を発表し、第一の柱である途上国支援について、2020年(平成32年)に現状の1.3倍、官民合わせて約1.3兆円の関連支援を実施していくとともに、第二の柱としてイノベーションを挙げ、気候変動対策と経済成長両立の鍵は革新的技術の開発であるとし、2016年(平成28年)春までに「エネルギー・環境イノベーション戦略」をまとめ、研究開発を強化していくことを表明しました。

また、12月7日の閣僚級会合において、丸川珠代環境大臣が日本政府代表として演説を行いました(写真1-1-3)。我が国の考え方として、[1]長期目標の設定、[2]各国NDCの提出・見直しのサイクル、取組報告・レビューの仕組みの法的合意への位置付け等を主張しました。また、我が国の国際貢献として、[3]2020年(平成32年)に官民合わせて年間約1.3兆円の気候変動に関する途上国支援の実施、[4]革新的技術開発の強化等を発表しました。さらに、国内における取組として、[5]地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画のできるだけ早期の策定、[6]排出削減取組の着実な実行、[7]適応計画に基づく具体的な適応策の実行についても発表しました。

これに加え、我が国は、COP21議長国であるフランスのほか、米国、中国、インド、南アフリカ等の主要国の閣僚や潘国連事務総長を始めとする国際機関の長等、合計14の国・国際機関とCOP21期間中に個別に会談を行い、新たな国際枠組みに関する相手の主張に耳を傾けつつ、我が国の主張への理解を求め、合意に向けて相互に協調していくことの重要性を確認しました。その結果、パリ協定に規定されている多くの点で我が国の主張が取り入れられることとなりました。我が国として、全ての国が参加し、公平かつ実効的な国際枠組みとなる「パリ協定」が採択されたことを高く評価しています。
パリ協定に関しては、各国政府やシンクタンク等によって、様々な評価がなされています。
協定を肯定的に評価する意見として多く挙げられているのが、全ての国が削減目標・行動をもって参加することをルール化した点です。具体的には、京都議定書の下で進められた排出削減の取組を更に広げるために、各国が削減目標・行動を決定することによって、その国の状況や能力等に応じた多様な参加の形態を認め、これによって途上国の参加を引き出した仕組みが評価されています(表1-1-2)。また、緩和、適応、及び途上国への資金支援といった従来の交渉における困難な論点についても位置付けることにより、パリ協定はバランスが取れた包括的な内容となったとの指摘もあります。加えて、COP21では地方自治体や民間企業、市民団体等、中央政府以外の様々な主体による積極的な取組が改めて評価されるとともに、パリ協定における長期目標や各国の政策自体が更なる低炭素投資や技術革新を誘発する機会を生み出すとも言われています。これらの点を総合し、パリ協定は厳しい長期目標を掲げつつ、多くの主体の関与によって成立した普遍性を備えた枠組みになっているとも評価されています。
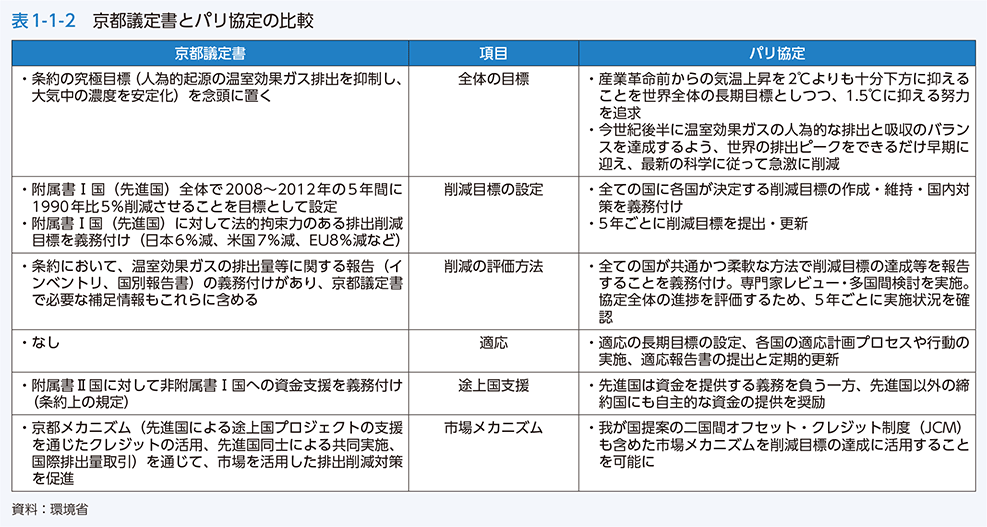
一方、課題に挙げられている点として、NDCに基づく国内対策の内容の強弱は各国がそれぞれ定めるため、国際枠組みとして拘束力のある削減目標等を持っていないとして懸念する指摘があります。また、パリ協定の実効性の向上や今後の各国対策の更なる強化も必要との指摘もあります。また、パリ協定は新たな国際枠組みとして採択されたものの、その細則は今後の交渉で定めることとされていることから、各国間のこれまでの信頼関係をベースにしつつ、パリ協定実施に向けた詳細ルールの交渉を行っていく点が重要視されています。
気候変動に関する最新の科学的知見は、COPの交渉に不可欠なインプットとして、これまでも重要な役割を果たしてきました。そういった知見の集約のために中心的な存在となっているのが、1988年(昭和63年)に世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)によって設立された組織である気候変動に関する政府間パネル(IPCC)です。
現在195か国が参加しているIPCCは、各国の政府から推薦された科学者の参加の下、人為起源による気候変動、影響、適応及び緩和方策等、地球温暖化問題について科学的・技術的・社会経済的な見地から包括的な評価を行い、得られた知見を政策決定者を始め広く一般に利用してもらうことを目的としています。2013年(平成25年)から2014年(平成26年)にかけて公表された第5次評価報告書(表1-1-3)は、世界中で発表された9,200以上の科学論文が参照され、800名を超える執筆者により、4年の歳月をかけて作成されました。
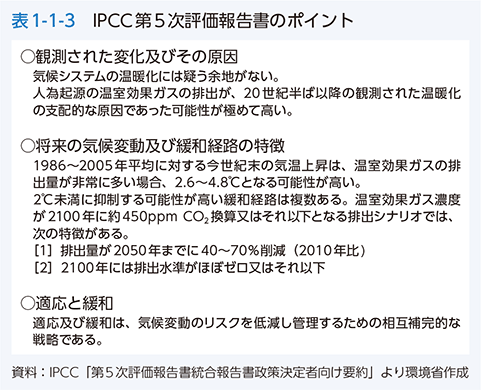
第5次評価報告書では、二酸化炭素(CO2)等、人為起源の温室効果ガスの排出が、20世紀半ば以降の観測された温暖化の支配的な原因だとした上で、代表的濃度経路(RCP)という四つのシナリオによって将来気候の予測が行われました。その結果、21世紀末(2081年~2100年)までの世界平均地上気温の1986年(昭和61年)~2005年(平成17年)平均に対する上昇量は、温室効果ガスの排出量が非常に多い場合のシナリオ(RCP8.5)では、2.6~4.8℃の範囲に入る可能性が高く、厳しい緩和シナリオ(RCP2.6)では、0.3~1.7℃の範囲に入る可能性が高いと予測されました(図1-1-1)。海洋では、海水温の上昇と酸性化が続き、世界の平均海面水位は上昇し続けると予測されています。
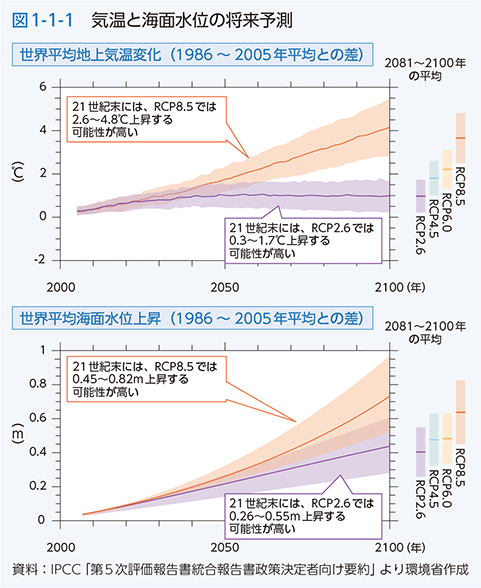
また、第5次評価報告書は、気候変動によるリスクである5つの懸念材料とCO2の累積排出量及び今後数十年間の温室効果ガス年間排出量の関係について整理しています(図1-1-2)。さらに、2050年(平成62年)までの排出量の変化の予測を示すとともに、以下を示唆しています。
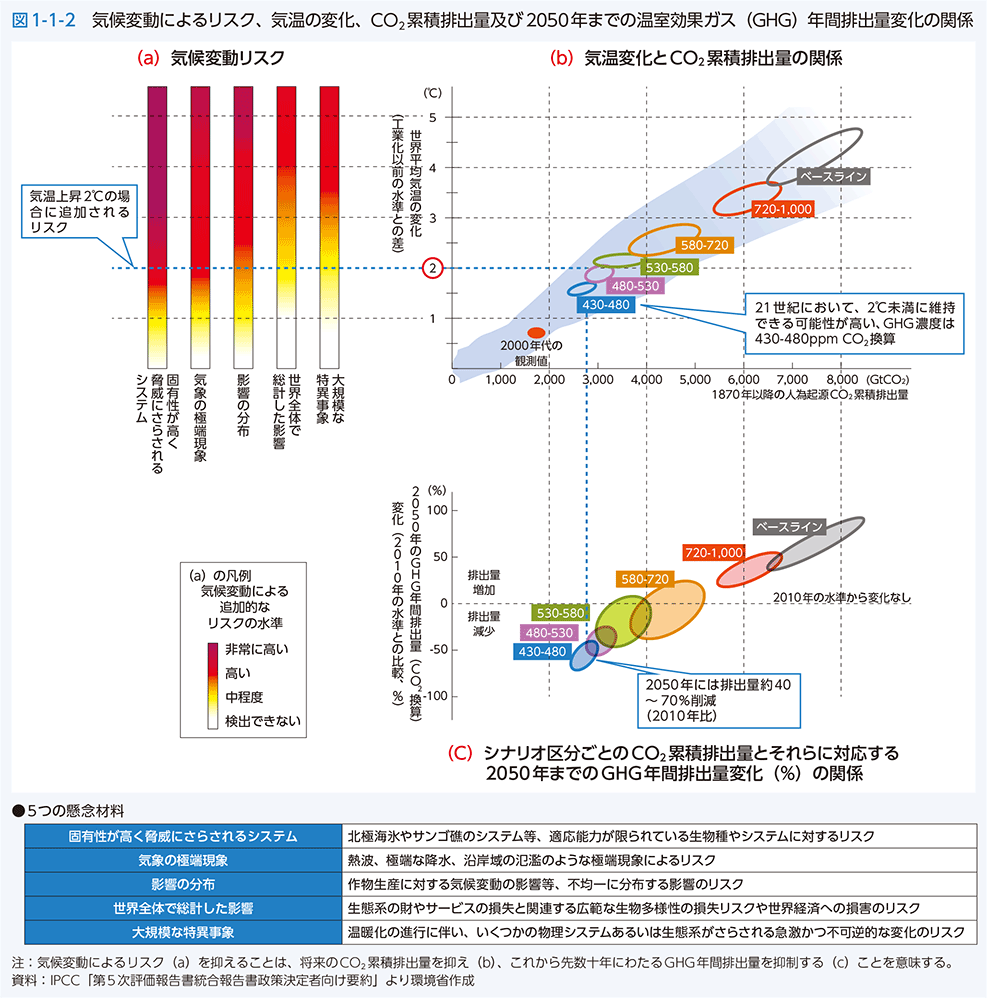
○今後数十年にわたり温室効果ガス排出の大幅な削減を行えば、21世紀後半以降の温暖化を抑制することによって、気候変動のリスクを大幅に低減することができる。
○CO2の累積排出量が、21世紀後半以降の、世界平均気温の上昇の大部分を決定付ける。
○気候変動のリスクを抑制するためには、正味のCO2排出量を最終的にゼロにし、今後数十年間にわたる年間排出量も抑制する必要がある。
温室効果ガス濃度が2100年に約450ppm CO2換算又はそれ以下となる排出シナリオは、工業化以前の水準に対する気温上昇を21世紀にわたって2℃未満に維持できる可能性が高いとされています。これらのシナリオは、世界全体の人為起源の温室効果ガス排出量が2050年(平成62年)までに2010年(平成22年)と比べて40~70%削減され、2100年には排出水準がほぼゼロ又はそれ以下になるという特徴があります。なお、排出シナリオについては、気候感度※等に不確実性が残っており、長期的な分析等にも大きな影響を与え得るため、実態把握や予測等の精度向上に向け、今後も科学的知見の集積が必要です。
注:「※」は、大気中のCO2濃度を倍増させることにより引き起こされる(気候システムの)変化が平衡状態に達したときの世界平均地上気温の変化量として定義される。
ここで挙げた例のように、地球温暖化に関する科学は、様々な示唆を与え、各国の地球温暖化対策のみならず、国際的な取組の向かうべき方向を示してきました。COP21決定により、IPCCに対して、産業革命前の水準から1.5℃の気温上昇の影響及び関連する排出経路に関する特別報告書を2018年(平成30年)に提供することが招請されるなど、国際交渉と科学は今や切っても切れない関係にあると言うことができます。
ア 京都会議(COP3)~カンクン会議(COP16)
1992年(平成4年)に採択された気候変動枠組条約の下、1997年(平成9年)のCOP3(於:京都)で採択された京都議定書は、先進国(条約上の附属書Ⅰ国)に対して法的拘束力のある温室効果ガス削減の数値目標を設定し、「京都メカニズム」と呼ばれる複数国間で協調して目標を達成する仕組みを導入することなどを内容として、2005年(平成17年)2月16日に発効しました。これまでに191か国及び欧州連合(EU)が締結し、我が国は2002年(平成14年)6月4日に締結しました(図1-1-3)。
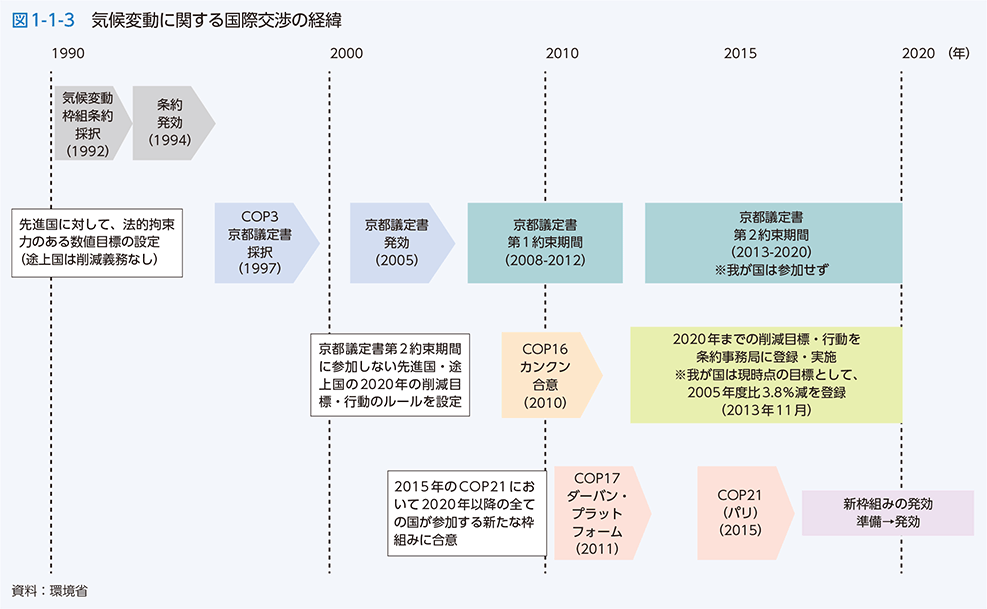
京都議定書は、温室効果ガス排出削減に関する法的拘束力を持つ初めての国際枠組みでしたが、当時世界最大の排出国であった米国が、2001年(平成13年)に京都議定書への不参加を表明したこと、また、その後、京都議定書において排出削減義務を負わない中国、インド等の新興途上国の排出が急増したことから、2012年(平成24年)において、排出削減目標の設定が課された京都議定書締約国におけるCO2排出量の合計は、世界全体のCO2排出量の僅か25.4%をカバーするにとどまることとなりました。
京都議定書の発効後初めて開催された2005年(平成17年)のCOP11において、京都議定書第一約束期間(2008年(平成20年)~2012年(平成24年))後の新たな国際枠組みに向けた交渉が開始され、2007年(平成19年)に開催されたCOP13では、全ての条約締約国による2013年(平成25年)以降の協調的な行動についての検討を行う特別作業部会を新たに設置し、2009年(平成21年)のCOP15で2013年(平成25年)以降の枠組みの具体的な内容を採択することなどを含む「バリ行動計画」が合意されました。
バリ行動計画を踏まえたその後の交渉を経て、デンマーク・コペンハーゲンで開催されたCOP15では、特別作業部会、閣僚レベルでの協議等を経て、30近くの国・機関の首脳レベルの協議・交渉の結果、「コペンハーゲン合意」案が作成されました。しかし、「合意案」に対して少数の途上国が強く反発し、最終的にはCOPとして「同合意に留意する」形となりました。翌2010年(平成22年)にメキシコ・カンクンで開催されたCOP16では、COP15の経験も踏まえた交渉の結果、先進国・途上国の2020年(平成32年)の削減目標・行動を位置付けた「カンクン合意」が採択されました。
イ ダーバン会議(COP17)~リマ会議(COP20)
カンクン合意は、議定書等の法的な合意ではないCOP決定にとどまること、先進国、途上国の対応の差異が明確であること、2020年(平成32年)までの取組を規定した枠組みであることから、それに続く法的な国際枠組みが必要とされました。こうした中、2011年(平成23年)に南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17では、気候変動枠組条約の下で全ての国に適用される議定書その他の新たな法的な国際枠組みについて2015年(平成27年)までのできるだけ早期に作業を終え、その成果を2020年(平成32年)から発効させ、実施に移すという道筋が決定されるとともに、その検討の場として、強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP)を新たに設置することが決定されました(図1-1-4)。
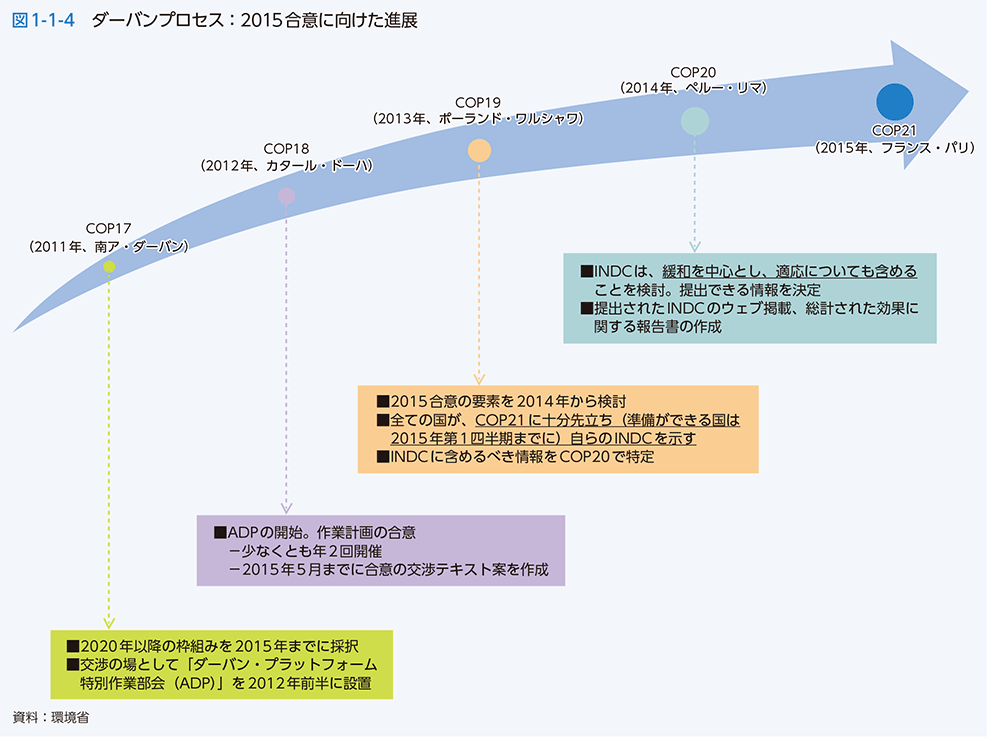
ここまでの経験から、国際社会は[1]全ての国に適用される国際枠組みに合意するに当たって、京都議定書のように特定の排出国に削減目標を割り当てる方法には大きな困難が伴うこと、[2]カンクン合意のように締約国が自主的に排出削減目標を設定するだけでは、長期目標を達成するために全体として十分ではないおそれがあることを経験的に学んできました。
そうした知見を踏まえて、まずは全ての国がそれぞれの事情に応じた「自国が決定する貢献案(intended nationally determined contribution、以下「INDC」という。別に提出がない限り、パリ協定におけるNDCとみなされる。)」を提示し、その後に国際的な協議を行う仕組みが提案されてきました。
2013年(平成25年)11月にポーランド・ワルシャワで開催されたCOP19では、全ての国に対し、INDCの準備を開始し、COP21に十分先立ち(準備ができる国は2015年(平成27年)第一四半期までに)INDCを示すことが招請されました。さらに、2014年(平成26年)のCOP20では、締約国がINDCを示す際に提供する具体的な情報が示されました。
こうした動きにより、新たな国際枠組みは、全ての国による参加を重視する方向性を共有しつつ、各国が国内事情に応じて自ら決定するINDCを基礎とすることとなりました。提出されたINDCを各国の決定として尊重しながらも、目標がいかなる前提に基づいて設定されたものかなど、各国のNDCの透明性・明確性を高めつつ、各国がNDCの実施・達成状況を報告し、そのレビューを受けるという考え、また協定全体の進捗を評価するため、定期的に世界全体の実施状況を確認し、その結果が行動及び支援を更新し強化につなげるという考えが定着しました。これらを具体化したものがパリ協定です。
平成28年3月31日時点で、189か国・地域(条約締約国全体の温室効果ガス排出量の約99%)によってINDCが提出されています。主要各国が提出しているINDCの内容は以下のとおりです(表1-1-4)。
次に、現在提出されているINDCの特徴を見ていきます。150か国・地域が定量化可能な目標を記載しています。定量化可能な目標があるもののうち、先進国はほとんどが削減の絶対量を記載し、世界全体のおよそ半数が現状の傾向を前提とする予測排出量(BAU)と比較した削減割合を記載しており、その他には国内総生産(GDP)当たり又は一人当たりの削減割合を記載するものなどがあります。カンクン合意の下での目標未提出国のうち79か国が目標を新たに提出し、定性的な行動の提出国のうち32か国が定量化可能な目標を提出するなど、様々な前進が見られました。目標年は、定量化可能な目標を示した150か国・地域のうち、137か国が2030年(平成42年)を含むものとする一方、2025年(平成37年)又はより長期的なものなど様々な目標を示す国がありました。
加えて、過半数のINDCが排出量取引を含む市場メカニズムの利用を予定している、あるいは検討していると記載しています。また、ほとんどのINDCが土地利用、土地利用変化及び森林(LULUCF)分野における排出・吸収量を算入しています。
具体的な対策・施策に関しては、多くのINDCが目標を達成するための国内法及び制度の整備について言及しており、特に再生可能エネルギーやエネルギー効率、持続可能な交通、CO2回収・貯留(CCS)、植林や森林保全等に焦点を当てています。また、INDCの作成に当たっては、利害関係者との間で事前協議を実施した国が多く、関係省庁や地方政府だけでなく、民間部門や市民等、様々な主体の協力が不可欠であると強調しています。気候変動への対処と社会や経済の発展が結び付いていること、あるいは更に踏み込んで、両者に相乗効果があることを指摘するINDCもあります。
提出されたINDCの内容に関しては、幾つかの課題も挙げられます。例えば、気候変動枠組条約事務局が作成した各国のINDCを総計した効果に関する統合報告書によると、前述のLULUCF分野における排出・吸収量について、多くのINDCではそれらの算定方式を明らかにしていないため、各国の約束の集約的効果を正しく見積もることが困難になっています。また、一部のINDCにおいては、削減率の計算や予測の根拠・データが明らかになっていないものもあり、今後はこういった算定ルールについて共通の枠組みが望まれています。
COP20の合意に基づき、気候変動枠組条約事務局は2015年(平成27年)10月1日までに提出された各国のINDCを総計した効果に関する統合報告書を同年10月30日に発表しました。同報告書では、147か国・地域から提出された119のINDCについて分析しており、全加盟国数の75%、2010年(平成22年)における温室効果ガスの世界総排出量の86%に相当する国をカバーするものとなっています。同報告書のポイントは以下のとおりです(図1-1-5)。
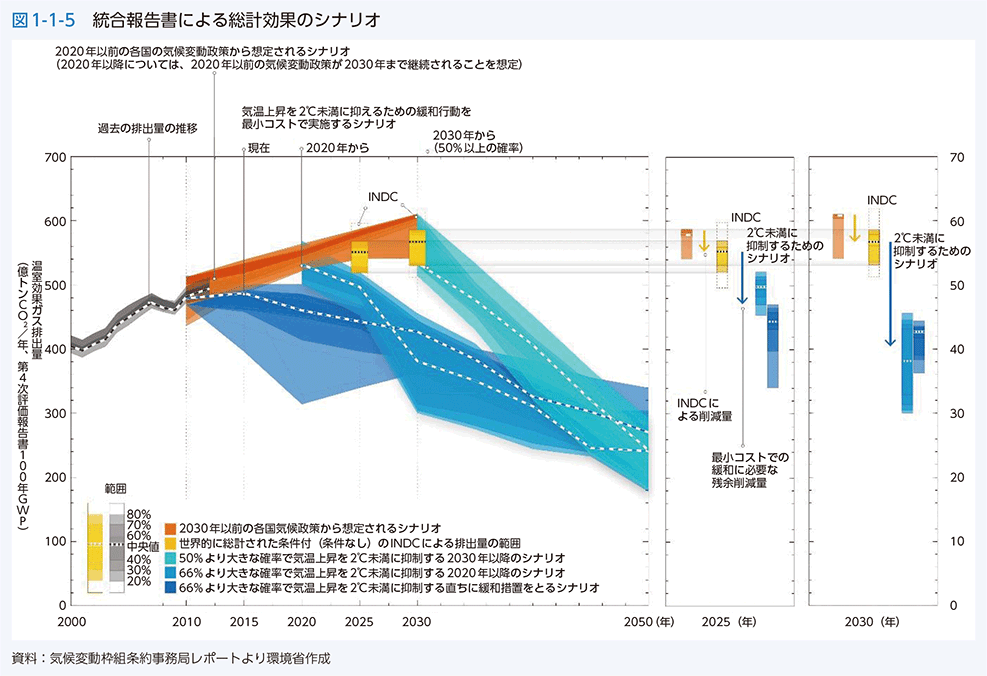
○INDCにより、2010年(平成22年)~2030年(平成42年)の排出量の増加率はその前の20年間と比べ約3割(10~57%)低減する。また、INDCがない場合と比べ、2030年(平成42年)に約36億トンの排出削減効果がある。
○2025年(平成37年)及び2030年(平成42年)の排出量は、2℃目標を最小コストで達成するシナリオの排出量からそれぞれ87億トン、151億トン超過しており、同シナリオの経路に乗っていない。(ただし、今世紀末の予測気温は、2030年(平成42年)以降の社会経済要因等にも依存するため、同報告書では評価していない。)
○2030年(平成42年)以降の一層の削減努力により2℃目標の達成の可能性は残っているが、その場合には2030年(平成42年)~2050年(平成62年)に年平均約3.3%の削減が必要。これは2℃目標を最小コストで達成するシナリオと比べ2倍の削減率に相当し、2030年(平成42年)以降に2℃に向けた必要な対策を取る場合は、相当多額のコストを要することとなる。
また、UNEPも2015年(平成27年)11月にレポート(The Emissions Gap Report 2015)を公表しました。2015年(平成27年)10月1日までに提出されたINDCによる温室効果ガス排出量の分析を行い、地球の気温上昇を工業化以前と比べ2100年に2℃あるいは1.5℃以内に抑える長期目標との整合性、2020年目標(カンクン合意)の実施状況、取組強化の可能性のある分野等を検討したものです。本レポートによれば、条件付きの約束も含めINDCが実施された場合の2030年(平成42年)の排出量は、2100年までの気温上昇が3~3.5℃以内となるシナリオと整合的であり、2020年(平成32年)以降の2℃目標を最小コストで達成する経路へ移行するためには、早期の政策・投資準備が必要とされています。そのためにも今回のINDCは国際合意を作るための最初のステップと考えるべきであるとして、早期対策の重要性や国際共同イニシアティブによる動きへの期待を挙げています。
その他様々な機関からも分析結果が示されていますが、いずれにおいても、現状のINDCから予想される温室効果ガス排出量では、2℃目標を達成することが難しいとされています(表1-1-5)。これらのことからも、今後更なる対策の強化が求められています。
パリ協定では、各国が5年ごとにNDCを更新・提出することが義務付けられるとともに、その目標は従前の目標からの前進を示すことが規定されました。それに先立って、やはり5年ごとに、パリ協定の目的に照らした世界全体での実施状況の検討(グローバル・ストックテイク)を行い、その成果は各国が取組の更新・強化を行う際に情報を与えることとされています。パリ協定に基づく最初のグローバル・ストックテイクは2023年(平成35年)に行われますが、COP21決定により2018年(平成30年)に長期目標に対しての進捗に関する促進的対話を行うとともに、その結果が各国がNDCを準備する際に情報提供されることになっています。また、2020年(平成32年)までに各国がNDCの提出・更新を行うことが求められています。
また、各国のNDC達成に向けた取組の状況について各国から定期的に報告され、専門家によるレビュー及び多国間による検討を受けるという透明性の仕組みも規定されています。
以上のようなPDCAサイクルによって、各国の取組の状況、世界全体での実施状況を検討し、評価し、その結果を行動及び支援の更新・強化につなげることが、パリ協定の重要なポイントです。
COP21におけるパリ協定を含む決定は、長期にわたる政府間の交渉の最終的な成果です。COP21に向けて、各国は気候変動の問題を最優先課題として位置付け、様々な場でパリ協定採択の機運を高めてきました。また、締約国政府の努力のみならず、気候変動に対処するための地方自治体、民間企業、NGOを含むあらゆる主体(非政府アクター)による精力的な動きや合意が、COP21を大いに盛り上げ、パリ協定の採択を後押ししました。ここでは、COP21前に見られた主な締約国における二国間、多国間の気候変動関連の動きと、COP21期間中等に見られた中央政府以外の主体による活発な動きについて、その概要を紹介します。
ア G7エルマウ・サミット――2015年(平成27年)6月7~8日
ドイツ・エルマウで開催されたG7サミットでは、2009年(平成21年)のG8ラクイラ・サミットで合意された2050年(平成62年)80%削減も念頭に、世界全体での中長期的な温室効果ガス排出削減目標の設定に関して議論が行われました。安倍総理は、前回ドイツで行われた2007年(平成19年)のG8ハイリゲンダム・サミットでも世界全体で2050年(平成62年)までに排出半減を目指すことなどを柱とする「美しい星50(クールアース50)」を提案しており、エルマウ・サミットにおいても、COP21における全ての国が参加する新たな枠組みの採択に向けて日本として積極的に議論に貢献する旨表明し、INDCに関する日本の考え方を説明しました。
議論の結果として、下記のような要素について合意がなされました。
○COP21での新たな枠組みの採択への強い決意
○今世紀中の世界経済の脱炭素化
○2050年(平成62年)までに温室効果ガスの2010年(平成22年)比40~70%幅の上方の削減を気候変動枠組条約全締約国と共有
○革新的な技術の開発と導入
○長期的な各国の低炭素戦略の策定
○非効率な化石燃料補助金の撤廃、輸出信用に関する経済協力開発機構(OECD)の議論の進展
○炭素市場や規制手法を含む、低炭素成長の機会への投資にインセンティブを与えるための戦略的な対話の場の設立
イ 気候変動に関する米中共同声明――2015年(平成27年)9月25日
2015年(平成27年)9月の国連総会に際して会談した米国のオバマ大統領と中国の習国家主席は、下記の点を含む「気候変動に関する米中共同声明」を発表しました。世界第一位と第二位の温室効果ガス排出国である中国と米国が、首脳級でCOP21の成功に向けた政治的な意志を示したことは、他の国々の参加を促し交渉に良い影響を与えました。
[1]COP21に向けた展望・共通ビジョン
COP21において全ての国が参加する野心的な合意を達成すべく協力を強化するとともに、2℃目標を念頭に、今世紀半ばまでの戦略策定の重要性、世界的に低炭素な経済への今世紀中の移行、2020年(平成32年)以降の継続的な資金援助の必要性等を強調。
[2]国内気候変動行動の推進
米国は2015年(平成27年)8月にクリーン電力計画を策定するとともに、中国は2017年(平成29年)に排出量取引の国内システムを開始。
[3]二国間・多国間の気候変動協力の促進
米国は、最貧国に対するものを除き、従来型石炭火力発電所の新設に対する公共投資を停止するのに対し、中国は、汚染・炭素排出が大きい案件等への公的投資を国内外で厳格に管理すべく政策・規制を強化。
ウ 気候変動に係る中仏首脳共同声明――2015年(平成27年)11月2日
フランソワ・オランド仏大統領の中国訪問に際し、習国家主席との間で下記の点を含む気候変動に関する共同声明を発表しました。
[1]パリ協定について
野心的で法的拘束力を有するパリ協定の採択に向けて、互いにまた他国のリーダー達と共に取り組む。今世紀内に世界経済を低炭素の道にシフトさせることが極めて重要。先進国が引き続き排出削減目標を掲げることを通じてリーダーシップを発揮。パリ協定には行動と支援に対する報告とレビューの実施を含む強化された透明性システムや締約国が約束を策定・提出・実施及び定期的に更新することについて規定すべき。
[2]中・仏両国の協力等について
気候変動領域における両国間の協調・協力を更に強化し、今後5年以内のできるだけ早期に、それぞれの2050年国家低炭素発展戦略を公表。
エ G20アンタルヤ・サミット――2015年(平成27年)11月17日
従来の気候変動交渉では、先進国と途上国の二元論的な立場で対立が目立っていた主要排出国も、新たな国際枠組みの構築に向けて建設的な議論を重ねるようになりました。その成果の一つとして、COP21直前にトルコで開催されたG20アンタルヤ・サミットにおいて、下記について、参加国間で意見の一致が見られました。
○2℃未満の目標の再確認
○各国の異なる状況に照らし、共通だが差異ある責任及び各国の能力の原則を反映した野心的な合意に到達することへのコミットメント
○特に緩和、適応、金融、技術の開発及び移転並びに透明性といった主要な事項についての議論に建設的かつ柔軟に取り組むことに関する交渉担当者への指示
上記以外にも、アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議、東南アジア諸国連合(ASEAN)+3(日中韓)首脳会議等、様々な地域的枠組みにおいて、各国は気候変動に関する協力関係の確立とモメンタムの形成に努めました。
COP21に向けた非政府セクターの活発な取組は、気候変動対策の議論に影響を与えました。特に、気候変動の悪影響が顕在化することによるリスクを敏感に察知した民間企業を中心に、気候変動リスクを回避又は最小化するため、あるいは気候変動対策を新たなビジネスチャンスと捉え、中央政府の動きとは独立して様々な連携・提言活動を実施し、締約国政府に対して新たな国際枠組みの合意を後押ししました。また、再生可能エネルギーの率先的な導入や都市のコンパクト化を通じた省エネルギー対策等で気候変動対策を推進する先進的な都市・地域や、さらには気候変動対策に積極的に関与しようと活動する地球環境国際議員連盟(GLOBE)や列国議会同盟(IPU)といった各国の議会・議員も、COP21のサイドイベント等の機会にその多様な取組の共有等を通じて連携をアピールし、COP21を盛り上げました。そうした背景もあり、COP21決定(合意文書)の中で、「気候変動対策に取り組み、対応する非政府主体の努力を歓迎し、そのスケールアップを招請する」とともに、「国内政策、カーボン・プライシング等のツールを含む、排出削減行動にインセンティブを付与する取組の重要な役割を認識する」ことが明記されました。
以下では、国、地方自治体、金融機関、民間企業といった利害関係者の類型別に、COP21に影響を与えた主な動きを紹介します。
ア 国・都市・民間セクター全体の動き
2014年(平成26年)に行われたCOP20の後、COP20議長国のペルー政府及びCOP21議長国のフランス政府は、気候変動対策に関する2020年(平成32年)までの野心的な取組を促進し、2015年(平成27年)の新たな国際枠組み合意への支援を更に向上させるため、自治体・民間企業等の様々な主体が宣言を行ってその取組を自主的に登録する「リマ・パリ行動アジェンダ(LPAA)」を立ち上げました。
このアジェンダを通じて、国、都市、民間セクターの行動がより活性化され、今後、地球レベル、国家レベル、地域レベルのリーダーの主要な取組を促進させるとともに、国以外の主体によるパートナーシップ、行動の促進について可視化を図り、他の主体の見本となることが期待されています。
アジェンダには現在、1万を超える様々な主体の目標が登録されており、その活動は気候変動枠組条約事務局のウェブサイト(http://newsroom.unfccc.int/lpaa/(別ウィンドウ))でも紹介されています。
イ 地方自治体を中心とした動き
(ア)自治体リーダーのための気候変動サミット
COP21の期間中、パリ市等の主催により、約700の地方自治体の代表のほか、アル・ゴア元米副大統領等世界的リーダー、ビジネス界の経営者、市民社会の活動家が出席し、「自治体リーダーのための気候変動サミット」が開催されました。同サミットでは、気候変動の影響に立ち向かう上で都市や地域の役割が重要であることを強調し、以下を主な内容とする「パリ市庁舎宣言 COP21へのゆるぎない貢献」が採択されました。
○世界五大陸の都市や地域のリーダーとして、気候システムの崩壊(climate disruption)への取組の再確認
○人類が原因である気候変動が既に数百万人の市民に悪影響を及ぼしており、その影響は数十年続くことに対する認識の共有
○都市の温室効果ガスの排出を2030年(平成42年)までに37億トン削減
○長期的で野心的な気候目標(例えば、再生可能エネルギーへの100%の転換、2050年(平成62年)までに温室効果ガス排出量を80%削減)の支持
(イ)都市間連携の促進に向けたイニシアティブ
世界各国で進行する都市化の流れは、今後の気候変動対策の方向性を決定付ける大きな要素の一つと認識されています。現在、既に都市化が進んでいる地方自治体における先導的な気候変動対策を世界中で共有し、今後急激な都市化が見込まれる途上国を中心とした地域に対してそれらの取組を水平展開することは、都市化が進む地域における地球温暖化対策を進める上で重要です。
こうした点を踏まえ、COP21の開催に合わせて、都市間の連携に関する以下のような様々なイニシアティブが参加者間で合意され、先進国・途上国双方の政府のパリ協定合意に向けた機運の醸成に貢献してきました(パート3第1章第2節で詳述)。
○世界大都市気候先導グループ(C40)による環境配慮型製品の率先調達等を通じた低炭素化の促進
○気候変動政策に関する首長誓約(Compact of Mayors)を通じた、気候変動政策における先進自治体の首長によるリーダーシップの表明と温室効果ガス削減目標等の公表
○気候とエネルギーのための首長誓約(Covenant of Mayors for Climate and Energy)を通じた多様な利害関係者を巻き込んだ形での参加自治体間の連携・協調
ウ 民間企業を中心とした動き
COP21首脳会合に際して、趣旨に賛同する国の首脳、民間投資家が集まり、「ミッション・イノベーション」を設立するための会合が行われました。同会合では、気候変動対策におけるイノベーションの重要性を踏まえ、クリーン・エネルギー分野の研究開発についての官民投資拡大を促すイニシアティブが共有されました。ミッション・イノベーションでは、以下のような取組目標を掲げており、現時点では、我が国を含む20か国、28の機関投資家が賛同しています。
[1]賛同国は、クリーン・エネルギー分野の政府研究支出を5年間で2倍にすることを目指す。
[2]新しい投資は革新的な技術に焦点を当てる。
[3]各国の事情があることを踏まえ、各国が適切な方法で取組を加速する。
COP21に至るまでの上記を始めとする取組は、パリ協定の採択を経て、世界的に一層加速化しています。今後、我が国が産業の国際競争力を強化し、持続可能性を前提とした安全・安心な社会の構築を進めていくためには、世界中のこうした動きを的確に把握し、地方自治体・民間企業を含むあらゆるセクターにおいて気候変動問題への迅速かつ適切な取組を促進していくことが求められます。
COP21決定(成果文書)において、「国内政策、カーボン・プライシング等のツールを含む、排出削減行動にインセンティブを付与する取組の重要な役割を認識する」ことが記載されています。諸外国においては、それぞれの国の状況を踏まえた様々な手法で地球温暖化対策の取組が進められています。
ここでは、諸外国における地球温暖化対策の主な動向を紹介します。
米国は、2025年(平成37年)に2005年(平成17年)比26~28%削減という目標を設定しており、様々な対策を実施しています。例えばこれまでに、大気浄化法の下で、乗用車や重量車の燃費基準を導入し、またエネルギー政策法及びエネルギー自給安全保障法の下で、機器や住宅等の省エネ基準を含めた建築セクターの排出削減対策の実施や、地球温暖化係数の高いハイドロフルオロカーボン(HFC)の代替物質の使用を承認しています。現在、新設及び既設の火力発電所に対する排出規制、重量車の2018年(平成30年)以降の燃費基準の導入等を進めています。また連邦政府による排出について、2025年(平成37年)までに2005年(平成17年)比で40%削減するという目標を設定しています。
EUは、2030年(平成42年)に少なくとも1990年(平成2年)比40%削減という目標を設定しており、「2030年気候とエネルギーに関する政策枠組み」(2014年(平成26年)10月)実施のための法制化に向けた提案を欧州理事会及び議会に提出することとしています。また欧州委員会提出資料(2016年(平成28年)3月2日発表)においては、既に欧州域内排出量取引制度(以下「EU-ETS」という。)の改正提案を提示しており、このほかの法的提案については、各メンバー国の努力分担に関する決定案を含め、今後12か月の間に示すとしています。「2030年気候とエネルギーに関する政策枠組み」においては、EU-ETS対象セクター及び非対象セクターからの排出量を、2030年(平成42年)までに2005年(平成17年)比で、それぞれ43%及び30%削減することや、再生可能エネルギー(電力及び熱)が最終エネルギー消費量に占めるシェアを2030年(平成42年)に少なくとも27%とすること、省エネルギー対策としてベースラインと比較して、2030年(平成42年)に少なくとも27%削減することなどが記載されています。
中国は、2030年(平成42年)までに2005年(平成17年)比でGDP当たりCO2排出量60~65%削減という目標を設定しており、2030年(平成42年)前後にCO2排出量のピークを迎え、また少しでも早くそのピークを迎えるよう最大限努力するとしています。そのため、気候変動対応の国家戦略の実施や地域戦略の整備、低炭素エネルギーシステムの構築等に取り組むとしています。
インドは、2030年(平成42年)までに2005年(平成17年)比でGDP当たり排出量33~35%削減という目標を設定しています。特に、火力発電所への新しく、より効率的かつクリーンな技術の導入、再生可能エネルギーによる発電の促進及び燃料構成における代替燃料の割合の増加や運輸部門における排出削減等、幾つかの重点分野において新しい行動を始めるとしています。
国内排出量取引制度、炭素税等、炭素に価格を付けるカーボン・プライシングに関する近年の動向及びその効果に関する評価は様々であり、例えば、IPCC第5次評価報告書では、カーボン・プライシングに関して「原理的には、キャップ・アンド・トレード制度や炭素税を含む炭素価格を設定するメカニズムにより、費用対効果の高い形で緩和を実現できるが、制度設計に加えて国情等のために、効果には差がある形で実施されてきた。キャップ・アンド・トレード制度の短期的効果は、キャップが緩いか排出を抑制することが証明されなかったため、限られたものになっている(証拠が限定的、見解一致度が中程度)。」と記載されています。このうち、排出量取引制度については、様々な国や地域で導入されています。
EUでは、域内の排出量の約45%をカバーする世界最大の排出量取引制度であるEU-ETSが、2005年(平成17年)から導入されています。EU-ETSの削減効果については、様々な機関が様々な分析結果を公表している一方、今なお制度の改善が進められているため、現時点で、EU-ETSの削減効果を一義的に理解することは困難ですが、欧州委員会による2015年(平成27年)の調査(Study on the Impacts on Low Carbon Actions and Investments of the Installations Falling Under the EU Emissions Trading System)では、「炭素削減や炭素価格は多くの企業及び業種において炭素効率的な解決策に投資するための主要な原動力ではなかった。しかしながら、特に初期の段階では、エネルギーコストの最小化、財政的な実行可能性や利益率の改善、経営層・雇用者層の意識喚起、正確な算定・モニタリングの能力向上といったことへの貢献を通じて、多くの意思決定に支持的役割(supportive role)を果たしたように見える」と評価されています。EU-ETSについては、制度対象企業への排出枠の割当が過剰となり、排出枠価格が下落するなどの問題が生じたことを踏まえて、第3フェーズ(2013年(平成25年)~2020年(平成32年))においては、[1]各加盟国政府ベースでの無償割当から、欧州ベースでの割当とし有償割当を拡大、[2]排出枠の一部を取り置き市場需給の安定化を図る「市場安定化リザーブ」の導入等、制度改善が現在も進められています。
米国では、2015年(平成27年)8月、既設の発電設備を対象とするCO2の排出規制策として、クリーン電力計画(CPP: Clean Power Plan)の最終版が公表され、大統領府の発表によると、当該計画が完全に実施されれば、2030年(平成42年)までに発電部門からのCO2排出量が2005年(平成17年)比32%削減することが可能としています。本計画では、削減目標達成手段として、国内排出量取引制度の活用が認められています。ただし、本計画に対して、全米の州の半数以上の27州(2016年(平成28年)2月時点)からその執行停止を求める訴えや法的正当性を争う訴えが提起されています。執行停止を求める訴えについては、2016年(平成28年)2月、米国連邦最高裁は、連邦控訴裁判所等における法的正当性に関する訴えの審理中は、本計画の効力を停止するとの判断を下しています。現在、法的正当性に関する訴えは連邦控訴裁判所等で審理継続中です。
韓国では、2015年(平成27年)1月に全国レベルの国内排出量取引制度が導入されました。第一計画期間は2017年(平成29年)までとなっていますが、現時点において取引実績はほとんどありません。同制度に対しては、排出枠の割当方法を巡り、制度開始当初から対象企業の約半数から異議が申請され、複数の企業が政府に対し訴訟を提起しています。こうした状況を踏まえ、2016年(平成27年)2月には、制度所管省庁の変更や排出上限の引上げ等制度の見直しが発表されました。
中国では、2013年(平成25年)~2014年(平成26年)にかけて国内2省5都市で排出量取引の試行事業が実施されました。本試行事業における排出量の実績は公表されていませんが、2015年(平成27年)9月の米中首脳会談後の首脳声明において、2017年(平成29年)に中国全土で排出量取引制度を開始するとの計画の概略が発表されたところです。
オーストラリア連邦では、2012年(平成24年)に固定価格排出量取引制度が導入されましたが、政権交代により、同制度は廃止となり、自主的に排出量を削減する企業にインセンティブを提供する「排出削減基金(Emission Reduction Fund)」が実施されています。当該制度下では、政府はオークションにより、排出量削減分を購入する仕組みとなっています。2015年(平成27年)4月と11月に第1回・第2回のオークションを開催し、計275事業が採択され、総削減量は約9,300万トン、総額12.2億豪ドル規模となっています。
CO2の排出に関して課税する炭素税に関しては、IPCC第5次評価報告書において、「いくつかの国では、温室効果ガスの排出削減に特に狙いを定めた税ベースの政策が、技術や他の政策と組み合わさり、温室効果ガス排出とGDPの相関を弱めることに寄与してきた。さらに、多くの国において、燃料税は(必ずしも緩和目的で設計されたものではないにしても)部門別の炭素税と同様の効果を持つ」とされています。世界銀行によると、既にフィンランド等欧州13か国とメキシコ、カナダの1州で炭素税が導入されています。これまで炭素税の導入が見送られていたフランスでも、2014年(平成26年)4月より導入され、今後段階的に税率が引き上げられる予定になっています。加えて、これまで京都議定書において排出削減義務を負うことのなかった途上国でも炭素税の導入が見られ、メキシコは2014年(平成26年)に導入しています。
これらの政策手法を巡っては、国際的にも様々な場で対話や議論がなされています。2015年(平成27年)6月のG7エルマウ・サミット首脳宣言においては「低炭素成長の機会への投資にインセンティブを与えるため、我々は、世界経済全体に炭素市場ベースの手法や規制手法等を含む効果的な政策と行動を適用するとの長期的な目標にコミットし、他国に対して、我々に加わるよう要請する」と記載されました。現在、これを受け、炭素市場及び規制環境についての戦略的対話の場である「炭素市場プラットフォーム」の立上げが進められているところです。
また、2015年(平成27年)6月には、国際エネルギー機関(IEA)本部において国際ワークショップ「産業/ビジネスにおける炭素削減にかかる補完的手段:価格付けや規制以外の自主的取組・その他アプローチ」が開催されました。同ワークショップでは、カーボン・プライシングや規制的手法以外の自主的取組等について、欧米やアジアからの官民多様な立場の専門家や参加者により議論が行われ、経験や分析等の情報が共有されました。その中で、日本の産業界からは、プレッジ&レビュー方式の自主的取組が地球温暖化対策として重要な政策手法であるとの紹介がなされました。
COP21期間中には、世界銀行総裁の主導の下に、21の国や州政府、石油・電気大手企業も含む70社以上が「炭素価格化リーダーシップ」を結成し、炭素の価格化を通じた低炭素社会づくりへの意思を明らかにしました。
世界中の大企業約1,000社が参加する非営利財団である世界経済フォーラム(WEF)は、我が国を含む世界の金融界、企業人、指導者ら約400名が「世界のリスク」を格付けし、その対策について意見交換する世界賢人会議(ダボス会議)を毎年1月に開催しています。ダボス会議では近年、気候変動に関するリスクが「発生の可能性が高いリスク」として継続して挙げられており、金融界や企業が地球温暖化をリスク要因として認識していることが分かります。IEAは、気候変動政策によって引き起こされる変化の結果として、化石燃料ベースのエネルギー資産への投資が、当該資産の稼働期間に全て又は一部の投資を回収できない座礁資産になるリスクがあることを紹介し、その資産価値について複数のシナリオに基づく分析をしていますが、それらの分析による価値は気候変動政策の発展や、それが需要や価格に与える影響が投資家にとってどの程度明確かによるとしています。
海外では、金融機関や機関投資家等が座礁資産から投融資を引き揚げる(ダイベストメント)活動や、保有株式等に付随する権利を行使するなどにより投融資先企業の取組に影響を及ぼす(エンゲージメント)活動が見られます。ダイベストメントの具体的な例として、2015年(平成27年)6月には、ノルウェー議会は、ノルウェー政府年金基金(資産規模約8,000億ドル(約88兆円)の世界最大級の政府系ファンド)の運用方針として、事業の30%以上において石炭採掘・石炭火力に関わっている企業について、現在保有している全株式の売却を正式に承認しました。エンゲージメントの具体的な例として、「Aiming for A」と呼ばれる機関投資家の連合は、BPやロイヤル・ダッチ・シェル等の大手エネルギー企業に対し、温室効果ガス排出量の管理の改善等を求めて株主行動を展開しています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |