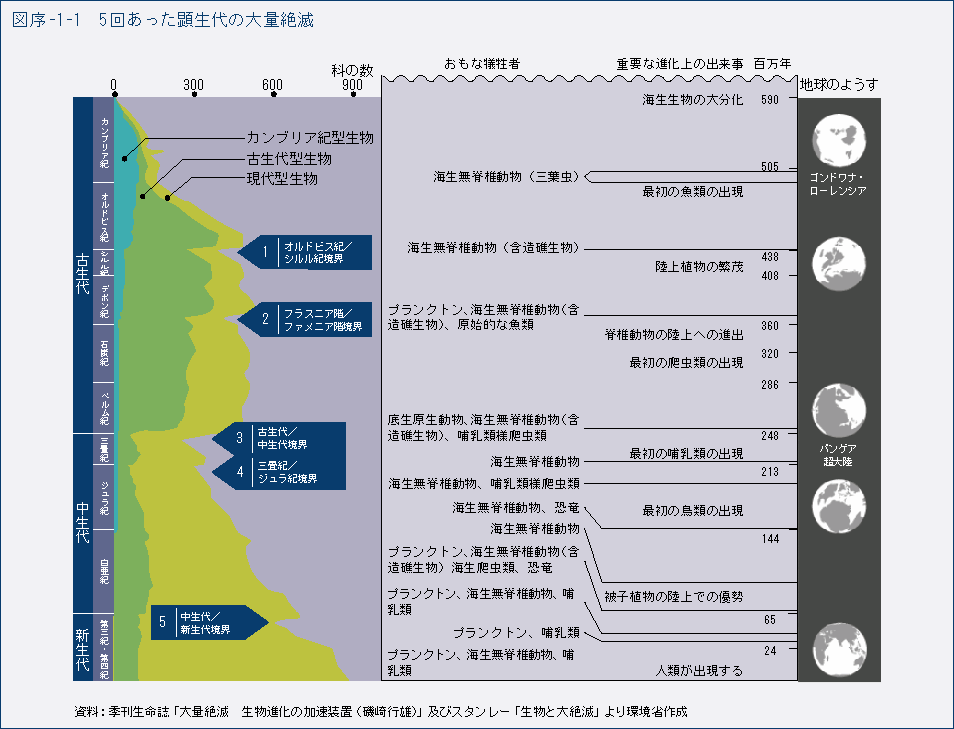
地球の歴史を1年に例えると、ヒトの歴史は約4時間に相当します。産業革命が起きた18世紀以降の人類の歴史は、わずかに1秒ほどです。地球にうまれた生命が長い歳月をかけてつくり上げてきた豊かで精妙な生態系の中で、さまざまな資源を活用することによって、ヒトはめざましい発展を遂げてきました。しかし、その発展の結果、ヒトの活動は「最後の1秒」で、自然の恵みを急激に消費し、地球の環境さえ変えてしまうほど規模の大きなものになっています。われわれの住む地球は、どこへ向かっているのでしょうか。
序章では、地球の歴史と人類の歴史を眺めつつ、近年の世界人口の変動や、資源の状況、経済活動などについて、マクロデータを通して世界規模のトレンドを概観するとともに、日本の状況についても考察していきます。また、その分析を通じて、地球規模での環境への影響を考えます。
この地球に生命が誕生したのはおよそ40億年前とされます。その後、単細胞のバクテリアが全地球に広がったものと考えられ、特に、シアノバクテリア(藍色細菌)は、光合成によって水と二酸化炭素から有機物を合成し、同時に酸素をつくり出すことが知られています。カンブリア紀(6億年前~)になると、現在生存している多細胞生物の主要なグループ(動物門)が一斉に現れたとされています。水中の光合成生物の活動によって生じた酸素は大気に溜り、やがてオゾン層が生成したことで紫外線がカットされ、およそ5億年前に生物が陸上に進出できるようになったようですが、それまで陸上は文字どおり不毛の地であったと見られています。その後、古生代のデボン紀(約4億1000万年前~)になると魚類が、石炭紀(約3億6000万年前~)になると両生類が繁栄したとされます。爬虫類が陸地から水中や空中にもその生息域を拡大していったとみられる中生代の三畳紀中期(約2億3000万年前~)には、哺乳類が誕生し、霊長類の祖先が生まれたのは、およそ8500万年前頃とされています。今から約6500万年前、恐竜をはじめとする巨大爬虫類が絶滅すると生息空間の空きが生じ、今度は哺乳類が爆発的に生息域を広げていったとされています。
サルからヒトへの進化について分子進化学の推定するところでは、ヒトへと続く系統からテナガザルの系統が1800万年~1200万年前に分かれ、オランウータンの系統が1200万年前に分かれたと考えられています。さらに、400万年~800万年前にゴリラが分かれ、その後、400万年~500万年前に、DNA塩基配列上、ヒトとはわずか1~2%の違いしかないチンパンジーが分かれていったとされます。ヒト属(ホモ属)はおよそ200万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から分化し、現生人類であるホモ・サピエンスは40万年~25万年前に現れたとされています。
多くの生物種は、長い時間をかけて環境の変化に身体の形態を変えて適応させてきました。しかし、後に見る人類による環境の改変は、こうした適応に必要な速度をはるかに上回って行われています。人類も一生物種であり、自ら急速に改変しつつある環境に身体の形態を変化させるという方法によって適応できないことは、ほかの生物と全く同様です。
人類は、進化とともに生活状態を改善させてきたとみられます。例えば、簡単な礫器の使用により、獲物の量が増え、獲物を捕らえる労力の節約は、生活を楽にしたものと考えられます。また、原人は進歩した石器作成技術によって、礫器に刃を付け、火をつくり出すことにも成功しています。旧人から新人にかけて道具の多様化と技術の精緻化が見られ、豊かな精神活動も営まれるようになったようです。新石器時代に始まったとされる原始農耕と家畜飼育は、古代に至り一層進展し、また、発明された金属器によって著しく生活様式が変わりました。我々はこうして、豊かな生活を実現してきたのです。特に産業革命以降、1人当たりの環境負荷は増大し、爆発的に増加した人口との相乗的な効果により環境への負荷が増大します。人類の活動は飛躍的に拡大し、これに伴って環境は改変され、環境への負荷も著しく増えていくことになります。
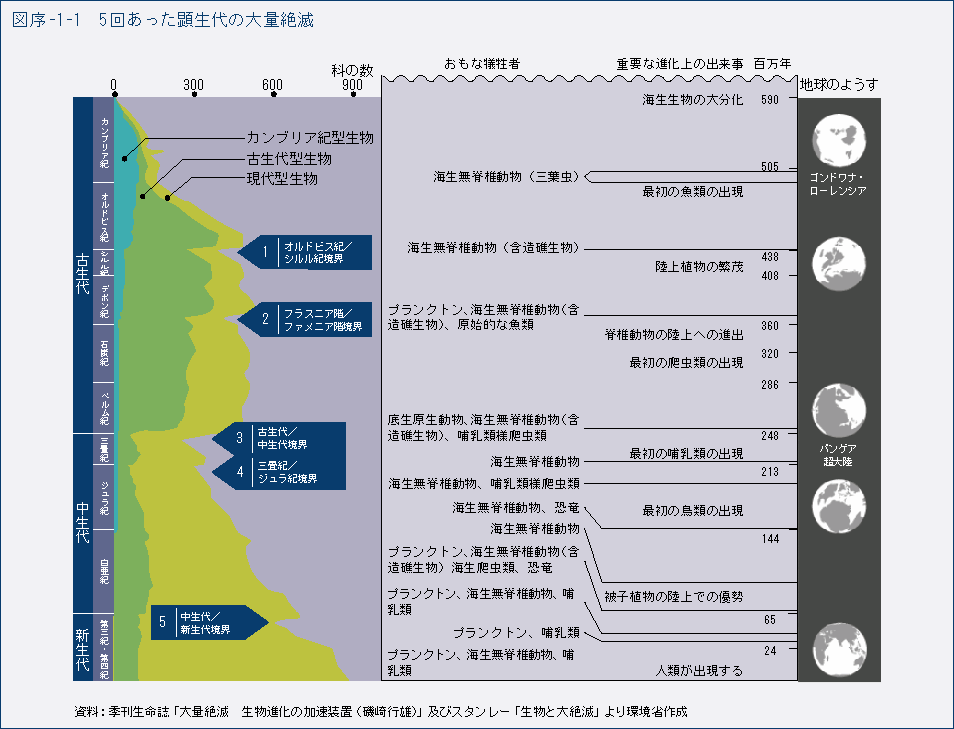
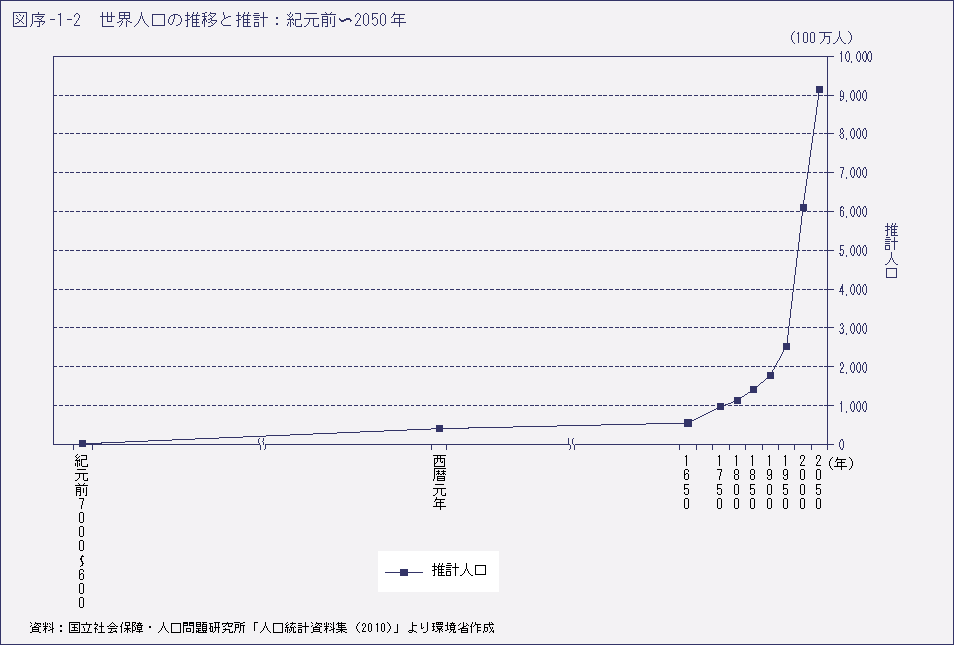
私たちの行う生産・消費活動は、資源採取、温室効果ガスや廃棄物の排出などを通じて、環境に負荷を与えています。一般に、人口の増加に伴って生産・消費活動は増加し、環境に与える影響もこれに伴って増加していくものと考えられます。したがって、人口動向を地域別に見ていくことで、今後、どの地域で環境への影響が増大していくと見込まれるのかを推測するてがかりが得られます。
国連人口基金の発表した世界人口白書 2009(State of World Population 2009)によると、2009年の世界人口は約68億人です。World Population Prospects 2008によると、2011年には70億人に達し、2050年には90億人を突破すると見込まれています(図序-2-1)。人口の地域別割合を見ると、アジア地域が他地域に比べて大きな人口を占めており、特に、インドを含む南中央アジア地域と中国を含む東アジア地域の二地域が大きな人口を占めています(図序-2-2)。
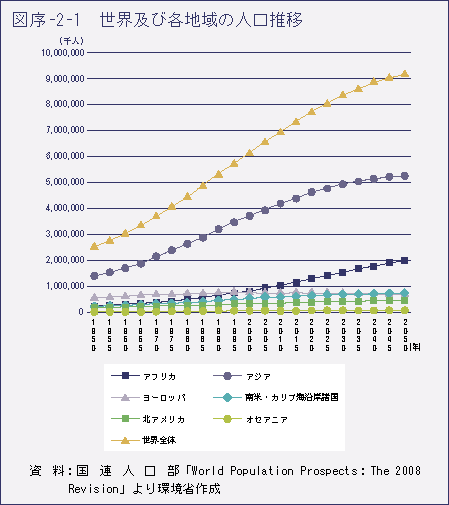
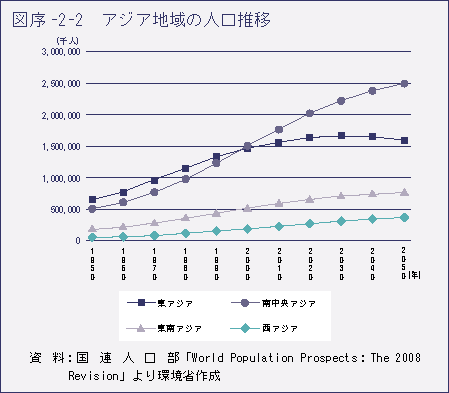
人口の成長率について見ると、これら二地域の人口動向には大きな違いが見られます。南中央アジアは今後も大きく人口が増える見込みですが、東アジアでは人口が2030年頃から減少に転じると予測されています(図序-2-2)。このことから、アジア地域においては、全般に環境への負荷の増加が懸念されますが、特に、南中央アジアにおいて、より長期にわたってそうした懸念が続くと考えられます。
アジア以外の地域を見てみると、アフリカの人口増加率が際立って高いことが分かります(図序-2-3)。2010年から2050年の間の平均人口成長率を年率で見ると、アフリカの人口成長率は約1.6%強と、大きな伸びを見せています。他方で、ヨーロッパの人口成長率はマイナス0.15%程度となっています。
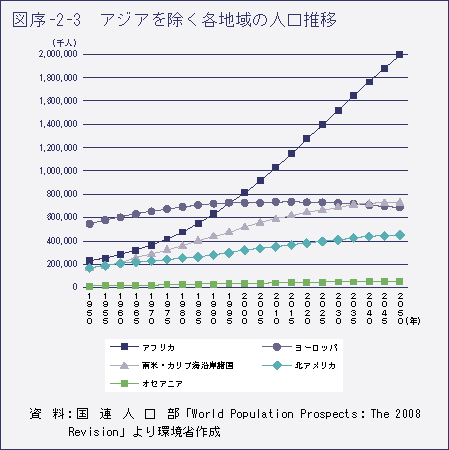
一方、日本の総人口は今後一貫して減少傾向を示すものと予測されており、平成17年(2005年)の約1億2,777万人をピークに減少率を高めながら年々減少し、2050年までに、総人口が1億人を割り込むと予測されています(図序-2-4)。人口の増減という観点から見れば、日本の総人口の減少は、一面では、環境への負荷を和らげる効果があると考えられますが、環境への影響については、生産・消費形態や産業構造、少子・高齢化の進展による生活パターンや生活水準の変化などさまざまな側面からとらえていく必要があります。
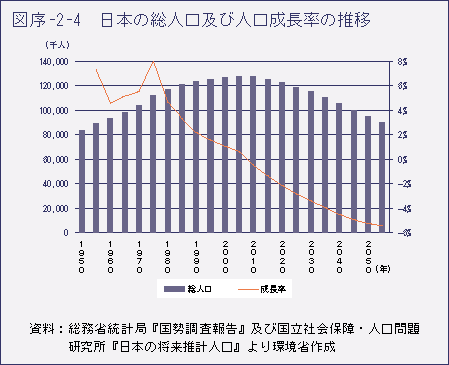
アジアやアフリカの人口増加に牽引される形で世界人口が近年一貫して増加傾向にある中で、居住地については、急速に都市化が進んでいます。国連人口基金のレポートによると、2009年には世界人口の半数に当たる34億人が都市地域に居住しています。この都市化の傾向は今後も続き、2030年までに約50億人が、2050年までには世界人口の約7割に当たる約64億人が都市地域に居住すると予測されています(図序-2-5)。こうした都市化の傾向は、アジアやアフリカといった開発途上の地域で顕著に見られます(図序-2-6)。
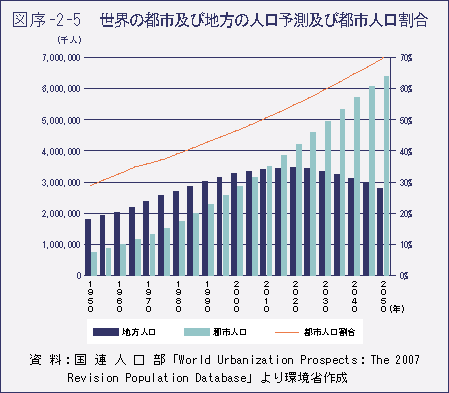
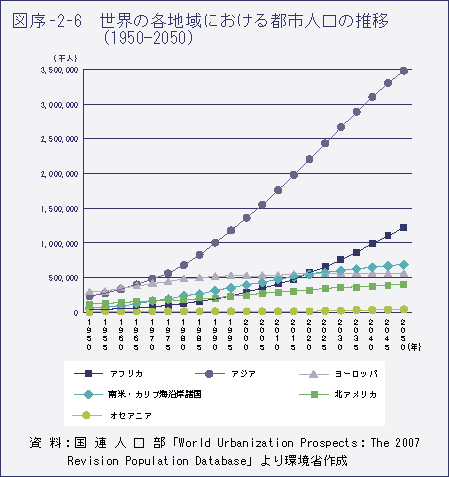
このような開発途上地域における急激な都市化は、環境に悪影響を与える側面を持ちます。
消費面では、都市化によるライフスタイルの変化に併せて、大量消費に伴う大量の廃棄物・生活排水が発生し、いわゆる生活型の環境負荷が高まります。一方で、開発途上地域は、急速な発展を支える大量生産を担う第二次産業において汚染除去技術の導入が一般に不十分で、生産活動からの排水や廃棄物の処理が適正に行われないことが懸念されます。
また、経済産業面では、経済の発展とともに第三次産業への移行が進み、経済の海外依存とインフォーマル部門への依存が高まり都市における労働需要の増加が起きますが、それに伴う人口の急激な流入により、過剰都市化が進行するとともに、失業、スラム化が進むため、それらへの対応が財政を圧迫し、インフラ整備の慢性的遅延を引き起こすものと考えられます。
さらに、途上国でのモータリゼーションを伴った都市化とそれに伴う郊外化は、インフラ不足と相まって、交通混雑や二酸化炭素排出などの環境負荷を加速度的に増加させることになります。
日本について、都市化の状況を見てみると、世界の流れとは異なる様子が見えてきます。日本の都市人口は2010年以降、8500万人前後で安定的に推移すると見られる一方、地方人口は大きく減少する傾向にあると予測されています(図序-2-7)。このことから、日本では、人口減少の影響が地方に大きく現れることが分かります。このため、地方において、里地里山の保全・管理の担い手不足を通じた環境保全上の問題や、高齢化に伴う限界集落の問題などが、より一層深刻化することが懸念されます。
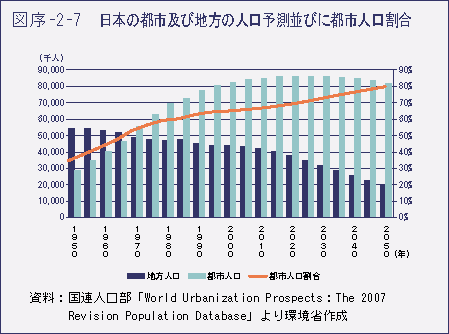
水は人間が生存する上で欠かせません。世界自然保護基金(WWF)のレポートによると、世界で使われている水のおよそ7割が農業用に、2割が工業用に、1割が家庭用に、使用されています。(図序-2-8)。また、1960年から2000年にかけて、世界の水使用量は約2倍に増えていますが、この期間に人口もおよそ2倍に増えており、人間1人当たりの水使用量は、ほぼ一定であることが分かります。したがって、今後も世界人口の増加に伴って、世界の水使用量も増えていくことが予想されます。
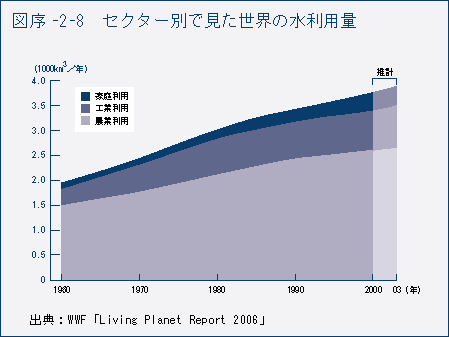
このように水資源の使用量は世界的に高まると予測されますが、水資源は偏在し、不足してきています。世界における年間1人当たりの水資源量を見ると、カナダやノルウェー、ニュージーランドには水資源が非常に潤沢に存在する一方、中東などの国では、水資源が不足していることが分かります(図序-2-9)。
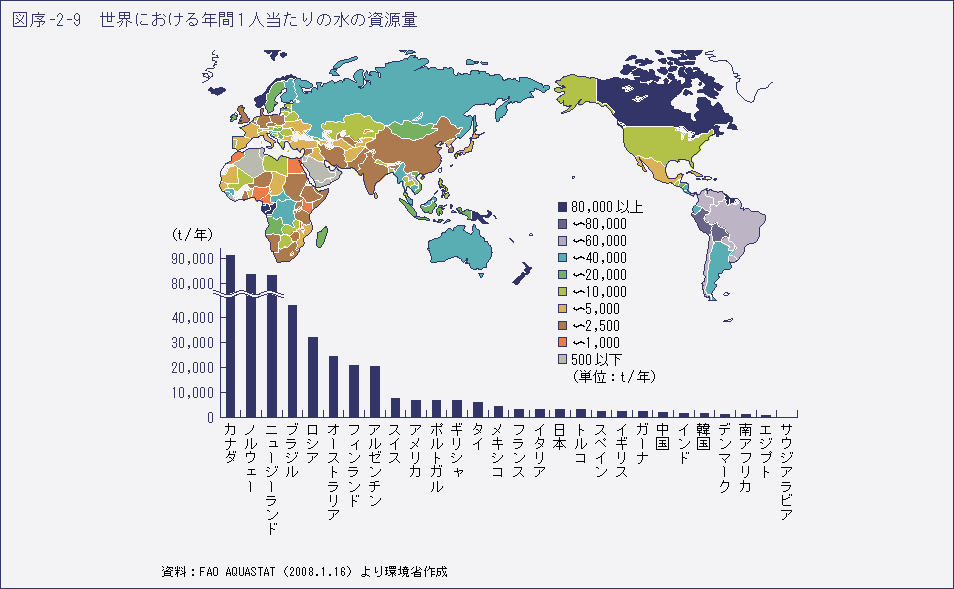
また、1人当たり水資源量と人口の関係を見ると、水資源の偏在性がより明らかになります。人間1人が1年間に必要とする水は約4000m3といわれていますが、それ以下の水資源量しか持たない国に約45億人が住んでいます。また、人口1人当たりの最大利用可能水資源量が1,700m3未満にある状態を「水ストレス」の状態、1,000m3未満にある状態を「水不足」の状態といい、それらの状態にある人口は、2008年に、それぞれ約20億人、約3.3億人にも上ります(図序-2-10)。
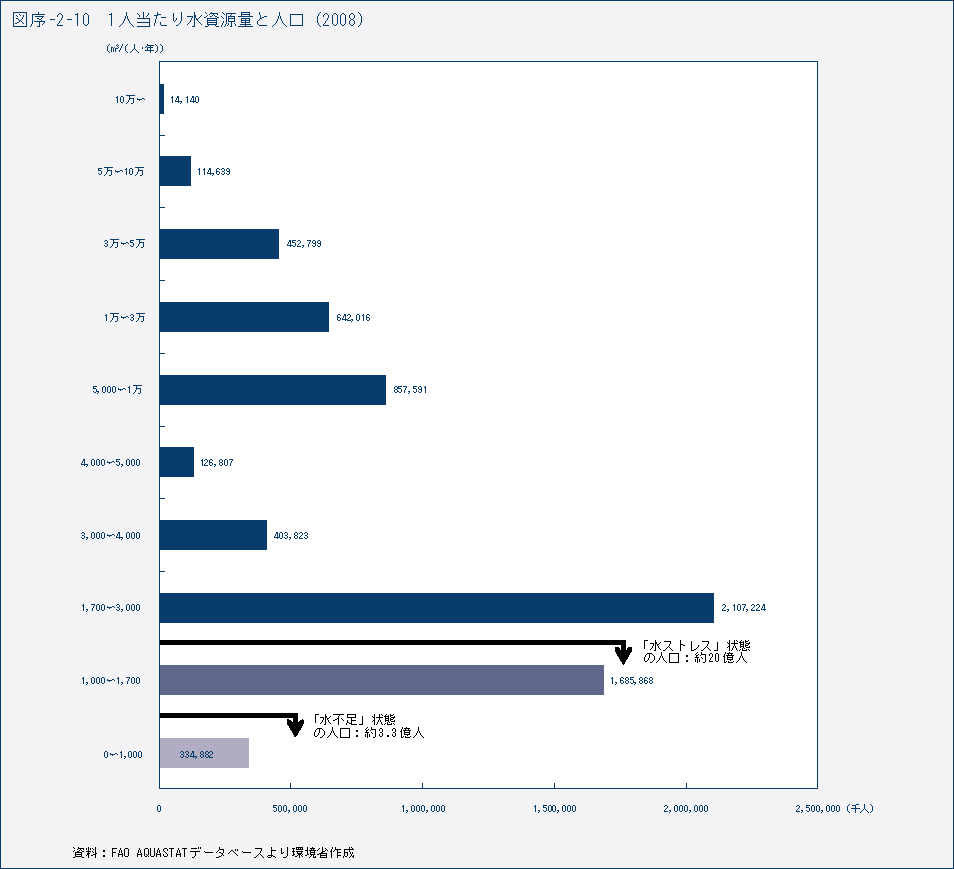
わが国の年間1人当たり水資源量を見てみると、約3,400m3であり、上述したような「水ストレス」状態にはないものの、近年は少雨の年と多雨の年の年降水量の開きが大きく、10年に1度程度の割合で発生する少雨時の利用可能な水資源量が減少する傾向にあり、利水安全度が低下してきています。
国連(UNESCO)が2006年に発表したレポートでは、2030年までに、深刻な水のストレス(制約)を受ける地域に住む人口は2005年に比べ10億人増え、39億人に達するものと見込まれています。今後、アジアでの水利用が著しく増加するものと予測され、1995年の2.16兆m3に比べ2025年には3.10兆m3と、約1兆m3増加すると見込まれています。これは、1995年の北米における水使用量のおよそ1.4倍に相当します(図4-1-9)。
こうした水の偏在や枯渇のため、水の入手可能性が発展の制約になりつつあり、十分な水供給に向けて相当規模の投資が必要となってきています。
ア 穀物の需給動向
人間の生存を支える穀物の需要は、人口の増加に伴って高まります。具体的には、近年の人口の増加に比例した需要増加、所得の向上に伴う畜産物や油脂などの需要増加を背景として1970年の11億トンから2007年には21億トンへと1.8倍に増加しています。
穀物の生産は、おおむね食料の需要に応じる形で増えてきています。農産物の生産量は、過去50年、収穫面積がほぼ横ばいとなっている一方で、単位面積当たりの収穫量(単収)を大幅に伸ばすことで、需要の増加に対応してきています。しかし、近年、単収が伸び悩む中で、主要穀物の主産地における干ばつや不作などの影響も加わり、生産量も伸び悩んでいます。穀物収穫面積の大幅な拡大が見込まれない中で、穀物単収の伸びの鈍化、地球温暖化や砂漠化の進行が今後の食料生産に影響を及ぼすことが懸念されます。
これまでは、過不足分を期末在庫で調整しつつ、食料需要の増加に生産量が対応する形で穀物の需給バランスがとられてきました。しかし最近では、穀物需要がますます増加する一方で、主要穀物の連年の不作により生産が減少し、2007年の期末在庫率は15.0%と、食料危機といわれた1970年代初めの水準まで低下し、国連食糧農業機関(FAO)が定める安全在庫水準(全穀物平均)である17~18%を下回っています。
今後、食料需要がこれまでの見通し以上に増大する可能性がある中で、生産の拡大が着実に図られなければ、食料需給はひっ迫し、現在、上昇傾向にある農産物価格はより高い水準へとシフトする可能性があります。
穀物の地域別貿易量(純輸出量及び純輸入量)の見通しによると、2007年から2019年にかけて、アフリカ、アジア及び中東の地域で純輸入量が増大する一方、欧州やオセアニアでは、純輸出量が増大することが予測されています(図序-2-11)。また、北米は、1995年から2019年にかけて純輸出量が減少するものの、依然として世界の主な穀物の純輸出地域であり続けることが予測されています。グローバル化により食料の生産・輸出国の偏在化が進んでいるため、何らかの需給変化が生じると国際価格への影響が大きく、不安心理による輸出規制、投機資金の流入が生じやすく価格高騰がより増幅されやすくなっていることが懸念されます。
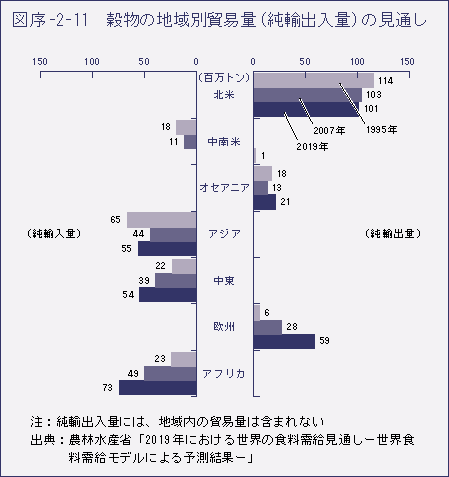
次に、日本の食料自給率についてみて見ると、過去数十年にわたって減少傾向にあることが分かります。カロリーベースで見た場合の食料自給率は、昭和36年度(1961年度)の78%から近年は約40%前後へと低下しており、日本の食の欧米化などが影響しているといわれています(図序-2-12)。一方、イギリスでは、日本とは対照的に、食料自給率が上昇しています。イギリスのカロリーベースでみた食料自給率は、近年低下傾向にあるものの、昭和36年の42%から平成5年の70%へと上昇しており、これは、イギリスの土地が平坦で効率的な農業生産が可能なことや、EC加盟による農業補助の恩恵を受けて小麦等の生産が伸びたことなどが理由として挙げられています。
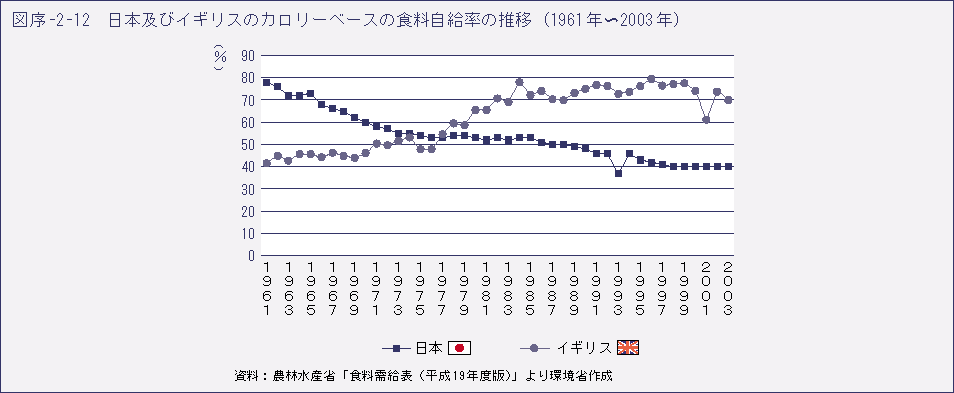
平成19年(2007年)から平成20年(2008年)にかけて起きた穀物価格の上昇は、途上国における穀物需要の増大やバイオ燃料原料用の需要拡大、干ばつの影響による穀物供給量の減少、また投機的な需要の増大などが理由として挙げられるほか、世界の穀物価格の上昇後に中国やロシアを含む主要な国々が穀物の輸出禁止や制限を実施した事も理由としていわれています。このように、需給のひっ迫が起きると、穀物の輸出国がいわば食料の「囲い込み」を行い得るため、食料の6割を海外に依存するわが国としては、国内生産の増大を図ることを基本として、これと輸入、備蓄とを適切に組み合わせていく国内方針の下で、食料自給率の向上に積極的に取り組む必要があります。なお、わが国では一年間に約1,900万トンの食料が廃棄されており、これは平成19年に国連世界食糧計画が行った食料援助量330万トンの約6倍となっています。
イ 魚介類の需給動向
1人当たり需要量の増加に人口の増加が相まって、世界の魚介類の需要量は、1970年の5,628万トンから2003年の1億2,600万トンへと2倍に増加しており、特に中国では、405万トンから4,756万トンへと11.7倍に増大しています。また、世界の年間1人当たり食用魚介類の需要量は、1970年の11.1kgから2003年の16.1kgへと1.5倍に増加しています。主要国・地域別同期間における同需要量をみると、アメリカでは1.4倍、EUでは1.3倍、中国では5.7倍に、それぞれ増加しています。
今後、人口増加と所得の向上に伴い、世界的に魚介類の需要量は増加するものと見通されます。特に、中国においては、牛肉などの肉類よりも、魚介類が贅沢品として考えられていることから、所得の向上に伴い魚介類の需要量は増加すると見込まれます。これに併せて、交通道路網、加工技術・加工場、冷凍・冷蔵施設が整備されるなど、流通インフラや加工・冷凍技術の進展に伴い、市場が広がっていることも、こうした需要の増加に影響を与えています。また、アジア地域においても、所得の向上により、魚介類の需要が増加すると見込まれます。
魚介類の生産(供給)量は、1990年代以降は、漁獲量が9,000万トン程度で頭打ちとなる一方、主に養殖量の増加に支えられて、需要量の増加に対応する形で増加してきています(図序-2-13)。2007年の生産量1億5,600万トンのうち、4割を養殖業が占めています。漁業生産量についてOECD加盟国と非OECD加盟国とを比べると、OECD加盟国の漁業生産量が減少する一方、非OECD加盟国のそれは増加しており、特に、非OECD加盟国加盟国の養殖業の生産量が近年著しく増大していることが分かります(図序-2-13)。漁獲生産量を国別でみると、中国が世界最大の魚介類生産国となっており、2005年の生産量は6,063万トンと世界の生産量の4割を占めています。また、中国の生産量の7割が養殖業によるものとなっており、干潟の開発・転用などを伴う内水面養殖が増加しています。
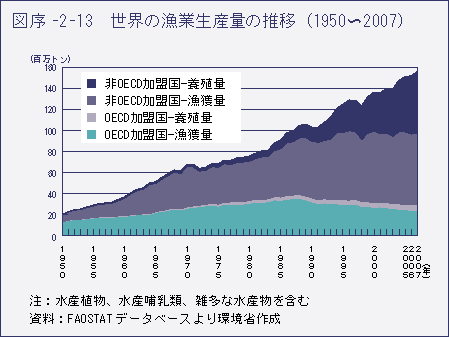
水産資源の利用について、FAOによれば、約半分が満限利用、4分の1が乱獲などによる過剰漁獲の状況にあります(図序-2-14)。今後、漁業は漁獲量の停滞が続くと見込まれることから、生産量の増加は、養殖業に頼らざるを得ない状況になると考えられます。
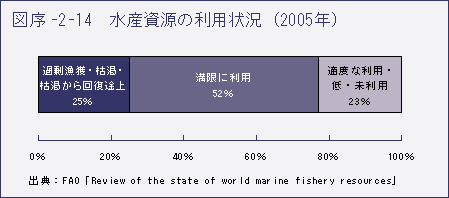
世界的に水産物需要が増加する中で、需給は引き締まってきており、一部の魚介類 では価格の上昇傾向がみられます。今後の魚介類の需給は、FAOによると、水産資源に制約がある中で、人口増加と所得の向上に伴い増加する需要量に対し、養殖業を主体に生産量も増加するものの、潜在的には需要量が生産量を上回るものとみられています。このため、最終的には価格の上昇やほかのたんぱく質食料への転換などを通じ、需給均衡が図られるとみられており、需要量は1999年~2001年の平均の1.3億トンから2015年には1.8億トンへと、1.4倍に増加するとともに、価格は2010年までは年率3.0%、それ以降2015年までは年率3.2%のペースで上昇すると見通されています。
エネルギーの消費は、二酸化炭素の排出等を通じて環境への負荷に大きく関係しており、長期的には今後も増加傾向にあると考えられています。国際エネルギー機関(IEA)の見通しでは、金融・経済危機の結果、2009年の世界のエネルギー消費量の減少はほぼ確実な状況にあるものの、現行のエネルギー政策のままでは、ひとたび景気が回復に転じれば、すぐに長期的な増加傾向に戻るとしています。
世界のエネルギー消費量(一次エネルギー)は、1971年の55億TOE(原油換算トン)から、2007年には120億TOEと40年弱の間に2倍以上に増加しています(図序-2-15)。今後も新興国を中心に経済発展が見込まれる中で、エネルギー消費量の増加傾向は続くと考えられますが、エネルギー消費量をエネルギー源別に見た場合、石油が約1/3を占めており、また、IEAの見通しでは、各国政府が既存の政策や対策を全く変えなかった場合、依然として化石燃料が世界の一次エネルギー源の大部分を占め、2007~2030年のエネルギー消費増加分の4分の3以上は化石燃料によるものと予測しています(図序-2-15)。さらにIEAの同見通しでは、化石燃料の中でも、石炭の需要が発電用需要の増大に牽引され今後大きく伸びていくと予想されており、ほかのエネルギー源と比較して二酸化炭素排出量が大きいこと(図序-2-16)を併せ考えると、化石燃料の利用の高度化等の取組が世界規模で積極的にされない場合、環境負荷が一層増大することが懸念されます。
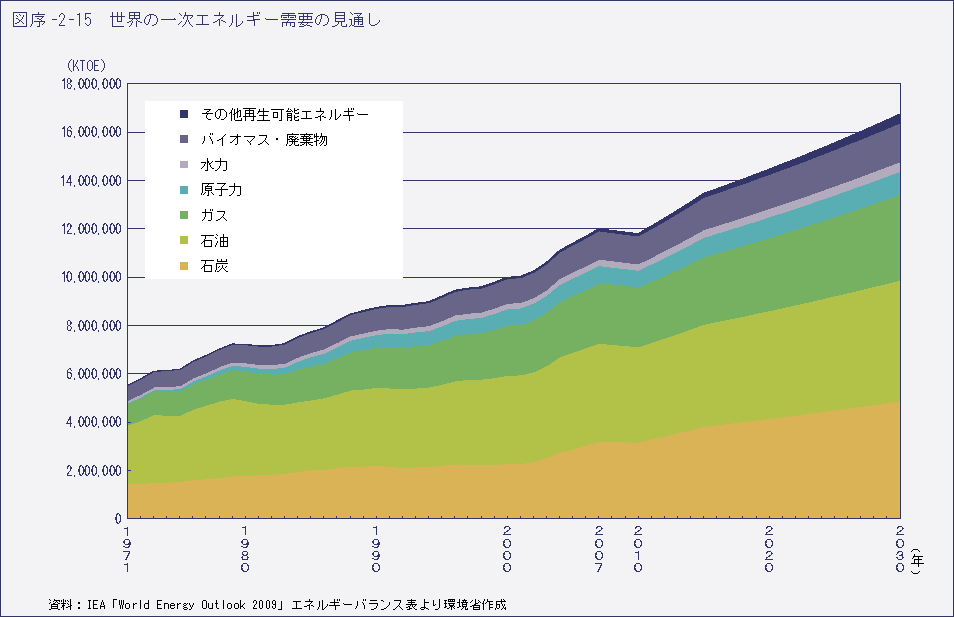
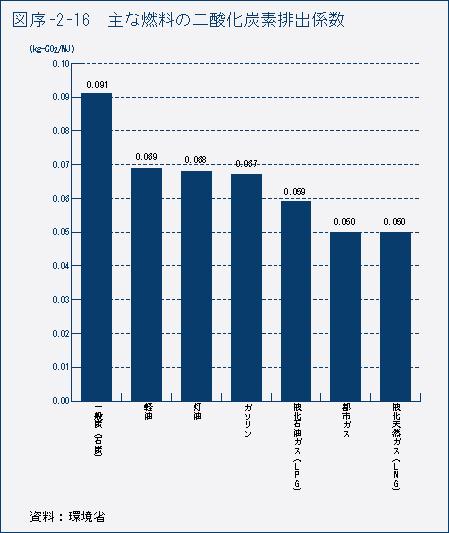
世界全体のエネルギー消費量が今後も増加していくことが見込まれる中、化石燃料に比べ二酸化炭素の排出が少ない再生可能エネルギーの重要性は増しています。世界の再生可能エネルギーの需要量は2008年の15.2億TOEから2030年の23.8億TOEへと増大することが見込まれています(図序-2-15)。また、世界の国々では、エネルギーの消費量や供給量に占める再生可能エネルギーの割合について目標を掲げ、同エネルギーの積極的な導入に向けた動きが出てきています(表序-2-1)。
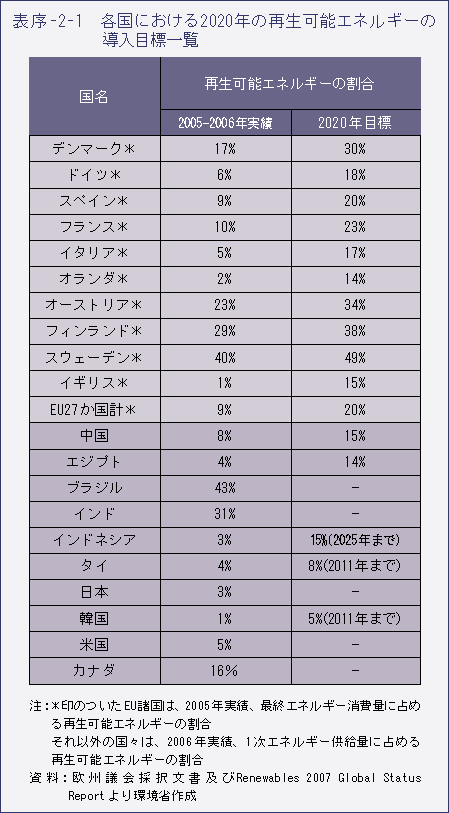
日本の一次エネルギー国内供給は、昭和40年(1965年)から平成19年(2007年)にかけて約3.6倍に増加しています。一次エネルギー国内供給のエネルギー源別構成割合をみると、近年、石油に対する依存の割合が減少するとともに、天然ガスによるエネルギー供給が高まってきていることが分かります(図序-2-17)。また、再生可能エネルギーを主な内容とする水力及び新エネルギー・地熱等(1,000kw以下の自家発電は未計上)の構成割合についてみると、1990年以降大きな変化は見られないことが分かります。
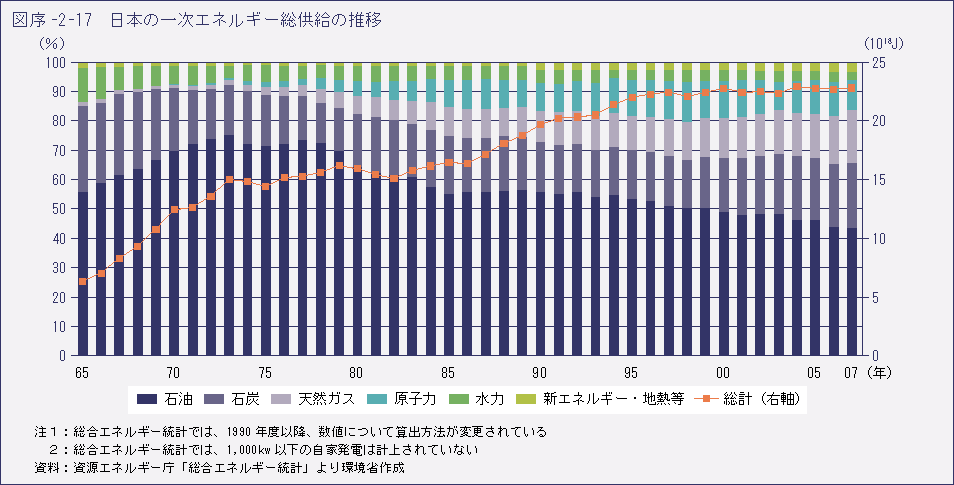
日本の将来のエネルギー供給のあり方については、現在、エネルギー基本計画の見直しにおいて、地球温暖化対策のあり方や新成長戦略の観点も踏まえながら検討が進められています。
人口の増加とそれに伴う生産活動の増大により、土地利用にも大きな変化が現れてきています。ミレニアム生態系評価では、生態系構造の最も大きな変化として、地球の土地の約4分の1が開墾されてきたことを挙げるとともに、1700年から1850年までの150年間より、1950年からの30年間に、より多くの土地が農地に改変されたと指摘しています。平成17年現在、全陸地の12%が農用地として利用されており、平成12年に比べ、約1.7%増加しています。
このように、農用地面積が拡大する一方で、森林の面積は大きく減少しています。UNEPによると、現代のような気候となって以降、人間の影響が広がる以前から現存していた森林は、主に人間の活動により、およそ半分が消失したとされています(図序-2-18)。現在残る森林は全陸地の約30%を占めていることを考えると、森林の開発という点のみでみても、人間の影響によりこれまで全陸地の約3割に相当する森林が利用され消失したといえます。UNEPは、こうした森林の消失は農業、畜産、木材や燃料としての森林の伐採、そして人口密集地の拡大といった活動の結果によるものとしています。
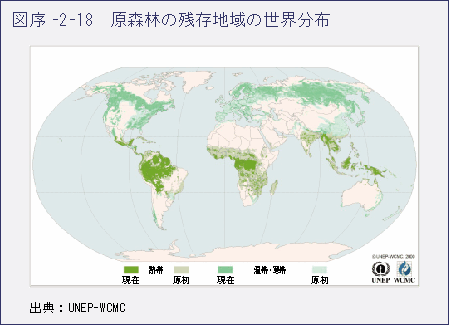
今後、開発途上国の経済発展による所得向上に伴って、食生活における肉類や魚類への嗜好が高まることになれば、穀物などの農作物の生産に比べてより多くの土地や水資源等が必要となり、環境への負荷が高まることが懸念されます。例えば、肉類の生産に必要な土地及び水の消費量を穀物などの農作物の生産と比較して見てみると、肉類の方がより多くの資源を消費することが分かります。食料の生産に必要となる土地面積量を、タンパク質1kg当たりで見た場合、穀物の生産に必要な土地面積に比べて、鶏肉の生産に必要な土地の面積は約7倍、豚肉では約12倍、牛肉で約20倍であるとされています(図序-2-19)。このように、開発途上国の所得の向上と、それに伴う食生活の変化により、今後、これまで以上に地球の土地資源等が利用される可能性があります。
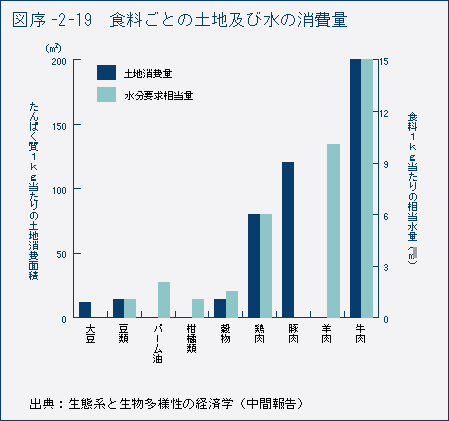
また、砂漠化も、土地に関する環境問題として挙げられます。砂漠化の影響を受けやすい乾燥地域は、地表面積の約41%を占めており、そこで暮らす人々は20億人以上に及び、その少なくとも90%は開発途上国の人々です(図序-2-20)。砂漠化は、気候的な要因としては地球的規模での気候変動、干ばつ、乾燥化などが、また、人為的要因としては過放牧、森林の過伐採(薪炭材の過剰採取)、過耕作など乾燥地域の脆弱な生態系の中で、その許容限度を超えて行われる人間活動が原因といわれています。
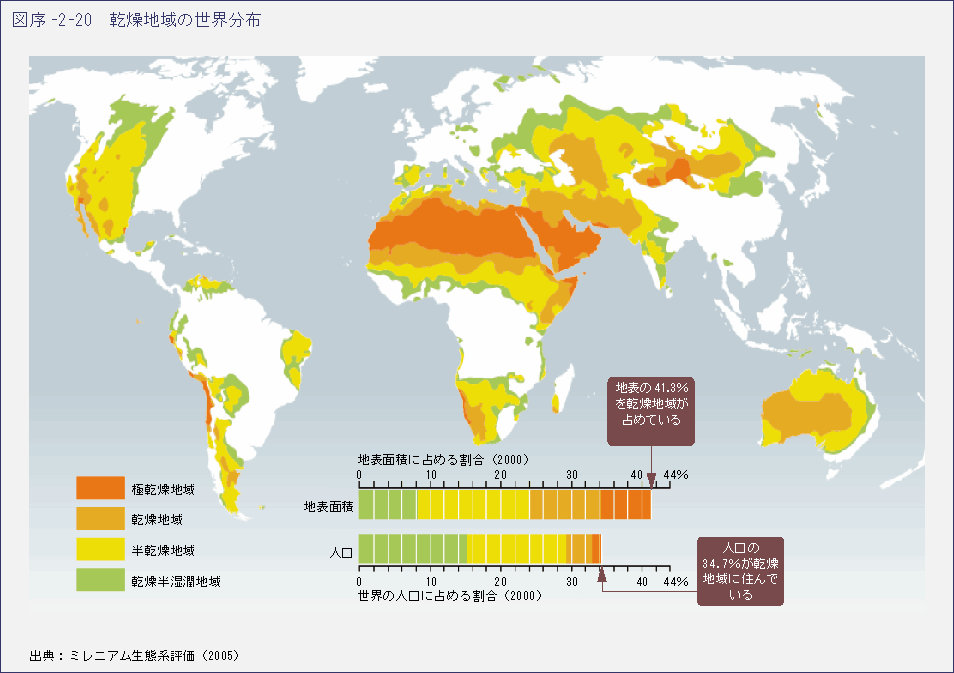
砂漠化は食料の供給不安、水不足、貧困の原因にもなっており、今後の世界人口の増加や都市化の進展、市場経済の発展を通じて砂漠化が進行することで、社会不安の一層の悪化が懸念されます。
わが国の国土利用の動向をみると、「農用地」面積が減少する一方で、「宅地」及び「道路」面積が増加していることが分かります。平成19年(2007年)の地目別面積を昭和40年(1965年)のそれと比較すると、「農用地」が170万ha減少し、昭和40年と比較して約26%の減少となっています(表序-2-2)。一方、昭和40年に比べて増加した地目をみると、「宅地」は102万ha、また「道路」は52万ha、それぞれ増加しており、昭和40年からの増加割合をみるとそれぞれ、120%及び63%の増加となります。このように、昭和40年以降の日本においては、「農用地」面積の減少とともに「宅地」及び「道路」面積の増加が見られてきました。近年においてもそのような傾向は見られるものの、農林業的土地利用(農林地及び埋立地)から都市的土地利用(住宅地、公共用地、工業用地等)への転換面積は近年減少傾向にあり、過去見られたような「農用地」から「宅地」及び「道路」へといった土地利用形態の転換傾向が緩和されてきているといえます。
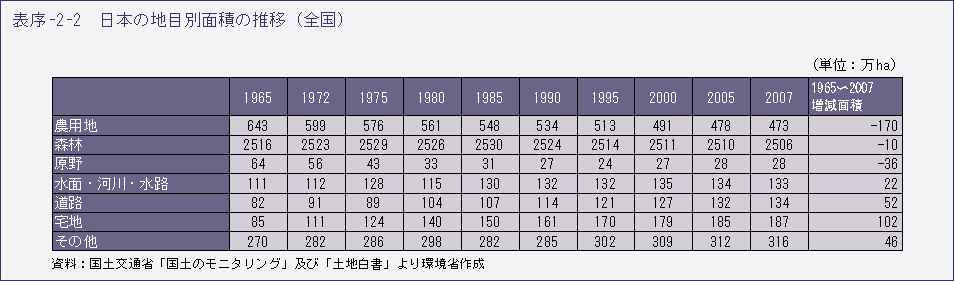
2008年の生物多様性条約第9回締約国会議(COP9)の閣僚級会合で発表されたレポート「生態系と生物多様性の経済学」(TEEB)の中間報告によると、2000年には、世界の自然界に元々存在する生物多様性の約73%しか残されておらず、こうした生物多様性の急激な減少は、文明が最初に発達した熱帯の草原や森林で生じたとしています。また、2050年までに、さらに陸上の生物多様性の11%が失われ、地域によっては20%が失われるとする予測が紹介されています。さらに、同中間報告では、こうした生物多様性の損失の背景として、自然地域の農耕地への転換や、継続的なインフラ施設の拡大、気候変動の影響の増加が大きく関係し、世界全体で、2000年から2050年にかけて生じる自然地域の損失は、オーストラリア大陸の面積に匹敵する750万km2にのぼるものと予測しています。
生物多様性の損失を平均生物種豊富度(MSA: Mean Species Abundance)という指標によって計測し、1970、2000、2010、2050年の変化を見ると、アフリカ、インド、中国、ヨーロッパで、顕著な影響があらわれると予測されています(図序-2-21)。
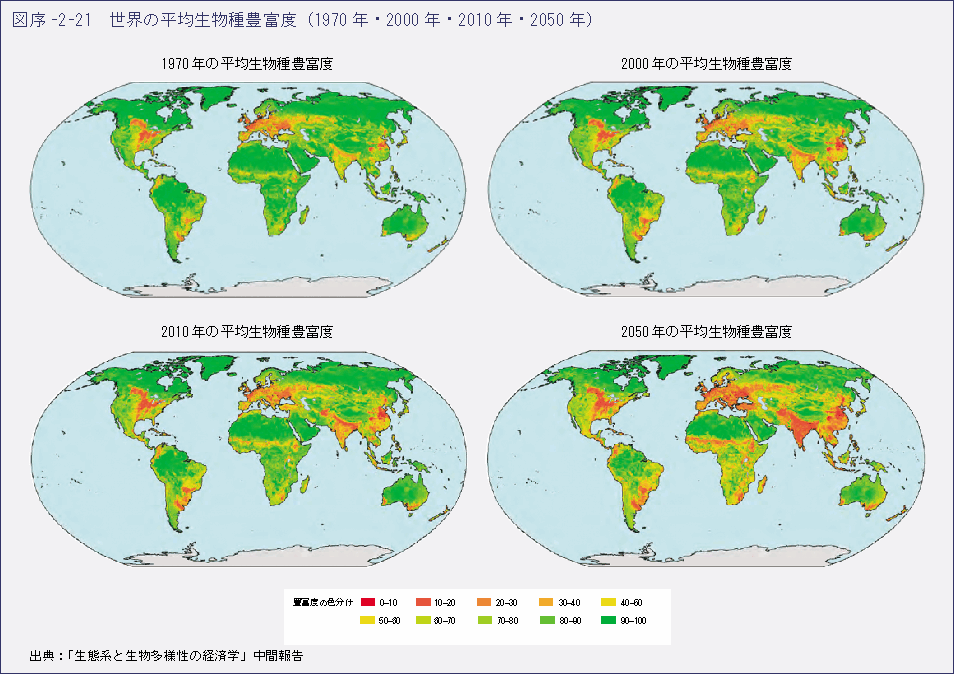
人間活動による影響のため深刻な被害を受ける可能性が指摘されている生態系の一つに、サンゴ礁があります。2009年にIUCNから発表された分析によると、サンゴ礁の「レッドリスト指標」(近い将来においても、追加的な対策をせずに生存すると見込まれる種の割合。値が1の場合、すべての種が「Least Concern(軽度懸念)」に分類されることを表し、0の場合、すべての種が「Extinct(絶滅)」に分類されることを表す)は1996年以降急激に悪化しており、この主な原因は1998年に起きたサンゴの白化現象によるものとしています(図序-2-22)。また、こうしたサンゴの白化現象は、頻度が増加するとともに長期化してきており、これは、世界的な気候変動の兆候である海水温の上昇と関係があるともしています。
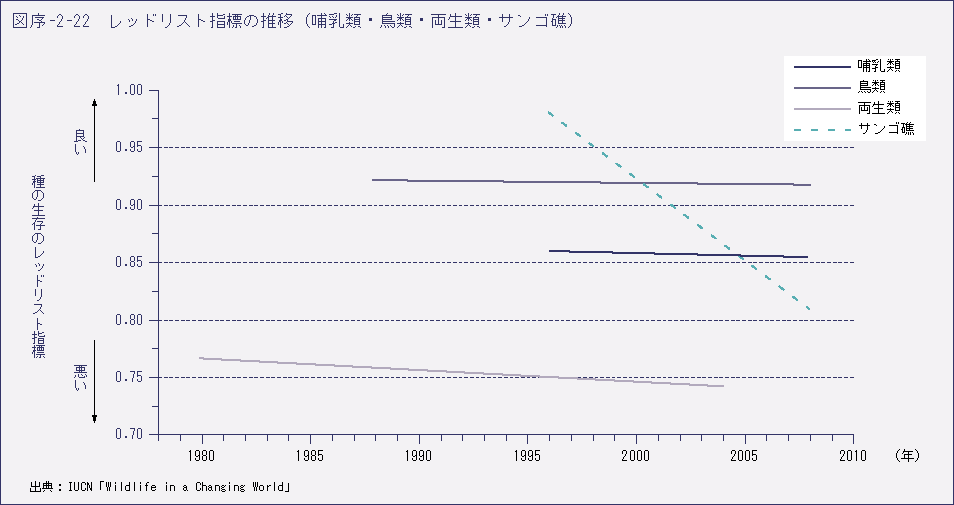
同様に、2009年に発表されたTEEBの政策立案者向け要約版によると、海岸の開発や過剰な漁業活動などの人間活動の結果として、現在、20%以上のサンゴ礁がすでに危機的な状況にあるか、差し迫った損失の危機にあるとされています。また、今後10年間で、地球温暖化や海洋の酸性化により、サンゴ礁の半減ないし全滅の可能性についても指摘しつつ、長期的にサンゴ礁が保全できるかどうかは、サンゴ礁が存在する地域の環境負荷の低減と二酸化炭素の大幅な削減次第であろうとしています。同TEEBの要約版では、こうしたサンゴの危機的状況に対応するため、公的部門による強力な政策が必要であり、社会的な公平性、生態系への効果及び経済的効率性を考慮して対策が採られるべきとしています。
日本の生物多様性の状況については、次の第1章で触れます。
平成16年(2004年)時点の年間資源使用総量(ほぼ、採掘される岩石量に相当)は、全世界で約220億トンであり、平成2年(1990年)からの年間増加量5.6億トンは、かつて資源枯渇の危機が叫ばれた1960~70年代の年間増加量3.8億トンを上回る勢いです(図序-2-23)。一方で、主要資源の可採年数は、銅32年、鉄73年、アルミニウム771年と金属種によってばらつきがあるものの、可採年数が限られているものがあります。また、リチウムイオン電池や液晶パネルの透明電極などに用いられ、今後需要の伸びが予想されるレアメタルについては、可採年数は、リチウム47年、インジウム51年、プラチナ392年など、資源量が限られたものもあります。さらに、これらのレアメタル資源は特定の地域に偏在しており(表序-2-3)、資源の安定した確保のため、資源の有効活用をさらに進める必要性があります。(独)物質材料・研究機構の予測によると、世界中が日本と同じレベルの省資源型社会に転換したとしても2050年には埋蔵量を超える資源需要が見込まれています(図序-2-24)。
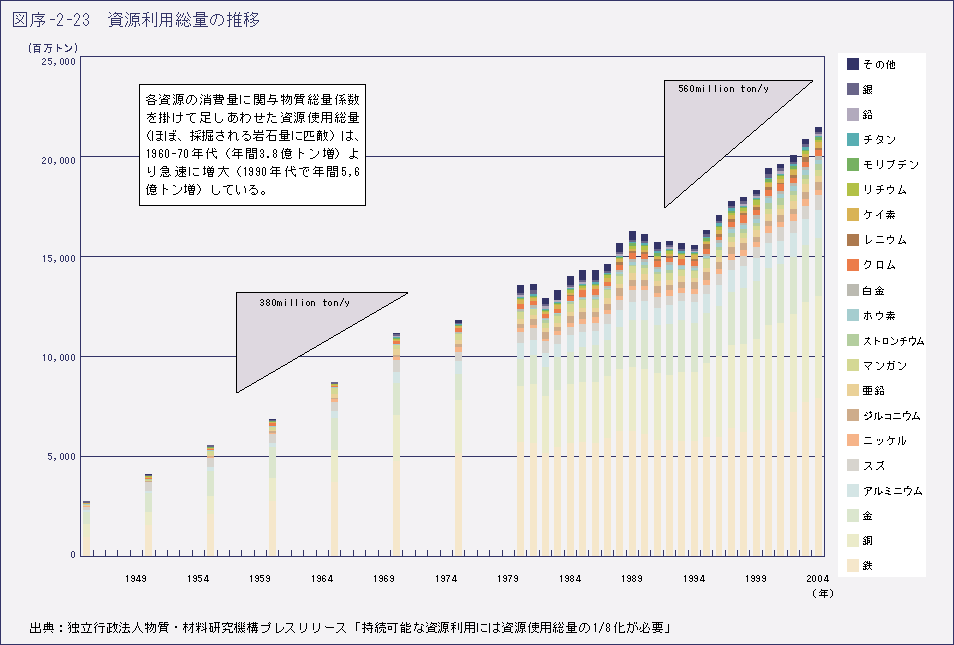
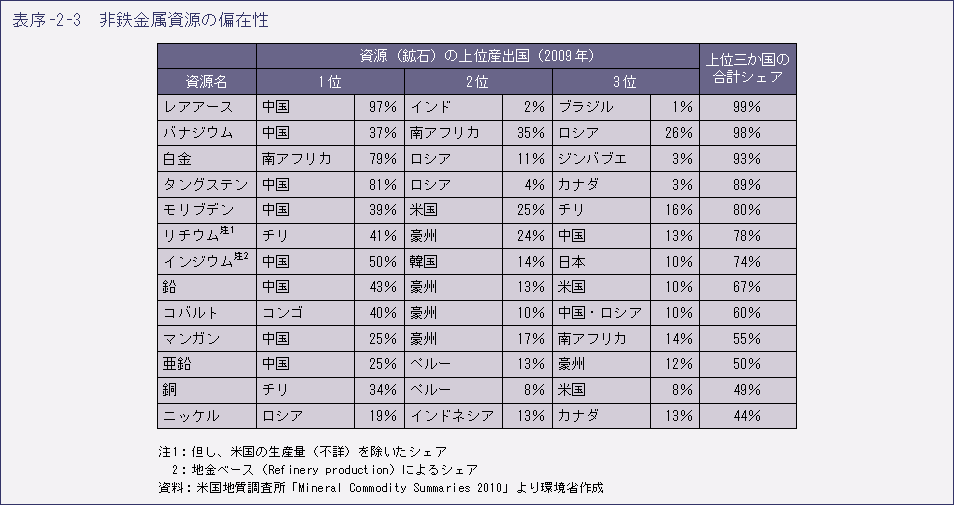
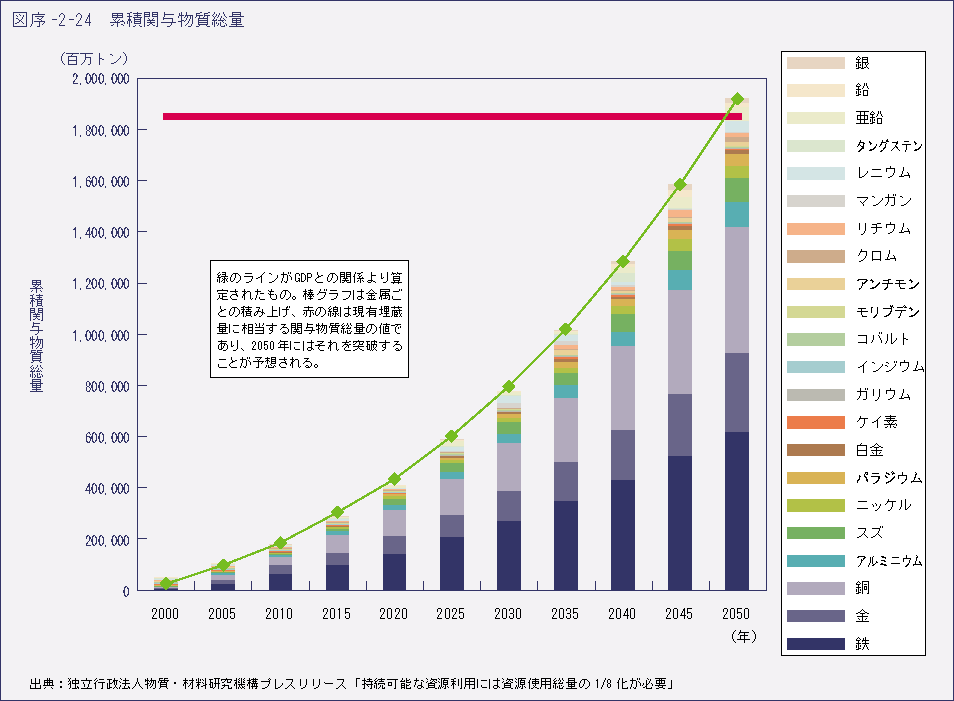
循環型社会を推し進めることは、資源の安定的な確保にもつながります。過去10年間の資源価格の推移を見てみると、資源価格の変動幅の大きさが目立ちます(図序-2-25)。こうした価格の変動は、輸入価格の高騰や、それに伴う物価の上昇といった形で、経済に大きな影響を与えます。資源の価格変動によるリスクを減らし、資源輸入国である日本の経済的安定性を確保するためにも、循環型社会を推進し、資源の安定的な供給体制の確保を図っていくことが求められます。
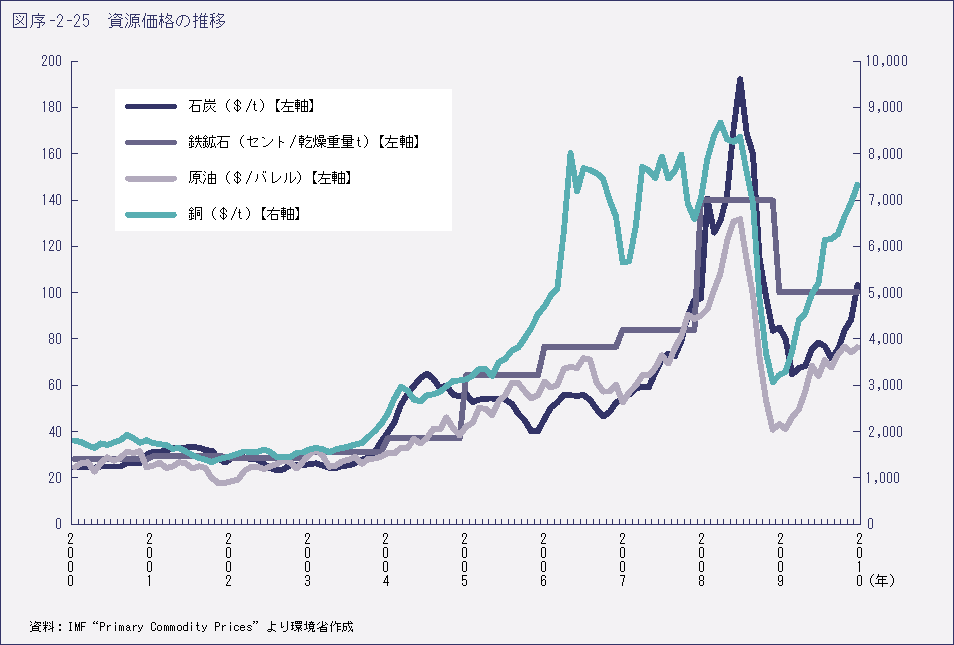
世界の廃棄物総排出量に関する将来予測によれば、2050年の廃棄物総排出量は約270億トンとなる見込みであり、2000年の約127億トンに比べ約2.1倍になるものと見込まれています。同時期の世界人口の増加(約1.5倍)よりも、廃棄物の方が大きな割合で増加するとの見込みです(図序-2-26)。1人当たり年間廃棄物排出量をみると、2000年において1人当たり年間約2.1トンであった廃棄物排出量が、2050年に約2.9トンと、約1.4倍に拡大することが予測されています。1人当たりの廃棄物量が引き続き増加していくことは、有限な資源の非効率な利用や廃棄物の埋立て処分等による環境への負荷を高めることにもつながるため、廃棄物をできる限り少なくし、より効率的な資源利用を目指した循環型社会の構築に向けた取組が、国際的規模で進められる必要があります。
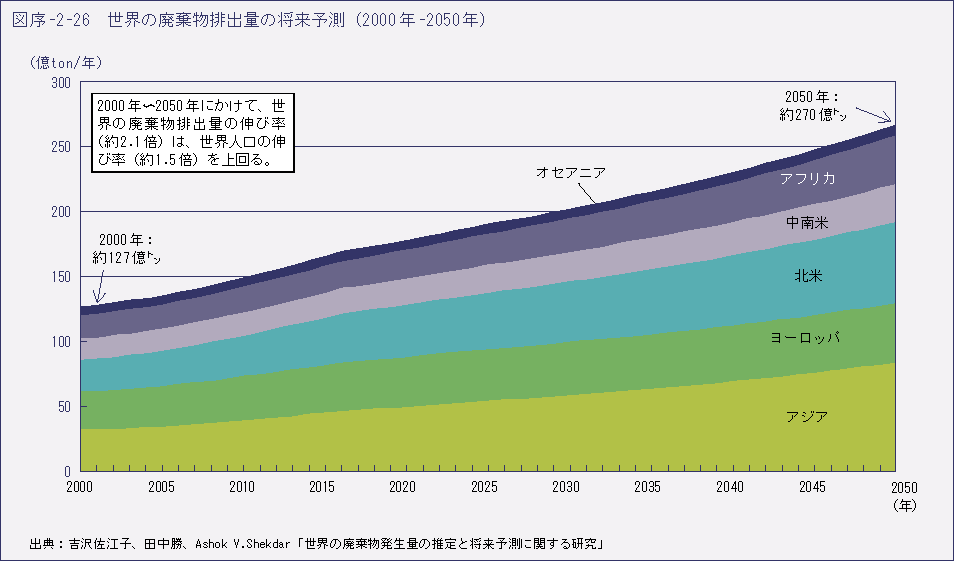
世界経済は、2007年アメリカで発生したサブプライムローン問題や、それに続く2008年のアメリカの大手証券会社の倒産等の影響を受け、2009年にはマイナス成長を記録すると見込まれています。こうした金融危機の根本的な原因は、市場参加者がリスクを適正に評価せず、適切なデュー・ディリジェンスの実施を怠っていたことなどに加え、不適切なリスク管理慣行や、複雑で不透明な金融商品、過度のレバレッジが組み合わさって、金融システムの脆弱性をつくりだしたことにあると指摘されています。この金融危機に端を発する世界的な経済危機に対しては、各国でこれを積極的な環境関連投資等によって乗り切ろうとする、いわゆるグリーン・ニューディールへと向かう動きが見られたところです。
2010年以降は、世界経済は再びプラス成長を続けると見込まれています。世界銀行の見通しによると、実質GDPで見た世界経済は、第2次世界大戦後最悪といわれる景気後退を受け、2009年にはマイナス成長となる見込みですが、2010年以降、再びプラス成長に入ると予測されています(図序-2-27)。さらに世界を高所得国と中・低所得国の二つに分けて経済成長率の動きを見てみると、2000年以降、中・低所得国の経済成長率が高所得国のそれを上回っていることが分かります。また、その傾向は少なくとも2011年まで続くものと見込まれています。
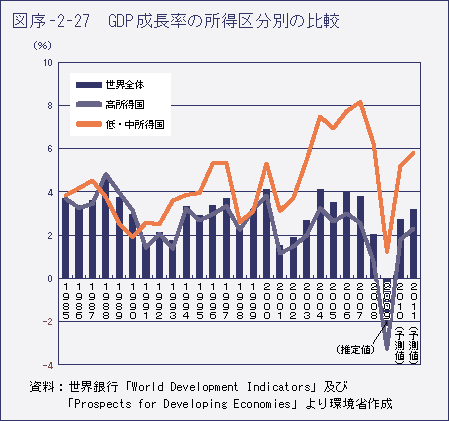
中・低所得国が大きく経済成長を遂げる中、地域・グループのGDPが世界経済全体に占める割合は大きく変化してきています。中国を含むアジア途上国のグループが世界経済に占める割合を大きく伸ばしてきており、今後も同様の傾向にあると見込まれている一方、主要先進国(G7)、先進国全体、そしてEUといったグループは急速にシェアを落としてきています(図序-2-28)。このことは、まさに、経済の趨勢がアジアへシフトしつつあることを表しています。これまでの経済発展が環境に負荷をかけつつ行われてきたことを考えると、これらの地域での環境対策の必要性は今後より一層高まるものと言えます。
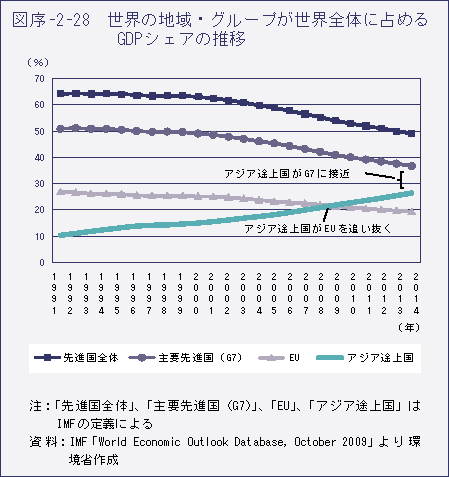
世界の貧困の状況について、国連のレポートによると、一日当たり1.25ドル(2005年物価水準)未満で生活をしている極度の貧困状態にある開発途上地域の人口数は平成2年(1990年)の18億人から平成17年(2005年)で14億人となっています。この結果、極度の貧困状態にある人は、平成2年には開発途上国の人口の約半数であったのが、平成17年には4分の1強となっています(図序-2-29)。
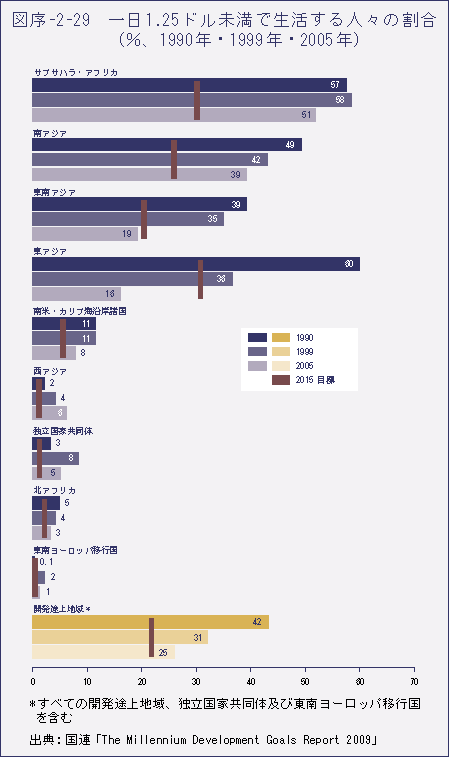
貧困率の推移や貧困状態にある人口を地域的にみると、平成2年から平成17年にかけて貧困率の劇的な減少が東アジアで起きましたが、これは、中国の急速な経済成長に大きく依るもので、これにより4億7500万人が極度の貧困状態から脱け出したとされています。一方で、サハラ以南のアフリカでは、平成2年から平成17年にかけて極度の貧困状態にある人口が1億人増えており、貧困率は引き続き50%以上となっています。
国連では2015年においても、依然として10億人もの人が極度の貧困状態にあるものと予測しています。
先進国においては、相対的な貧困、つまり所得の格差が問題となります。所得の不平等の度合いを表す指標の一つとして、ジニ係数(0から1の間の数値で示され、1に近いほど格差が大きい)があります。1980年代半ばから2000年代半ばにかけてのOECD加盟国のジニ係数の変化を見ると、24か国中19か国についてジニ係数の値が上昇しており、多くの国で不平等の度合いが高まっています(表序-2-4、図序-2-30)。
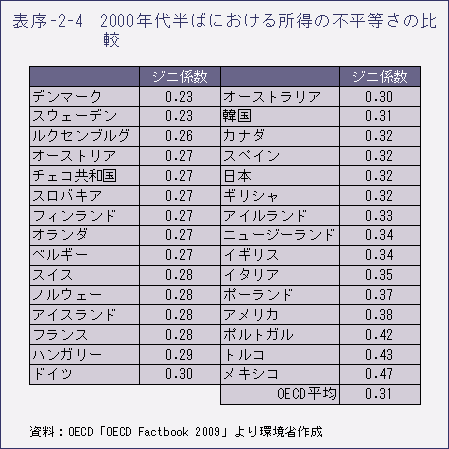
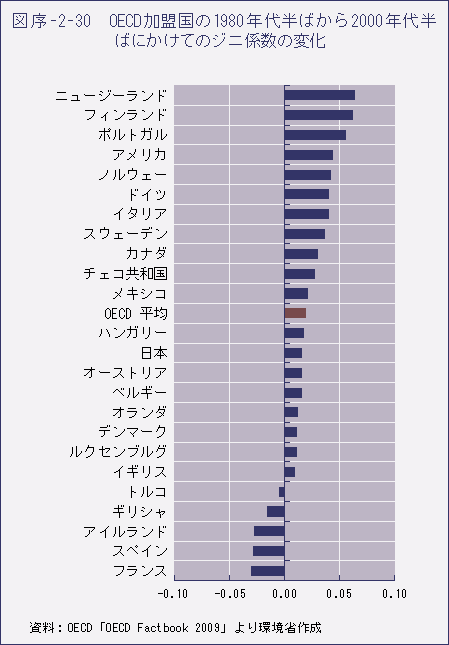
日本のジニ係数については、当初所得については年々上昇していますが、再分配所得についてみると、平成11年の調査以降ほぼ横ばいで推移してきています(図序-2-31)。厚生労働省が行った平成17年所得再分配調査結果によると、平成17年のジニ係数は当初所得で約0.53、再分配所得で約0.39となっています。また、税・社会保障の再分配によるジニ係数の改善度は、近年、調査ごとに大きくなってきており、平成17年の調査では26.4%と過去最高を記録しています。
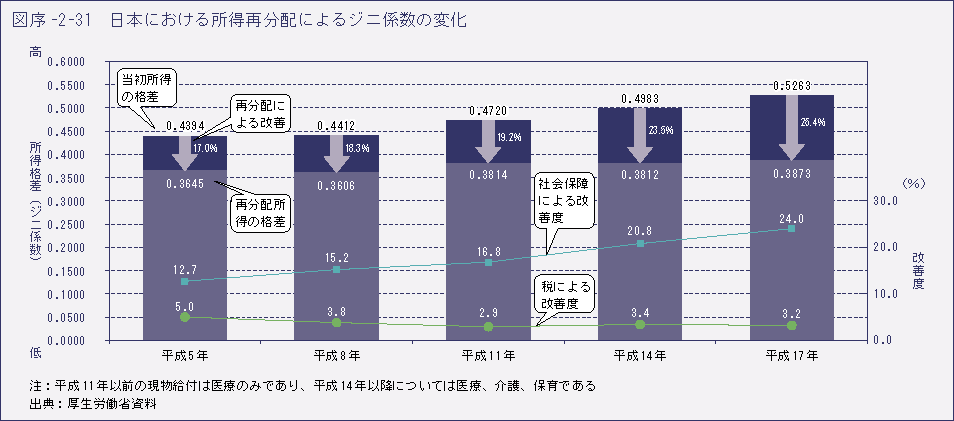
所得で見た場合の格差が広がりつつある中、必ずしも所得といった経済的な指標だけでは「生活の質」を測れないとする考えもあります。EUが2008年に発表した調査結果によると、「生活の質」に影響を与える要素について、EUの人々の84%が経済的な要素が大きな影響を与えるとする一方で、環境の状況が「生活の質」に影響を与えるとする人も80%に上ります(図序-2-32)。また、同調査結果では、3分2以上のEUの人々が、社会の発展度合いの測定において、経済的な側面だけでなく、社会的、環境的指標も等しく扱われるべきだとする調査結果を報告しています。欧州委員会によると、2007年に民間の調査会社が5大陸10か国に対して行った同様の調査においては、さらに高い75%の支持が得られたとしています。
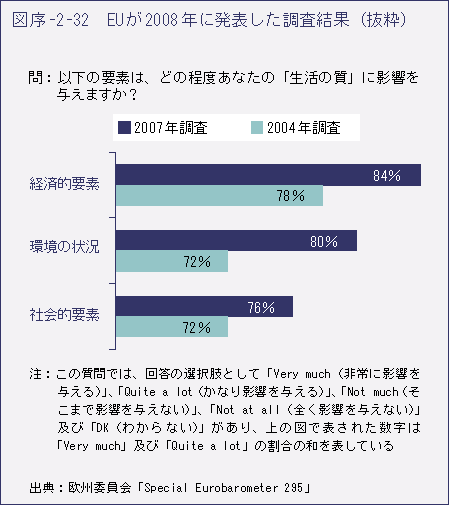
人口の推移から貧困・格差の状況まで、環境問題に関わりの深い幾つかの経済社会事象を世界的な視野で見てきました。
さまざまなデータを通して浮かび上がったのは、人口増加や経済活動の増大に伴って資源消費や環境への負荷も増大していること、また国際的な経済社会の趨勢や資源の有限性を考慮すると、これまでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動を継続することは極めてむずかしい、ということでした。人口増加に伴う食料需要の増加は、土地資源や水資源の需要増大につながり、経済活動の進展に伴ってエネルギーのニーズが高まるとともに、各種資源の消費が増加します。また、途上国で顕著に見られる人口増加は都市への人口集中を加速させ、さまざまな環境問題を惹起、深刻化させるとともに開発に伴って生物多様性が損なわれていくこととなります。このように、これまで人類が遂げてきた進歩の過程を見ると、必ずしも環境の保全が図られてこなかったと言えます。
その一方で、生活の質は必ずしも経済的な側面だけでは測れないという意識が高まり、多くの人々が、こうした資源の有限性を無視した際限ない発展を指向するあり方に疑問を感じています。近年、世界の多くの国や地方、その他さまざまな主体が地球温暖化対策や生物多様性の保全などの取組を積極的に行うようになっています。また、多くの国々や国際機関においては、「グリーン成長」と呼ばれる環境を軸とした経済発展のあり方が模索されています。これまでの発展のあり方を見直し、環境の重要性を認識した上で人類のさらなる発展を希求する、人類の発展史上重要なパラダイムシフトが、今、起きているのです。
以降では、第1章でわが国の環境の現状を見ていきます。また、第2章から第5章にかけて、地球温暖化、生物多様性、水問題そして環境と経済というそれぞれ切り口から、人類がいかに環境を保全しながら発展していこうとしているのか、また、それが可能なのかを検証していきます。
もし地球の外から人類を1日観察すると…
地球に人類が誕生したのは、ついこのあいだと言えます。この数百年であっという間に68億人まで人口を増やしました。1日に約37万人が生まれ、約16万人が亡くなり、差引き毎日約22万人が増えています。
人類は淡水を1日150km3ほど使いますが、その大部分で、1日に約800万トンの食料を生産しています。一方でその少なからぬ部分を捨てている事実もあります。
粗鋼を毎日 約370万トン生産しています。自動車を1日20万台製造する一方で、古くなった約12万台を廃棄しています。それほど使用しない場合でも自動車は個々に所有しており、所有価値から利用価値への転換は緒についたばかりのようです。また毎日 約108万トンの紙を生産しています。
エネルギーの動力利用を覚えたのは、わずか200年前です。100年前には、1日100万バレルの原油しか使っていませんでしたが、今ではその80倍の8000万バレルを使っています。これらの化石燃料などによって電力を1日に65TWh生みだし、二酸化炭素は1日に約8,000万t-CO2排出しています。
岩石を1日6,000万トンほど採掘し、鉱物資源を消費しています。また、1日約3,500万トンの廃棄物は、この50年で倍増する予測もあります。
熱帯林等を切開き、焼払いにより農地を広げ、ほかの生きものの生息域を奪うことで、個体数を増やし、寿命を伸ばしてきた面があります。その過程で、地球の森林は半分になり、不毛な土地が増え、1日に100もの種が絶滅しています。
1cmの土壌をつくるのに自然は100年~1,000年かけること、豊かな森林は数千年かけて形成されること、また、枯渇性鉱物資源や豊かな生態系の形成には、天文学的な時間が必要なことを認識する必要があります。この億年の実りを1日で費消してしまうようではいけません。
これまでさまざまな叡智を結集して数々の危機を乗り切ってきた人類ですが、この危機は、うまく乗り切れるのでしょうか。
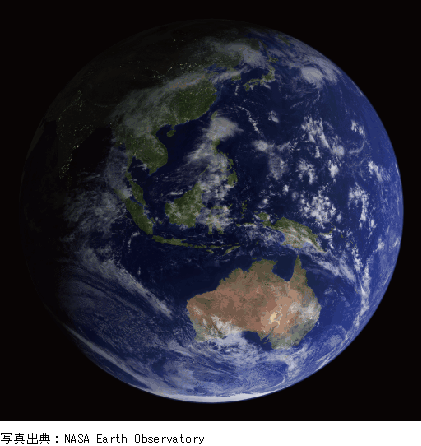
| 前ページ | 目次 | 次ページ |