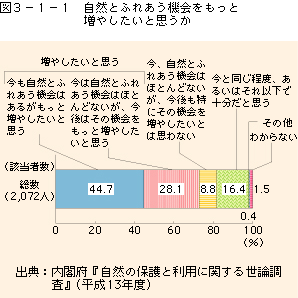
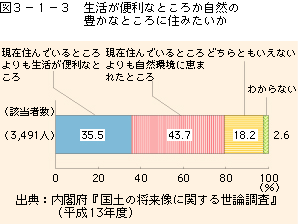
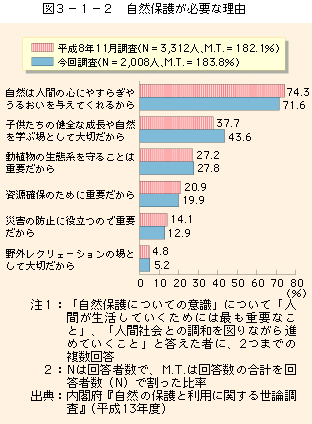
|
第3章
|
日本で、そして世界へ |
| 第1節 くらしの環境革命から始まる環境と経済の好循環 |
|
1 くらしの環境革命を目指して
|
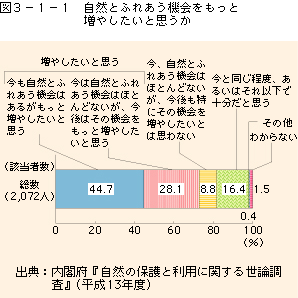 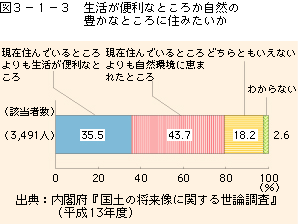
|
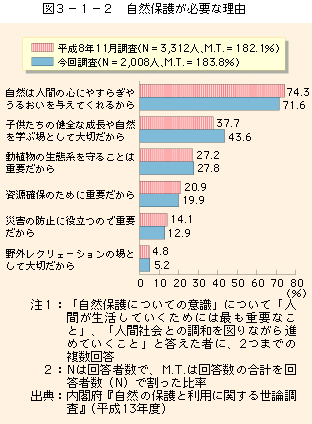 |
|
コラム
|
情報が省エネをもたらす |
①省エネナビ 省エネナビは、家庭での使用電力から省エネ効果が一目でわかるように金額に換算して表示する機器システムのことで、測定器と表示器から構成されています。測定器から1分ごとに送信される消費電力データを料金に換算して表示し、各家庭で決めた目標に対する使用量の割合を知らせます。目標を超えると省エネ度インジケーターや警報ブザーで知らせてくれます。家庭用以外にも、オフィス用の省エネナビもあります。(財)省エネルギーセンターの家庭用のモニターでは、1年平均で約13%の低減効果がありました。 ②家庭用エネルギーマネジメントシステム(HEMS) HEMSは、家庭内における電化製品を最適制御することにより、省エネルギーと快適性を追求した住環境制御システムです。具体的には、人感センサーによって消し忘れを防ぎ、システムに学習能力を付与することにより家庭内の使用状況に応じた最適の電源や温度設定の制御等を行うものです。現在、導入に向けた研究が進められています。またIT技術を活用することによりネットワークで結び、省エネナビ同様にエネルギー使用量を表示することで、意識啓発につなげることもできます。地球温暖化大綱においては、2010年までに全家庭の30%以上にHEMSを導入することを目標にしています。また、業務用ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)もあります。 |
|
|
2 「環境ビジネス」と「環境誘発型ビジネス」
|
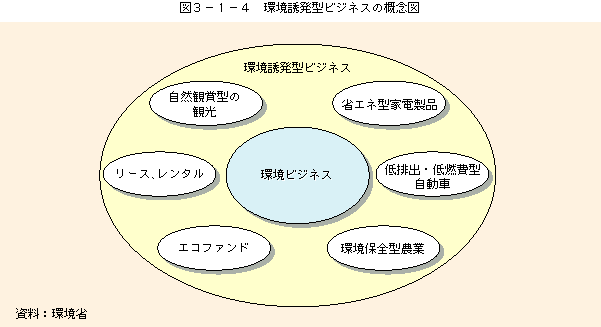
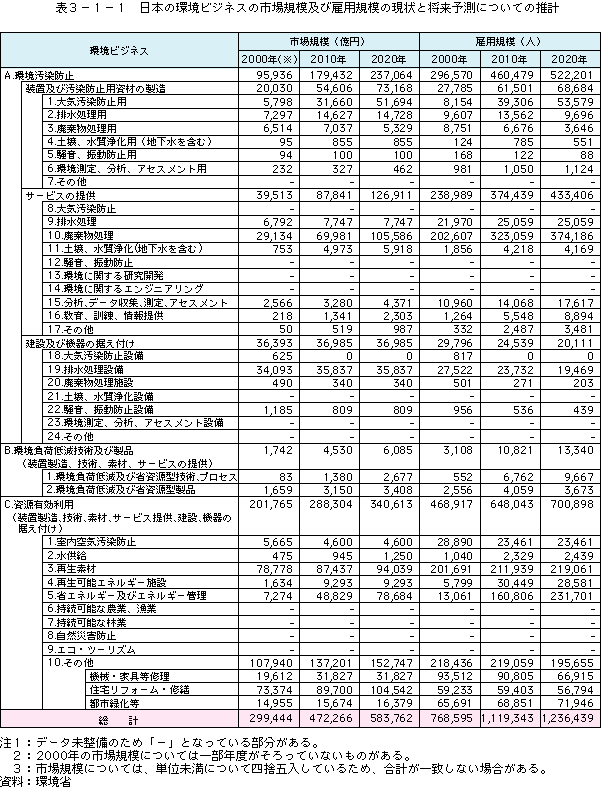
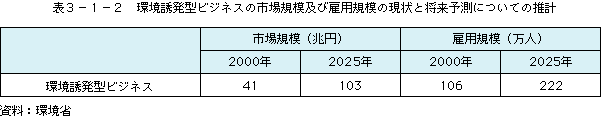
|
3 環境と経済の関係についての検討
|
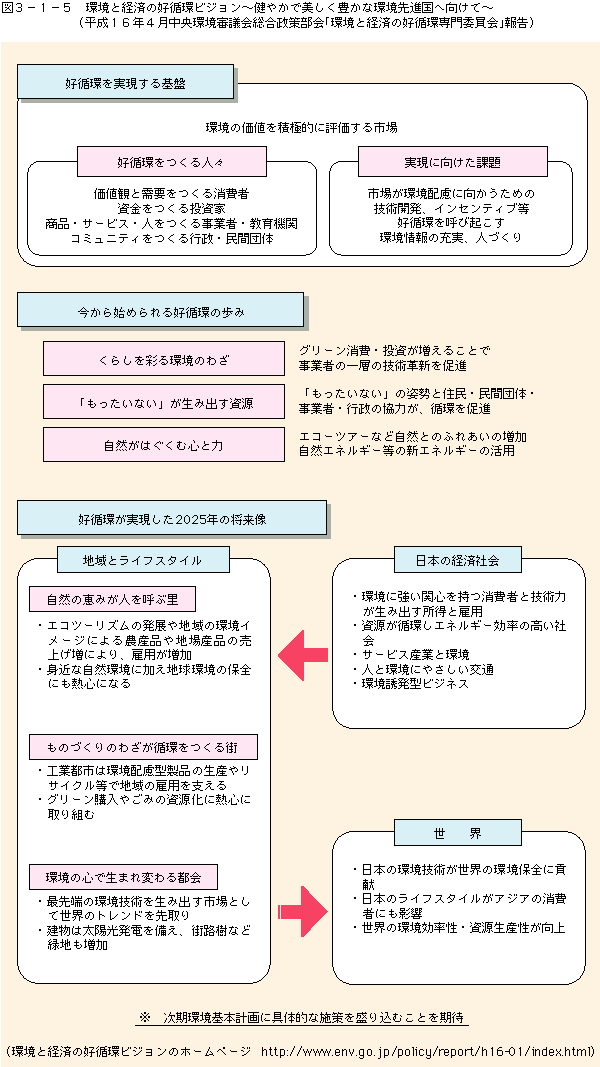
| 第2節 環境で育む心、心が守る環境-環境教育の推進- |
|
1 子どもから高齢者まであらゆる世代での環境教育の重要性
|
| 小学校低学年において、自然への感性や環境を大切に思う心を、恵み豊かな自然の中で培っていくことは健やかな心身の発達のために重要と考えられます。小学校高学年、中学校では、環境にかかわる事象を具体的に認識し、因果関係や相互関係の把握力、問題解決能力を育成させることが望まれます。高等学校では、環境問題が総合的な問題であることを理解し、さまざまな自然や社会の出来事の中から環境の状況の変化を捉え、人間の行動が環境に与える影響を予測し、その結果を適正に判断するなどの能力の育成が求められています。また、環境保全のためのライフスタイルを実践したり、社会的活動においても環境に配慮した活動を実践する能力と考え方を身に付けていくことも求められています。大学においては、環境問題を専攻する学生が増加しており(図3-2-1)、将来の環境ビジネスや環境施策を担う人材として期待されています。また、学校教育だけでなく、子どもに対する環境教育を家庭、地域社会が自らの問題として認識していく必要があります。 | 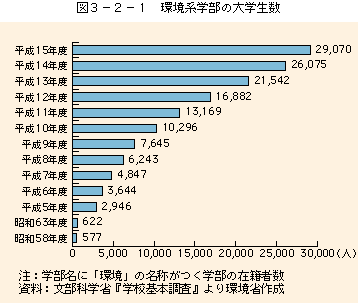 |
|
2 環境教育の推進に向けた具体的な方策
|
 |
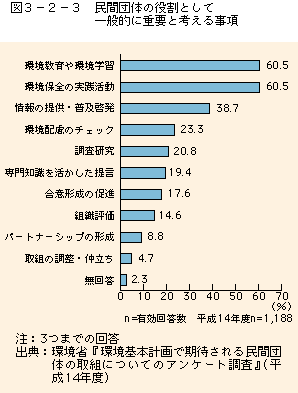 |
| 企業も環境教育を行っています。平成14年度で約4分の3の企業が従業員に対する環境教育を実施しています(図3-2-4)。地域の代表的な企業などでは民間団体と協力して地域の子どもたちなどの環境教育に取り組んでいる例もあり、今後、活発になることが期待されます。 行政には、学校、事業者、民間団体などが行う環境教育に対しての人的、技術的、財政的な支援の拡充のほか、国内外の先進的な事例の把握、環境教育に関する実態調査などが求められています。また、行政自らも環境保全活動の主体として職員を教育し、環境保全活動に取り組むことが求められています。また、こうした各関係者間のパートナーシップの構築が重要です。 |
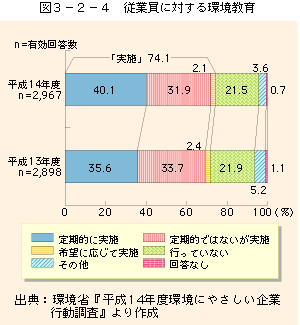 |
|
3 地域で取り組まれている環境教育
|
| (1)自然体験型の環境教育 財団法人キープ協会(山梨県高根町)では、小学生、家族、指導者を対象にしたプログラムや自然体験型環境教育の事業を実施しています。プログラムのメニューでは、自然科学を楽しむ「かがくの寺子屋」、家族で楽しめる日帰り型プログラム「家族のための自然あそび」など、幅広い年齢層を対象としたプログラムを数多く主催しています。 例えば、「家族のための自然あそび」は、連休期間や夏休み、週末を中心として開催されています。同協会のレンジャーと森の中を散歩し、木の実や枝などの材料を集め、その材料を組み合わせて昆虫や動物などの作品を作る半日のプログラムなどを実施するものです。 こうした自然体験型環境教育の事業を通じて、「主体的な関わりから、問題解決に挑む人づくり」を目指しています。((財)キープ協会のホームページ http://www.keep.or.jp/) |
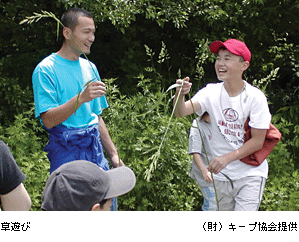 |
| (2)消費者教育 環境教育は、消費者教育の視点を併せもつものでもあります。エコライフやグリーンコンシューマー活動を積極的に行っている市民団体である沖縄リサイクル運動市民の会(沖縄県那覇市)では、平成11年より環境教育プロジェクトを立ち上げ、一般や児童を対象に、「買い物ゲーム」を行っています。この環境に配慮した買い物の模擬体験を通して、商品に付随する容器包装ごみに関する情報に関心を持ち、分別やごみ減量の工夫など、自ら考えて行動することを推進しています。 (「沖縄リサイクル運動市民の会」のホームページ http://www.ryucom.ne.jp/users/kuru2/) |
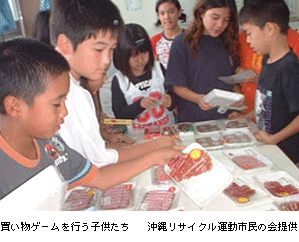 |
| (3) シニア環境大学 環境教育は、あらゆる世代に対して行われる必要があります。大阪府吹田市では、行政・民間団体・事業者等が連携し、シニア層を対象にした「すいたシニア環境大学」を開催しています。シニア環境大学では、環境問題全般にわたる講義、環境に係る民間団体の活動紹介、先進的な取組をしている企業による講義、学校での教育実習等の実践的な内容のプログラム(年間約20回)を用意し、修了生が地域の環境保全リーダーとして活動できるよう、環境教育の人材を育成する事業を行っています。 (すいたシニア環境大学のホームページ http://www.city.suita.osaka.jp/kobo/chikyu/page/004086.shtml) |
 |
|
コラム
|
緑のカーテン |
| つる性植物を利用した緑のカーテンは、熱エネルギーの遮断効果、葉の気孔からの水分蒸散により、日差しを和らげてくれるだけではなく室温の上昇も抑えるほか、騒音の低減効果などもあるといわれています。 緑のカーテン作りは、学校でも取り組まれており、子どもたちが植物に親しみながら、緑のもたらす涼しさを体感することができることから、環境教育を実践する場としても注目されています。  |
|
| 第3節 日本発の環境関連の国際標準を目指して |
|
1 国際標準を巡る動き
|
|
2 日本発の国際標準を作る動き
|
| 第4節 世界へ広げる環境のわざ-国際環境協力- |
|
1 政府の国際環境協力
|
|
2 地方公共団体の国際環境協力
|
|
3 企業の国際環境協力
|
| 日本の企業も、さまざまな形で国際環境協力を行っています。例えば、ある自動車会社は、環境改善や保全に向けた活動を助成する制度を作り、「持続可能な発展のための社会的投資」を基本テーマとして、環境技術と環境学習の2つの分野で地域に根ざした実践型プロジェクトに対して支援を行っています。 環境面での技術水準と意識の高い日本企業の海外直接投資が、開発途上国の環境保全に重要な役割を果たしている例も見られます。直接投資の場合、単に製品を輸出するのではなく、環境に配慮した企業の運営、環境効率の向上を含む生産設備の維持管理システム等のノウハウも、併せて供与されます。これは環境技術の効率的な移転につながり、開発途上国の人材育成にも役立っています。 |
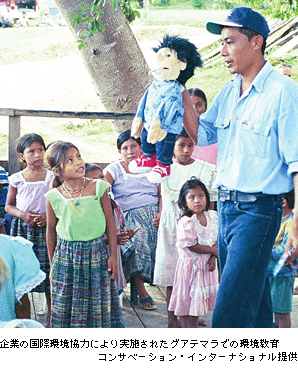 |
|
4 NGO等の国際環境協力
|
| 開発途上国で活躍するNGO等の民間団体のきめ細かな対応は、環境分野をはじめとする日本の国際協力において極めて重要であると認識されてきています。また、その活動の場の多様性や迅速性、地域に根ざしたアイデアも注目されるところです。 例えば、NPO法人「緑の地球ネットワーク」では、中国の黄土高原で保水や土壌の浸食防止と改善のためにマツや灌木を植林したり、貧しい村の小学校にアンズやリンゴなどの付属果樹園を造り、その収益の一部を教育条件の改善に充てる活動を行っています。このNPOは、植物園、実験林場等を造り、造林樹種の多様化や技術改善、人材育成にも取り組んでいます。 |
 |
| むすび 環境のわざと心で地球環境保全 |