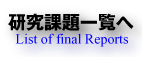 |
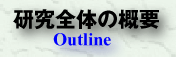 |
|
課題名 |
A-1 オゾン層の回復を妨げる要因の解明に関する研究 |
||
|
課題代表者名 |
今村 隆史 (独立行政法人国立環境研究所成層圏オゾン層変動研究プロジェクトオゾン層モデリング研究チーム) |
||
|
研究期間 |
平成11−13年度 |
合計予算額 |
318,102千円 (うち13年度 100,943千円) |
|
研究体制 (1)塩素負荷と極渦活動度の変化によるオゾン層破壊の変化とその検出に関する研究 (独立行政法人国立環境研究所、東北大学、名古屋大学、東京大学) (2)成層圏の冷却化に伴う極成層圏雲組成及び反応の変化に関する研究 (独立行政法人産業技術総合研究所、東京大学) (3)温暖化及び大気組成変動がオゾン層破壊に及ぼす影響のモデル化に関する研究 (独立行政法人国立環境研究所、東京大学、京都大学、広島市立大学、姫路工業大学) (4)オゾンゾンデ観測に基づく中緯度におけるオゾン変動要因の解析的研究 (国土交通省気象庁観測部) (5)観測データ等による三次元光化学モデルの検証に関する研究(独立行政法人国立環境研究所) |
|||
|
研究概要 1.序 モントリオール議定書などに基づいたフロンnロンをはじめとしたオゾン層破壊関連物質の規制の結果、対流圏における有機ハロゲン化合物の濃度の減少は1995年頃から認められる様になり、成層圏での濃度も現在ピークに達し緩やかな減少に転じ始めたと考えられている。しかしながらその一方で、南極オゾンホールはその面積、出現期間、オゾン破壊量などいずれの点からも拡大を続けている。また1990年代に入ってからの北極域でのオゾン層破壊もその程度が増している。例えば2000年3月には高度18km付近で70%にも及ぶ北極域のこの高度領域において過去最大のオゾン破壊が観測された。これらの事実はオゾン層の将来は単に大気中のハロゲン濃度のみに依存しているわけではない事を示唆している。 将来のオゾン層の状況に関して、1998年の「オゾン層破壊の科学アセスメント」の中でも、成層圏を取り巻く状況がオゾン層破壊が顕著化していなかった1980以前に比べて変化しているため、成層圏ハロゲン濃度が1980年レベルまで減少してもオゾン層が1980年以前の状況に戻らない可能性のある事が指摘されている。大気ハロゲン濃度以外に成層圏オゾン濃度変動に影響を与える要因としては、温室効果気体(CO2、CH4、N2Oなど)や航空機エンジン排ガスなど人間活動に伴う汚染物質の増大、水蒸気や火山噴火などに伴う硫酸エアロゾル量の変動と言った大気組成の変動や更には気候変動(地球の温暖化)が考えられている。しかしながら、その要因がこれまでに観測されてきたオゾン減少トレンドにどの程度寄与してきたのか、将来のオゾン層破壊にどの程度影響を及ぼすのか等、について定量的な評価を行うためのメカニズムの解明は充分になされているとは言えない。 今後のオゾン層の将来予測に向けて、極域ならびに中緯度でのオゾン減少トレンド要因の分類化、地球温暖化の進行や大気組成変動に対するオゾン層の応答を明らかにする事が必要である。
2.研究目的 本研究は、オゾン層破壊物質である有機塩素・臭素濃度が減少段階に転じたにも拘らず、オゾン層の回復が認められない現状を受け、現在およびこれまでのオゾン層破壊の観測からオゾン層の回復を妨げていると思われる現象の検出・抽出、回復に影響を及ぼし得ると思われる要因の定量化に向けたモデル数値実験、モデル化に必要なプロセスの解明を目的とした。課題を構成する各サブテーマの目標は次の通りである。 (1)塩素負荷と極渦活動度の変化によるオゾン層破壊の変化とその検出に関する研究 極渦内でのオゾン層破壊には塩素・臭素濃度の増大ならびに極渦と極渦内の極成層圏雲生成が重要な役割を果たしている。それ故、極域でのオゾン層の回復を左右する要因を考える上で次の3つの疑問を明らかにする必要がある。1)極渦はここ数十年間でその大きさや強度は変化していないのか、2)極渦内および極渦の縁での化学的なオゾン破壊速度は単にハロゲン濃度から類推されるレベルにあるのか、3)極渦内でのオゾン破壊が中緯度のオゾン破壊にも影響を及ぼしているのか。そこで本サブテーマでは、長期間の気象データを用いた極渦の変動の可視化と変動の特徴の抽出、国際共同観測に基づく極渦内オゾン破壊速度の決定実験と極渦内での化学的オゾン破壊数値シミュレーション、観測とモデルに基づいた中緯度上空への高緯度空気塊の到来とそのオゾン変動への影響評価、を行うことを目的とした。 (2)成層圏の冷却化に伴う極成層圏雲組成および反応の変化に関する研究 極域でのオゾン層破壊において極成層圏雲(PSC)の組成ならびにPSC上での不均一反応による活性化ハロゲンの生成、更には活性化ハロゲン(ClOx、BrOxサイクルを構成するラジカル類)の気相中での活性化速度がオゾン分解速度に影響を及ぼしている。極域オゾン破壊に影響を及ぼしている反応場が極域成層圏の冷却化に伴い変化しているかを、観測データやモデル解析から引き出すための基礎データの決定が不可欠である。そこで、本サブテーマでは赤外遠隔計測データからのPSCの組成情報の抽出のための分光データの決定、ガス状のClOxの光学活性リザーバーとして以前から予測されているClmOn型活性種の安定性に関する反応データの決定、氷表面でのNOy化学種の光化学反応データの決定を行った。 (3)温暖化および大気組成変動がオゾン層破壊に及ぼす影響のモデル化に関する研究 CO2などの増加に伴う地球温暖化、メタンやN2Oなどの微量気体変動、極域オゾン減少の中緯度への波及、火山噴火などによる成層圏エアロゾルの変動、などはオゾン層破壊に少なからず影響を与えるものと考えられている。将来のオゾン層変動予測に向けては、数値モデルに上記の要因を組み入れる必要があると同時に、予測のためのモデルの性能の評価とモデルの改良が必要である。そこで本サブテーマでは、光化学−放射結合モデルとして大気大循環化学モデル(CCSR/NIES AGCM)およびCCSR/NIES AGCMをベースとした化学輸送モデル(CCSR/NIESナッジングCTM)の開発、CCSR/NIES AGCMを用いた火山噴火などのモデル化、CCSR/NIESナッジングCTMを用いた極−中緯度空気の混合のモデル化、成層圏エアロゾルの効果を考慮したオゾン破壊サイクルに対するメタン増加の影響評価、などを行うことを目的とした。 (4)オゾンゾンデ観測に基づく中緯度におけるオゾン変動要因の解析的研究 中高緯度でオゾン減少トレンドの最も大きい冬季から春季にかけて集中的にオゾンゾンデ観測を実施し、通常(週一回)より観測間隔の小さい(時間分解能の高い)オゾンの高度分布データを取得する。この観測データと気象データを基に、オゾンの高度別トレンドを詳細に解析し、またオゾンの高度分布の変動特性について解析を行う。この成果と他のグループで得られた成果により、中緯度域でのオゾン減少トレンドに対する輸送や化学的オゾン破壊の影響を評価する事を目的とした。 (5)観測データ等による三次元光化学モデルの検証に関する研究 非総観的な分布の衛星データから総観的マップを得るために、「トラジェクトリーマッピング」手法を用い、特定の日時へと計測値を時間的に前後移流させることによって総観的マップを構築する。さらに、この手法を短寿命種にも適用するために化学変化を考慮に入れた「トラジェクトリー光化学ボックスモデル」を開発する。開発した手法を用いて、ILASデータをもとにした1996/1997年のオゾン破壊プロセスの解明を目的とした。
3.研究の内容・成果 (1)塩素負荷と極渦活動度の変化によるオゾン層破壊の変化とその検出に関する研究 1.極渦活動度の長期変化及び年々変動 欧州中期気予報センター(ECMWF)や米国環境予測センター/米国大気研究センター(NCEP/NCAR)、気象庁(JMA)等によって作成される天気予報用の三次元気象データ(客観解析データ)を用いて、渦位と呼ばれる物理量(保存量なので、一種のトレーサーとして扱える)の分布を求め、極渦の可視化を行った。可視化された極渦の長期変動から、極渦の特性を表すパラメータを抽出して、そのトレンド及び長期・短期変動について解析した。その結果ここ40年間に北半球では、極渦持続期間が長く、極渦が強く、そして極渦半径が大きく、なる傾向がある事が明らかになった。極渦のトレンドは北極域での近年のオゾン破壊の深刻化と良く呼応している。一方南半球でも極渦の強度と半径に焦点を絞って解析を行ったところ、極渦の強度に関しては正のトレンドがあるが、極渦半径は一定または縮小傾向にあることが明らかになった。 2.極渦内オゾン破壊速度の決定実験(MATCH) 1999/2000年に東シベリアヤクーツク、2000/2001年、2001/2002年の冬についてヤクーツク及び西シベリアサレクハードにおいて、欧州プロジェクトMATCH実験に即したオゾンゾンデ観測を行い、それぞれの冬・春季のオゾン破壊速度決定の一翼を担った。特にヤクーツクは欧州とアメリカ大陸との間にある唯一の北極域オゾンゾンデステーションであるためMATCH実験にとって重要な役割を果たした。1999/2000年には、米国と欧州が初めて共同で行った北極成層圏オゾン集中観測実験であるSOLVE/THESEOが実施され、MATCH実験はその一環として、欧州、米国、日本、ロシア、カナダ等の参加によって行われた。その結果、北極域において最大のオゾン破壊(高度19kmで約70%)が確認された。 3.極渦内オゾン破壊のシミュレーションとオゾンゾンデ観測データによる検証 欧州中期予報センター(ECMWF)の全球気象データを用いたトラジェクトリー光化学ボックスモデルによって1995年12月1日から1996年4月31日の極渦内及び極渦の縁におけるオゾン破壊のシミュレーションを行った。その結果、3月半ばまでについては、モデルと観測結果は良い一致を示した。3月半ばには極渦の分裂があり、極域と中緯度の空気の混合があったためモデルはオゾン濃度を過小評価した。極渦の縁では極渦内部よりオゾン濃度は高かったが、これは主に12月1日における初期濃度の差によるものであり、オゾン破壊速度の絶対値に大きな差はなかった。巨大NATの有無についての感度実験を行ったが、その効果は1月、2月には小さかった。 4.極渦内オゾン破壊が日本を含む極渦外のオゾン層に及ぼす影響に関する観測と解析 極渦内でオゾン破壊された空気塊が日本上空に到来している事を示すデータが、北海道でのオゾンゾンデおよびミリ波放射計によるオゾン観測、北海道ならびにつくばでのフーリエ変換赤外分光計によるHCl, HNO3, HFなどの観測、三陸での大気球観測などを通して取得された。例えば国立環境研究所と名古屋大学太陽地球環境研究所が1996年4月23日に北海道母子里で観測したオゾン鉛直分布と、気象庁が札幌において1972年4月23日に観測したオゾン鉛直分布を比較すると、1996年4月23日には高度19km付近で50%以上オゾンが減少していた。トラジェクトリー上で走る光化学モデルによる解析を行った結果、オゾン濃度の観測値の差異は主として塩素濃度の差である事が分かった。また、PSC発生条件を変えた計算の結果、塩素負荷の高い状況では気温低下も相当の影響を及ぼすことも明らかになった。 (2)成層圏の冷却化に伴う極成層圏雲組成および反応の変化に関する研究 1.極成層圏雲(PSC)組成決定のための赤外分光データの取得 高角度反射および透過型フーリエ赤外分光(FTIR)測定装置で赤外光透過基板上に堆積させた模擬PSCの反射および透過スペクトルの測定を行った。その結果、PSCのタイプIの候補とされているNATおよびNADでは異なる周波数帯域にクリスチャンセン効果に伴う吸光度の急激は変化が認められる事が分かった。この事は、赤外大気計測を用いたPSCの組成の同定を可能にものと考えられる。 2.酸化ハロゲンラジカル類の安定性 世界で始めて高リュードベリ状態原子(イオン化エネルギーよりわずかに低いエネルギー状態にある原子)を用いた反応実験用の質量分析装置を開発した。高リュードベリ原子はArやXeなどの希ガス原子を電子線衝撃することで発生した。開発した質量分析装置の特徴は電子を捕獲してマイナスイオンになり易い(電子親和力の大きい)化学種を高感度に検出できる可能性がある点である。実際、NO2でその感度を測定した結果、109molecule/cm3台の感度が得られた。開発した装置を用いて、極渦内で存在の可能性が指摘されているClO3, ClO4などの酸化ハロゲンラジカルの検出を試みたが、検出されなかった。検出感度の見積もりから、上記の酸化ハロゲンラジカル類は熱力学的に不安定で、その定常濃度はかなり低い事が明らかとなった。 3.氷表面へのNOxの吸着とその光化学反応 PSCタイプIIの組成として考えれらているIce表面へのNOxの吸着とその光脱離過程を表面光脱離質量分析装置を作成して調べた。その結果、Ice表面へのNO2の吸着はN2O4の形で起こる事、大気の窓領域での光脱離では光解離したNOが氷表面あるいは内部に取り込まれて緩和する事で脱離が阻害されている事分かった。 (3)温暖化および大気組成変動がオゾン層破壊に及ぼす影響のモデル化に関する研究 1.極域オゾン破壊と極域−中緯度間の輸送過程のモデル化 極域でのオゾン分解の数値モデルのために、3次元化学輸送モデル(CCSR/NIESナッジングCTM)への臭素系の光化学反応の導入を行った。その結果、極域での臭素の気相反応によるオゾン破壊は10-20DU程度であるが、火山爆発などで硫酸エアロゾルが増大した条件下ではエアロゾル上での不均一反応を介したオゾン破壊への寄与が増大し、特に北極域では最大で40%が臭素反応系によるオゾン分解であるケースも見出された。また、極渦内の空気塊のトレーサーとしてN2Oを標的化学種として、極渦崩壊時の中緯度空気との混合過程をCCSR/NIESナッジングCTMでシミュレーション実験を行い、ILAS観測データと比較した。その結果、渦位からは極域空気塊は極渦崩壊後約3週間ほどで中緯度空気との区別出来なくなるのに対し、低濃度N2O空気塊は約2ヶ月間存在する事が予想され、観測データと良い一致が得られた。また、モデル計算結果の解析から、極渦崩壊後の北半球高緯度成層圏での水平渦拡散係数などの見積もりが可能となった。 2.CO2増加に伴う成層圏化学・放射過程の変化 CO2の増加は放射冷却を促進する事で成層圏の冷却化をもたらし、気相化学過程のみを考慮するとオゾン生成反応の促進と分解反応の抑制によりオゾン層の回復を促すはずである。そこで、中・低緯度成層圏でのオゾン収支に対するCO2増加の影響の全体像を把握する目的で硫酸エアロゾル上での代表的な不均一反応も考慮に入れた1次元化学モデルでのCO2倍増実験を行った。その結果、CO2の増大は予想通り、上部成層圏での気温低下によるオゾン濃度の増大をもたらし、その結果下部成層圏では紫外線到達量が低下することでNOx生成量が抑えられ、結果としてNOxサイクルの低下によるオゾン分解速度の減少→オゾン濃度の増大が引き起こされる事が明らかとなった。一方、極域オゾンでは成層圏の冷却化は成層圏での循環やPSC生成などへの影響を通してオゾン層変動に影響を与えるものと予想される。よって、化学・放射過程と力学過程を結合した3次元モデルでの解析が必要であり、CCSR/NIES AGCMを用いたCO2増加実験に向けたモデルの整備を行った。 3.火山噴火などによる成層圏エアロゾル変動のモデル化 火山噴火が成層圏エアロゾル量・分布を大きく乱す事で成層圏での化学・力学過程に与える影響評価のための数値モデル解析を行う目的で、CCSR/NIES AGCMを用いたエアロゾル数値実験を行った。まず、火山噴火を想定しない平穏時での成層圏エアロゾルの分布を対流圏での硫黄化合物(SO2, OCSなど)の化学・輸送過程もモデルに含めてシミュレーション計算を行った。モデルにより再現された硫酸エアロゾルの表面積分布などは平穏時の観測結果と同様な値が得られた。硫酸エアロゾル上での代表的な不均一反応のオゾン分解への影響も調べられた。なお、SOxの地表放出から対流圏を通過して成層圏硫酸エアロゾル生成を3次元モデルで再現した研究は本研究が始めてである。更にCCSR/NIES AGCMをピナツボ火山噴火を想定した数値実験にまで応用した。その結果、噴火直後の大量のSO2の成層圏への流入はSO2→硫酸変換時間の増加を招く事、エアロゾル生成に伴う放射強制力への影響が平穏時と比べて1桁程度増加する事、エアロゾルの輸送過程の再現が観測結果と良い対応を示している事、噴火後の気象場への影響はエアロゾルの長波吸収が主として引き起こしている事、不均一反応を介したオゾン破壊の加速など認められる事、火山噴火の数年以上のタイムスケールの力学場に対する化学的影響が無視出来ない事、などを大気大循環モデルで初めて明らかにした。 4.エアロゾル反応を考慮したメタン増加の影響評価 メタンの増加はCl+CH4®HCl+CH3反応を通してClOxサイクルの停止反応の加速をうながし、結果としてオゾン分解速度の低下(回復の促進)をもたらす、とされている。一方、メタンの酸化によって生成するH2COは硫酸エアロゾル上での不均一反応―特にHNO3との反応―によってHOX, NOXサイクルに影響を与え、結果としてオゾン分解速度の変化をもたらすと考えられている。この仮説を評価するために、H2CO+HNO3→HC(O)OH+HONO反応を中心とした不均一反応データを決定した。その結果、HC(O)OHがホルムアルデヒドを介したNOy→NOx変換の指標になりうる事、平穏時の成層圏エアロゾルレベルでは上記不均一反応(後続の不均一反応を含む)はNOx/NOyバランスには大きな影響を与えない事がわかった。 (4)オゾンゾンデ観測に基づく中緯度におけるオゾン変動要因の解析的研究 北半球中高緯度は冬季から春季にかけてオゾン減少傾向が顕著な地域である。そこで、気象庁高層気象台(つくば市)において、冬季から春季にかけて3年間にわたり、集中的にオゾンゾンデによる特別観測を実施し、通常(週一回)より観測間隔の短い(時間分解能の高い)オゾンの高度分布データを取得した。そしてこの特別観測データをもとに、極渦の接近、オゾン分圧の低下などの現象に注目して事例を取り上げ、各事例についてバックトラジェクトリなどを用いて、オゾン層の変動機構の解析を行った。その結果、北半球中緯度(つくば)上空のオゾン層に対しては、高緯度の極渦の発達及び低温によって極渦内部で起こる化学的なオゾン破壊、オゾン量の少ない低緯度からの空気塊の移流、成層圏内でのオゾン輸送などが影響していることがわかった。また、これらの結果をもとにして統計的な解析を行い、圏界面高度、準2年周期振動(QBO)、太陽活動などの要素が中緯度のオゾン層に与える影響の度合いを見積もることができた。 (5)観測データ等による三次元光化学モデルの検証に関する研究 本研究では、特定の日付および地域における長寿命化学種のILAS データの移流を行って、当該地域における計測された化学種の空間分布を得るために、トラジェクトリー上を移動するモデルを開発・使用した。短寿命化学種については、トラジェクトリー光化学ボックスモデルも用いた。分布の不均一なトラジェクトリー到着点を規則的グリッドに補間するためには、バーンズ客観解析スキームを適用した。また、トラジェクトリー光化学モデルを1996年冬季のオゾン破壊プロセスの研究とオゾンゾンデ・データの解析に適用した。統計的アプローチの適用にあたっては、極渦内の数多くの非断熱トラジェクトリーを考慮した。非断熱冷却率の平均値は、これらのトラジェクトリーに沿った交差等温位面上運動の平均値とした。温位475Kでのオゾンゾンデ観測によって得られたオゾン混合比は、モデルによって得られたその温位の平均オゾン混合比と標準偏差内で一致した。
4.考察 極域でのオゾン層破壊では極渦の存在が化学的オゾン分解の点からも輸送の点からも重要な役割を果たしている。その極渦の長期変動を明らかにするため、極渦の特徴を強度・半径・持続期間・安定性と言った量を定義して分類し、その年々変動ならびにトレンドを明らかにした事(サブテーマ−1)は、今後の極渦活動の変動予測に対する新たな指針とモデルの検証データの提供の点から価値がある。また、極域でのオゾン破壊速度に関する国際共同観測実験(サブテーマ−1)とトラジェクトリー化学モデルによる解析(サブテーマ−1,5)は、特に北極域でのオゾン分解速度予測における問題点を明らかにした。また、3次元化学輸送モデルの開発と化学反応モジュールの充実により、今後の規制で問題となる臭素・ヨウ素化合物に関連するオゾン分解反応への寄与の評価が可能になりつつある(サブテーマ−3)事は大きな進展である。極域でのオゾン層破壊では極成層圏雲(PSC)の組成やPSC上での反応が重要な役割を果たしている事は既に指摘されており、数値モデルへのインプットデータの充実は重要な課題である。観測データからのPSCの組成情報の抽出のための分光データの整備やPSCを介した反応データの蓄積(サブテーマ−2)はモデルへの直接・間接的インプットデータの蓄積に貢献するものである。 極域でオゾン破壊された空気塊が中緯度成層圏でのオゾン減少に及ぼす影響はサブテーマ−1,3,4で調べられた。日本上空でのオゾンならびにオゾン破壊関連物質の集中観測ならびにトラジェクトリー解析から北極域でオゾン破壊された空気塊の到来が確認された(サブテーマ−1,4)。極域空気塊と中緯度大気との混合が渦位の変化から解析したのでは早くに起こりすぎ、N2Oなどのトレーサー物質の追跡により混合過程の理解が可能になる事が、CTMなどのモデルで確認できた事(サブテーマー3)は今後の極域−中緯度相互作用を理解する上で有用な成果である。 大気組成変動の中でもCO2の増加は気候変動との関連から、オゾン層の将来予測において重要な課題である。本課題では、その第一段階として、1次元化学モデルを用いた気相オゾン分解反応を中心にCO2の増加がオゾン層破壊に及ぼす影響評価に取り組み、CO2増加が放射および化学過程に与える影響とその相互作用を明らかにした(サブテーマ−3)。1次元モデルは極域を含めたオゾン層の将来予測に直接結びつくものではないが、中・低緯度の成層圏オゾンに与える影響の全体像を理解する上で貴重な情報を提供するものである。温暖化のオゾン層−特に極域オゾン−に与える影響は成層圏循環や気象場の変化、更にはPSC生成を含む化学過程を正当に考慮する必要があり、そのモデル開発(CCSR/NIES AGCM)は、H13年度FS-1課題と連携して進められており、下記の成層圏エアロゾルの数値実験への応用でも分かる様に、世界的レベルに達しつつある点は評価できる。 今後の火山噴火などによるオゾン層変動などを評価するためにも、将来予測モデルでのこれまでの火山噴火時のオゾン層変動の再現実験は不可欠である。火山噴火が成層圏での力学や化学への影響を3次元大気大循環モデルで再現した例はこれまでになく、今後のオゾン層変動に対する火山噴火の影響の評価を可能にした点(サブテーマ−3)は特筆できる成果である。エアロゾルを介した不均一反応としてオゾン層予測モデルへの導入前にその寄与を評価しなければならない反応がいくつか提案されている。その一つとして、メタンの増加→塩素の不活性化→オゾン層の回復、と言うシナリオに対し、CH4酸化®H2CO生成®不均一反応を通したHOx、NOx、ClOxの活性化によるオゾン破壊の加速と言う仮説を評価するための反応データの決定がなされ、ギ酸の観測の重要性が指摘された(サブテーマ−3)点は、化学モデルの進展にとって重要であった。 以上の様に、本研究課題では各サブテーマが関連しあいながら、オゾン層の回復を妨げる可能性のある物理的・化学的要因をこれまでの観測データから抽出するとともに、数値モデルを用いた評価が行われる一方で、その定量化に向けた試みも行う事が出来た点で、初期の目的を達したと考えられる。
5.研究者略歴 課題代表者:今村隆史 1957年生まれ、東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了、理学博士、 現在、独立行政法人国立環境研究所オゾン層モデリング研究チーム総合研究官 主要論文: (1) T. Imamura, Y. Rudich, R. K. Talukdar, R. W. Fox, and A. R. Ravishankara: "Uptake of NO3 onto water solutions: rate coefficients for reactions of NO3 with cloud water constituents", J. Phys. Chem., 101, 2316-2322 (1997). (2) T. Imamura and H. Akiyoshi: "Uptake of acetone into sulfuric-acid solutions", Geophys. Res. Lett., 27, 1419-1422 (2000). (3) T. Imamura and N. Washida: “Rate constants for the reactions of HCCCO and NCCO radicals with molecular oxygen”, Int. J. Chem. Kinet., 33, 440-448 (2001).
サブテーマ代表者 (1): 中根英昭 1951年生まれ、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了、理学博士、 現在、独立行政法人国立環境研究所大気圏環境研究領域上席研究官 主要論文: (1) Nakane, H. et al., "Comparison of ozone profiles obtained with NIES DIAL and SAGE II measurements", J. Meteorol. Soc. Jpn., 71, 153-159 (1993). (2) Nakane, H. et al., "Lidar observation of ozone over Tsukuba (36°N, 140°E)", NASA Conf. Publ., 3266, Ozone in the Troposphere and Stratosphere Part 2, 863-866 (1994). (3) Nakane, H. et al., "Variation of ozone and aerosols in Eastern Asia during SESAME", Polar Stratos. Ozone 1995, Pyle J. A., Harris N. R. P., and Amanatidis G. T., eds., Pub. Eur. Communities, 492-496 (1995).
(2):佐藤 優 1958年生まれ、熊本大学工学部卒業、現在、独立行政法人産業技術総合研究所環境分子科学研究グループ主任研究員 主要論文: (1) 佐藤 優、極オゾンホール形成の化学的メカニズム、資源と環境,3, 219-227、1994.7 (2) 佐藤 優、極成層圏エアロゾルの生成の物理化学、エアロゾル研究, 11,100-107,1996.6
(3): 今村隆史 (同上)
(4): 下道 正則 1953年生まれ、京都大学大学院終了、現在気象庁観測部オゾン層情報センター所長 主要論文 (1)下道正則:反転観測によるオゾン鉛直分布導出プログラムについて、高層気象台彙報, 50, 45-51, (1990). (2)下道正則:反転観測による新オゾン鉛直分布導出プログラムについて、高層気象台彙報, 53, 27-38, (1993). (3)下道正則・伊藤真人:波長別紫外域日射計のボールダー国際相互比較、高層気象台彙報, 55, 11-18, (1995).
(5): Lukyanov Alexander 1955年生まれ、Moscow Physical Technical Institute卒業、ロシア高層大気観測所主任研究員 主要論文: (1) Lukyanov, A, V. Panasenko, and V. Yushkov, "Using numerical method of finite volumes for research of viscous flow near furface sensor", Trudi CAO, 179 62-68 (1992), (2) Lukyanov, A, M. Khaploanov, N. Sholohova, and V. Yushkov, "Influence of velocity on results of humidity measurements by optical rocket hygrometer", Trudi CAO, 179 69-73 (1992), (3) Lukyanov, A, V. Yushkov, H. Nakane, H. Akiyoshi, "Ozone loss rate from box model studies and ozonesonde data along the air mass trajectories arriving at Yakutsk station in winter-spring season", Polar stratospheric ozone, 1997, 297-300 (1998).
|
|||