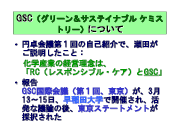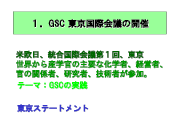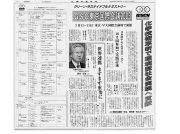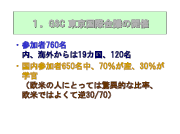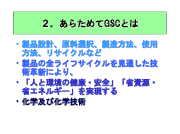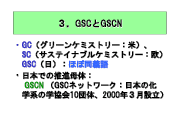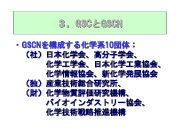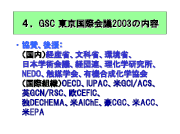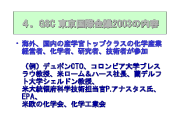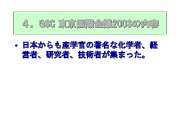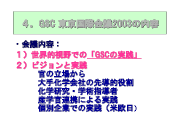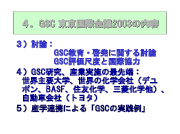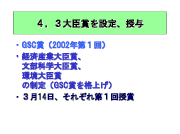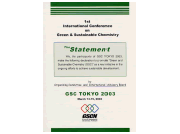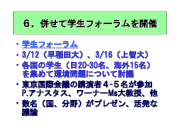| <ゲスト> | ||
| 蒲生 昌志 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 | |
| <学識経験者> | ||
| 原科 幸彦 | 東京工業大学工学部教授 | |
| 安井 至 | 東京大学生産技術研究所教授 | |
| <市民> | ||
| 有田 芳子 | 全国消費者団体連絡会事務局 | |
| 石川 廣 | 日本生活協同組合連合会環境事業推進室長 | |
| 後藤 敏彦 | 環境監査研究会代表幹事 | |
| 崎田 裕子 | ジャーナリスト、環境カウンセラー | |
| 角田季美枝 | バルディーズ研究会運営委員 | |
| 中下 裕子 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長 | |
| 村田 幸雄 | (財)世界自然保護基金ジャパンシニア・オフィサー | |
| <産業界> | ||
| 出光 保夫 | 日本石鹸洗剤工業会環境保全委員長 | |
| 瀬田 重敏 | (社)日本化学工業協会広報委員長 | |
| 田中 康夫 | 日本レスポンシブル・ケア検証センター長 | |
| 横山 宏 | (社)日本電機工業会地球環境委員会副委員長 | |
| 大野 郁宏 | 日本チェーンストアー協会環境問題小委員会委員 小林珠江代理 | |
| <行政> | ||
| 西郷 正道 | 農林水産省大臣官房技術総括審議官 大森昭彦代理 | |
| 片桐 佳典 | 神奈川県環境科学センター所長 | |
| 鶴田 康則 | 厚生労働省大臣官房審議官 | |
| 仁坂 吉伸 | 経済産業省製造産業局次長 | |
| 南川 秀樹 | 環境省環境保健部長 | |
| (欠席) |
北野 大 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授
河内 哲 (社)日本化学工業協会ICCA対策委員長 菅 裕保 (社)日本自動車工業会環境委員会副委員長 | |
| (事務局) | 安達一彦 環境省環境保健部環境安全課長 | |
 (蒲生) はじめまして。産業技術総合研究所の蒲生と申します。よろしくお願いします。本日はこのような場で話をする機会をいただき、大変光栄に思います。最初に申し上げておくべきことですが、今回お話する内容は、私自身の個人的な意見あるいは見解であり、必ずしも私が属する、関係する組織の意見を代弁、代表しているわけではないことを了解していただきたいと思います。
(蒲生) はじめまして。産業技術総合研究所の蒲生と申します。よろしくお願いします。本日はこのような場で話をする機会をいただき、大変光栄に思います。最初に申し上げておくべきことですが、今回お話する内容は、私自身の個人的な意見あるいは見解であり、必ずしも私が属する、関係する組織の意見を代弁、代表しているわけではないことを了解していただきたいと思います。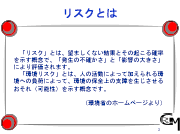
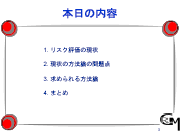
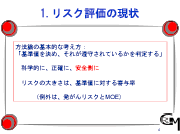

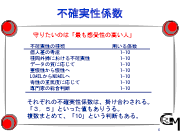
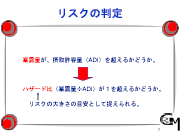
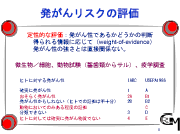
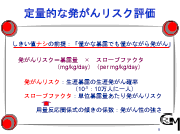
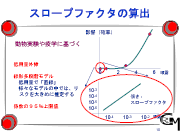
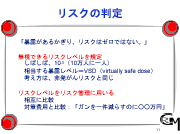
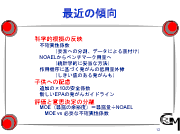
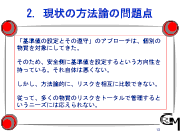
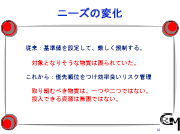

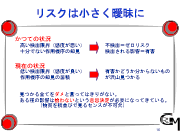
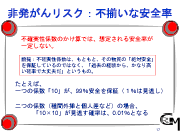
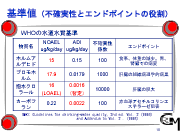
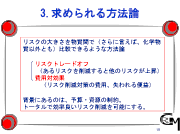
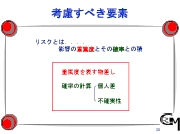
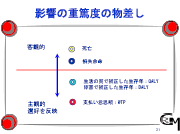
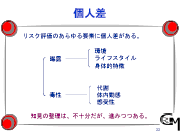

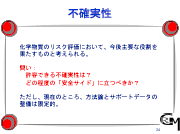
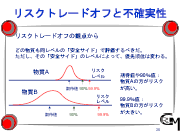
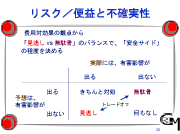
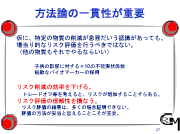

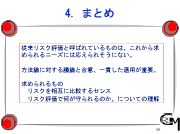
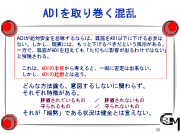
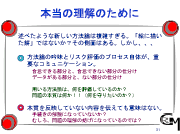
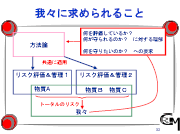
 (石川)
(石川)