| <学識経験者> | ||
| 安井 至 | 東京大学生産技術研究所教授 | |
| <市民> | ||
| 有田 芳子 | 全国消費者団体連絡会事務局 | |
| 後藤 敏彦 | 環境監査研究会代表幹事 | |
| 崎田 裕子 | ジャーナリスト、環境カウンセラー | |
| 角田 季美枝 | バルディーズ研究会副運営委員長 | |
| 中下 裕子 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長 | |
| 村田 幸雄 | (財)世界自然保護基金ジャパンシニア・オフィサー | |
| 山元 重基 | 日本生活協同組合連合会環境事業推進室長 | |
| <産業界> | ||
| 出光 保夫 | 日本石鹸洗剤工業会環境保全委員長 | |
| 河内 哲 | 日本レスポンシブル・ケア協議会企画運営委員長 | |
| 瀬田 重敏 | (社)日本化学工業協会広報委員長 | |
| 田中 康夫 | 日本レスポンシブル・ケア協議会企画運営委員 | |
| 仲村 巖 | (社)日本自動車工業会環境委員会副委員長 | |
| 小林 珠江 | 日本チェーンストアー協会環境問題小委員会委員 | |
| <行政> | ||
| 岩尾 總一郎 | 環境省環境保健部長 | |
| 大森 昭彦 | 農林水産省大臣官房技術総括審議官 | |
| 片桐 佳典 | 神奈川県環境科学センター所長 | |
| 鶴田 康則 | 厚生労働省大臣官房審議官 | |
| 増田 優 | 経済産業省製造産業局次長 | |
| (欠席) |
北野 大 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 原科幸彦 東京工業大学工学部教授 橋本伸太郎 (社)日本電機工業会環境政策委員会委員長 |
|
| <ゲスト> | ||
| 浦野紘平 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 | |
| 神沼二眞 | 元厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所化学物質情報部長 | |
| 宮本純之 | 国際純正応用化学連合(IUPAC)環境問題上級顧問、 (財)化学物質評価研究機構顧問 |
|
| 山本喜久治 | 化学リーグ21政策センター | |
| 司会(事務局) 安達一彦 環境省環境保健部環境安全課長 | ||
| ○事務局が配布した資料 | ||
| 資料1 | 今後の進め方について検討が必要な項目(案) [PDF(73KB)] | |
| 資料2 | 地域フォーラムの進め方と今後のスケジュール(案) [PDF(59KB)] | |
| ○事務局が配布した参考資料 | ||
| 参考資料1 | 「化学物質と環境円卓会議」(リーフレット) [HTML] | |
| 参考資料2 | 「化学物質と環境円卓会議」の運営要領 [PDF(8KB)] | |
| 参考資料3 | 化学物質と環境円卓会議第1回議事録 [HTML] | |
| ○ゲストが使用した資料 | ||
| 化学物質に関するリスクコミュニケーションについて [PDF(953KB)] | ||
| 化学物質と環境に関するリスクコミュニケーション [PDF(275KB)] | ||
|
適切なリスクコミュニケーションと科学者の役割 [PDF(864KB)] SCOPE/IUPAC International Symposium on Endocrine Active Substances [PDF(1,627KB)] |
||
| 「環の国」化学物質と環境 -円卓会議:意見- [PDF(255KB)] | ||
| ○円卓会議メンバーが配布した資料 | ||
| 地域対話参加者別割合 [PDF(101KB)] | ||
 (後藤) 後藤です。環境監査研究会で、環境マネジメントや環境報告書に携わっています。この円卓会議にかかわる関係でいいますと、PRTRの法律を作るときの技術検討会の委員もしていました。現在、ISOで環境コミュニケーション規格を作っていますが、その日本のエキスパートにもなっています。どうぞよろしくお願いします。
(後藤) 後藤です。環境監査研究会で、環境マネジメントや環境報告書に携わっています。この円卓会議にかかわる関係でいいますと、PRTRの法律を作るときの技術検討会の委員もしていました。現在、ISOで環境コミュニケーション規格を作っていますが、その日本のエキスパートにもなっています。どうぞよろしくお願いします。 (山元) 日本生協連は約600の会員生協の連合会です。生協としてもいろいろ事業的な取り組み、あるいは組合員の活動等々、環境活動を積極的にしていますので、その辺の視点からも参加させていただければと思っています。よろしくお願いします。
(山元) 日本生協連は約600の会員生協の連合会です。生協としてもいろいろ事業的な取り組み、あるいは組合員の活動等々、環境活動を積極的にしていますので、その辺の視点からも参加させていただければと思っています。よろしくお願いします。 (司会:安井) 安井です。それでは、司会役を務めさせていただきたいと思います。ほかの2人の学識経験者が欠席ですので私に回ってきたものと理解しています。
(司会:安井) 安井です。それでは、司会役を務めさせていただきたいと思います。ほかの2人の学識経験者が欠席ですので私に回ってきたものと理解しています。 今日はこのような席にお招きいただきましてありがとうございました。私自身は今はフリーになりましたので、あまりお役に立つかどうかわかりませんが、まず自分の立場をはっきりさせるために少し過去のお話をしたいと思います。
今日はこのような席にお招きいただきましてありがとうございました。私自身は今はフリーになりましたので、あまりお役に立つかどうかわかりませんが、まず自分の立場をはっきりさせるために少し過去のお話をしたいと思います。 (有田) 提言の中に3つ書いてあるのですが、市民の側にはこういうものが必要だということが、インターネット利用技術の習得と知識となっているのですが、例えば企業側に求められるものはどういうものがあるか、もしお考えがあったらお聞かせいただきたいのですが。
(有田) 提言の中に3つ書いてあるのですが、市民の側にはこういうものが必要だということが、インターネット利用技術の習得と知識となっているのですが、例えば企業側に求められるものはどういうものがあるか、もしお考えがあったらお聞かせいただきたいのですが。 (小林) 今日のご説明の中の今のご提言については、私はまだホームページを拝見してないし、その中身については何も知識も持っていないので、それについてのコメントはできません。ただ、3つのご提言で、後藤さんの発言と共通する部分と少し違う部分とがあるのでが、私は企業といっても小売業ですので、非常に一般市民に近い側からの発言になると思います。確かに無料でこんなにいい情報が見られる、それを一般市民がインターネットの利用技術を習得し、その情報をきちんと認識できるということはすばらしいことだと思います。けれども、私はそういうことを理解できる、活用できる、そういう国民性を持たなければだめだ、そういう国でなければだめだということはおっしゃるとおりですが、私の感覚としては、そこに至るにはかなり長い時間が必要だと思います。どうしたら本当に理想とするそういう社会ができるのだろうということにこの円卓会議が活用できれば、本当の意味の円卓会議になるのだと私は強く思います。このテーマ、先生のご提言だけでも、きちんとどうすれば本当に正しい情報が伝わり、そのことを受けて市民の方が混乱しないで、すべて危険だというふうにならない、あるいはきちんと自分の正しい判断で選択できる、どうすればいいのかということをぜひこの円卓会議を使って共有して啓蒙できるようにしていただきたいと思いました。
(小林) 今日のご説明の中の今のご提言については、私はまだホームページを拝見してないし、その中身については何も知識も持っていないので、それについてのコメントはできません。ただ、3つのご提言で、後藤さんの発言と共通する部分と少し違う部分とがあるのでが、私は企業といっても小売業ですので、非常に一般市民に近い側からの発言になると思います。確かに無料でこんなにいい情報が見られる、それを一般市民がインターネットの利用技術を習得し、その情報をきちんと認識できるということはすばらしいことだと思います。けれども、私はそういうことを理解できる、活用できる、そういう国民性を持たなければだめだ、そういう国でなければだめだということはおっしゃるとおりですが、私の感覚としては、そこに至るにはかなり長い時間が必要だと思います。どうしたら本当に理想とするそういう社会ができるのだろうということにこの円卓会議が活用できれば、本当の意味の円卓会議になるのだと私は強く思います。このテーマ、先生のご提言だけでも、きちんとどうすれば本当に正しい情報が伝わり、そのことを受けて市民の方が混乱しないで、すべて危険だというふうにならない、あるいはきちんと自分の正しい判断で選択できる、どうすればいいのかということをぜひこの円卓会議を使って共有して啓蒙できるようにしていただきたいと思いました。 こんにちは。私の資料になぜか「先生資料」と書いてあるのですけれども、環境省はこれから気をつけた方がいいと思います(笑)。
こんにちは。私の資料になぜか「先生資料」と書いてあるのですけれども、環境省はこれから気をつけた方がいいと思います(笑)。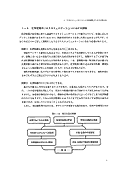
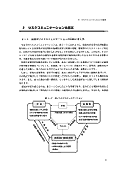
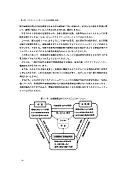

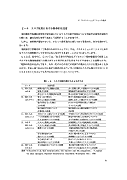
 (仲村) 浦野さんのお話は大変よくわかるし、納得できるような気がします。こういう中でコミュニケーションの大切さが1つあるわけですが、もう1つ、絶対がないといいますか、相対で考えるのと、白黒がないと、行政上、やはりこういうものはフレキシブルに対応しないといけないということを言っているのだと思うのです。法制化しようとするとどうしてもデジタル化しなければいけないところもありますし、白か黒かを分けていく。それに対してこういうものは、化学業界はよく知りませんが、例えば我々業界ではよく、「自主規制」というのをしています。自主規制は、結果が変わったら、あるいは状況が変わったら次の対応を変えられるのです。我々は非常にいい制度だと思っているのですが、何か行政の中にもそういう比較的自由度のある、フレキシブルな仕組みを入れていかなければいけないのではないかということを言っているのではないかと思うのですが、そういうことでもいいのでしょうか。
(仲村) 浦野さんのお話は大変よくわかるし、納得できるような気がします。こういう中でコミュニケーションの大切さが1つあるわけですが、もう1つ、絶対がないといいますか、相対で考えるのと、白黒がないと、行政上、やはりこういうものはフレキシブルに対応しないといけないということを言っているのだと思うのです。法制化しようとするとどうしてもデジタル化しなければいけないところもありますし、白か黒かを分けていく。それに対してこういうものは、化学業界はよく知りませんが、例えば我々業界ではよく、「自主規制」というのをしています。自主規制は、結果が変わったら、あるいは状況が変わったら次の対応を変えられるのです。我々は非常にいい制度だと思っているのですが、何か行政の中にもそういう比較的自由度のある、フレキシブルな仕組みを入れていかなければいけないのではないかということを言っているのではないかと思うのですが、そういうことでもいいのでしょうか。 (村田) 10の誤解の中に1つだけつけ加えていただければと思う点があります。それは市民はみんなゼロリスクを求めていたり、それから特に化学物質を排出している企業は全部悪だと思い込んでいるという誤解もあるのではないかと思います。それを加えていただければ大変ありがたいのですが。
(村田) 10の誤解の中に1つだけつけ加えていただければと思う点があります。それは市民はみんなゼロリスクを求めていたり、それから特に化学物質を排出している企業は全部悪だと思い込んでいるという誤解もあるのではないかと思います。それを加えていただければ大変ありがたいのですが。 (片桐) リスクコミュニケーションは合意ではなくてお互いに理解するためだというのはよくわかりますけれども、価値観がそれぞれ違っているという中で、リスクコミュニケーション自体が途中で行き詰まってしまうというようなことがよくあるのではないかと思うのです。どうしても違った意見の中でもって進めなくなってしまう。そういったときにはどのようにしていったらいいのかという考えがあったら教えていただきたいのですが。
(片桐) リスクコミュニケーションは合意ではなくてお互いに理解するためだというのはよくわかりますけれども、価値観がそれぞれ違っているという中で、リスクコミュニケーション自体が途中で行き詰まってしまうというようなことがよくあるのではないかと思うのです。どうしても違った意見の中でもって進めなくなってしまう。そういったときにはどのようにしていったらいいのかという考えがあったら教えていただきたいのですが。 宮本です。早速本題に入らせていただきたいと思います。私の話は、題をつけるとすれば、「適切なリスクコミュニケーションと科学者の役割」です。先程も少しお話が出ていますが、悪い言い方をすると、リスクコミュニケーションを狂わせる最大の原因の1つはサイエンティストにある。私は自分がこれまでその分野でずっと仕事をして、いろいろな事例に直面してみて、そのように思わざるをえないところが多々あると思いました。ですからそういうことも含めて、少しリスクコミュニケーションにおけるサイエンティストの役割とはいかにあるべきか、ということについて皆さん方に少し話題を提供させていただきたいと思います。
宮本です。早速本題に入らせていただきたいと思います。私の話は、題をつけるとすれば、「適切なリスクコミュニケーションと科学者の役割」です。先程も少しお話が出ていますが、悪い言い方をすると、リスクコミュニケーションを狂わせる最大の原因の1つはサイエンティストにある。私は自分がこれまでその分野でずっと仕事をして、いろいろな事例に直面してみて、そのように思わざるをえないところが多々あると思いました。ですからそういうことも含めて、少しリスクコミュニケーションにおけるサイエンティストの役割とはいかにあるべきか、ということについて皆さん方に少し話題を提供させていただきたいと思います。
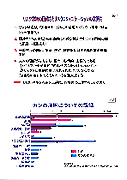
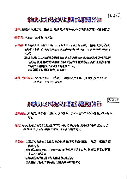
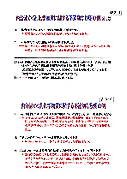

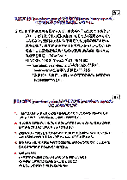
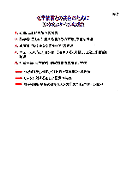
 (角田) バルディーズ研究会の角田です。今の科学がリスクコミュニケーションにとってとても大切だというお話はよくわかりますし、浦野先生が座長であったときにも科学の大切さということは十分認識されていたと思いますが、科学といっても、こういう言葉はあまり使いたくないのですが、専門ばかという言葉がありますように、1つの科学の領域については詳しくても、ほかの科学の領域については全く詳しくないというような専門家がマスメディア等に登場して、また混乱した情報を流すということは多々あるわけです。リスクコミュニケーションというのはその後に意思決定がそれぞれあるわけですが、その意思決定に対して科学者がどこまでできるのか、といったところは議論が必要ではないかと思います。その辺はリスクコミュニケーションと科学者に関してもう少し議論が必要かと思いますし、先程言われた社会科学者とか、あるいはイギリス等でやっているパブリック・イン・サイエンスのような、一般市民に科学をきちんと伝えるというようなところがまだまだ日本では不十分だと思いますので、その辺も必要ではないかと思います。
(角田) バルディーズ研究会の角田です。今の科学がリスクコミュニケーションにとってとても大切だというお話はよくわかりますし、浦野先生が座長であったときにも科学の大切さということは十分認識されていたと思いますが、科学といっても、こういう言葉はあまり使いたくないのですが、専門ばかという言葉がありますように、1つの科学の領域については詳しくても、ほかの科学の領域については全く詳しくないというような専門家がマスメディア等に登場して、また混乱した情報を流すということは多々あるわけです。リスクコミュニケーションというのはその後に意思決定がそれぞれあるわけですが、その意思決定に対して科学者がどこまでできるのか、といったところは議論が必要ではないかと思います。その辺はリスクコミュニケーションと科学者に関してもう少し議論が必要かと思いますし、先程言われた社会科学者とか、あるいはイギリス等でやっているパブリック・イン・サイエンスのような、一般市民に科学をきちんと伝えるというようなところがまだまだ日本では不十分だと思いますので、その辺も必要ではないかと思います。 (中下) 科学者の方々がそれぞれ自分たちのことを反省され、自己研鑽を遂げられるというようなことは大変結構なことだと思います。ぜひやっていただきたいと思うのですけれども、私ども弁護士の立場からすると、やはり化学物質によってさまざまな被害が発生してしまったということについては、深刻に受け止めざるをえないのではないか。つまり、科学者の方々が自己研鑽をいろいろ頑張られても、やはり限界があるということを示しているのではないだろうか。市民が感情的になるとか、不安感を過剰に持つというようにも言われましたが、それは感じ方はいろいろあるのでしょうけれども、その不安感に基づいて厳しい対策を要求するということは決しておかしなことでもないし、むしろ未然防止という点からは、そちらの方が正しかったということもあるのではないか。これはBSEがまさにそうではないかと私は思うのですが、この点についてどうお考えかということです。
(中下) 科学者の方々がそれぞれ自分たちのことを反省され、自己研鑽を遂げられるというようなことは大変結構なことだと思います。ぜひやっていただきたいと思うのですけれども、私ども弁護士の立場からすると、やはり化学物質によってさまざまな被害が発生してしまったということについては、深刻に受け止めざるをえないのではないか。つまり、科学者の方々が自己研鑽をいろいろ頑張られても、やはり限界があるということを示しているのではないだろうか。市民が感情的になるとか、不安感を過剰に持つというようにも言われましたが、それは感じ方はいろいろあるのでしょうけれども、その不安感に基づいて厳しい対策を要求するということは決しておかしなことでもないし、むしろ未然防止という点からは、そちらの方が正しかったということもあるのではないか。これはBSEがまさにそうではないかと私は思うのですが、この点についてどうお考えかということです。 (崎田) 簡単なことなのですが、今の宮本さんのご発言で、私は生活者の視点でジャーナリスト活動とか環境学習の推進をしていますが、もう1つ全国ネットの市民活動の事務局長というのをしており、そこで2~3年前、内分泌かく乱化学物質が大変問題になったときにみんなで勉強会を設定しました。そのとき考えたのが、いろいろなお立場の方のきちんとした講義をきちんと受けようということで、1か月ごとに科学者の方、行政の仕組みづくりの方、マスコミの方、NPOとして活動していらっしゃる方をお呼びして勉強しました。実をいいますと、その中で一番まじめに発言されようとする科学者の方が、誤解のないように発言しようとされるほど何をおっしゃっているかわかりづらい。ごめんなさい。悪いと言っているのではないのですが、一般市民としてそういうことがあって、そういうところがわかりやすく伝われば、市民がもっとぐさっとくることはいっぱいあるのにと思いながら伺ったことがあります。
(崎田) 簡単なことなのですが、今の宮本さんのご発言で、私は生活者の視点でジャーナリスト活動とか環境学習の推進をしていますが、もう1つ全国ネットの市民活動の事務局長というのをしており、そこで2~3年前、内分泌かく乱化学物質が大変問題になったときにみんなで勉強会を設定しました。そのとき考えたのが、いろいろなお立場の方のきちんとした講義をきちんと受けようということで、1か月ごとに科学者の方、行政の仕組みづくりの方、マスコミの方、NPOとして活動していらっしゃる方をお呼びして勉強しました。実をいいますと、その中で一番まじめに発言されようとする科学者の方が、誤解のないように発言しようとされるほど何をおっしゃっているかわかりづらい。ごめんなさい。悪いと言っているのではないのですが、一般市民としてそういうことがあって、そういうところがわかりやすく伝われば、市民がもっとぐさっとくることはいっぱいあるのにと思いながら伺ったことがあります。 (河内) 先程、後藤さんからも化学物質に対するデータを取るような努力が足りないというような話がありましたけれども、今実際、新規化学物質に関しては、社会的な合意といいますか、化審法によりまして、難分解性とか長期毒性について疑われる物質はできるだけ製造しないという取り組みは十分できているのだと私は理解しています。それから、既存化学物質については確かに、膨大な化学物質が世の中に出ていて、すべてに対してまだデータを取りきれていないのは事実です。したがって、国をあげて今、取り組んでおられますし、我々の産業界もそれに対してできるだけ大量に使われているものに対しては優先的にかなりのスピードで今データを取ろうとしているわけです。そういう努力はぜひ認めていただきたい。
(河内) 先程、後藤さんからも化学物質に対するデータを取るような努力が足りないというような話がありましたけれども、今実際、新規化学物質に関しては、社会的な合意といいますか、化審法によりまして、難分解性とか長期毒性について疑われる物質はできるだけ製造しないという取り組みは十分できているのだと私は理解しています。それから、既存化学物質については確かに、膨大な化学物質が世の中に出ていて、すべてに対してまだデータを取りきれていないのは事実です。したがって、国をあげて今、取り組んでおられますし、我々の産業界もそれに対してできるだけ大量に使われているものに対しては優先的にかなりのスピードで今データを取ろうとしているわけです。そういう努力はぜひ認めていただきたい。 ご紹介いただきました化学リーグ21の山本です。今日は話す機会がなくなるのではないかと思って心配していましたが、何とか間に合ったようです。私は10分ぐらいで終わりますので、そのあと皆さんに十分ディスカッションしていただきたいです。今、お話を聞いていましても、なかなか化学物質のリスクとか環境というのは一筋縄ではいかないなと痛感しました。今まで3人の方たちからかなり専門的な、しかも科学的なお話を伺っていたのですが、私の話はほとんど専門用語がありません。非常にわかりやすい話になるかと思います。パワーポイントをお願いします。
ご紹介いただきました化学リーグ21の山本です。今日は話す機会がなくなるのではないかと思って心配していましたが、何とか間に合ったようです。私は10分ぐらいで終わりますので、そのあと皆さんに十分ディスカッションしていただきたいです。今、お話を聞いていましても、なかなか化学物質のリスクとか環境というのは一筋縄ではいかないなと痛感しました。今まで3人の方たちからかなり専門的な、しかも科学的なお話を伺っていたのですが、私の話はほとんど専門用語がありません。非常にわかりやすい話になるかと思います。パワーポイントをお願いします。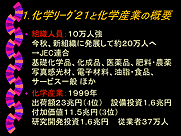
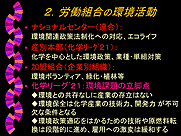
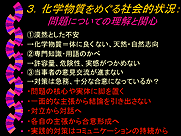
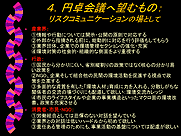
 (瀬田) 先程の3月の神奈川県でのフォーラムに関してですが、せっかくこういった地域でやっていただけるわけですから、地域の実態を少し見ていただくということも有効ではないかと思います。そこで、1つの提案ですけれども、例えば円卓会議を午後から実施するのであれば、午前中にメンバーの方々に例えばどこかの工場を見学していただくというようなことを考えてはどうでしょうか。たまたま私ども旭化成は川崎に工場がありますので、もしもそういうことでご同意いただけますならば準備をしたいと思います。第1回のときに私からご説明をしたつもりですけれども、私がこのメンバーの一人になってから、とにかく一生懸命勉強しました。その結果、私が当然と思っている今の化学工業は昔の化学産業とは全く違っているということを私自身があらためて実感したわけで、そこのところを皆さんに見ていただくということもコミュニケーションの1つかなという感じもします。
(瀬田) 先程の3月の神奈川県でのフォーラムに関してですが、せっかくこういった地域でやっていただけるわけですから、地域の実態を少し見ていただくということも有効ではないかと思います。そこで、1つの提案ですけれども、例えば円卓会議を午後から実施するのであれば、午前中にメンバーの方々に例えばどこかの工場を見学していただくというようなことを考えてはどうでしょうか。たまたま私ども旭化成は川崎に工場がありますので、もしもそういうことでご同意いただけますならば準備をしたいと思います。第1回のときに私からご説明をしたつもりですけれども、私がこのメンバーの一人になってから、とにかく一生懸命勉強しました。その結果、私が当然と思っている今の化学工業は昔の化学産業とは全く違っているということを私自身があらためて実感したわけで、そこのところを皆さんに見ていただくということもコミュニケーションの1つかなという感じもします。 (田中) 私どもも実はこの市民参加の地域対話をずっとやってきました。その頻度や参加の状況について
(田中) 私どもも実はこの市民参加の地域対話をずっとやってきました。その頻度や参加の状況について